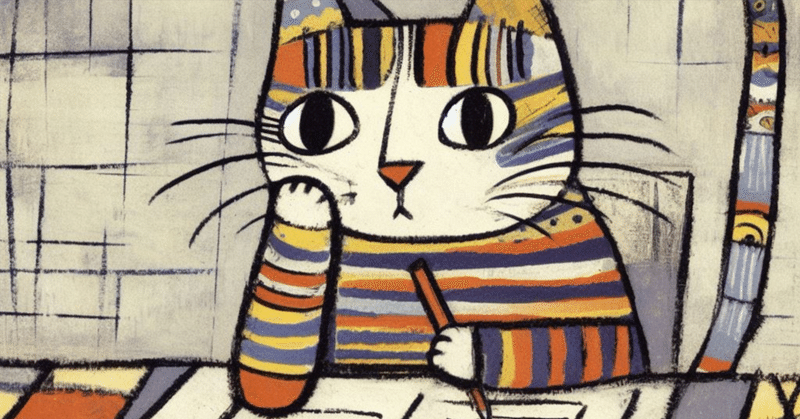
授業中の教師の雑談に関する研究 (価値づけることの葛藤/Agency/権力の非対称性)
書く気にならないまま書いているのでぐだぐだ。
それでも書かねば。ねばねば。nattoNEBANEBA。
JKの、まとまらない、たんきゅーかつどうのマトメです。(実施:2021末〜2023末の探究活動)
はじめに
この研究もどき(所謂探究活動)に固執するかしないか論争が、私の心の中で、永遠より長い間繰り広げられている。「永遠より長い」なんてそんなものは存在しないと言われてしまったら、残念ながら手元に被せる言葉はない。ただ、心の中でずっと、きっと、それは存在するのだと思う。それこそ大学3年の終わりには強制的に卒業論文について意識せざる得ないわけで、事象だけが私の願望の外側で淡々と進み、きっと私の意識は時間に取り残されるのだろうという予感ゆえの、複雑な気持ち。永遠は、「永遠」という言葉で形容できる段階で、私のこの名付けられない感情よりマシであると、羨ましく思う。その意味では「長い」という表現は永遠と同一直線上にあることになるため、やはり不適切な表現であったことは認めなくてはいけない。長くも深くもない。ただ永遠の方がマシだと思う感情に侵されている。
しかしながら、過去の栄光に浸って、そこから逃れられない「固執」ではないことも述べておきたい。書き終えた直後は、なんだかんだ達成感があった。お恥ずかしい話ではあるが、今思うと、自惚れ以外の何者でもない。「よくこの論文で満足していたな自分」と、時間を置いて発酵させるうちにその思いは強まっていた。しかし、可能性は感じていることもまた、私の中で消せない感情としてある。もっと丁寧に勉強し、先行研究を読み込み、いろいろな可能性を考えてから手放したい。まだこの雑談研究に可能性を感じてしまう自分がいる。これ以上のものは書けないというプラスの意味での「固執」ではなく、まだもっと良いものが書けるはずという「固執」。
そろそろ本題に入ろうと思ったり思わなかったり。本来であれば不特定多数の目に研究を晒すことで次の一歩を踏み出したいけれど、調査について不特定多数に晒すお約束はしていないので、具体的な調査についてここでは述べられないことをあらかじめ記しておく。
そしてこれからこの文章を読み進める人には、私が論理的な文章を不得意とすることついて理解していただきたい。思考がとっ散らかっていることが、大学院には進めないかも…と思っている最大の理由であるほどに、非論理的な人間。(当人まだ学部の授業も受けていないくせにそこを心配しているあたりダメ人間)
==================================
序章


本研究は,教師による授業中の雑談について,現状の役割を,教師と生徒という当事者の“認識”に着目して分析を行った上で,「教師と生徒双方が『エージェンシー(Butler,1997)』を発揮するきっかけとなる雑談」の再構築を試みたものである。
と、偉そうな冒頭の言葉で始めています。今振り返るとどの口が言っているんだという感じです。しかし調査協力者の皆様や、指導教員、指導教員ではないけれど色々教えてくださった先生、学外で出会った研究者の方々や大学生/大学院生の皆様には感謝してもしきれません。内容は私の力不足ですので、その点についてはご承知おきください……。第三章は学校にブチギレながら書きました……。すみません……。
先行研究の整理
序章では、まずはじめに授業中の教師の雑談に関する先行研究の整理がてら、この研究で中心になりそうなことを以下の流れでまとめた。詳細は「付録 =序論の本文=」にあるためここではかるーく。[ ]部分は感情。
雑談の有用性をめぐる議論
そもそも先行研究に矛盾が見られる→各々の定義がありすぎる→そもそも定義できるの→雑談と判断するのに当事者である教師及び生徒の視点がなさすぎるんじゃない→ひとまず、個人の”認識”に着目することで現状の雑談の役割を明らかにして、雑談の曖昧さを引き受けたまま研究できないかなぁ。[この時点で雑談を明確に定義しないことを色々な人に指摘されました…反省しています…]「無駄である」ことが持つ意味
先行研究たちは「教育手法としての雑談」という視点で、雑談の有用性について、あるいはその教育的価値の有無に限定された議論なのでは。雑談がいかに学習において無駄ではないかという論点での先行研究は多いけど、学習から少し離れて、「無駄」な雑談が授業にもたらすものを考える必要もあるのでは。新たな雑談の可能性 - 「遂行中断性」とエージェンシー -
前述の1,2や、教育哲学や教育社会学の文脈での研究から、教師-生徒間において様々な非対称性が指摘され、かつ双方が自由になることのない現状がある授業場面こそ、双方がエージェンシーを発揮することができる場へと変えていく必要があるのではと考えた。そのために教師から生徒に対する「働きかけ」ではない新たな雑談について検討したい。しかしそもそも、授業場面における、教師が一見無目的なように見える雑談さえも、目的の内に吸収されてしまうのはなぜなのかについては明らかにされていない。よって、教師および生徒がエージェンシーを発揮するための雑談を新たに構築するために、まずはそれを困難にしている要因を明らかにしよう。
本研究の必要性
以上のことから本研究では、授業の遂行性から教師および生徒が解放され、双方がエージェンシーを発揮するきっかけとなる授業の余白としての雑談を「中断の雑談」とし、その可能性について検討した。エージェンシーの視点から再構築される「中断の雑談」には、以下のことが期待される。一つは、生徒エージェンシーおよび教師エージェンシーを発揮する条件について新たな視点を投じることである。特に教師エージェンシーについては、一斉授業から脱却し教師の裁量が広がり、子供中心のアクティブラーニングが勧められている中で、それでも、あるいはそれゆえに、遂行性に苦しめられる状況を批判的に捉え、授業のなかで教師が遂行性から自由になる時間の意味を考えるきっかけとなる。二つ目は、学ぶべきものが溢れている今、授業場面において、「教育的に価値のあるもの」が残され、「その他」は排除されている状況に疑問を持つことである。冗長とされるものにスポットライトを当てることで、「価値がある」「効果がある」ということの意味を、立ち止まって考え、議論する機会としたい。
本研究の構成
以下では、本研究の構成を述べる。本研究では、授業における教師による雑談の役割について、序章、第1章、第2章、第3章、終章の、全5章で検討した。
第1章では三つの調査による定量的かつ定性的分析を通して、現状授業で行われている教師の雑談の役割を明らかにした。一つ目にあげた先行研究の課題より、当事者の視点を重視するため、「教師の意図」および「生徒が雑談と捉えるかどうかの“認識”」をもとに検討した。
第2章では、第1章で明らかにした現状行われている雑談について、雑談は深い興味ではなく、浅い興味を育むとした先行研究(田中ら、2017)をもとに、「興味の深化」に対する雑談の影響を明らかにした。第1章と同様、当事者の認識を出発点とした。
第3章では、第1章および第2章で明らかにした現状の雑談とは異なる立場で、序章で指摘した目的の内にあることによる遂行性が生む問題と、「中断の雑談」が実践で見られにくい要因について、教師の語りをもとに検討した。
終章では、第1章から第3章までの内容をまとめ、教師と生徒双方がエージェンシーを発揮する土台となる「中断の雑談」の可能性について総括的な考察を行い、本研究の意義と残された課題について述べた。
目的だけ(1〜3)
第一章の本章の目的
本章では、現在教室内で行われている教師による雑談の役割を、教師および生徒の視点から三つの段階で明らかにすることを目的とした。第一に、教師が授業中の教師による雑談をどのように捉えており、意図がある場合にはどのような目的を持って行っているのかを、教師個人の過去の経験や教師としての信念に着目して定性的に明らかにした。第二に、第一で明らかになった教師の意図を生徒はどのように受け取っているのかを、生徒が教師の発話を雑談と認識する/しないことによる差異に着目して雑談が生徒に与える影響を定量的に明らかにした。そして第三に、教師の意図とそれらが生徒に与える影響のズレや一致について、教師と生徒という二つの視点から定性的に明らかにした。
[方法や結果や考察は倫理的にあまり書くと怪しいので……。インタビューしたりアンケートしたりして、インタビューは定性的に、アンケートは雑談認識群と無認識群に分けてt検定を用いて分析して…みたいな感じです。]
第二章の目的
本章では、雑談は浅い興味のみを生起させる(田中ら、2017)とされていたこと(序章)、生徒が雑談か雑談でないかを判断する基準に、もともとの生徒の科目への興味関心が影響していた可能性が考えられたこと(第1章調査2)の二点を踏まえ、雑談の認識と興味の深化の関係について、興味を「科目的興味」「授業的興味」の二つに分けて明らかにすることを目的とした。
第三章の目的
本章の目的は、教師および生徒がエージェンシーを発揮するための「中断の雑談」を新たに構築することである。そのために、それを困難にしている要因を、教師の語りから明らかにする。また教師の語りから、序章で指摘した「遂行性」による「葛藤や不安」が、現場の教師に確認されるかという点についても考察を行うことで、現場に即した「中断の雑談」の可能性を探っていきたい。さらに、第一章および第二章で確認された、授業場面において〈調整機能〉〈理解促進機能〉をもつ雑談とは異なる視点で、雑談が辞書的な意味として持つ「無駄である」ということが授業にもたらすものについての検討を行う。
[第三章が、今振り返ると本当によろしくない文章ですが、最も魂を込めて書いた部分でした…ざっくりとですが終章にお任せします……]
終章
本研究において得られた知見
本研究の目的は、教師による授業中の雑談について、現状の役割を明らかにした上で、教師と生徒双方が「エージェンシー(Butler、1997)」を発揮するきっかけとなる雑談の可能性について検討することであった。
具体的には、生徒が教師の発話を「雑談と捉えるかどうか」の認識による、授業や科目への理解に差異はあるのか(第1章)、生徒による雑談の認識の有無は、興味の深化に影響を及ぼすのか(第2章)、授業中の雑談を、教育手法としてではなく遂行中断性を促すものとして捉え直すことの困難さは何によるものなのか(第3章)の3つのリサーチクエスチョンに沿って、生徒対象のアンケートを分析し、個別インタビューから考察を行った。以下では、上記3点の問いについて検討した第1章から第3章までで得られた知見を整理し、次にそれらを通して総括的考察を行う。
まず、生徒が教師の発話を「雑談と捉えるかどうか」の認識による、授業や科目への理解に差異はあるのか(第1章)という問いについて、アンケート調査による量的分析とインタビューによる質的分析を行った。その結果、教師が授業中に行う雑談には意図があり、教師は雑談に〈調整機能〉〈理解促進機能〉という二つの役割を期待していること、教師の発話を生徒が雑談だと認識する場合、〈理解促進機能〉より〈調整機能〉が強く機能すること、雑談だと認識しない場合は逆の現象が起こることが示唆された。一方、教師の中にある「授業へ生徒を惹き込む」という意図は、雑談の認識に依らず反映されていることが明らかになった。以上の調査結果から、現状の授業中の教師による意図が含まれている雑談は生徒の認識による差異があるものの、学習の効率化や生徒を授業に惹き込むための手法といった視点から考えると、一つの有効な手段だと考えられる。
続いて、生徒による雑談の認識の有無は、興味の深化に影響を及ぼすのか(第2章)について、授業内容や教師について同一条件である複数のクラスを対象としたアンケート調査を用いて分析をした。その結果、学習を促すための興味の深化という視点で雑談について考えるならば、雑談だと認識する場合、深い興味を促す可能性は低いことが示唆された。一方で、冗長な雑談がある場合とない場合で、浅い興味ではあるが、印象に残るかどうかが異なっていた点を踏まえると、生徒の興味を深める前段階としての雑談を位置付ける可能性があることが明らかとなった。
最後に、授業中の雑談を、教育手法としてではなく遂行中断性を促すものとして捉え直すことの困難さは何によるものなのか(第3章)について、4名の教師を対象としたインタビューによる質的分析を行った。その結果、教師は授業中、生徒の反応に支えられている一方で、全ての生徒の要望に応えることの難しさから、要望よりも教師の信念を優先し、それと引き換えに教師自身の発話に対するクオリティに葛藤している可能性が考えられた。それは、学習内容や教育効果につながる発話でなければならないという意識によるものであることが考えられた。このことから、「繋げる雑談」ではなく、授業の余白として「中断の雑談」の必要性が、教師の語りからも示唆された。
以上より、現状の授業中の教師による雑談は、生徒によって学習理解を促す効果もある一方で、科目の興味によらず生徒を一旦は授業に惹きつける効果があり、授業の土台を作る役割があることが示唆された。加えて、授業中の雑談の新たな役割として〈中断機能〉によって生徒が教師の知性から解放されること、また教師による雑談が生徒によって許容される中で、支えられる対象としての教師が露呈することが期待される。それは、教師-生徒間の権力性を和らげ、平等な関係性を構築し、互いのエージェンシーを発揮することにつながることが考えられる。授業中の教師による雑談が、方法論としてのコミュニケーションや学習効果を高めるための手段としてだけでなく、教師と生徒の「支え合い」により生まれるエージェンシーという視点から捉え直されることで、教師と生徒双方が社会の中で主体として活動し、「対等である」という事を考えるきっかけとなると考えられる。
本研究の意義
本研究の意義として、次の3点を指摘することができる。
第一に、既存の「雑談」という言語を調査者によって一方的に定義するのではなく、発話内容そのものだけでなく、生徒がその発話を雑談だと捉えるかの認識による傾向の差異を示したことである。その発話を授業における当事者である生徒がどのように認識するかによって生徒に及ぼす影響が異なることを示した。 雑談を発話内容そのものだけでなく、認識に着目したという点で、雑談を多面的に捉える視座を得た。
第二に、認識によって興味の種類および深さに違いが見られた一方で、生徒が科目への興味によらず授業へ積極的になると示唆されたことである。特に理解度に差が見られる場面などで有効であり、誰一人取り残さない学びを実現する可能性を示したといえる。
第三に、雑談に関する先行研究は言語学や心理学の立場からの研究が多い中で、本研究は心理学的な統計手法を用いながらも、第3章では異なる立場をとっている点で、雑談研究に新たな視点を投じるものであった。また、教師の語りから質的に検討したことによって、「主体性」という言葉の曖昧さと評価することの葛藤、様々なプレッシャーなど、教師の現状も明らかとなり、教師という役割の遂行性の中断を試みることの重要性が改めて指摘された。
本研究の限界と今後の展望
本研究では、現状の雑談が教育手法としてのみ用いられていることを、教師・生徒双方の視点から明らかにし、その背景要因として教師の語りから遂行性による問題を抽出し、教師・生徒がエージェンシーを発揮するきっかけとなる雑談を通した遂行中断性の実践についての示唆を得た。
しかしながら、限られた事例を対象とした可能性にすぎず、過度な一般化はできない。本研究の対象校は前提として生徒が教師の話を聞く体制が整っており、そうでない場合にどのように雑談が行われていくのかについてまでは明らかでないため、今後、対象校を広げる必要があると考えられる。また、特に第二章のデータの分析は丁寧に行えていないため、今後もう一度分析法から考え直す必要がある。また、興味の深化について教師による雑談における時間的変化も考慮し、興味の種類および深度がどのように変容していくのかについて長期的に分析を行う必要がある。そして「繋げる雑談」ではなく、授業の余白としての「中断の雑談」が発生した後の教室の変化について詳細に検討する必要がある。生徒が授業から解放され外に意識が行った時、それがもたらすものは何か、本研究の第3章では教師を対象としたインタビュー調査のみ行ったため、対象を生徒に広げ、引き続き調査を行いたい。
また小玉(2016)は、アレントとベンヤミンの主張を重ねて「遂行中断性とは、法の外部に位置し、法を刷新して新しい権力システムを樹立する政治の条件を指し示す概念として位置付けることができる」と述べている。これを踏まえると、今後、中断の雑談の実践に関する研究を進めるだけでなく、それが政治的に持つ意味について、事例をもとに考えていく必要がある。それは、中断の雑談を「用いて」、主権者教育を教師が生徒にどのように施すかということだけではなく、中断の雑談が「発生する」ことで、政治的主体としての人間がどのように存在しうるのかということなのではないかと考える。しかしながら、中断の雑談を推奨し促そうとすると、教師の遂行性を高める可能性もある。重要性を説くのではなく、ただ中断の雑談というものが自然と起こる場へと学校をつくっていく必要があり、今後中断の雑談が起こる条件について検討していくことを展望としたい。
教師にとって「うまくやらなきゃいけない」、生徒にとって「集中して理解しなきゃいけない」雑談から、教師と生徒双方が自由になる雑談へ授業を組み替えていくためには、中断の雑談の有用性について示すだけではなく、中断の雑談が発生する場の成立条件について、ヒントとなるであろう学校外の空間にも目を向けて検討していく必要がある。
==================================
反省会と言い訳と今度
高三の夏休みからの私は、学校という、THE研究を推す存在への反発で、教育哲学や教育社会学の世界をこっそり覗き見した。もともと哲学に興味はあったけれど、それと教育は独立したものとして捉えており、それらを同じ机の上で考えてみる作業ができたのは、(受験の夏ではあったが)とても幸運な機会だった。本もたくさん読んだ高三の夏。本には、論文には含まれない筆者の思いや思想が垣間見えて、論文より好きかもとか思ったりした。そんなこんなで色々な出会いをして論文を書いた私だが、やっぱりあの論文だけではダメダメだったという思いが、激落ちくんで何度も擦っても消えない。
哲学だけでは語りきれない教育の存在を描くことが、私の探究ではできなかった。先生たちの語りも、本当の意味で大切にできなかった。論文を書いた後、先生と話す中で、先生を自由にすることは、必ずしも良いとは限らないのかもしれないと感じた。私たちが苦労だと思っていることに、教師としてのアイデンティティややりがいを見出している先生もいる。それが良いことなのか悪いことなのかはまだわからないけれど、第三者が勝手に奪っていいようなものでもないとその時思った。けれども、それが生徒を苦しめているのなら、やはりそれは先生がつらくともやめてほしい。でもただやめろといってもそれはおかしい。何かに対してそれは良くない、こうあるべきだと、理想論を語ることも重要だけれど、このテーマで研究する私はそれで終わらせてはいけない気がした。そこで私は教師教育学への興味も芽生えたのだと思う。評価すること、教えることと学ぶことの距離感。これは今でも考え続けている問い。ただ、私が先生のことをわかっていなかったのと同じように、先生は生徒のことをやっぱりわかっているようで何もわかっていないのだなとは思う(ここはあえて全教師に喧嘩を売ってみたい)。人間、そう簡単に分かると思うなよ!!「分からないから尊重している」と思うのも傲慢だなと最近思ったり。相手を尊重することは本当に難しくて、そう簡単にできる訳ではない。教師と生徒なんて、もうその肩書きだけで、わかり合っていると思っている面の60%は偽物だと思う覚悟が必要だと思う。そうではない40%の面ももちろんあるかもだけれど。色々な先生に「あなたって〜」とか「妥協するなんてあなたらしくないよ」とか言われて前は嬉しかったのに、三年生はストレスだった。私の、雑談を違う視点から捉え直したいという内から湧き出た思いは逃げという妥協であり、非論理的なものであり、研究ではないと。なら私は研究をしなくていいからこちらの視点でこの調査を行いたいとブチギレたのも今では良き思ひ出(?)あー、本当に三年生の私って不真面目。学校の先生にはたくさん嫌われたんだろうな…。
以下では、論文では書けなかった今後の話について感情的に書きます。
教育の恣意性に気づくきっかけ
一つは、本当に、教育手法としての雑談と、授業の余白としての雑談は別物なのかということです。教師の意図的な手法としての雑談であったとしても、その発言を無駄なものだと認識し、それによってさほど授業に引き込まれていない生徒もいるのも事実で、彼らにとっては「余白の雑談」なわけです。一方で、「先生の発話には全て意味があると思っている」としていた生徒の存在も踏まえると、雑談と思うかどうかだけでなく、その「認識の変化」に着目してその要因を探ることで、雑談の曖昧さというものが、授業という場面において「教師の発話に意味があることを前提としている生徒」に対する認識の変化を要請する、“揺さぶり”となる可能性があるのではないかと考えます。それは雑談だけではないのかもしれませんが、教育の恣意性とそれに対する生徒の認識の変化を考えることは、教育そのものの新たな側面に光を当てることができるのではないかと思います。(少し誇張しすぎかも、でも大学ではそこもっと考えたい)
独特な権力関係/教師の専門性
二つ目は、教師という存在の難しさです。正直まだ答えが出ていませんが、人間の関係性に着目する以上、抽象度はさまざまだとしても、色々な人間関係のうちの一つに、「私があなたをこうしたい」と権力性が生まれる難しさがあって。今思っているのは、人と人ではなく、人と場、空間との関係に目を向けることで、違った視点を投じれるのかなとも思ったりしています。
(ここの文章、少し前に書いた文章なんですけど、その後ジンメルさんに出会って、私ってやっぱりジンメルさんなのかと、再度興奮しています。)
さらに言えば、「教師は,生徒の変化や成長といったものに自身の意図などといった恣意的なものを投射するべきではない」という主張は、それが理想としてはあるのかもしれないけれど、人間は相互に依存して、相互に見返りを求めていると思うので、そんなの誰もなれなくない?とも思うわけです。ただ、それでもやはり考えなければならないのは、教師であったり、親という存在は、決してその見返りが、子供から大人に対して求めにくいという点で人間一般の関係性とは少し異なるということです(ここに教育学を探求したい思いの根本があるのかも)。そういった意味で、評価することの難しさとかを超えて、教師という仕事の難しさがあって、それに対する尊敬の気持ちを持ちつつも、でもそこで終わりたくはないなぁという。この研究では、教師エージェンシーにも着目しましたが、それが学校という現場において受け入れにくい現状もあると思いますし。この点についてはもっと話したいことなどもあるのですが、本当に答えが出ません…。ただやっぱり譲れないこととして、生徒にとってよかったらそれでいいんだ、とはなりたくない。先生にとっても良いものであって欲しいという願いは変わらないと思っています。
教育の偶然性(醍醐味)
そして研究を通した抽象的な葛藤でもあるのですが、教育ってやっぱり偶然性の塊だということを痛感して。意図のうちに終わることなんてなかなかない。
教育という場面において、その営みに深く関わっている方々は、何か大きな発見をするというより、偶然的な、小さな幸せのかけらみたいなものに心を動かされて、それを生きがいにしていることも多いのかなと。でもそれは測り得ないし、有用性をもとに広めようとすると、本質から離れてしまう気がする。でもだから反対に、測れるものであったり、わかりやすい言葉も広まりやすい。でもそのわかりやすい言葉(アクティブラーニングとか)だって、それぞれの場面において解釈されて、そこで少しずつ変化していって、その場に馴染んでいくものでもあると思うから、全部が批判の対象になるのも違う気がする。研究したりするということそのものが、意図に引き寄せてしまうようにも思うし……。このジレンマをどう乗り越えていけるのかというのが個人的な今後の問いです。
私の第三章は研究として評価されるものではないかもしれないけれど、書けてよかったなとは思っています。あのまま、流されて興味の分析だけしなくてよかったなと。私のしたいことは、無駄であるということがどういうことなのか。広義では「意味のある」ものなのかもしれないけれど、雑談の、温泉に入った時の「あ〜」みたいな固有の温かさ、有用性とかから少し離れた価値みたいなものに、それをメソッド化することなく光を当てるにはどうしたらいいんだろう。ということについて考えることだったのだと思います。そしてそんな思いで9月に始めた調査も(遅すぎる)、教師の「繋げる雑談をしなければならない」という語りが、私の雑談に対する理想を美しく引き裂いてくれました。
でもだから私は、教育学がやりたいと思ったんです。「自己や他者の弱さ(多面性)と向き合う営みとしての教育」に光を当てられるような研究をするために、大学に進学してもっと基礎を学んだ上で、もっと深く思考したい。
私は、今も未来も大切にしようとする教育学に惹かれました。けれど、色々な分野や人が関わり集まる分野であるからこそ曖昧で、それぞれの「こうしたい」という思いがあって、時にはそれが矛盾してしまうこともある。そしてその矛盾は、理論と実践の対立だけではなく、概念、政策、実践などの複雑な絡み合いによるものであると思います。だから大学で色々な「学」を勉強することで、その矛盾に向き合えると信じています。ただ実践と理論の対立として教育学を捉えたくない。
あと、具体的に研究内容にツッコミを入れると、「中断の雑談」が良いとしても、いざ実践した時、結局じゃあその役割から解放された後はどうなるの?ということです。雑談は授業のメインではなくて、あくまで刺激としてその行間的なポジションを貫くのだとしたら、やはり授業というメインに戻ってくるのか、それでも戻ってこなかった人が教室にどのような影響を与えるのかという視点でも考える必要があります。そしてそもそもここでは、「教師の雑談」に着目しており、生徒同士の雑談には焦点を当てることはできていません。なんかそういえばこの間Xで、生徒間の雑談に関する論文出ていた!!ダウンロードだけして読んでいない!!!読みたい!寝れない!
なんか他にもたくさん反省すること、あったぞ。思い出せない。朝型なのにこんなに遅くまで起きているせいだ。きっと。
小話(探究活動とは何だったのか)
SDGsか、学問もどきか、
SDGsや地域連携など、あらかじめ定められた枠に沿って行う「総合的な学習の時間」とは異なる「探究の時間」。私の高校は自分で問いをこねこねして、リサーチクエスチョンを丁寧に磨いていくことを重視していた。その意味で個人が尊重されており、嬉しく思っていた。しかし、とても素敵な先生方に囲まれてた一方で、先生方の顔色を過度に伺おうとするわたしという存在にずっと悶々としていた。「SDGs/地域連携/社会課題解決」vs「学問もどき」の構図があるように思えて、苦しかった。さらに言えば、そのいずれかにしか分類されないような気がして、息苦しかった。学問もどきの先に、社会開題解決につながることはあるけれど、そこが出発点ではないし、基礎研究ならそれ以前の話。”もどき”としたのは、アカデミック寄りな探究活動を行う学校あるある、かもしれないが、基準が高等教育の研究にあると感じたからである。「大学レベルの研究だ」「大学レベルにはいかないとしても…」「大学レベルを超えている」など、探究活動をアカデミックな研究と同一直線上におき、高等教育のサブとしての中等教育があるように思えた。その意味での「高大接続」なのですか、その関係に対等性はないんですね。そう思った。
けれども、高校のうちから研究に関われることは、人によってはとても嬉しいことで、私もどちらかと言えばそういう人だ。キャリアの選択肢に研究が含まれているなら尚更。さらに個々の関係性を見ていけば、決して高校生が大学の研究のサブとして搾取されているようなことはなく、良い関係を築いていると思う(理系だと基礎/応用研究によらず、そもそも実験機器を使わせてもらえるだけできっと天国なのでは。憶測だけど。)
変える必要があったのは、高校側の意識だったのかもしれない。大学を卒業している高校の先生は(特に修士や博士を取得している場合であれば尚更)、大学の研究を知っており、その基準や価値観が根強くあるように感じる。彼らによる「高校生の研究であることは理解している」という視点はすでに大学の基準が内面化されていたように思う。
いや、そうじゃないかも……!!高校の先生たちはちゃんとわかっていたのかもしれない……。先生たちからの提案やアドバイスがあまりにも本格的でそれに圧倒され、学問の型にこだわりすぎてしまったのは私の方だったのかも。
(この本格的な指導は大変嬉しいことだった。研究倫理や、統計手法など丁寧に指導してくださったことも感謝の気持ちで溢れている。そして悩み続けてなかなか動き出さない私の隣を一緒に走り続けてくださった先生方のことが本当に大好きであることは何度でも述べておきたい。)
学問って、高校って、大学って何さ
その学問の型をめぐって二つの思いが、私の心の中に、ひっそりと存在し続けている。
一つは、大学を意識した”先取り”という意味ではとても良いけれど、そもそもそういった学問の型なんていうものがあるのか、あるとしたら守破離の段階を経て守られるべきものなのか、ということ。この問いについてはまだ「問いのこねこね段階」にすら達していないけれど、学問”らしさ”という三文字に込められた特性や習慣も、良いものとそうでないものがあるだろうから、それらは丁寧に見極めていく必要があるのだと思う。きっとそれは高等教育学の先生方がやられているのかもしれない。大学で高等教育学の授業あるかな、なかったら他大学でも聴講したいなぁ、できるかなぁ。
もう一つは、学問の型云々や先取り云々、大学進学などによらず、研究をするときの倫理や、論理的な文章は、すべての人が体験していても良いものなのではないかということである。高校進学以上に、大学進学は”現状”当たり前のものではない。大学進学率を上げようとする試みも大切なのかもしれないけれど、それを考えたり試みている間にも中等教育課程を終えて働く人は毎年いるわけで、応急処置的な意味であっても良いのかなと。ただそれをサポートできる高校の先生というのは少数派だろうし、結局大学の二番手になりそうだという一つ目の問いの懸念に戻ってしまう。そして「何でも早期化」の主張に自分が加担してしてしまいそうでなんか嫌。
高校という場が、独自の思考の場として耕されていったらいいなと。大学の先生が高校生に型を一方的に教えるだけでもなく、「高校生の視点」という字面に釣られて高校生の席が用意されるのでもない、思考の場が。(このことについてお話しされていた大学の先生がいらしゃって、私はとても嬉しい気持ちになったのでした)
そういう私は、学問のことなんて、まだ1mmもわかっていのだということは最近ことあるごとに思う。だからこれらの主張はあくまで学問を知らない外野からの偏見でもあるということを記しておきたい。偏見を記録しておく主な理由は、これから大学で学び内部の人間になってしまったら、この感覚はきっと忘れ去ってしまうだろうと、本能的に思ったから。本当に、本当に、私は感化されやすい人間で、一度完全に感化されてから批判的に見るまでのタイムラグが果てしない。だからこれから、私は感化されに学問の世界に足を踏み入れることになる。学部の授業はとてもとても大切な基礎となる勉強が大半だと思うので、なんちゃって学問を語ることのないように、たくさん勉強したい。勉強したことは使ってみたいとその刃の鋭さはわからないようにも思うけれど、私が調子に乗っていたらどうかこう言っていただきたい。「君、さてはイキってるな?」と。
”好き”は原動力ではなかった
探究活動は、決して「好き」を追いかけるだけではなかった。「楽しい」だけでもなかった。ただ、私にとってこの雑談研究は、部活や委員会、家事、課外活動、大学受験など”を”傍らで行いながら、高三の12月までやり続けるくらいに、高校生活の「真ん中」に据えたいと思うものだった(※)。そして私なりに、必要な研究だと思っていた。意義を見失ったり、データの分析がうまくいかなくて立ち止まったり、エクセルのシートが混沌として絶望したり、方向性に悩んだり、調査を進めてから良い先行研究に出会ってしまったり、現状を捉えきれていないことに葛藤したり、自分がどの立場で何様のつもりで研究しているのか怖くなったり、大好きだった学校を嫌いになったり、尊敬する先生と話せなくなったり、授業を純粋な心で参加できなくなったり……色々なことを含めて、好きとか嫌いとかそんな尺度では測れないものだった。ただ知りたくて、考えたくて、この研究のその先に、まだ言葉にしきれない思い描く理想らしい社会の姿があることだけをどこかで信じていた。結果として、この研究が私のアイデンティティ的な存在になるのだという根拠のない確信だけが、私の足の裏よりももっともっと下の奥深くに確かにあるのだった。
※反面生徒にしていただきたいこと
私はこの探究活動を通して大学進学を決意しました。しかし共通テスト前日さえ頭の中が雑談のことでいっぱいだった私は案の定……(当日の問題文さえ思考の種)。割り切って努力できないところが自分の未熟さでした。これを読んだ受験生はどうか割り切って、身を置きたい場所に身を置く努力をされることを願っております。かくいう私は、もう過去のことですので、これも運命だったのだと前を向いています。人生のスケジュールが真っ白になり、ある意味でこれからが楽しみです。
どのような道に進んだとしても「そこでしか出会えない人/こと」があるはずです。それらが”未来”である時点は”今”を分析して好みの”未来”を掴もうと努力しても良いと思いますが、その”未来”が”今”となったら、その時はもう、目の前に「そこでしか出会えない人/こと」が広がっています。それを両手いっぱいに抱えて大切に温める以外に、私にできることはないでしょう。そして本当に出会うべきだった人/ことには、いつか必ず、然るべき時に出会えると願っています。そしてこれからの大学生活は、出会って満足するのではなく、出会いに影響された自分との壁打ち思考も大切にし、内面を磨いていくことも忘れないようにしたいものです。
悲観的に過ごすことで生まれる思考もあり、この世界に無駄な感情などないと考えています。それを無駄だと捉えている人はきっと、その人が考える正しい方向へと進むにあたって、その感情が不都合であるにすぎないのでしょう。私も実際、「悲観を楽観に変えるための取り組み」を無駄だと捉えているわけですから。そういった私の基準をもとに述べるとしたら、就職や浪人、第二志望への進学など、希望の進路ではなくモヤモヤを抱えている人も、無理して前を向く必要はないと思います。それが回り回って”価値がある”と言いたいのではなく、何の理由や価値もなく、ただそれが人生である、だけなのだと思います。有用性の外側で、私の人生に無駄なものなどないと、この人生を生きる私だけでも思っていてあげないと、あまりに人生が可哀想。(ただ、受験や就活以前に、ハラスメントや虐待など他者によるあなたの心身を蝕む何かがあるのだとしたら、それらは無駄/有用論争と同一の机上においてはいけないと思います。それらを嫌だと思い助けを求めることは、あなた自身の人権です。その経験が人生の糧になるなどと、思わなくて良いのです。結果的に糧だと思うことがあなたの未来を少しマシな明るさにしてくれるのなら、それはそれで必要だとも思います。でも現状苦しいのなら、無理して糧にしなくて良いと、私は考えています。)
けれど今の私は個人的な気分として、前を向いて、この素敵な春を小走りで掴みに行きたいと思っているので、あたたかく見守って(かまって)いただけると嬉しいです。
長々と失礼いたしました。毎度のことですが私の話にオチはないので今回もまた強制終了します。
高校生活で出会ってくださった全ての方に、心からの感謝をこめて。
2023.4.1. しいたけ
付録
=引用文献=
黒い部分は、noteでは省略したもの(怪しい文書みたいになってしまった)

=序章の(概ね)本文=
1. 雑談の有用性をめぐる議論
学校という空間は,公的な面を持ちつつ,他方で私的な会話がなされる空間である。そういった私的な会話は,授業場面においても起こりうる。授業はただ機械的に進むわけではなく,教師という人間と生徒という人間が影響を受けあって,相互的に進んでいくものであるからだ。
授業中の教師による雑談に着目した岸(2018)は,そういった相互干渉は「子どもからの反応に応じて当初の計画を変更するような意思決定」であり,「授業を展開していく上での意思決定は教師の基本的技能」であるとした。そして雑談を「当該教授内容に関係のない教師の発話」と定義した上で,高校のバレエの授業分析を行った。その結果,次の①〜③の三点を指摘した。①教師は雑談を意図的に行っている場合が多く,生徒との関係の親密化,そして円滑な授業進行のための方略として,雑談を有効利用していること,②授業の回数を重ねていくにつれて,雑談内容が「日常生活」から「バレエ」に関する雑談が増えたとし,雑談が教師と生徒の信頼関係の変化につながっていること,③教師の雑談には「生徒の精神面の調整」「授業進行の調整」 という二つの調整機能をもっている可能性があることである。
一方で,雑談による授業への負の影響を指摘する研究も存在する。例えば,教育心理学における「興味」に関する研究を,高低ではなく深度の視点から整理した上で,興味の深さをより明確に捉える「鼎様相モデル」という枠組みを提示した田中・市川(2017)が挙げられる。田中ら(2017)では,興味の深度を捉えるための枠組みとして,時間的持続,内容本質性,価値随伴性という「鼎様相モデル」が提案されている。そこでは,授業の途中に教師が入れる雑談(=学習内容に関わりのないもの)について,こういった工夫(松原・庄司,2005)は,一時的に生徒の注目を集め,浅い興味を生起させることはできるが,持続的に学習に対する深い興味を育むことができないとしている。また,雑談は実践に取り入れやすく,生徒の注意をひきやすい一方で,このような表面的特徴によって換気された興味は効果が限定的で,むしろ学習を阻害する場合もあるとされている(Durik and Harackiewicz,2017)。
また,速水ら(1996)は,生徒が教師から受けた感動体験について,教師の働きかけを7つのカテゴリーに分け,生徒による「教師から受けた感動体験」についての作文から考察を行った。そこでは,7つのカテゴリーの一つである「雑談・会話」について「内容的に非常に変化に富んで」おり,「先生の無意図的な言葉が生徒本人の物の見方や考え方を変えていくという例が多い。そこでの感動は急に自分の中に何かがひらめく,ハッとするようなものが多い」としていた。
以上三つの先行研究は,特別なシステムやICTなどのモノを必要としない雑談が,授業において無駄なものか,それとも教育手法の一つとなりうるかということについて検討している。雑談は,教師が一人いれば始められる工夫であるという点で,汎用性の高さが期待できるため,これらの研究は大いに示唆的であると言える。一方で,これらの研究には異なる主張が二つ存在する。一つ目は,教師による雑談の意図の有無について,意図があるとした岸(2018)に対し,速水ら(1996)は「無意図的」としていたことである。二つ目は,雑談は「適切に挿入すると効果的である」とする岸(2018)に対し,田中ら(2017)は,雑談は深い興味を育まず,学習理解を阻害する可能性があるとしていたことである。これらの矛盾の原因として,何を雑談とするかという雑談の定義に差異がある可能性が考えられる。他方で,そもそも雑談を定義することは可能なのだろうか。前述の三つの先行研究では,調査者が雑談を判断しており,その多くが「授業に関係のない」というキーワードを用いているが,何が「授業に関係のない」発話であるのかは,教師でも生徒でもない第三者が一方的に決定できることなのだろうか。
これらのことから,先行研究に残された一つ目の課題として,雑談をめぐる分析に,教師と生徒という当事者の視点が欠けていることを挙げたい。しかしこの当事者の視点というのは,生徒である筆者が定義することで解消される課題ではないと考える。雑談という存在の曖昧さを,個々の“認識”を軸とすることで,曖昧さを引き受けたまま分析することを試みる必要がある。
2. 「無駄である」ことが持つ意味
しかしこれらは「教育手法としての雑談」という視点で,雑談の有用性について,あるいはその教育的価値の有無に限定された議論である。その背景の一つとして,教師に求められるスキルの拡大によって,学習を効率化しようとしていることが考えられる。例えば,高校で新たに設定された「情報Ⅰ」という科目をはじめとして,授業時間には限りがあるにも関わらず学習指導要領に規定される学習内容は増加しており,教師生徒双方への負担が指摘されている(豊田・登本・髙橋,2022;倉本・宮本・久保・長濱,2023)。また,平成29・30・31年の学習指導要領改訂によって,主体的・対話的で深い学びの実現が求められており(文部科学省,2018),それに伴い,授業に占める生徒が能動的に書いたり話したりする時間の割合が増えている。そういった時間が一定量必要とされているからこそ,生徒に対し知識をインプットするためのコミュニケーションである講義部分で「より効率的に必要な知識を伝達する高度なティーチングスキル」が求められている(枝川・谷・佐藤,2016)。このような背景から,雑談が「学習を効率化させる道具」としてのみ捉えられているのではないか。
ここで,学習を効率化させる道具としての雑談ではなく,雑談という言葉が持つ本来の意味に立ち戻って考えたい。「雑談」を辞書で引くと,「はっきりした目的やまとまりのない話」とされており(Table 0 ※省略),言い換えれば,「目的」がない雑談とは,手段を通じて何か実現しようと思わない話のことであり,「まとまり」がない雑談とは,同じところに集まった一つのかたちにならない話,筋道が立たない話であると言える。日本語以外の雑談に該当する単語も,雑談以外の意味には,「だべる」「くだらない世間話」「むだ話」「冗舌」といった,“無駄”という意味合いを含む言葉が並んでいる。しかし,前述までの先行研究で示されている雑談には目的が存在し,授業という一つのかたちにまとまろうとする働きかけであり,辞書に記されている意味合いとは異なる「雑談」である。雑談という無駄話が,いかに無駄ではないかを考えることが,議論の中心となっているのではないか。
以上より,先行研究に残された二つ目の課題として,雑談が辞書的な意味として持つ「無駄である」ということが授業にもたらすものについての検討が行われていない点が挙げられる。
3. 新たな雑談の可能性 - 「遂行中断性」とエージェンシー -
※長すぎたので、以下略しながら(もっと知ってから引用すべきだった方々で溢れているので本当に恥ずかしい。申し訳ない。自分が烏滸がましすぎる本当にごめんなさい。)
よってここからは,学習効果に関する議論から一度離れ,本来の雑談について考えたい。
教育現場での「歓談」についてMeyer(2004)は,「教師の方向づけの割合が低い」ブルジョワ階級のサロンの歓談(Konversation)を先駆けとして示している。一方,現在の歓談(Unterhaltung)を「重要な調整的な機能」として「クラスの社会的な雰囲気の進展や維持に役立つ」と述べている。また,前者のKonversationは「話し合い」といった意味があるのに対し,後者のUnterhaltungは「エンターテイメント(娯楽)」「維持」という意味がある(Table 1)。このことから教師による雑談が,双方向的なものから,生徒を授業に惹き込むエンターテイメント的なものへと,そして生徒の授業への意識を教師が維持するためのものへと変化していることが考えられる。
教師をエンターテイナー,生徒を観客と見たとき,そこに生まれるのは一方向的な関係性だけなのだろうか。田島(2023)は,教師と生徒の知性の平等について記述しているランシエールの『無知な教師』をもとに,観客が「パフォーマンスを自分が見聞きしたり体験したりした物語に結びつけ」ていることを例に,「解釈する主体」としての観客の能動性を生徒に重ね合わせている。そして生徒のエージェンシー(Butler,1997)が発揮されるための授業のあり方について,「受動的」であると批判される一斉授業において,生徒が「解釈する余地」を,「授業後」に見出している。田島の指摘する「授業後」に近い役割を,授業中の雑談の新たな役割として見出すことは可能だろうか。
雑談の新たな役割について検討するにあたり,本研究で用いる「エージェンシー」について……
(略)
ここからは,バトラーや小玉(2016)が指摘する,ヴェルナー・ハーマッハーによる「遂行中断性(afformative)」という言葉を用いて,エージェンシーを発揮する雑談とは何かについて考えたい。……
(略)
また,小玉(2016)によれば,ハーマッハーは遂行中断性をベンヤミンの「暴力批判論」にあるプロレタリア・ゼネストのイメージと重ね合わせて捉えている。「目的達成のための手段である政治的ゼネストとは異なり,プロレタリア・ゼネストは,目的―手段関係の外部に位置する無条件の中断である」とし,小玉は,「遂行性にはらまれている『アイデンティティの固定化』という限界を超えるためには,遂行性を宙づりにしつつ,刷新することを可能にする遂行中断性が重要である」とした。またバトラー(2007=2008)は,「転用戦の場」と位置付けられた遂行性を,「わずかの複雑さを集団のなかに許容するだけで,結局は同質性の再設定でしかない複数性にすぎない」としている。これを現状の先行研究によって示された雑談と重ねて考えると,「授業に関係のないように思える話を行い,わずかの自由さを許容する『雰囲気をつくる』だけで,結局は授業への再導入でしかない」と言えるのではないか。これは前述の「目的―手段関係の外部に位置する無条件の中断」とは言い難く,遂行性の限界である「アイデンティティの固定化」に近いものなのかもしれない。このことからも,遂行中断性に着目した雑談の必要性が考えられる。
さらに,「エージェンシーを発揮する教師」について,教育社会学研究の視点で雑談の可能性を述べる。教師の教室内における権力性について石野(2020)は,教師-生徒間の知の非対称性だけでなく,発言機会の非対称性を,教師による発言機会の分配に着目して考察を行った。その結果,「発言機会の分配ルールを生徒と共有することで,教師は道徳的秩序に基づいた発言機会の分配を演出」し,教師の権威を維持していたとした。しかしその権威は常にあるものではなく,「教師がその振る舞いによって絶え間なく維持する必要のある」脆い権威だとした。そのため,その権威を回復させる必要が生じた場合は,学習内容を進めることより優先して行われる特徴があり,この教師による権威回復の試みは,「生徒『個人』にとっては強制的な服従を強いられる経験になり得る」とした。そして権力の維持は生徒との相互行為によって交渉され続けるもので,「教師は教科を教えるという訓練と同程度に,その交渉の方法についても訓練される必要がある」とした。このように権力を保持する教師は,同時にその権力を「絶え間なく維持すること」が求められ,それを教科教育をこえて,「訓練される必要がある」ものとされる。しかしこの教師の発言機会の優位は,前述で指摘される,教師の遂行性による課題の原因の一つになっているのではないだろうか。教師の知識や発言機会といった権力の優位が認められたとしても,教師自身が,主体として自由であるとは言い難い。自由と権力の乖離は,教師と生徒双方のエージェンシーを押し込めてしまっているのではないか。「個人は孤立させられては断じて自由ではな」く,「自由の成立する場は,意志,志向,感情といろいろ変化はあっても,そうした人間の内面にあったのではなく,人間が集う間の空間なのである」(Arendt,2004)ように,エージェンシーが発揮されるということは,学校という空間で教師と生徒が互いに支援し,尊重し合いながら,共に生きるということなのではないか。そのためには,授業後や放課後だけでなく,教師-生徒間において様々な非対称性が指摘され,かつ双方が自由になることのない現状がある授業場面こそ,双方がエージェンシーを発揮することができる場へと変えていく必要があるのではないだろうか。それを踏まえると,教師エージェンシーという視点からも,教師から生徒に対する「働きかけ」ではない,新たな雑談について検討される必要があると考える。しかし授業場面における,教師が一見無目的なように見える雑談さえも,目的の内に吸収されてしまうのはなぜなのかについては明らかにされていない。よって,教師および生徒がエージェンシーを発揮するための雑談を新たに構築するために,それを困難にしている要因を明らかにすることを,本研究の三つ目の課題とする。
もう既に消したい感情にかられている。消えたい。反省。本当にこれで「論文書き終えた〜」とか思っていた過去の自分の存在を消したい。ここでもまた肝心な部分を載せていないから尚更。あぁ無理。もう無理。眠いおやすみなさい。ぎり入学式前に書き終えたぞ。さようなら、高等教育に進む前の私。
高等教育に進む私へ、
ディシプリンに縛られないようにね。君は縛られたがりだろうから、たくさんつまみ食いして、ディシプリンの間を行き来して、つまみ食いして、荒らしまくるんだぞ。大学のお勉強、楽しみだね。本当にたくさん勉強したいね。
大学によらず、そして分野によらず、勉強会・研究会・読書会など開催される場合には、ぜひ私も混ぜさせてください!!!素人ですが事前勉強も頑張りますので…!!(情報難民より)
教育学はどのような学問にもつながるなぁとやんわり思っていますが、それが本当にそうなのか考えたいのです!!だってきっと、他分野の方も、その方が志す学問のことを、そう感じているのだろうと思うので。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
