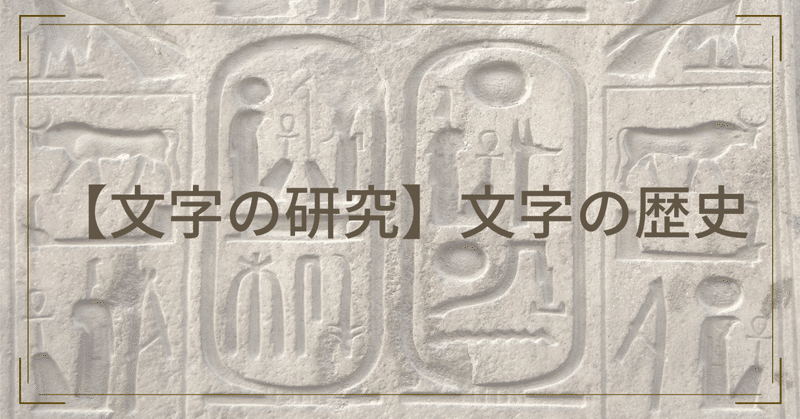
【文字の研究】文字の歴史
どうも、地方公務員のばたやんです。
今回は、グラフィックレコーディングを学んでいるなかで文字について調べましたのでそれをまとめていきます。
🔷なぜ、文字を調べようと思ったのか
私は、グラフィックレコーディングを学んでいます、グラフィックレコーディングとは会話の内容やスピーチなどを図やイラストを使って可視化し理解できるようにするという技法のことで、会議の会話促進や講演会の記録などで用いられます。
グラフィックレコーディングについては、以前note記事にまとめていますのでそちらをご覧ください。
この、グラフィックレコーディングの言葉や文字を絵や図に変換し分かりやすくする、という考え方について、太古の昔、人間って象形文字のような絵を文字として利用して、そこから文字が生まれたんじゃなかったっけ?という記憶がよぎりました。
そこで、象形文字から文字への変遷や成り立ちを調べることで、今なぜグラフィックレコーディングが注目されているのかわかるのではないかと考えたため、文字を調べることとしました。
🔷文字とは
文字って何なのかを理解していないと文字の歴史を理解するのは難しくなりそうなので、ここで文字の定義づけを行っておきます。
文字というのは、言語を、点や線の組合せで、単位(ひとまとまり)ごとに記号化するものである。言葉・言語を伝達し記録するために線や点を使って形作られた記号のこと。言葉・言語を、視覚的に記録したり伝達したりするために、目に見える線(直線や曲線)や点を使って形作られた記号のことである。
あれ?これってグラフィックレコーディングの基本的な考え方と同じなのでは?
ますます興味が沸き上がってきますね。
○絵文字と象形文字の違い
携帯電話全盛期に反映し現在も使われている絵文字ですが、文字が単語に結びつきを求めないという点が象形文字と異なります。
要は、絵文字は1つの概念や1つのイメージを表す文字ということです。
象形文字は文が語に分解でき、その語と文字が一対の対応(意味づけ)がされます。
🔷文字の歴史
まず初めに、そもそも文字の起源とは何だったのか、から調べることとしました。
○文字以前
文字の起源は多くの場合、物事を簡略化して書かれた絵図から生まれていったとされているようです。
絵図という状況を表すもの(いわゆるピクトグラム)があって、そこから絵図ごとに単語の意味づけがされていって象形文字が生まれたというように考えられます。
○文字の発明
紀元前4千年紀にシュメールで起こったとされている、そこから紀元前3千年紀ウル王朝時代には古代クサビ形文字へと発達していったとされています。
先述した文字の定義では、言語を単位ごとに記号化したもの、とありましたが、これはつまり文字以前であった絵図から象形文字へ移り変わるときに起こった意味づけがさらに細分化されて現在の文字という形態へと移り変わってきたと想像できますね。
そもそも我々人間の祖先は、言語によるコミュニケーションを確立したからこそ生き残ってきたといっても過言ではありません、それを言語以外の伝達方法として絵図で伝える方法が発明され、それをより高度化したものが文字なのではないかと考えます。

🔷今回の調査で思ったこと
この調査を通して、絵図から文字へ移り変わるときに言葉・言語を伝達・記録する目的があった点がとても気になりました。
グラフィックレコーディングも、会話の内容などを伝達・記録するという点が似ているようで、でもこちらは言葉や言語情報を絵図にしているところが、文字の歴史と照らすと原点回帰のようにも感じるのです。
しかしながら後退ではなく、次の段階への前身のように感じている、ここの言語化できない違和感を解き明かしたいと、調査を通して感じました。
学びを進めていく中で、見えてくることがあれば都度noteにまとめていこうと思います。
この記事の内容が誰かの力や気づきになれれば幸いです。
それでは、地方公務員のばたやんでした。
