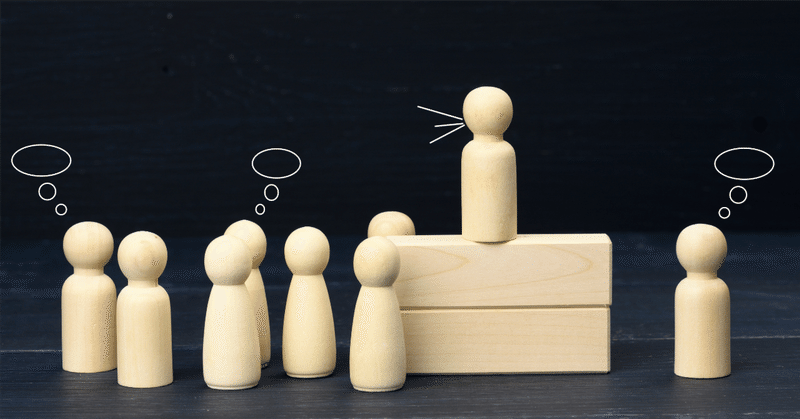
組織開発事例Vol.2:経営とミドルを繋ぐ事業変革プロジェクト(大手製造業B社)
今回は大手製造業B社X事業部の経営陣・ミドルとともに歩んだ事業変革プロジェクト事例をご紹介します。約1年のプロジェクトを通じて、組織変革へ向けての経営チームの器づくり、ミドルが変革の当事者として立ち上がるための支援と対話プロセスのデザインをし、経営とミドルの大きな分断を乗り越える取り組みとなりました。

1.変革を阻む経営とミドルの分断
X事業部は世界No.1商品を持つビジネスを展開しており、社内の稼ぎ頭ではあるが業績は横ばいが続き、新中計においてさらなる成長を求められていました。
業績を倍にするという大きな目標を掲げる中で、経営陣はこれまでのやり方では通用しない危機感を抱えており、本プロジェクトが立ち上がりました。
経営陣へのヒアリングからは、「顧客密着の関係性」がこれまでのコアコンピテンシーであり、間違いなく情報を持っているものの、その情報を活かしきれてないのではないかという課題仮説が浮かび上がった。現場には貴重な情報が多く眠っているはずなのに、ボトムアップでその情報が出てこない、スピード感を持った改善が進まない、対処療法的な課題解決を繰り返すといった状況が起きていた。経営チームの中にも「トップダウンでなければならない」という思い込みもあり、現場を信じて任せることができず、イタチごっこが繰り返されていました。
また後のアンケートで明らかになるのですが、ミドルはミドルで「戦略は経営が考えるものだ。自分たちは言われたことをやるだけだ」という思い込みがありました。貴重な情報を持っている当事者でありながら、自分たちの声を聞いて経営が変わるとは思わない、自分たちから組織を変えていけることはないという意識が強く、自分の目の前のできる範囲だけでなんとかしようという行動パターンが定着していました。
結果、組織内で必要な対話やコラボレーションが起きず、情報を持っている現場は諦め、情報を持っていない経営陣が無理やり決めるという関係性のパターンが繰り返されることで、組織の変革が進まない状態に陥っていました。

2.最初の一歩としての経営合宿
当初はミドル育成に対する相談でしたが、本質的な組織変革を起こしていく上でまずは経営チームが変革の器(コンテナ)となれるかが大切です。これまでの成功パターンを作ってきた経営陣が無自覚に変革を拒んでいる可能性も多くあるからこそ、「変化の土壌を作る」ことを目的とした経営合宿から取り組みスタートしました。
合宿の1つ目のポイントは「組織の現状を見立てる」ことです。
経営チームが普段から組織課題の見立てをしていないわけではないですし、エンゲージメントサーベイなどから組織の状態を一定把握はしていました。一方で、組織の「主流派」である経営陣に見えていないこと、届いていないこと、無意識に見ないようにしていることがあることも事実です。また「事業」に関する声は聞けないことが多いため、部課長100人以上にアンケート(匿名)をとり、定性面も含めて現場の声をしっかり聞き見立ての質を高めていきました。
一方で経営者にもプライドがあるし、自分たちがそれを作り出してしまっているかもしれないという怖れもあり、現場からの声をそのまま受け止められないものです。そこで「組織変革に関するケース」を活用し、経営チームという「ロール」にとって必要なプロセスであることを受け入れる土台を作る仕掛けを入れました。また、「主流派・非主流派モデル」「1%の真実に目をむける」等の心理教育をしながら進めることも大切です。

受け止める準備さえ整えば、歴戦の経営チームです。自然とそこから本質的な課題がクリアになり、覚悟を持った変化が生まれてきます。その中で、「自分たちが何をやり、現場に何を任せるのか」を決めることがホットスポットになりましたが、自分たちのプライドと不安を乗り越え、「事業部全体の戦略コンセプトまでは自分たちで作り、各部門の戦略と日々の業務プロセス改善は現場に託す」という意思決定が行われました。これまでの「トップは考える人・ミドルはやる人」という役割分担から、「ミドルが自分たちで環境分析して打ち手を考え、トップはそれを支援する」という関係性へと大きくシフトできたことで変革の一歩目を踏み出しました。
3.ミドルが立ち上がり現場からの変革が始まる
次はいよいよミドルの出番です。
ただこれまでトップダウン文化で抑圧と諦めを重ねてきたミドルを巻き込むためには工夫が必要です。特に経営からどのようなメッセージを送るかは大切であり、感謝と自分たちの願いに加え、限界の吐露(=我々は現場が見えていない)と権限移譲へのコミットメントを丁寧に伝えるよう意識しました。特に「任せる」ではなく「託す」という言葉を用いることで、そこにある想いが大事であること、自分たちにできることを任せるのではなく、自分たちにできないことを託すというニュアンスが伝わったことが大きなインパクトを生みました。
またあえて指名制ではなく、手挙げでミドルのプロジェクトメンバーを募ったことも大きなメッセージになりました。結果的に18名が手を挙げたのですが、これまでの昇進トラックに乗っている人だけでなく、予期せぬところからも声が上がりました。組織変革には内発的動機が不可欠であり、変革や会社への想いを持っている人たちをプロジェクトメンバーに巻き込む仕掛けが重要になります。(不満や批判的な声を持っているメンバーが手を挙げることへの怖れを感じることもありますが、「不満の背後には願いがある」という意識を持って受け入れることで、結果として組織に必要な声がもたらされ、変革が動き出すことも多くあります。)
経営陣にとっては組織には自分たちの知らない熱を持ったメンバーがいることだけでも大きな気づきであり、普段自分たちに近いところにいないメンバーや若手からのハッとするような面白い声が後々のプロジェクトに大きな影響を与えることにもなりました。
ミドルの変革メンバーとの取り組みでは「3つの逃げない」がキーワードでした。
組織開発というと「関係性」「コミュニケーション」「マインド」に意識が向くことが多いですが、「構造」「システム」の課題にしっかり向き合わなければ持続的な解決へと辿り着かないため、「氷山の上下」を往復し両面をしっかり扱いきることを大切にした設計を行いました。

Step1ではPJメンバー間で問題意識を共有し取り組むべきテーマを決めていきます。問題の症状はどこか、問題が引き起こしているコスト(インパクト)は何か、そのレベルはどうか、といった観点から組織の構造的な課題を明らかにし、まずは外側(氷山の上)のボトルネックを見つけます。部分的な解決策ではなく、組織内で起こっている悪循環をどこで断ち切るかがここでのポイントです。
ここではいきなり100点を目指さないことも大切にしました。当然、PJメンバーが立てた仮説は、経営メンバーから見た時に論理性に乏しいことや見えていない部分があることも事実です。しかしここで論理性を追求しすぎて「正しさ」を迫ると、彼らの意志が小さくなり、「やらされ感」さえ芽生えるリスクがあります。それでは元々あったトップダウン文化へ逆戻りしてしまいます。経営課題や事業課題視点を大きく外していなければ、メンバーの内発的動機を大切に前に進めることが変革を前進させる鍵になります。

今回は4つのテーマが立ち上がり、それぞれのメンバーが関心の高いテーマに取り組む形でチームを組成しました。基本的には本人の意志のあるテーマに選んでいただき、部分最適にならない視点の確保という意味で、1つのチーム内にマーケティング、営業、研究、生産等異なる部門のメンバーが配置されるように調整をかけます。
<プロジェクトで取り組んだ4つのテーマ>
・戦略がないのはなぜ?
・次の事業の柱になり得る新製品が過去10年間生まれないのはなぜ?
・製造部のシステム化目標が達成されず、品質問題が多発するのはなぜ?
・情報共有/連携に時間がかかり、全事業部員が忙しすぎるのはなぜ?
ここからチームごとの活動へ移ります。Step1で氷山の上の課題を構造化しましたが、そこだけを見て安易な問題解決に逃げないことも重要です。問題が起こるメカニズムの探求、その背景にある思想や組織の感情を扱い、真の問題を探っていかなければ根本的な解決には至りません。
そのために「時間軸を広げる×空間軸を広げる」アプローチが不可欠です。時間軸では、50年社史から戦略策定・実行の意思決定のプロセスや価値観を読み解く、新製品開発の歴史を紐解き成功・失敗のパターンを紐解くなどに取り組みました。
また空間軸では、顧客・取引先・離職者へのアンケートやインタビューから関係者の本音を聴き出し、非主流派の声にも目を向けていきます。また社内メンバーへのヒアリングや対話を重ね、組織の中にある怖れや萎縮など感情のプロセス構造分析などを重ね、根源的な課題を明らかにしていきます。
その後Step3で症状(外)と構造・思想(内)を変えるための仕組みや体制を考えていきます。そして外側に戻ってきて具体的な仕組みに落とす。つまり「何(before)を何(After)に変えるのか」を経営チームに伝わるロジックで組み立てることが大切です。
組織開発や対話などの取り組みが増えてきている中で、なかなか具体的な変化に繋がらない原因が、解決策を意識やマインド、あるいは「コミュニケーションが大事」といった抽象的なものにとどまってしまっていることが考えられます。
だからこそ具体的な戦略・戦術、仕組み、ルール、体制・配置、リソース配分、マネジメント方法、会議体に落とし込むこと、やることだけではなく、やらないことを決めることが非常に大切です。今回であれば、60点戦略をブラッシュアップし続ける経営とミドルの新体制の導入を決定、開発戦略は研究部課長の仕事として任せるための運用のガイドラインを策定、自信がない人でも問題解決を進めるためのモデル導入と工場トライアル実施の決定など、(もちろんやりながら改善し続けることは前提としながら)具体的な行動、変化に結びつくための仕掛けへ結びつけました
4.経営とミドルのガチ対話から変化をカタチにする
本プロジェクトのもう1つの大きな鍵が、経営とミドルの「ガチ対話」の場のデザインです。経営とミドルそれぞれの取組を経て、意識や視点、事業や組織に関する課題認識も変わり、具体的な解決策も見えてきましたが、実際に双方向でのコミュニケーションが発生するとうまくいかないのはよくあることです。またミドルや次世代リーダー育成研修では経営トップには「最終発表するだけ(良くてもコメントをもらう程度)」ということが多いですが、継続的な対話こそが「現実」を変えるために必要不可欠です。
今回は3つのフェーズで対話を行いました。
第1フェーズはファシリテーターをクッションに入れた間接対話。いきなり直接だと、ミドルは遠慮する、経営は肯定的なフィードバックをしない、などのいつものパターンが発生し、考えていることがうまく伝わらない可能性が高いため、あえて間接的にすることで、「伝えたいことを伝えきること」「相手の立場に立ちやすくすること」ができます。
第2フェーズでは、ミドルのチーム代表者と経営チーム、ファシリテーターの三者対話を行います。ファシリテーターが介入し、関係性を認知することで自分たちのパターンに気づけるようにすること、伝えきれない要点や想いを引き出すサポートなどによって、少しずつこれまでとは異なるコミュニケーションのパターンが生まれてきます。
そして第3フェーズは直接対話です。ファシリテーターは必要な場面のみ介入しますが、ここまでのプロセスで確実に変化が出ています。双方が想いを持って、思考を重ねながらこの場にいる皆さんですので、対話から新たな可能性が創発されていきました。

ここまでやるのかと思われるかもしれませんが、思っている以上に組織の中ではコミュニケーション不全が起きていることが多くあります。またトップがオープンだと思っていても、そこには必ずランクが存在し、上位者が思っているほどはオープンには捉えられていないものです。また、経営チームがコンフリクトの当事者であることも多いので、ここにどこまで踏み込めるかという意味でも今回のような対話のプロセスは非常に効果的です。
5.「氷山の上下」を扱うことが組織の変容を生み出す
ここまでの内容はX事業部における変革の第一歩ではありますが、今回の取組を通じて生まれた経営とミドルの新たな関係性から様々な動きが生まれています。今回のミドルのプロジェクトメンバーが中心にブラッシュアップを重ねた顧客軸での事業戦略シナリオが「新中期経営計画」にアウトプットされる、マーケティング・営業・研究の新体制・リソース配分に関する提案の実践・検証が始まる、生産本部における上司部下のコミュニケーションモデルが導入され品質問題が減少、エンゲージメントサーベイの注力ポイントのスコアが約10ポイント改善するといった具体的な変化が起きています。
組織開発に取り組む中で、私たちが感じていることが、
「氷山の上だけでも変わらない、氷山の下だけでも変わらない」ということです。
いかに氷山の上下を行き来しながら、分断が起きている関係性の中で大切な対話が行われ、関係性と行動のパターンが変わっていくことが、本質的な組織の変容を生み出す上で大切なのではないでしょうか。
---
バランスト・グロース・コンサルティングの最新イベント情報はコチラから
https://balancedgrowth.peatix.com/events
---
