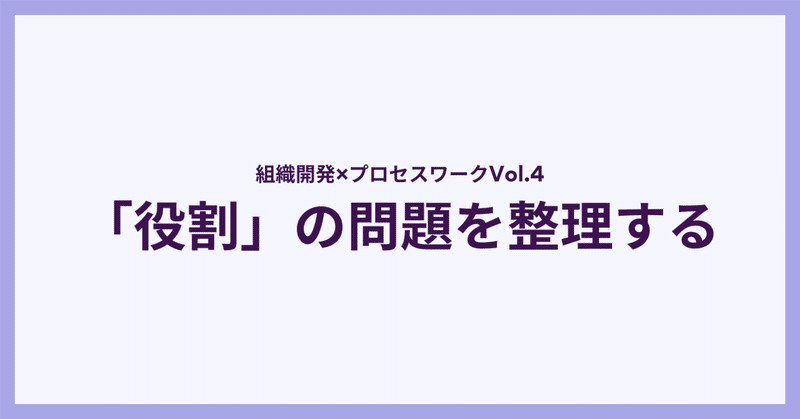
組織開発×プロセスワークVol.4〜「役割」の問題を整理する〜
組織というシステムについて考える上で、「役割」という視点は欠かせないものです。
皆さんご存じの通り、組織には様々な役割が存在します。わかりやすく「部長」「課長」といった役職や「〇〇担当」「ジョブ・ディスクリプション」なども組織の役割です。
一方で、どんな組織にも必ずある「役割」という存在が、組織の課題を正しく捉えることを難しくしたり、組織開発での適切な介入を阻んでしまうことが多くあります。
今回はプロセスワークの「役割(ロール)」という概念を土台に、より効果的な組織変革に繋げていくためのヒントをお伝えします。
組織の健全性が失われる「役割」の問題
最初に覚えておきたいのが、「役割」は「個人」が埋めるが「個人」そのものではない、ということです。言い換えると「役割」は組織に必要な機能であり、人そのものではありません。
例えば、「部長が適切な意思決定ができない」という組織の課題があったときに、「意思決定する」というのは機能であり、その機能を「部長」という人が「役割」として組織の公式/非公式のルールの中で担っていることが多いだけで、部長がいなくても決める機能が果たされればOKだと考えられます。なので、「意思決定できない〇〇部長がダメだ」という風に考えるのではなく、機能を果たす人の問題なのか、機能をどうワークさせるかという問題なのかを区別して組織課題を捉えていくことが重要です。
どのような時に組織の機能不全が起きるのかを知っておくことも、組織開発の打ち手を検討する上で助けになります。下記の「役割」の問題のパターンを参考に、組織やチームの中でどのような役割の問題が起きているかを理解するところから課題の見立てを始めていきましょう。

例えば役割の必要性や混乱は下記のように生じます。あるグループにおいてグループリーダーが満足に役割を果たしていないと不満が起きています。一方で彼女の前任者が部下Aとして残っている状態です。すると現場の経験の多いAを周囲が頼るようになり、Aはリーダーの足りない点を指摘、さらにリーダーは自信を無くします。このような例では公式に与えられている役割の機能の所在が不健全になってしまっているので、組織の健全な意思決定にまで揺らぎが生じてきかねない、機能不全状態といえます。上長に介入してもらい、リーダーの自信回復の支援(コーチングなど含む)、Aに対する1on1での理解の醸成とAへの支援のお願いなどを行うことで、徐々にシステムはあるべき姿に近づき機能するようになっていきます。
2つの「役割」(外的役割・内的役割)
プロセスワークでは、個人が持つ役割には「外的役割」「内的役割」という2つの種類があると考えており、この視点も組織の課題認識を深め、最適な解決策を生み出していくことに繋がります。
組織における役割として話題に挙がるのは、多くの場合、「社長」「部長」「上司」「新入社員」といった長期に固定化された立場や機能としての外的役割です。
一方で、自覚、合意されにくい「リーダー」「自由の戦士」「犠牲者」「抑圧者」といった一人ひとりが体現している内的役割も同時に存在しています。なんとなく感じている人も多いと思いますが、実はこの内的役割が組織に与えている影響は非常に大きく、組織開発においてはこの力動をどう扱うか、組織のエネルギーにしていくかが大切です。
換言すると、「外的役割」は、システムにおける中心的な機能、あるいは、公式機能の維持を目的とした機能であり、「内的役割」は、関係性における感情的な動きと、内面の保全を担うための機能であり、その背後には個人の重要な価値観が隠れています。また、多くの場合、システムの中で対立する2つのニーズの両局面表現します。
先ほどの4つの役割の問題もよくあるパターンですが、「役割」と人物が同一化されたときに問題が生じることになります。
3つの現実レベルからロールを捉える
同時に、役割やその違いを超えて誰もが共有する想いやビジョンの存在がエッセンスレベルで存在します。このエッセンスレベルが組織や役割の対立を超えて、組織を繋げていく重要な要素となります。役割の問題が起きている時にも、一度このレベルを体感することで、それぞれの内的役割・外的役割が効果的に発揮されるようになります。
(「役割」の考え方も、以前ご紹介した「3つの現実レベル」にも紐づいています。)

例えば、リーダーシップという文脈で考えれば、ドリームランドのリーダーロールは、現実の役職としての管理職に関わりません。「うちの社員は当事者意識がない」と聞くこともありますが、当事者意識を持っていると感じる人は、リーダーロールをしっかり取れる人であることが多いものです。いかに個々人が内なるリーダーシップに繋がり、そこから各自の役割やミッションを動かすことができるかをデザインしていく必要があります。組織開発、対話、コーチングが生かされる理由もそこにあります。
組織開発の場面でエッセンスの領域は重要ですが、下記のような場面にそれは見られます。組織やチームの一体感を持つためのワークなどでは、弊社は歴史の振り返りを一緒に行うことがあります。組織のルーツをたどり、歴史の隅に活躍したヒーローのエピソードを聞き、様々な危機を乗り越えて今があることを共有していきます。今、大きな壁の前にあったとしても、部門間の牽制や分断が見えてきたとしても、同じ組織の一員であるという意識が深く共有されたとします。その瞬間は葛藤や対立ではなく、一つである感覚を共有するエッセンス領域の体験です。「では、ここから今をどう進めよう?このチャレンジの未来をどう描こう?」と進むのが組織開発のプロセスになります。
「役割(ロール)」の捉え方についてイメージついたでしょうか。
普段なかなか意識しない観点だったかもしれないですが、「機能としての役割」の問題か、人の問題かをしっかり切り分けることで組織の見え方が変わってきますし、組織の中の「内的役割」やさらに奥深くにあるエッセンスのレベルで組織のプロセスを捉えることで組織開発の取り組みが変化していきます。
ぜひ新たな視点として自分たちの組織を見立て、介入する参考にしてみてください。また、自分自身が組織の中でどのような「役割」を持っているかを考えるところから始めて見ることで多くの気づきが生まれてくるのではないでしょうか。
---
バランスト・グロース・コンサルティングの最新イベント情報はコチラから
https://balancedgrowth.peatix.com/events
---
