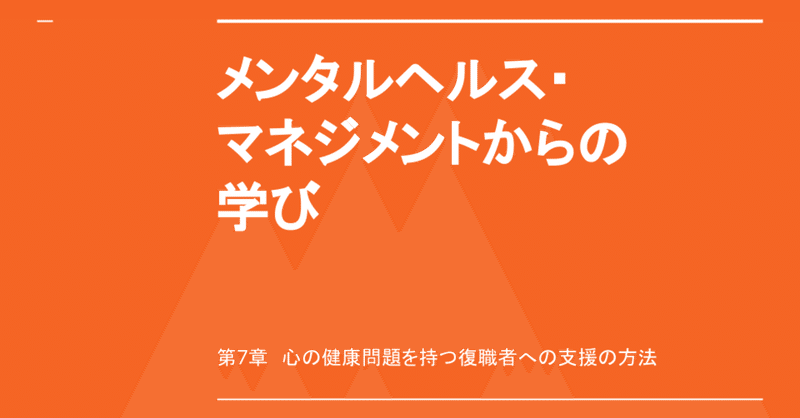
メンタルヘルスマネジメントからの学び#17【完】
メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種を目指して、覚えたこと、感じたことなどをアウトプットしていくことで、記憶の定着と自分の考えの整理をしていきたいと思います。なお、内容については間違いなど普通にあると思います。これを見て落ちても責任は取れませんので悪しからず。
第17回目は、とうとう第7章。最後となりました。2020年中に書き終えられませんでしたが、今年もよろしくお願いします。前回はこちら。
第7章 心の健康問題を持つ復職者への支援の方法
心の健康問題で休業した労働者が職場復帰するにあたり、職場適応や再発防止のためどのような配慮が必要か、管理監督者として部下の復帰支援を円滑に行う方法について学びます。1節は「職場復帰支援の手引き」について、2節は一連の流れのおける職場復帰の具体例について、3節は復職に関する労働者の健康情報の管理方法について、4節は中小規模事業場において活用できる社会資源などについて学んでいきます。
1 心の健康問題で休業した労働者の職場復帰支援
職場復帰支援を行うにあたり、管理監督者が気にしなければいけないのは労働者の病気に対する不安だけではなく、職場復帰に対する現実的な不安です。また、精神疾患の場合、まったく元の状態に回復するということが多くないため、職場復帰後のケアが再発防止の大事なポイントになります。
職場復帰支援に関してはルール作りの手引きとして、2004年10月に厚生労働省より「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が発表されています(2012年7月改定)。ここには、5つのステップが示されており、いくつかのステップをまとめて再構成したりしながら、事業場の持つ人的資源やその他の実態に即した形で実施していくことがよいとされています。ということで、職場復帰支援の流れを以下に示します。この前のテストでは、「職場復帰」の場所が出題されました。そんな問題が出るんですね驚きました。
<第1ステップ>病気休業開始及び休業中のケア
ア 病気休業開始時の労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出
イ 管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によるケア
ウ 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応
エ その他
<第2ステップ>主治医による職場復帰可能の判断
ア 労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能の判断が記された診断書の提出
イ 産業医等による精査
ウ 主治医への情報提供
<第3ステップ>職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
ア 情報の収集と評価
(ア)労働者の職場復帰に対する意思の確認
(イ)産業医等による主治医からの意見収集
(ウ)労働者の状態等の評価
(エ)職場環境等の評価
(オ)その他
イ 職場復帰の可否についての判断
ウ 職場復帰支援プランの作成
(ア)職場復帰日
(イ)管理監督者による就業上の配慮
(ウ)人事労務管理上の対応
(エ)産業医等による医学的見地からみた意見
(オ)フォローアップ
(カ)その他
<第4ステップ>最終的な職場復帰の決定
ア 労働者の状態の最終確認
イ 就業上の配慮等に関する意見書の作成
ウ 事業者による最終的な職場復帰の決定
エ その他
職場復帰(この位置テストに出ました!)
<第5ステップ>職場復帰後のフォローアップ
ア 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価
ウ 職場復帰支援プランの実施状況の確認
エ 治療状況の確認
オ 職場復帰支援プランの評価と見直し
カ 職場環境等の改善等
キ 管理監督者、同僚等への配慮等
2 管理監督者による職場復帰支援の実際
<第1ステップ>
職場復帰支援は主治医から復職診断書が出されてからではなく、休業の判断がなされた時点から開始されます。休業中の労働者への連絡頻度や内容、窓口などは、本人の病状や会社のルールによって検討して決定し、本人にも説明しておく必要があります。提供する情報も職場状況、職場復帰支援に関する仕組み、傷病手当金制度などの必要な情報を知らせながら、安心して療養に専念するように働きかけます。労働者から辞職や役職の辞退などの申出がある場合がありますが、そういったことは健康状態が回復してから判断することであり、まずは、安心して療養に専念してもらうことが先決です。
<第2ステップ>
休養や治療により症状が改善すると、労働者が職場復帰を希望します。管理監督者は、職場復帰可能とする主治医の診断書を提出するように伝えます。診断書には、必要と思われる就業上の配慮についてできるだけ具体的に記載をもらうように、労働者にアドバイスをすることが大切です。
<第3ステップ>
職場復帰には、労働者の症状の評価、職場環境の評価との組み合わせで総合的に判断します。管理監督職は、職場環境についての情報を示しながら積極的に情報の収集と評価に加わることが大事です。
まず、確認するのは、労働者の職場復帰に対する明確な意思です。必要に応じて、労働者に同意を得たうえで、主治医に連絡して、「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」を用いることを提案しています。発症から初診までの経過、治療経過、現在の状況、就業上の配慮に関する意見などを情報提供事項として挙げられています。テスト的には、病名が情報提供項目に挙がっているかというものがありました。細かいところついてきます。
職場復帰の可否の判断は、「情報収集と評価」の結果をもとに、主治医や産業医等の医学的な考え方も考慮しつつ、管理監督者等の意見を十分に考慮しながら総合的に判断します。
職場復帰が可能と判断された後は、職場復帰支援のための具体的なプランを作成します。プラン作成時に次の事項を検討します。管理監督者が行う業務上の配慮や、配置転換、移動などの人事労務管理上の対応について、産業保健スタッフの意見を聴きながらできるだけ具体化していきます。
職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき事項
(ア)職場復帰日()
(イ)管理監督者による就業上の配慮(業務でのサポート内容や方法、業務内容や業務量の変更、段階的な就業上の配慮、治療上必要なその他の配慮)
(ウ)人事労務管理上の対応等(配置転換、勤務制度変更の可否及び必要性、段階的な就業上の配慮の可否及び必要性)
(エ)産業医等による医学的見地からみた意見(安全配慮義務に関する助言、職場復帰支援に関する意見)
(オ)フォローアップ(フォーローアップ方法、タイミング、就業上の配慮や医学的観察が不要になる時期について)
(カ)その他(労働者自らが責任をもって行うこと、試し出勤制度の検討、事業場外資源が提供する支援サービスなど)
その他、職場復帰後のフォローアップのタイミングや労働者本人が再燃・再発を防ぐために工夫すべきことについても明確にしておくことが大事です。
<第4ステップ>
最終的な職場復帰の判断を事業者が行うステップです。第3ステップの情報をもとに会社が最終的な判断をします。労働者の状況に応じて、職場復帰支援プランの内容は適時更新します。また、就業上の配慮について、主治医も知っておくべき情報があるため、労働者を通じて主治医に伝えるようにしておくとよいです。
<第5ステップ>
職場復帰を果たしたのち、フォローアップのステップです。職場復帰可否の判断は、多くの不確定要素を含んだまま行われることも多く、また精神疾患の中にはどうしても再発を防げないケースもあるため、職場復帰支援においては、復帰後のフォローアップが非常に重要となります。
受療の様子、症状の再燃の有無、業務遂行能力や勤務の状況、意見書などで示されている就業上の配慮の履行状況などについてチェックし、もし何らかの問題が生じた場合はできるだけ早めに関係者間で対応することが大事です。管理監督職は身近で様子を見る立場であることから、フォローアップにおいては重要な役割を担っています。
3 プライバシーの保護
今までもプライバシーに関することは書いてきたのですが、復職に関する情報もプライバシーに深くかかわるものであるため、本人の同意を得たうえで扱うように配慮が必要です。
職場復帰に関して注意が必要なのは、職場復帰の可否判断は労働者にとって、情報交換に関する同意を拒否することは、それだけで職場復帰が認められないのではという不安に直結するため、職場復帰支援における同意については労働者が不利な立場に置かれないように管理監督者としても十分な配慮が必要です。
職場復帰支援に関する情報は、復職サポートと事業者の安全(健康)配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきです。産業医が選任されている場合は、産業医が健康情報を集約と調整を行うようにします。
4 職場復帰支援におけるその他の留意事項
心の病による休業は、労働者の自信を失わせる出来事です。キャリアデザインの見直しも必要となる場合があります。管理監督職は、これまでのワークヒストリーの振り返りや現存する問題点の整理などについて、労働者の話を聴きながら相談に応じることができれば、労働者にとって大きな支えとなります。なぜ自分がこういった状況に至ったかなどについても単なる偶然で済まさずに、これまでの労働感や自己の健康管理の在り方も含めて見つめなおす機会にできれば、症状の再燃・再発の予防だけでなく、今後の仕事生活をより豊かにするものにするきっかけとすることができます。
中小規模事業場では、産業医などの必要な人材が確保できない事情があります。管理監督者は人事労務管理スタッフや衛生管理者、衛生推進者と連携しながら、必要に応じて産業保健総合支援センターや地域窓口(地域産業保健センター)、中労働災害防止協会、労災病院勤務者メンタルヘルスセンター、精神保健福祉センター、保健所、地域障害者職業センターなどの事業場外資源のサポートを求めることが必要となります。
また、一部の医療機関、外部EAP機関、NPOでうつ病などを対象にした復職のためのリハビリテーションプログラムが試行されるようになっていますので、これらの外部資源によるサービスをうまく活用することも大切です。
まとめ
5つのステップを守ることよりも、各ステップで行うことを理解したうえで、会社の方針と労働者の現状を踏まえた柔軟な対応を行えるように事前の準備を行うのがポイントになります。そのためにも、日ごろから良好なコミュニケーションを各方面と取っておくことが管理監督者としては必須事項なんだと思います。特に職場復帰支援では、一度仕事から離れた部下が復帰するわけですから、一度決めたとおりに進むということはないと思ったほうがいいです。状況が変わるたびに調整ごとが必要になるので、個人情報に留意しつつ、柔軟な対応を心がけましょう。
さて、今回でメンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種については最後となります。ぶっちゃけ書きすぎな気もしないでもないですが、まずは、知識がないことには始まりません。医者もまずはアホみたいな量の勉強をして色々な知識を得るところから始めます。一般人である私たちはなおさら知識をしっかりと蓄えて、実践の中で試行錯誤する体験を経て、経験に変えていかなければなりません。頑張っていきましょう!
カスタマーサクセスの必要性と、トークンエコノミーな未来におけるコミュニティのあり方を考えます。ってだけではないですが、ざっくばらんに気になったことnoteします
