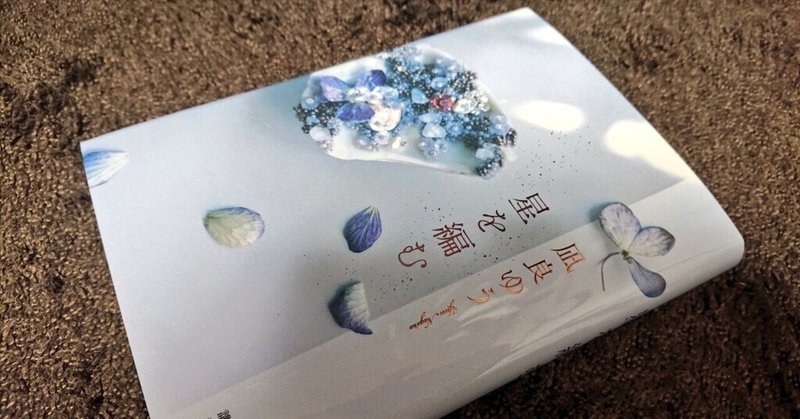
【書評】『星を編む』凪良ゆう
約1年前に読んだ凪良先生の長編『汝、星のごとく』からその続編にあたる『星を編む』という作品を読み終えました。
本作は、『汝、星のごとく』前日譚と後日譚にあたる物語であり、前作と繋がっている構成となっています。
『星を編む』は、全中編の三つの物語によって構成されたスピンオフ作品となっています。
「春に翔ぶ」では、櫂と暁海の理解者である北原先生の過去を描いた話であり、明日見という教え子と北原先生を中心に物語が進められ、北原先生の過去から、北原先生が櫂と暁海に対する思いやりや優しさの原点を知ることが出来ることができ、彼の内面性を知る上では、「春に翔ぶ」という作品はとても重要な作品であることを痛感させられました。
タイトルにもある通り「春に翔ぶ」という意味を知ったことで、北原先生や明日見の思いに強く共感させる見事な物語であり感動させられました。
そして、表題作にもある「星を編む」では、『汝、星のごとく』で描かれた櫂と尚人の編集者の植木さんと二階堂さんの姿を通して描かれた物語であり、前作の櫂の結末を読んで悲しくなった私と読者の方々にとって、考えさせられる思いというものがあり、編集者の立場からみた櫂と尚人の人間像がより浮き彫りになることが窺えられ、私自身が本作の中でも特に胸を締め付けられる思いがあったシーンがあるので、ぜひとも引用したいと思います。
ただひとつの星のような物語を遺し、すべての悩みから解き放たれた櫂くんが少し羨ましい。
櫂くんと尚人くんはもういないけれど、ふたりが遺した作品にはいつでも会える。
(P.183より引用)
作品というものに対して、物語から得られる光輝くものを愛して編むということで、物語を必要としている人たちへとつなげることが出来ることは、編集者という存在があるからであり、櫂と尚人を支える編集者の植木と二階堂の姿がより鮮明に逞しく見えるものがあり「星を編む」に相応しい、凪良先生の美しい言葉の表現力は読者の私たちを優しく包み込むものがありました。
そして最後の物語「波を渡る」では、暁海と北原先生のその後の姿が描かれる物語であり、前作の『汝、星のごとく』を読み終えた後のカタルシスをもう一度、体感させられるものがありました。
生きることは楽しいこともある反面、辛いこと、苦しいこともたくさんあるものだと感じる。
暗くて狭い闇の中でもがきながらも、救いを求めればいつか、それは希望に変わるものがあると痛感させられました。
櫂と暁海を繋ぐもの、それはどれだけの時間と月日が経とうと風化されることはなく、一生心に残り続けるものがあるということを実感させられるものがありました。
私は「波を渡る」の中で、暁海が思いを馳せるこの表現がとても好きだと感じました。
わたしにとって櫂は煌めく火花だった。
そして北原先生は海だった。
あの夏、夜の海へと落ちていった幾千の火花を思い出す。
(P.285より引用)
『汝、星のごとく』から『星を編む』へと繋がり櫂と暁海、北原先生、尚人、植木さん、二階堂さんたちの物語は読了後も、私の中で留まり続けるわけは凪良先生の持つ文学に秘められた言葉の力によるものだと確信しました。
よろしければ、サポートお願い致します。 頂きましたサポート資金は、クリエイターとしての活動資金として使わさせて頂きます。これからも、宜しくお願い致します。
