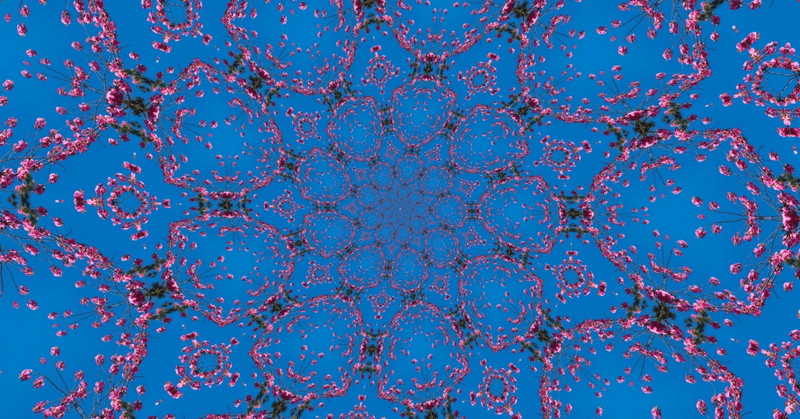
ITは経営資源の中ではどこになるのか?ITの投資対効果を考える。
DXレポートによれば、日本企業におけるIT投資の約80%は保守運用コストであるようです。もちろん業種や業態により違いはあるでしょうが、全体的な状況は10年以上前から変わっていないようですね。
ITの投資対効果、ROIを上げるというのは以前から言われていることではありますが、これでは投資対効果も上がらないでしょう。そもそもITの投資対効果を測ることは言うよりも難しいのです。ITの投資対効果を測るのはなぜ難しいのか?今回はITの投資対効果について考えていきたいと思います。
ITは何が出来るのか?
そもそも、ITは何ができるのでしょうか?ITに詳しい人からは今更そんなことを考えてどうするのかと言われそうですが、DXを推進していかなければならない今だからこそ、改めてITが何ができるのかを知っておく必要があるかと思います。私も研修や講演などの機会があると、「ITは何ができると思いますか?」と聞くことがありますが、多くの人は「売上が上がる」、「利益率が改善する」、「業務の改革ができる」というような回答をしていただきます。これらの回答は間違いではないのですが、正確にITができることを表しているかというと疑問です。もっと狭い意味でITが何ができるかを正しく捉える必要があります。ちなみに私はこの質問に対して「ITは情報をインプット(入力)して、溜めて、アウトプット(出力)する」と答えます。インプットはほとんどの場合は画面からの入力、アウトプットは画面や帳票への出力です。要するに、従来のITとは、誰かが画面から入力した情報をDBに溜めて、画面や紙に計算したり集計したりした情報を出力するだけのものです。出力された情報を見て次のアクションを行うのは人間であり、場合によってはロボットがアクションします。
何あたりまえのことを言っているんだと言われそうですが、この当たり前のことが正確に理解できていないと、ITやデジタルを正しく活用できなくなってしまいますので、この当たり前の部分を改めにしっかりと認識しましょう。
ITが出来ることを絵にすると以下のようなイメージです。

IoTやAIが入ると以下のようなイメージです。

IoT、AIをどう理解するかは様々な見方がありますが、従来のITとのIoT、AIが同関連するかという観点で、私は上記の絵をよく用います。業務プロセスの中でIoTやAI、ロボットが行う部分が増えてきたので、人間が行わなければならない部分が減ってきた、自動化できる部分が広くなったということになります。この点については、また別の機会に書いていきたいと思います。
戦略マップでITの効果を見える化する
さて、IT投資対効果を理解するということで、バランススコアカードの戦略マップを使って整理したいと思います。バランススコアカードの戦略マップは、経営指標は財務指標だけではなく、中間指標となる顧客や業務プロセス、人・学習などの視点を取り入れて、そのつながりを見えるようにしたところに大きな意義があります。イメージ図は以下の通りです。

では、戦略マップの中ではITはどこに位置づけられるでしょうか?この質問もいろんな答えが返ってくるのですが、私な以下の図のように整理します。

先ほど見たITが出来ることを考えると、ITが財務や顧客のところに入るものではないということは理解できるかと思います。従来のITはあくまで業務プロセスを効率化するための手段であるため、戦略マップでは業務プロセスのしたに入れるのが適切でしょう。上記の図ではITの中に「仕組み・ルール」も入れいていますが、従来型のITは業務上の仕組みやルールと一体となり、あくまで手段として業務プロセスを支援する、ということになります。
戦略マップでITの位置づけを整理すると、ITの投資対効果が「売上アップ」や「利益アップ」などの財務指標、また「顧客満足度アップ」などの顧客視点には直接現れてこないことがイメージできるでしょう。仮にITが意図通りに構築され利用されていたとしても、提案内容が悪ければ受注率・受注件数は上がらず、売上も上がりません。財務指標や顧客指標を達成するにはIT以外の要素が入ってくるため、正確にITの投資対効果が見えないのです。では、ITの投資対効果を測るにはどうしたらよいでしょうか?それはやはり、業務観点の指標(KPI)を定めることになります。業務のKPIを定めるには、あるべき業務の姿が整理されている必要があります。ITの投資対効果を測るのが簡単ではないというのは、業務のKPIが定まっていないければITの効果が見えにくくなるためです。ITの投資対効果が見えないから保守運用コストに全体予算の80%も使っているという状況がずっと続いているのでしょう。ITの投資対効果を高めるには、ITが出来ることを正確に理解し、現状のITの効果を測るために業務を整理するところから始めるという、王道のような道のりを行くことが結局近道ではないかと思います。
なお、「従来のIT」という表現をしてきましたが、「守り偏重の会社内の業務システム」という意味を込めています。昨今のITやデジタルは手段としてだけではなく、資産としてのデータ、ビジネスプラットフォームそのもの、マーケティング関係の攻めのITなど、「従来のIT」とは区別して整理した良いものと明確に分けるためにこのように表現しています。この点もまた別に機会に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
