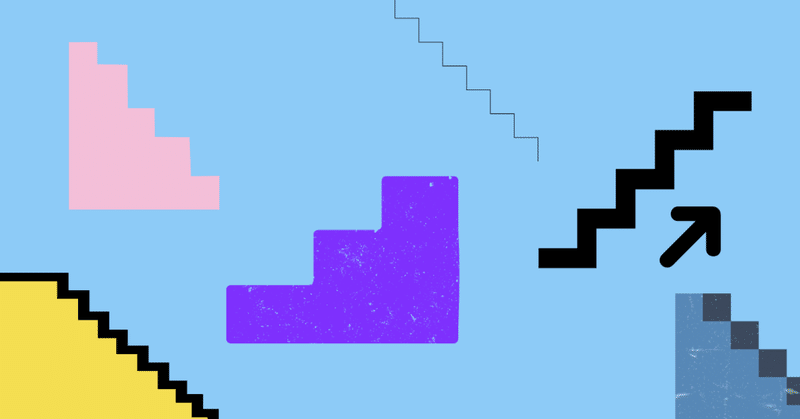
「良い」英語教師とは ②
今回は、私が目指していきたい英語教師像について。
色々な分類が出来るが、前稿で説明した以下の4要素に分けて、「どういう状態が『良い』のか」を自分なりに纏めたい。(なるべく簡潔に…!)
① 「教職」として求められる資質能力
② 授業で求められる資質能力
③ 英語教授に関する知識と教養
④ 検定試験で測れる英語能力
最初にお伝えしたいのは、現在の私は、2年半の教職課程を終えようとしている英語教師未満の普通の主婦だということである。
言うなれば、母親の身体からもうすぐ外の世界へ出てこようとしている胎児が、
「生まれたら何しようかなぁ~どんな人間になるのかなぁ~、ウキウキわくわく♡」
と胸躍らせている状態にほぼ等しい、と思う。
(胎児が実際そんな気持ちを抱くのかは不明だが)
なので、以下もそんなウキウキわくわくアラフォーベイビーが小躍りしながら書いている程度のもんと思って頂けたらこれ幸いである。
① 「教職」として求められる資質能力
「教職」として求められる資質能力は多岐に渡る。
教育に対する熱意・情熱はもちろんのこと、生徒理解や、適切なコミュニケーション力等…。
教師としての根幹部分なので、必要な資質能力は全て兼ね備えてるべきであると思う。
その中で、私が非常に重要だと考える能力は「エンパシー」である。
・エンパシーの高い教師
「エンパシー」とは?
以下の通り、辞書には「他者の感情・経験等を理解する『能力』」とある。
empathy: the ability to understand another person’s feelings, experience, etc.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/empathy?q=empathy
能力である以上は、自分の意識や努力次第で高めることが出来るのだ。
作家ブレイディみかこさんの息子さんは、エンパシーとは「他者の靴を履くこと」と中学校のテストで解答したそう。
( 著書「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」より)
感情ではなく、理性的に「他者の靴を履く」こと。
それがどんなに臭くて汚くても。
学校においてエンパシーが最も必要とされるのは、対生徒に関してである。
色々な特性、興味、経験を持つ生徒1人ひとりに対して、想像力を働かせながら生徒の姿を正しく捉えることが出来るか。
決して生徒に対しての感情や思い込みで判断するなど、「自分の靴」に生徒を引きずり込むのではなく。
エンパシーは、生徒との関係づくりに必要な土壌づくりの役目を果たすと思う。
対同僚においてもエンパシーを働かせることは非常に有効であろう。
( 私は、クラスの雰囲気と同じくらい、職員室の雰囲気を大切にしたいと個人的に考えている。長くなるのでまた別稿にて…。)
学校には多様な教師が存在する。
経験値や教授スタイルが多様だし、学校・学年・教科目標の中には定量化できないものも多いので、各教師の考える方向が多様になることもままある。
( これは今お手伝いしている公立中学校の様子から体感している )
そんな中、同僚との意見や考え方の対立がある場合も、一旦自分の靴を脱ぎ捨てて、他者の靴を履いてみようとする。
それは結局、自分の思想を広げるということに繋がる。
自分の靴が脱げなければ他者の靴は履けないということだ。
そして逆説的に、自分の靴に頓着しない人は自主自律の人だということでもある。
簡単なようで難しいエンパシー。
この能力の達人になるには、日常的に意識したり、学習したり、経験値を高め続けたり、相当高い壁を上る必要がありそうだ。
でもここは新米英語教師 ( 未満 )、まずは、自分の価値観や考えに固執しすぎないように意識することから始めていきたい。
特に私は社会人経験者なので、社会での当たり前を学校に押し付けたり、今までの経験を以てして生徒に誤った形で接したりということを、無意識にしてしまうかもしれない。
ひとまず、自分の靴は半分くらい脱げた状態でスタート地点に立っていたいなと思う。
② 授業で求められる資質能力
・生徒の「なぜ」に適切に応答できる教師
AIを筆頭とした科学技術の進歩によって、英語力がなくても国際社会で活躍できる時代が来るかもしれない。
そもそも今現在だって、みんながみんな英語を話せなくてもいい。
「じゃあなぜみんな英語を勉強しなきゃいけないの?」という声が聞こえてきそうだが、その問いに対して私は「批判的思考を高めるためには絶好の科目だから。」と答えたい。
これからの時代、英語が話せなくても、批判的思考は必須である。
生成AIで出てきた答えをそのまま鵜呑みにしているような生活をしていたら、いつかAIに支配される人間になっていくだろう。
大事なのは「膨大な情報を批判的に捉え、自ら取捨選択する力」「その思考を的確にアウトプットする力」だと考える。
そのため英語が嫌いな生徒にも、英語という科目を大いに活用して批判的思考力を高めてほしいと願うし、そのための様々な仕掛けを授業内に散りばめられる教師でありたい。
そして、授業内で出てきた生徒の「なぜ」に対して適切な応答をする。
「なぜ」は、今向き合っている物事 ( 例えば教えられている文法事項 ) を違う角度から見ようとする姿勢から出る言葉だからだ。( まさに批判的思考 )
受け身の姿勢で授業を受けているだけでは、この言葉は出てこない。
「なぜ」に対する教師の応答によって、生徒の英語に対する興味・モチベーションは良い方向へも悪い方向へも変化するであろう。
教師は「モチベーター」としての役割も大きいと考えるので、いかに生徒の興味を掻き立てられる応答をするかが重要になってくると思う。
そのためにはやはり、日頃からの生徒理解や、英語という言語に関する知識・教養が必要になってくる。
簡潔にと思いながら毎度長くなってしまう…。
③ 英語教授に関する知識と教養、④ 検定試験で測れる英語能力については次稿に書き納めたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
