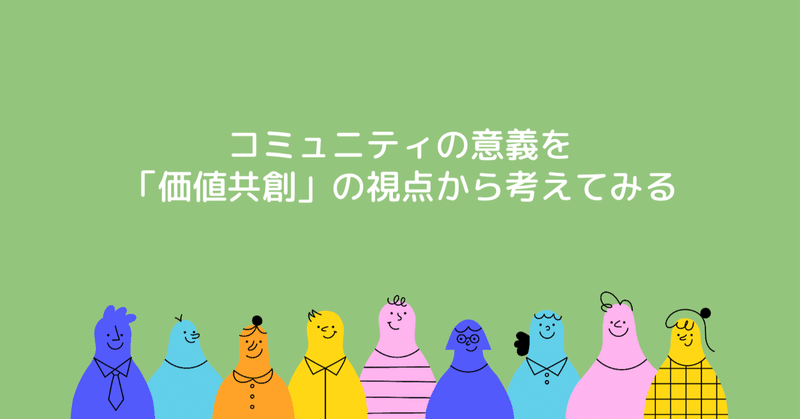
コミュニティの意義を「価値共創」の視点から考えてみる[4]:価値共創の場としての「コミュニティ」
※このブログは、コミュニティマーケティングAdvent Calender 2023 の12/15分のエントリーです。
前回は、価値共創について書きました。4回目にしてようやくコミュニティの話が出てきます(お待たせ!)。
価値共創を生み出すための必要要件
ここでもう1つ図をご紹介しましょう。

「価値共創マーケティング - デジタルが可能にする顧客との新たな価値の創り方」
これは、日本における先行研究として、岐阜聖徳学園大学経済情報学部教授 / 広島大学名誉教授の村松潤一先生がValue-in-Context(文脈価値)向上の一連の過程を4Cアプローチという理論によって整理したものを、Monitor Deloitte 社が同社のレポート「価値共創マーケティング - デジタルが可能にする顧客との新たな価値の創り方」内で図式化したものです。
ここでは、価値共創の本質として①体験プロセスに入り込むために顧客と接点を設ける、②企業と顧客双方向のやり取りによって③スキルやナレッジを交換することで、④顧客の文脈価値が高まっていくという流れがこの4Cの説明です。
このうち、①〜③は、④顧客の文脈価値を高めるためのプロセスで、①のContact(設定)は、顧客1社1社とそれぞれ構築することもできます。ただそれではリソース面でも限界がり、リバレッジが効きません。それを解決するのが、複数顧客が同じ場に集まり、他社との価値共創を追体験することができる場としての「コミュニティ」だと思うのです。
コミュニティは、他社の価値共創を追体験する場
初回で書いた認知の限界と限定合理性は、製品/サービスを提供する企業側はもちろん、顧客側も同様です。お互いが個人あるいは組織の中で、より合理性の高い意思決定をしようとしますが、組織の中で得られた情報だけで果たして合理性が高いのか実際はわからないということに薄々気づいています。
また、企業は顧客に対して一方的に価値を提供できません。あくまでユースケースを提案するだけで、提案した価値を価値共創を通して顧客がどう受け止めるのかは顧客によって異なります。

例えば企業と顧客の1on1ミーティングの場合、その顧客の文脈価値は確認できますが、別の顧客はまた別の文脈価値を決定しているので、顧客の数だけそれを繰り返さなければなりません。また、企業主催のセミナーには多くの顧客(潜在含む)が集まりますが、基本的には企業側が話すだけなので、企業から一方的な価値の提案をしているに過ぎません。
では企業コミュニティはどうでしょうか。コミュニティの場合、それぞれに異なる文脈価値をもった顧客が集まります。これにより企業は、様々な顧客との価値共創によりそれぞれの顧客が決めた文脈価値を効率的に把握することができますし、顧客は、企業と別の顧客との価値共創(別の顧客が決めた文脈価値)を追体験することができます。
特に大きいのは顧客が他社との価値共創を追体験できる、という点で、これは個別の1on1や企業主催のセミナー等ではなかなか実現することができません。
1つめの記事の、認知の限界性から企業体を超えたつながりが必要になるのではないかという流れから、コミュニティは、企業にとっても顧客にとってもより合理性の高い意思決定をするために、企業と顧客の価値共創を追体験する場であると思うのです。
これまで書いてきた内容をベースに、言いたいことをまとめるとこんな感じです。

企業にとっては、マーケティング活動上で重要な顧客理解・顧客育成・顧客創造につながります。また、コミュニティから得られた新たなインサイトがイノベーションの源泉となり、企業が向上した価値の提案をおこなうことによって新たな価値共創が生またり、戦略の意思決定のバックアップとなる可能性があります。
顧客にとっては、他社との価値共創を追体験することにより、自社の意思決定の合理性が高まったり、新たなアイディアの創出につながります。企業 / 顧客の両者にとってメリットがあり、そしてそれを可視化・具現化できる場がコミュニティであると考えると、どんな企業にとってもコミュニティは、高付加価値経営を実現するための近道にも見えてくるのです。
さいごに
企業が主体となるコミュニティは、スタートアップやIT系SaaS企業などで活発に取り組みが広がってきているように見えます。継続してサービスのアップデートを続ける(=向上した価値を提案し続ける)SaaS企業は、継続して価値の共創がしやすい環境ですし、風土文化が異なる企業からの転職組が多いスタートアップなどは、元から異文化コミュニケーションが前提なのでコミュニティという概念を取り入れやすいと思います。
ただ、私は日本の伝統的中小企業やレガシー企業にこそ、コミュニティが広がったら良いなと思います。冒頭で私の関心対象について書きましたが、終身雇用制がまだまだベースとなる日本で、企業や組織の同質性が高まっているようなケースの場合、最初は組織を越境した社内コミュニティでも良いですし、顧客として外のコミュニティに参加するでも良いですし、いずれにしても新たなイノベーションの源泉をコミュニティを通して見つけることができるようになったら良いなと思うのです。
長い文章おつきあいいただいてありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
