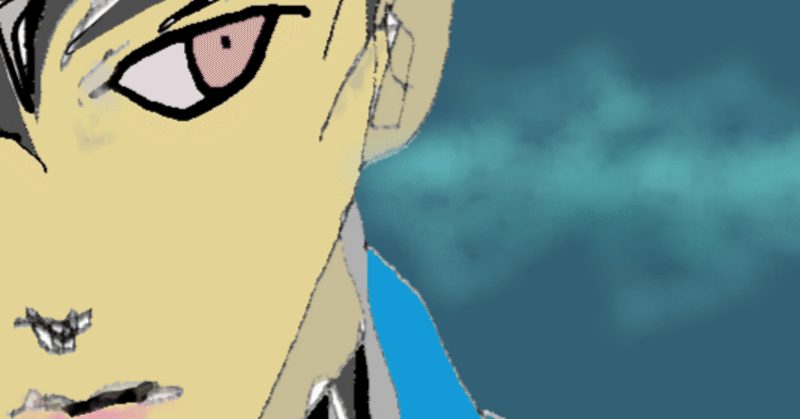
本を書く✧♡
父自身の本、父について書かれた本、まとめて4冊が家にあった。
1冊はある青年が出版した本。
2冊は母が出版した父の本。
1冊は父の友人である小説家が書いた父の伝記。
38歳という若さで肺結核で亡くなっている父だから、自分で自分の本を出版するということはできなかっただろう。
1冊目。「アイモゴ記」。
東京の青年が、古本屋で秋田文学の古雑誌を見つけて、そこに載っていた父の小説を出版したいと思い、自分で自費出版したという本。
その石川さんという青年は、ずっと母と手紙のやり取りをし、子供の我々にも、時々不思議なプレゼントをくださった。
父の小説の何が、そんな石川青年の心を捉えたのであろうか?
その後、母は、そんな父の本を2冊、自費出版した。
2冊目。「津軽平野」
3冊目。「狐のいる村」
いずれも、母の育った村を舞台とした小説や、詩、日記などが掲載されている。教師として働いていた母が、なにやら土日、知人と毎週、家の応接間で、編集会議を開いて、活動していることに、子供心ながら気づいていた。
嶋先生という人だった。
その頃、高校生になったばかりの姉と中学生になったばかりの私は、喫茶店の珈琲文化の洗礼に会ったばかりで、豆から珈琲を入れることとか、生クリームを浮かべたウィンナー珈琲というものを作ってみたりと、いろいろ楽しく模索していた。
今日も、午前中から、応接間で会議をしている母と嶋先生のために、姉妹2人で心を込めて、ウィンナー珈琲を運んだ。
でも、何時間経っても、2人は珈琲を飲むわけでもなく、ずっと編集会議を続けているようであった。
2人が冷めても手をつけていない珈琲を見て、びっくりした。
つまり、2人はそんな珈琲に手を付ける間もなく真剣に編集会議をしていたということだ。いったい、朝から午後まで、2人は同じ姿勢で何を話していたのだろうか。それはたぶん、父の原稿の話だろうと思う。
自分がその時の母と同じ年齢になった時、自分のシゴト以外に、土日にそんな誰かの本の編集会議とかとてもできない気がした。
普段の仕事だけでへとへとだったからだ。
母は、自分のシゴトをする傍ら、父の本を作っていた。
それはいったいどういう気持ちだったのだろう?
母が作った本は、自分が何歳になった時からあったのだろうか。
中高生の頃だと思われる。父が書いた小説は、母の生まれた村の小説で、母の実家である公の家の村の大きな精米所の物語だった。
父はそこの精米所の帳場として数年働いた。
その時の小説である。
小説でもありながら、どこか実話でもある。
そんな話だ。
中高生である私は、父の書いた小説にあまり興味を持たなかった。父の書いた小説は農民文学というジャンルだったので、なんだかつまらなそうと思って読んだことが無かった。
ところが、ある時、母の弟である、叔父が亡くなった。
母の実家の当主である叔父の死である。
突然、一週間、母の実家で過ごすことになる。
実家で、母は、「先生」と呼ばれ、葬儀に来るいろいろな村の人から慕われている、一目置かれていることが伝わってきた。
よく聞き取れない津軽弁で話す、母の故郷の人々。
「おめだのあぐだのとさ」
ええええ?今、何と言った?
数回言われて、やっと言葉の意味がとれる。
「お前の家の秋田の父さん」と言っていたのだ。
自主的に集まって、自分たちで葬儀の料理を作る女たち。
「わの練りごみ、かねが~」と鍋を持って提供するあば。
(練りごみという片栗粉でとじた野菜の煮物を提供する年取った女性)
聞いたことも見たことも無い津軽弁の洗礼を受けた。
面白い。地元の人の元気な津軽弁は面白い!
叔父の葬儀から帰って、父の小説を読む気になり、読んだ小説の面白かったこと!母に、この人はあの葬儀の時に出会った、あのおじさんだね?と確認しながら、登場人物のすべてが実在する小説を読んだ。
そして、父の書いた小説を初めて読んだ高校生の時に、初めて父がいないことが悲しくなった。きっと父が生きていたら、面白いユーモアにあふれた人で、私に色々なことを教えてくれただろう。こんな面白い人と出会えなかったことが悔やまれてならない。
でも、母は、そんな父を娘たちに出会わせたいと思ったのに違いない。
だから、自分のシゴトだけでも忙しいあの時期に、自分の休日を返上して、父の本を編集し、作り上げたのだ。
父の本があったから、私は父に出会えた。
母の作った本の答えを受け取った気がした。
でも、そんな父の本を持つ私は、自分が本を書くならどのような本か、まだわからないでいる。
本を書くなら私は誰のために?
