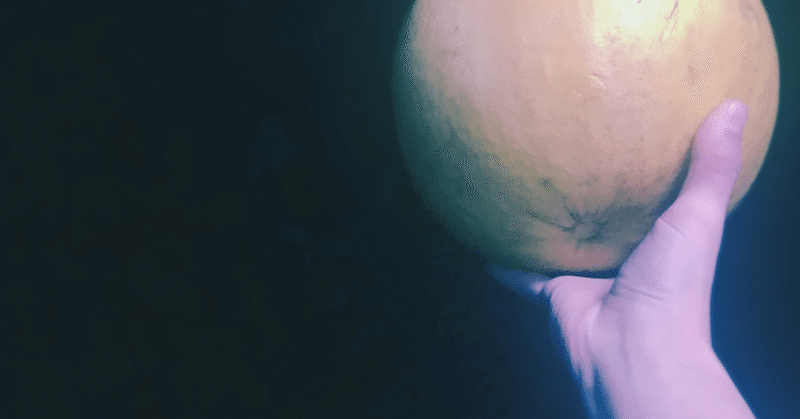
つぎはぎの歌
とてつもない頭痛で目が覚めた。少し遅れて、二日酔いか、と思い当たる。昨日は五〇〇ミリリットル缶を三本開けたんだっけか。
上体を起こすと、鈍い痛みのある背骨からぽきりと音がした。布団にしてはやたら冷たいと思ったそこは滑らかなフローリングで、どうやら寝落ちてしまったようだ。傍にあった発泡酒の空き缶が、からんからんと転がる。
床の上に腕を這わせて、スマートフォンを探す。真四角の機械の、無機質な冷たさに触れると、この上なく安心する。まるで赤ちゃんのおしゃぶりだ。
目が覚めて一番最初にやることは、もちろんツイッターだ。みんなそうだと思う。
まずは自分ホーム画面で、昨夜の発言を見る。お酒を飲んだ夜は(そもそも飲まない日の方が希少だが)自分が何をつぶやいたのか、ほとんど覚えていない。
『今日も五限とサークルサボって酒盛り』
『あのクソ野郎、ほんとぶっ殺してやる』
『人生、虚無だぜ、虚無』
『タバコも酒もうめぇなぁ』
ピントがぶれっぶれの缶ビールの写真が付いたツイートたちが、女子大生の、というかあたし自身の発言とは思えなくて、また気だるさに襲われる。黴やら埃やらがこびり付いた汚ねぇテーブルの上の、安いタバコを咥え、火をつける。ジュボッ。百円ライターの、今にも死にそうな軽い音が好きだ。
ラインの通知は十三件。遠くに住んでる両親からの安否確認が二件。ミスドの広告が二件。ソーシャルゲームのイベント通知が三件。
『萌南(もなみ)さんへ』
『今週末の教会バザーのステージ、ソプラノが足りません。出欠を早く出してください』
アイコンにしている焚き火の写真みたいな、水をぶっかけたら消えちゃいそうな、簡潔な業務連絡。思わず、げっ、て声が出た。
久々に連絡してきたと思ったら、そんなことか。
画面のアイコンに向かって、思い切りタバコの煙を吐きかける。なーにがミサだ。てめー、実家は筋金入りの寺じゃねーか。浄土宗の。
フリックしようとした指は少しだけ宙を彷徨って、テーブルの上の灰を潰す方向に落ち着いた。
火をもみけして、グリズリーみたいにのそりと立ち上がった。壁の時計は十時半を指しているが、電池が切れてからはただの置物と化している。だが、陽の高さから推測するに十二時を過ぎたあたり――つまり三限の授業まであと一時間といったところだろう。高等遊民であるあたしたち大学生にも、野生でサヴァイブしていた頃の遺伝子が受け継がれているのだと、こういう時にあたしは思う。
三限は先週ブッチしてるから、ノートとレジュメ見せてもらわんといかんな・・・・・・なんてことを考えながら、ユニクロのマネキンが着てそうな、無難で人畜無害そうなワイシャツとジーパンに着替える。
時計の電池、変えなくちゃあな。顔の浮腫みのせいで一重になってしまった瞼を、アイプチで押し上げながら考えた。単三電池って生協にあるっけ? コンビニには? 振り子のついたニトリの時計は、お値段以上のデザイン性で、なかなか捨てることができない。まあ、化粧する度に考えてることなんだけどさ。
そういえば、この時計の振り子のリズムは、BPMが綺麗な一四〇の、二拍三連なんだっ
て、笑ったことも、あったっけ。
火曜三限は社会学の講義だ。いつも自分のゼミに篭っては村上春樹の小説におけるあの特徴的な比喩だの、「こゝろ」における欲望の模倣について論じている研究室ヤドカリのあたしも、この授業だけは他のゼミの子と一緒になって、様々なグラフやら論文やらで、社会の姿をこねくりまわし、ときには何らかの社会の様相を、持ち前の読解力と文章力でもってでっちあげたりしている。
「滝田(たきた)」
「おー、モナちゃん」
滝田は講義室の一番後ろの席に座って、鞄から出した教科書を、潔癖なまでにきっちりと揃え、机の左端に寄せている。
滝田ほむらは友人の一人で、言語学を専攻している。同じ学部と部活だからおそらく似たもの同士なんだろう、ゼミの時間以外はほとんど一緒にいる。月曜日の夜に酒を浴びるほどのんでも、火曜日の朝に惰眠を貪っても、あたしの単位が守られるのはひとえに彼女の尽力によるところが大きい。
「またお酒? 顔色悪いよ」
先週のノートのコピーを差し出しながら、滝田が言う。彼女の隣の席に滑り込みながらそれを受け取る。
「それ以外にある?」
「体に悪いよ。タバコも始めたでしょ? 服に匂いついてるよ」
まじか、と、ワイシャツをつまんで鼻に近づけた。よく分からないが、それはきっと、私が頭の先からつま先まで煙に付きまとわれているからだ。修学旅行で行った浅草寺では、浴びるとご利益のある煙をみんな喜び勇んで被りに行ってたってのに、なんだってタバコは駄目なんだろうな。少なくともあたしのストレスにはご利益があるぜ。
頭の中でどれだけ言い訳をこねくり回しても、滝田が言うならば詮無い。あたしはタバコ臭いのだ。
「つーか、今週のバザー。部長に出欠出せって怒られたんだけど」
ニコニコ動画のカテゴリランキングをスクロールしながら、あたしはへらへら笑って見せた。
「まだ出してないの?」滝田は目を丸くする。
「ソプラノ足んないんだって? そんなんあいつがやりゃいいのにな、知ったこっちゃねーっつの。あたし、休部中だぜ?」
休みなのに引っ張り出してくるなんて、どーゆー了見だっての。そう言いながらも頭では静かに考える。あたしは部長のことになると、途端に口が悪くなる。まるで、「あいつを罵倒しないと出られない部屋」に入れられたみたいだ。
教授が部屋に入ってきて、講義が始まる。先週いなかったせいで、話の内容は全く分からない。
まっさらなホワイトボードに、ミミズみたいな教授の板書が這っていくのを見ながら、確かに、あたしは部屋にいれられているなと思う。失恋っていう、とてつもなく深くて抜け出せない部屋。
大学生になりたての頃の記憶は、もうあんまり無い。と言っても一年半くらいしか経っていないけれど、その間も世界は変わっている。少なくとも、大学内の喫煙所がのきなみ閉鎖になるくらいの時間は経った。
萌南さくらという一九歳の人間は、世間知らずで、自分の周りで息をしている人間は全て善い人で、同時に尊いものだと信じていた。 真っ白なあたしは、数あるサークルの中から合唱部を選んだ。どうしてかは分からない、過去のツイートでも遡ったら、それらしい文言にぶち当たるのかもしれないけれど、病みちらかした自分とご対面する度胸はない。
部長............暮樫(くれがし)たたらはそのサークルの、工学部の同級生だった。
「某、なんて変な苗字だよな」
と、彼は新入生歓迎の飲み会でぼそりと言った。今思えば彼なりのジョークだったのかもしれない。なんにせよ暮樫たたらは、それ以降自分から口を開くことなんてなかったから。
中学の頃から合唱をやっていた暮樫たたらは、存在そのものが合唱の為にあるみたいだった。歌を歌う為に酸素を吸って、音を出すために仕方なく二酸化炭素も一緒にばらまいているような。大きな体を一生懸命揺らして、何かを生み出していく姿に憧れた。あたしには、そんな風に情熱を注げるものなんて持ち合わせていなかった。
十九になった年の、一番雪が降った日に付き合い始めて、桜の開花宣言がされた時期に別れたから、暮樫たたらとの思い出はいつだって冬の景色の中だ。でも本当に好きだったんだ。別れ話をした時、彼が運転する車の窓から差し込んだ熱が痛かった。
そうしていつのまにか、サークルからも足が遠のいた。暮樫たたらとの口の利き方を忘れた。
その癖に部活で知り合った人とも、暮樫たたらとも赤の他人になってしまうのが嫌で、退部ですらもなかなか踏ん切りがつかない。今や、滝田だけが唯一のパイプラインだ。
部員なのか部外者なのか、その絶妙な境界線の上を、絶えず行ったり来たりしている。
ヒットソングの歌詞みたいに、あたしはどこにも行けないままだ。
「そうだ」
講義が終わった後に立ち寄った学食で、海藻サラダを咀嚼しながら、滝田は鞄からCD-Rを取り出す。
「これ、先月の独唱会の音源。部員には配ることになってるから、モナちゃんにも一応」
「そういや、もうそんな季節か」
独唱会っていうのは、年に一度それぞれが自分の好きな歌を持ち寄って、独りで歌うイベ
ントだ。言わばマイクにエコーがかかってなくて、選曲がやたらイタリア民謡に偏りがちな陰キャ向けのカラオケである。
CDケースに触れた自分の指は、血管の中で軟体動物が暴れているみたいにどくどくとうねりをあげていた。
この中には部員一人一人の歌声が録音されている。
もちろん、暮樫たたらの声も。
「そーいや、話変わるんだけど」
滝田はデザートに108円の杏仁豆腐をつけるかどうか迷いながら言う。
「暮樫くん、好きな子できたって」
へーっ。
あたしは、同じように自分のデザートを杏仁豆腐とプリンのどちらにするか悩む振りをする。いかにも「そんなことどーってことないよ」って感じで。
「二年の巻幡さん、知ってるでしょ。あの子がツイッターで『芋けんぴたべたい』って言ったら、暮樫くん、翌日練習に芋けんぴ持ってきたんだって」
滝田は早口でまくし立てる。別に話して欲しいと頼んだわけでも無いのに。
巻幡さんはサークルの後輩だ。毎日髪をアイロンで丁寧に巻いている、目と胸が大きい女の子だ。新歓コンパで一度だけ会った。
左心房の辺りにドロドロとしたものがふき黙ってくるのを感じる。動脈硬化かもしれない、よくない感情が血管に詰まって、道を塞いでいる。
うわさ話と一緒に飛んできた唾を、さりげなく手で退ける。滝田の白い歯の間から、ワカメがだらりと垂れ下がっているのを見た。夜の墓場で動き回る影みたいな黒い海藻は、臼歯によって細かくすり潰される。ぐにゅり、ぐしゃり、ぐしゃり。喉の奥から小さく、唾液が分泌されるにちゃ、にちゃという音が漏れている。
「好きにしてもさ、アプローチの仕方が、なんか面白くない?」
滝田は透明な唾液をべたつかせて、再びサラダに箸をつける。教科書に載っていそうな、寸分違わない、正しい所作で。それを見ながら、私はまた口元だけで笑って見せる。脳みそが死んでいても、ショッキングなワードを使う口だけが動いていれば、周りは手を叩いて、おもしろい方向に世界を担いでいく。
「童貞かよってね。そりゃウケるわ」
そんなことあたしが一番知ってらぁ。
私は滝田から目を逸らし、いろはすを思い切り喉に流し込む。食道が水分で満たされるのを感じる。吐瀉物が頻繁に行き来する食道は、自らを傷つけない物質が珍しいのか、かすれた熱を発して、水が胃へ向かうのを拒もうとする。何かが、胸の辺りから、少しずつせり上がってくる。液体でも固体でもない、目に見えない何かが。
今、この水に溺れて消えてしまいたい。なんとなくそう思った......なんて、クッせぇわな。
あたしたちは大学生だから、浮ついた噂話は誰だってするし、そういう話は空気みたいに充満している。学食に百人の大学生がいたら、九十八人はそういう話をするだろうし、残りの二人だってこっそり耳をそばだてている。陰キャだとか陽キャだとか、そういう分類は、あんたの前世がゾウリムシか否かってくらいの些末な要素でしかない。なんてったって我らは華の二十代で、繁殖期だ。どいつもこいつも繁殖することしか考えてない。学生の八割六部八厘くらいが、繁殖する片手間で勉学に励んでいるようなものだってことくらい、スタンフォード大学の研究結果を参考にしなくても分かる。
とはいってもだ。
暮樫たたらに好きな人ができた、というビッグニュースは、血管を通じて体全体を駆け巡り、講義が終わるころには動悸や喉の渇き、涙腺の緩みなどの様々な症状を、私の体に引き起こしていた。
帰宅するやいなや部屋の中に倒れ込んだ。頬に当たったフローリングが冷たかった。異なる時間の同じ場所、この座標上に暮樫たたらの体があったことを思い出す。
別離ってもんは、苦くて、いつまでも尾をひくようなものだと思っていた。あたしが暮樫たたらのことをずっと考えるようように、暮樫たたらもあたしのことをすこしでも考えてくれていたら良いなと思った。暮樫たたらにとっての半年というのは、あたしが思うよりもずっと長い時間だったのかも知れない。
あたしは反射的にスマホを開いた。こういうときにはTwitterで病み散らからすのが我々さとり世代の流儀だ。デコラティブに装飾された一四〇字は、フォロワーたちに消費されてコンテンツになる。それでよかった。それだけがあたしの心の傷を紛らわせてくれる。傷ついた価値が生まれる。
液晶にはニコニコ動画のランキングが開きっぱなしになっていた。
ボカロの新曲をチェックするのは、ここ十年来のあたしのルーティンだ。雨にも負けず、風にも負けず、失恋の寒さにも負けずに続けていた、呼吸と排泄と寝食とソシャゲのログボにならぶ日課だった。
最近熱いのが「人力ボカロ」だ。
ボカロ(VOCALOID)は、収録された音声を繋ぎ合わせて歌を歌わせることのできるソフトウェアのこと。初音ミクみたいな。
そのボカロの「声」を作るところから自分でやるのが「人力ボカロ」。
つまり、アニメやキャラクターソングからキャラクターの声を切り貼りした後、何らかの方法で合成して、曲を歌わせた作品を指す。音声編集ソフトを二三インストールできる程度の知識と技術、あとは愛さえあれば、「推し」が好きな歌を歌ってくれるという代物だ。
中学時代に引きこもってパソコンをいじってばかりだったあたしは、そういう技術に、周りより少しだけ強い。
何を隠そう、私もニコニコ動画に動画を投稿している、ちょっとした「人力ボカロP」なのだ。(Pはプロデューサーの略。音声合成を使って曲を作る人につける愛称だ)今まで沢山の「推し」にいろんな歌を歌わせてきた。物語の途中で死別したキャラクターには失恋ソング、二頭身のキャラクターには電波系のアニメソグ・・・・・・とか。
今日も今日とて、ランキングの中では無数の人間が、「推し」を奏でている。それを見ていると、ぐずぐずに病みきったあたしの脳みそもいくらか麻痺する。つーか尊い。マジ尊い。頭から食べたいくらいに尊い。推し、最高に尊ばれるために生まれてきたって感じ。
毛細血管にまで達した尊みが、あたしの手足をイソギンチャクの触手みたいに震わせた。
推しの尊さにもだえた弾みで、鞄の中から何かがかしゃんと、落ちた。
滝田から貰ったCDだ。
裏面のプリズムが、照明をつけない部屋の中で私を呼んでいた。
まるでRPGの、ラスボスの誘いのようだ。「私と手を組んだら世界の半分をお前にやろう」という類いの。
手がじんわりと汗ばんだ。
これがあれば、暮樫たたらが歌ってくれる。 合唱の為に存在している男が、あたしの為だけに歌ってくれるのだ。
今日の夕飯は肉じゃがということになっている。
テーブルの前にあぐらを掻く。箸を上げ下ろしするだけの単調な作業で、じゃがいもを口に運ぶ。
地元から離れた大学に進学したあたしの為に、母は毎月タッパーに詰めて食糧を送ってくる。バイトを掛け持って、奨学金を借りても金が無いあたしにとってはありがたい限りで、頭が上がらない。大学生は何かと金が入り用なのだ。徹マーしたり、酒をしこたま飲んでゲーセンでスロットを回すための金が。
母はとても旧弊的な人間だった。(田舎の人間なら大抵そうだろうけど)家ってものにがんじがらめにされていた。「どこの学部でもいいから大学に行って欲しい。そうしないと就職できないから」「女の子はいつか男の人と結婚して、子どもを作るのが幸せなんだよ」「女の子は正しい作法でご飯を食べなくちゃいけないんだよ」と、毎日のように言われて過ごした。食事の度に箸の持ち方を指摘されるので、夕飯の時間が一日で一番嫌いだった。生まれついてどんくさいあたしは、いつまで経っても正しく箸を持つことができなかったから。
床に落ちたグリンピースをつまんで食べる。埃がついていたような気がする。掃除をしなくなってどのくらい経つだろう。最近は人前で泣き出してしまわないかってことだけを気にとめて過ごしていた。日課以外、するべきことも、やりたいこともなかった。
花柄が剥げ賭けた箸でじゃがいもをつついていると、妙に煙草が吸いたくなった。愛煙家の性だな、と笑ったついでに、人参がぽろりとテーブルに落ちた。
煙草の端が赤く灯る度に、あたしは小学校の保健室を思い出す。「煙草を吸った人肺」という七厘の中の炭みたいな肺の模型が、象牙色のカーテンの側の、木製の棚の上で静止していた。あれが人間の体の中に入っていたとしても、人間の方ももう炭になってんだろーなと笑っていたのを覚えている。
あたしの肺は、この半年でどれくらい、あの黒いオブジェに近づいただろうか。自分がこんな汚い煙を体内に入れて楽しむドマゾになるなんて子どもの頃は想像もしていなかった。煙草は火を付けた最初の一口目だけが最高に美味しいのであって、それ以降はクソだ。でも、吸い終わった頃には、もう次の一口目を欲している。
食べ終わった後のタッパーを、一週間分の食器が堆積して悪臭を放つシンクに放り投げる。
鉄は熱いうちに打つのが吉だ。早速ノートパソコンを開く。
使い慣れた音声編集ソフトをいくつか立ち上げると、滝田から貰ったCDをインポートする。部員の声が記録された、いくつものWAVファイルが並んだ。ひとつずつさわりだけ聞いて、暮樫たたらの音声を探していく。暮樫たたらの声なら、吐息ひとつで特定できる自信がある。
まるで、ホラーゲームでロッカーに隠れてる主人公を探すモンスターの気分。この間見たばかりのゲーム実況を思い出す。
「暮樫たたら。テノールです」
イヤフォンから暮樫たたらの声が聞こえてきたとき、あたしは思わずうっ、と唸った。
知ってる。
暮樫たたら。
十月三十一日生まれ。蠍座。
身長一七〇センチ。
BMIに換算すると標準体重よりも少し太り気味で、それを少し気にしている。
血液型はB型。
好きな食べ物はマクドナルドの月見バーガー。
spotifyでマイナーなヒップ・ホップをかけながら蘊蓄を垂れ流すくせに、好きなアーティストはクリーピー・ナッツ。
イギリスに旅行したことがあって、バスケ観戦が好き。
そして何より、声帯が良い。
「寺山修司の『思い出すために』歌います」
暮樫たたらは、あたしの嗚咽なんておかまいなしに、曲の情報を語り続ける。あたしはその声に聞き入る。
唾を飲み、WAVファイルを編集ソフトに読み込ませる。一人暮らしのアパートだというのに、誰かに見られて居るような気がして、モニターを隠すように背中を丸めた。
生協のポンコツPCが暮樫たたらの音声を嚥下し終わると、画面にぎざぎざの波形が現れる。お弁当の中にちょこんといるバランみたいだ。
本来は決して触れられないし、見ることもできないはずなのに。
あたしは、デスクトップに横たわる暮樫たたらの声に、矢印の形をしたカーソルを宛がう。
「せ」「え」「ぬ」「が」「わ」「の」「て」「ま」「わ」「し」「お」「る」「が」「ん」・・・・・・
暮樫たたらの波形の部分部分を「切り取り」して、WAVファイルを選択。フォルダに保存。たったこれだけの作業を、五十音・拗音その他歌を歌わせるのに必要な音の数だけ繰り返す。
「ぬ」と「が」の間のくぼみは、ルビンのつぼのようになめらかだ。反対に、母音を同じくする「せ」と「え」は、まるで幹を絡ませあった二本の合歓の木みたいに離しがたい。
「ん」は口を閉じて発音する音なのでマイクに音が入っていない。くそっ、もっと口開けよ。あたしは舌打ちをする。
あらゆるソフトウェアの間を、矢印の形をしたカーソルはせわしなく動き回る。抽出が上手く行く度に、やった、と、掠れた声を上げてしまう。
暮樫たたらの声帯の、すべてを切り刻んで、明らかにする。普段は見ることすら叶わない、波形の藪の中を掻き分けていく。そうして、ひとつひとつ丁寧に、名前をつけ、保存していく。 フォルダの中に整列している「暮樫たたら.WAV」を見た。
音楽ファイルを示すアイコン。四角い紙の中に、円に囲まれた音符マークが記されているデザインだ。
あたしは理科の教科書に載っていたイラストを思い出す。薄い膜に覆われた円形の核を持つ動物の細胞。でも、そのイメージは間違いじゃ無いかも。
これらは紛れもなく、暮樫たたらの声を構成する細胞なのだ。
暮樫たたらとのデートは、ほとんど家だった。一緒に歩いている所を誰かに見られたり、噂話として消費されることが恥ずかしかったし、嫌だった。暮樫たたらが家に訪ねてくる日には、必ず料理を作っておいた。大学に入学したての頃に買ったきりだった「かんたん! はじめてのお料理」の一ページ目から、一品ずつ作って出した。六畳一間の、小さなアパートの部屋の中で、生焼けのハンバーグや、表面が炭のようになった魚を摂取した。
人間の細胞は、百日で新しいものに入れ替わるという。ということは、同じ食事を摂取していたあたしたちの細胞は、少なくとも百日間は、よく似た色やにおいをしていたのではないだろうか。
ねえ。
懸命に米を咀嚼している時に、暮樫たたらはテーブルの向こうで顔をしかめた。きちんと拭き上げたガラステーブルの下に、ストッキングに包まれた足首がある。長い間正座しているので、感覚が無かった。自分の脚じゃないかのようだった。
「なあに?」
君の箸の持ち方さあ、おかしくない?
「そうかなあ」
あたしはなんでもない顔を装って笑ったけど、背筋が冷たくなるのを感じた。いつもはこんなポカはおかさない。足首の痛みに気を取られるあまり、手の方に気が回らなかったんだ。つい、染みついた癖の通りに箸を持ってしまったらしい。脳みそに氷水をぶっかけられたような気分がして、体が強ばる。フレアスカートの裾をきゅっと握った。
正しくはこうじゃないかな。舐った箸を装着した右手をこちらに向ける暮樫たたらの口の中で、半熟卵の黄身がすりつぶされて、白く粟立っている唾液と混ざり合い、くちゃくちゃと踊った。
「小さい頃に利き手矯正したせいで、正しい持ち方わかんなくなっちゃったんだー」
あたしは馬鹿みたいに大声で笑った。どうして料理なんて作ってしまったんだろう。どうして箸なんて用意したんだろう。「馬鹿みたい」じゃなくて、あたしは馬鹿だ。正真正銘の馬鹿なのだ。
「ごめんね」
申し訳ない気持ちで、言葉だけが空中に飛び出した。暮樫たたらは、ふうん、と返事をして、また箸を舐った。
暮樫たたらの音声ファイルたちを、今度は別のフリーソフトに読み込ませる。今度は切り取った音声を合成するためのソフトで、譜面を模した画面に歌詞や音程を入力することで、その通りに音声を出力してくれる。本当に凝る人は歌詞や音程まで自分で設定するけれど、インターネットには有志が作成した楽曲のデータがあるので、ただ歌わせたいって人はそれをダウンロードすればいい。ものぐさなあたしはモチロン後者だ。
暮樫たたらに何を歌わせるかは最後まで迷ったけれど、結局、ネットで一番流行ってる曲にした。鬱アニメのエンディング曲で、生まれ変わったらまた君と一緒にドーノコーノみたいなやつ。
ダウンロードが済んだら、暮樫たたらの音声に合うように、タイミングなどの微調整を行う。
別々の所から寄せ集めて作られた歌は、でこぼこで、いかにも機械音って感じだった。引き延ばされた「あ」は夜中にお墓から聞こえてきたら確実にちびる。逆に「い」は無理に音程をそろえたせいで、下手くそなミッキーマウスの物まねみたいだ。音程を上手くそろえられなかった「に」が、「な」の後ろからひょっこりと顔を出す。これが暮樫たたらの声だってことに気づく人はいないかもしれない。
でも私には、目の前で歌う暮樫たたらが見える。背筋をぴんと伸ばして、空を飛ぶ白い鳥のように心地よさそうに空気を振動させる暮樫たたら。彼はラブソングを歌う。彼が語る喪失の悲しみに、私は恍惚とする。脳みそがちかちかした。瞼の裏を、蝋燭の火のような、ぼんやりとした光が、行ったり来たりを繰り返していた。
暮樫たたらとの無数の記憶が、沸点に達したお湯のようにぽこぽこと吹き出してくる。一緒に誕生日を祝ったこと。海へ行ったこと。経験したことの無い無数の景色は生きている。あたしはその光景をずっと前から知っている。それらは全て、あたしの中にずっと前からあった景色だ。
やっと会えた、とあたしは言った。いつのまにか涙が零れている。くたびれたパーカーの袖で目尻をぬぐうと、ノートパソコンを胸の中に抱き寄せる。
プレイヤーのリピートボタンを押して、あたしはベッドに横になる。彼が話しかけてくる。イヤフォンを耳の奥までぎゅっと突っ込んでるっていうのに。
「このドラムは120くらいかなあ」
「100くらいじゃないの」
彼は右手で四拍子を取りながら、BPMを数えてみせる。
「そっかあ」
「そうだよ」
彼が笑う。つられてあたしも笑う。
「あたしにはやっぱり、合唱なんて向いてないみたい」
「そんなこと、もう関係ないさ」
脚を抱えて小さくなると、モーターの生ぬるい風があたしの髪を撫でた。
そうだね。そんなこと、もう関係ないね。
あたしの体温と同じモーターのぬくもりに、ひそやかなささやきに、ついまどろんでしまう。
目が覚めたら、退部届を書こうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
