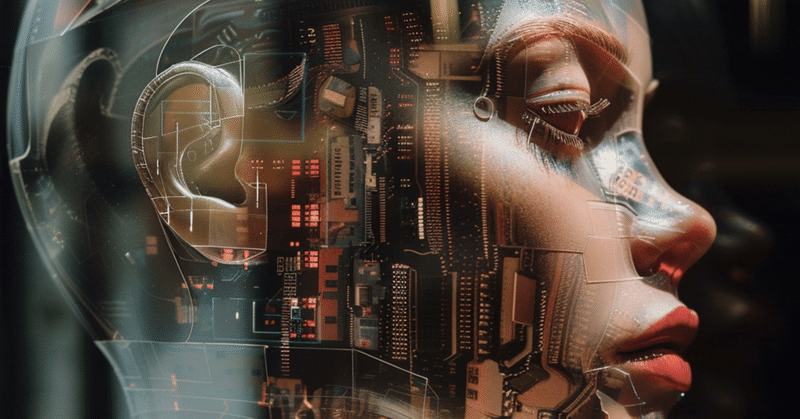
人間がやるべきことを整理してみる
どーも、福元彩です。
AIアートを制作したり、デザインや物語制作の勉強をしたり、あれやこれやとやっておりまして。
その中から、体験した出来事や考えていること、日々学んだことなどを共有しております。
今日は「使うところを考える」というお話しを。
またまた進化しちゃったAI
open AIが「gpt-4o」を発表したことが世間で大騒ぎになっておりますが。
質問に対する回答の速度がgptー4tuboより2倍早くなったりだとか。
音声認識機能も格段にアップして、同時翻訳もかなりのレベルで行うことができたりだとか。
AIの進化がとどまることを知りませんねー。
このままだと、落合陽一さんが2025年にくると言っているシンギュラリティが早まっちゃったりして。
そんなAIの進化にワクワクしつつも、改めて「人間はAIとどう関わっていくべきなのか?」を考えないといけないなぁと感じています。
特に「生成系AI」と言われるものが台頭してきてからというもの、「クリエイティブ」というものの概念が覆されてしまっているわけで。
ここはしっかりと向き合わないといけない問題だと多くの人が感じているんじゃないでしょうか。
どこに使うのか?
そもそも、「クリエイティブ」というものの要素を分解してみると
設計図を作る×良いアウトプットを作るスキル×試行錯誤の回数
この掛け算で出来ています。
この要素の中で、今までは右の2つに膨大なコストがかかっていたけど、生成系AIによってそれが大幅に縮小されるとしたら、新しいクリエイティブの可能性が広がるわけで。
どうやら、やっぱり「生成系AI」というものは使った方が良さそうですよね。
じゃあ、どこに使うのか?
まず、この要素の中で人間が関与するところはどこなのかを考えてみると、、
「設計図を作るところ」は、人間がやる必要がありますよね。
ですが。
アウトプットに関してはAIも人間も出来てしまうわけで。
しかも、AIの方が圧倒的なクオリティのものを圧倒的なスピードで仕上げてきます。
「じゃあ、AIに作らせちゃえばいいじゃん」となりそうなところですが、実はここにこそ人間の手を加えるべきだと思っていて。
確かに、AIがアウトプットしたものは凄くクオリティが高いかもしれないけど、「そこに感動が生まれるのか?」というと…
「ふ~ん」で終わりそうじゃないですか?笑
それって恐らく、「AIがプロセスを見せられない」ということが原因だと思っていて。
#だっていきなりアウトプットしちゃうから
対して人間は、出来上がるまでの過程が山程あるので、それを知ることで感情移入して感動に繋がるんじゃないかなと思うんですよね。
そここそが「AIとの差別化ポイント」なわけで。
となると、人間がやるべきことは「設計図を作る」ことと共に「アウトプットすること」だと思うんですわ。
#ですわ
「設計図を作ってから最終的にアウトプットするまでの試行錯誤にAIを使って、色んなパターンを試してブラッシュアップする」というのが1つの正解なんだろうなと個人的には思います。
そんなこんなで、AIの進化に伴ってAIとの付き合い方をもう一度考えないといけないよねーというお話しでした!
何かの参考になれば。
では、また!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
