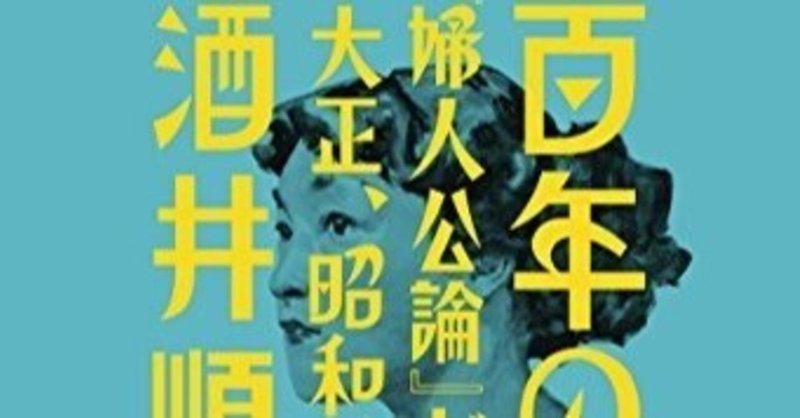
百年の女『婦人公論』が見た大正、昭和、平成
■ 感想

「百年の女『婦人公論』が見た大正、昭和、平成」酒井順子(中央公論新社)P414
大正五年に創刊された『婦人公論』を通して見る、女の100年史。歴史を紐解き、日本女性がどう生きてきたか、何と闘ってきたのか、414Pとなかなかのボリュームの本書を読み終えて思うことは、これだけの情報をこのサイズに纏め上げるなんてという驚き。圧巻のストーリーテラーぶりに昂奮冷めやらず、心の中でひとりスタンディングオベーション状態。
100年前の憲法下において、女性の権利は無いも同然。男性に隷属する第二の性であり、政治は愚か意見を口にすることも憚られた。そんな不遇の性としての人生しかなかった時代、世の女性に向けて「女性解放」を呼びかけた平塚らいてうたちのペンは、まさに剣よりも強し。
しかし与謝野晶子、伊藤野枝、神近市子など、時代を切り開いた女性たちが活躍した頃創刊した「婦人公論」は当初、「現代婦人の卑俗にして低級なる趣味を向上せしめ」などと新しい女性たちの為の雑誌とは云えないものだった。女性を侮蔑した内容の多さに、福沢諭吉は「男にとって都合よく女を従わせようとしているだけの書」とばっさり。流石、一万円札になる人は違う。これからも永遠の推しです!と心に誓いながら、時代は大正デモクラシーへと突入。
伊藤野枝、大杉栄、神近市子の、美は乱調にありが展開され、白蓮、波多野秋子と、政治的大変革と共に自由恋愛解禁で、今の時代のようにスキャンダルが紙面を賑わせ、近松門左衛門の心中ものが大流行となり世間で心中が多発し始めるって、ドラマや本の影響で部活や仕事を決めました、なんて話とは訳が違う。法律的に結婚相手を自由に選ぶことが難しく、女性には「姦通罪」があったからとはいえ、「なら死にましょう!」と多発してしまうとは、大正の時代の人の恋愛は濃度が特濃。
発言も今のように多角的に配慮…などは無縁の為、波多野秋子、有島武郎の両名の遺体が発見された時に伊藤野枝は「婦人に対して私が感じたのは、軽蔑と反感でした」と、ジェイン・オースティンのタイトルかのような厳しい言葉を連ねた。が、その後「甘粕事件」で伊藤野枝が憲兵に虐殺された時には、平塚らうてうに痛烈なコメントを書かれるという大ブーメラン。
そんな濃厚な大正を経て、満州事変、五・一五事件、二・二六事件と不穏な空気が時代を包み込み始める。戦時下に国民の戦意高揚を狙って、内閣情報部が「ペン部隊」として作家を戦地の前線へと送り、戦地ルポを書かせていたことを知らず驚いていたら、林芙美子は「是非ゆきたい、自費でもゆきたい」と従軍し、その時のことを記したのが「北岸部隊」とか。尾道で林芙美子文学碑を見た時に、「わ~、林芙美子さんだ~」と呑気に感動していたけれど、今度はできる限りの著作を読んだ上で文学碑に向き合い、記念館にも訪れたい。
そして、第二次世界大戦、日本敗戦、GHQにより民主主義国家へと現代の日本への歩みを進め、高度経済成長の時代を迎えた。平成へと時代を移すと、「成田離婚」「おやじギャル」「バブル」「冝保愛子」「サイババ」「オウム真理教」と自分でもその時代の温度感を知っているワードが立ち並び、ああ時代とはこうして繋がり、続いていくんだなあと当たり前のことながら腑に落ちる。100年の歴史と政治もきっちりとおさえながら、膨大な情報を硬軟織り交ぜて纏め上げ、社会と世相を語る酒井さんの手腕は圧巻。
そうして辿り着いた『婦人公論』100周年の記念号の特集につけられたタイトルは「100年分の幸運」。その記念号で美輪明宏さんは、「100年分の幸運がテーマのようですが、残念ながらそんなものはありません。」と異を唱え、「棚からぼた餅は落ちてこない、幸福は研究と努力で自ら掴み取るもの」と。「幸運」ではなく「幸福」。人間にとって何が本当の幸いか、人の数だけそれぞれの形の喜び、幸せ、理想があり、それが最も優しく温かな形で実りゆく人生を送れる、そんな真の自由のある国へ。いつかそんな日はくるのかと、今日の日本では憂うことばかりでも、時代とともに悩み、行動し、変革を続けてきた先人たちの本を読み、思考することを続けていきたい。
100年の女性史としてだけでなく近代日本の歴史を沢山の人物を通して辿ることができ、読み応えがありすぎて疲労感満開の労作。こんなに興奮した日本史が今までにあっただろうかと著者でもないのに万感胸に迫る、超推し本!
■ 寄り道読書

🔲『青鞜』の冒険: 女が集まって雑誌をつくるということ/森まゆみ
🔲「新しい女」の到来―平塚らいてうと漱石/佐々木英昭
🔲伊藤野枝集/森まゆみ(編)
🔲神近市子自伝 わが愛わが闘い/神近市子
🔲与謝野晶子詩歌集
🔲放浪記/林芙美子
🔲花ざかりの森・憂国/三島由紀夫
🔲大杉栄自叙伝/大杉栄
好きな作家も数多登場するので読みたい本をあげていたらきりがなく、とりあえず自分の本棚の中の積読本から近く読みたい本のリスト。
大正・昭和と、目まぐるしく移り変わる時代性を加味しても、矢張りこの時代の作家の熱量は凄まじい。表面上は平和となり、人は優しくはなったように思えるが、人情は薄らぎ、繊細さは過度を極め、全体的な平熱は低くなった。
思想の良し悪しはあれども、必死で考え、抗い、前へと進んだ時代の熱量と、強い個性を持った作家たちの作品をどんどん読んでいきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
