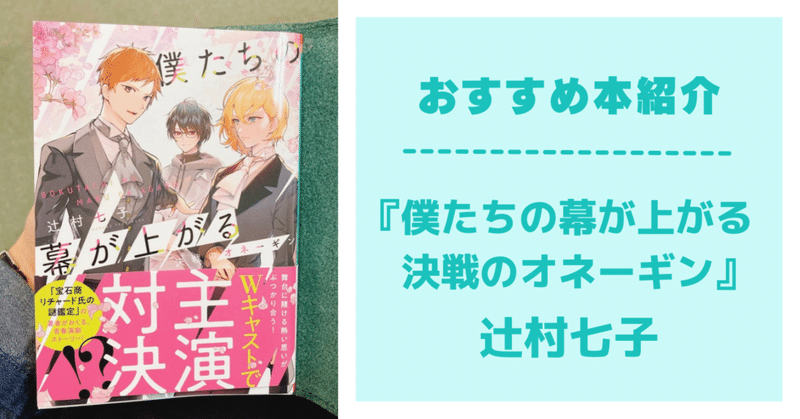
『僕たちの幕が上がる 決戦のオネーギン』――物語の持つ力、言葉の力を信じる人への祝福
今回はおすすめ本紹介の記事です! 読書感想文でもありますが、展開のネタバレは控えるよう気を付けてみました。
「宝石商リチャード氏の謎鑑定」シリーズの辻村七子先生の『僕たちの幕が上がる 決戦のオネーギン』。ピュアフル文庫から発売されています。
3月発売だったので結構時間が経っているのですが、、、まあとにかく書きます!
さて、タイトル副題付きっぽいな? と思った方もいらっしゃるかもですが、その通り「決戦のオネーギン」は副題で、今回おすすめしたい作品は『僕たちの幕が上がる』の続編作品なので、まずは1巻の紹介から入ります。
『僕たちの幕が上がる』(1巻)あらすじ
さて、ここからは略してシリーズと1巻を「僕幕」、今回の続編を「僕幕2」と呼んでいきます。
僕幕1巻のあらすじや要素はこんな感じ!
・ある事件をきっかけに芝居ができなくなってしまった元戦隊ヒーロー俳優と、今をときめく若手演出家のバディもの
・主人公は俳優の方の二藤勝、脚本家は鏡谷カイト
・1巻ではカイトは新たな劇の主役に抜擢し、勝は俳優生命をかけて初めての舞台に臨む。
・カイトが勝を抜擢した理由とは? 勝が芝居をできなくなった理由とは?
・舞台にかける夢と友情を描いた熱い感動の青春演劇バディ・ストーリー!
【読了】#僕たちの幕が上がる /辻村七子
— ハセベアツ (@hsb_atsu) November 8, 2021
好きな本は紙&電子派! 先にKindleで✌️
辻村先生の役者と脚本家の話ってことで期待しかなかったけどやっぱり抜群に当たり前に面白かった‥!
誰かが誰かの特別になること、その「誰か」が物語を通して生まれること、演じることでその「誰か」になること!→
これは当時の感想ツイートを掘り出したものです~
続きのツイートに、
・小説を読む私たちは物語の持つ力を本当に実感していて、媒体は舞台だけど『物語』がひとつのモチーフになっているから、物語やその登場人物に救われる、っていう要素はずるいくらい響く
・役者自身と演じる人物という2人の人間が1つの身体で表現される二重の構造の生かされ方が本当に面白かった。役作りとして登場人物の背景を考えさせられるとき、読者は僕幕というこの小説の登場人物の背景を知りたくなる。登場人物の謎が少しずつ明かされる期待や楽しみがあった。
と書いていました。物語を扱う物語の良さってありますよね……。
この時点で読みたいと思った方はぜひ読んでください! 文章もたいへん読みやすいです。
『僕たちの幕が上がる 決戦のオネーギン』あらすじ
さて、では続編である僕幕2の方ですが、感想に入る前に、あらすじ・要素はこんな感じ。
~あらすじ~
・勝とカイトのもとに、演劇界の重鎮から新たな舞台の話が持ち込まれる。
・演目はロシア古典文学、プーシキンの『オネーギン』。
・主演に抜擢された勝だが、今回はドイツでとある演劇賞を受賞した海山の秘蔵っ子、南未来哉とのダブルキャストだった。
~要素~
・若く生意気な未来哉の本当の想い
・自分が思う自分の価値と、与えられる価値
・現在の世界情勢においてロシア文学を扱うことに対するアンサーもあり
『僕たちの幕が上がる 決戦のオネーギン』感想
さて、やっと感想ですが、もうね、当たり前にめちゃくちゃ面白かったです。
どう面白かったかというと、キャラクターが魅力的でエンタメ性も高いし、その上、自分の価値を信じられないことだとか理不尽な出来事だとか重くて目を逸らしたくなるテーマにも真摯に向き合われていたのが、胸が熱くなる物語でした。
何かを演じる人たちの物語、やっぱり、人から人への想いが何層にも重なっているのが良いですね。
書き手から何を受け取るか、書き手の意図からは離れて、俳優が登場人物とどう向き合うか、脚本家や演出家が作品とどう向き合っているか、そして彼らが俳優に何を期待するか――。
そういう中で、今回の新キャラだった若くて生意気な未来哉、実は「自分には顔の良さしかいいところないもん!!!」「二藤勝と自分が張れるわけないもん!!!」っていう駄々っ子で、それがめちゃくちゃ最高でした。笑
カイトは勝に自分自身の価値を引っ張り上げてもらった過去がずっと昔にあって、それが1巻で勝を抜擢した理由や勝を信頼している理由にもなっているんですが、そういう背景を持つカイトが、今度は未来哉に対してお前には価値がある、と引っ張り上げる。あまりに力強い言葉だったので最後に引用を載せています。
やっぱり、誰かに救われた人間が、その経験をもって別の誰かに手を差し伸べる、という構図は熱くなるものがありますよね……。
今回はWキャストということで同じ役を演じる相手が自分以外にもいる分――かもしれませんが、自分が自分をどう思っているか、その自分でこの役にどう向き合えばよいか、っていう役者による自分との対話のようなものも多く描かれていました。
でも、「自分が自分をどう思っているか」「本当に自分が何かに値する人間なのか」っていう問いは演じる人間じゃなくても生きている限り誰でも思ってしまうことです。
自分の価値を信じられない登場人物に対してそんなことはない、と別の人物が説得するとき、読者である自分自身にもあなたは価値がある人間だよと説得されてしまうような、そんな力がこの作品を含む辻村先生の作品にはあると思っていて、今回もそうして胸を打たれてしまいました。
あと要素としてピックアップした「現在の世界情勢においてロシア文学を扱うことに対するアンサーもあり」というのは、作中でもウクライナ攻撃が発生した想定で、『オネーギン』をやるのはどうなんだ、みたいな声が上がってきたのに対して、声明を出そう、という動きがあるのです。
日本語版『オネーギン』の翻訳者の森かなえという登場人物がいて、作品自体に対する解釈だとかのサポート役として出てくるのですが、この方が声明を出すときに動きます。あまり目立たないキャラクターではあるのですが、実際にもこういうシーンでサポートしている、大きな役目を果たしている役割の方を描き、スポットライトを当てる姿勢も私はこの作品の好きなところだなあと思います。
それから、素敵なサブキャラとして、もうこの人のことみんな大好きだよなと思って「僕幕 檜山」で検索したらやっぱり愛されてるー! と思ったキャラクターである檜山さん。
これまで特に賞は取ったり目立った実績があったりするわけじゃないけど実力派な女優さんが、主演女優側のWキャストの片方として出てきます。
明るくてはっきりしていて、場を引き締めることも和ませることもあるようなそんな存在感の方。
この僕幕という作品、2巻ではハラスメントだとかそういう問題も途中で扱うんですが、これまで目立った実績がなかった理由のひとつ(あくまでも可能性だけど)に、檜山さんはそういったことにNOと言い続ける人だったからかもしれない、というのがあります。
ハラスメントが発生しているのかもしれない、という違和感に気付いたのがこの檜山さんで、動いたカイトの報告の電話で『鏡谷演出は人の痛みがわかる人ね。あなたと仕事ができて嬉しいです』(p.107)と言うような人。
あとはもう、読んでない方には読んでほしい……。
読んだ方には本当によかったよね、と肩を叩き合いたいです。
他にもたくさん語れるところはあるのですが、今回はおすすめ本紹介ということでコンパクトにまとめたかったので、そろそろまとめたいところ。。。
ここまででしっかり作品の魅力は伝わったでしょうか。
最後に、ああやっぱりこの作品が好きだ、と思っためちゃくちゃ大事なところを引用します。
でもここまでで読みたくなった人はここで読むのをやめて、作中で出会った方が感動すると思う……ので……あの、どういうことかなって知りたい方とか、もう読んだ方向けと思っていただければと思います。
読まないどこ! という方は引用形式の部分をサッとスクロールしちゃってください。やや長めです。
「(中略)役者には二つの価値があると言っているんだ。一つは商品としての価値。お客さんが判断する価値。もう一つは演劇とは何の関係もない一人の人間としての価値だ。お前はそれを一緒くたにしている。もちろん完全に分離させて考えることは難しいかもしれないが、それにしても行き過ぎだ」
「……美男でもなくて演技もしてないぼくに価値なんかないんだけど?」「ある。お前がどう思おうが関係ない。あるものはある」
「ない」
「ある!」
鏡谷カイトは大喝した。未来哉がびくりとすると謝罪したが、言葉は止めなかった。
「全ての人間には価値があるんだ。そうでなければ誰も芝居を見に来ない。人は誰も自分の背中を本当の意味で見ることはできないが、他人の背中を見ることはできる。それを通して自分の背中を見たいんだ。言っていることがわかるか(中略)お前には価値があるんだ。これはお前という建造物を建てるための土台の基礎の基礎だ。基礎のないものの上には、ピラミッドどころかあずま屋も建てられない。そこを理解した上で、仕事に取り組んでほしい」
私が読書が好きなだけじゃなくて必要だって感じる理由は、自分をいつか救うであろうこういう言葉に出会うためだって思います。
自分自身にも訴えかけられているようだ、と先に書いたのはこの部分で特に思ったことでしたが、読んでいる途中に、祝福とか祈りとか信念とか、そういうものが頭に浮かんでいました。
通院の長い待ち時間の間でやっと僕幕2を読んでますがやはり辻村七子先生の‥人間はただ生きているだけで価値があるということに対する祝福とか祈りとか信念とか‥
— ハセベアツ (@hsb_atsu) May 1, 2023
タイトルを今回「物語の持つ力、言葉の力を信じる人への祝福」としてみたのは私が上記に引用した言葉を受けて、読者に対する祝福とか言祝ぎだなって思ったからでした。
舞台という、物語によって何かを伝えようとする人間の意志や信念が、この作品をドライブするエネルギーで、そういうエネルギーに舞台じゃなくても生かされてきたなと思う方は、きっとこの物語で何か響くものがあると思います。
心からおすすめです!
ということで、今回の記事はここまでです。読んでくださったあなたに感謝です!
※辻村七子先生ファンの方でこの記事にたどり着いた方がいらしたら、宝石商シリーズの方も、これよりももっとがっつりした感想文を書いてますのでよければぜひ覗いてみてください。
マガジンと、1~4巻の記事のリンクを貼っておきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
