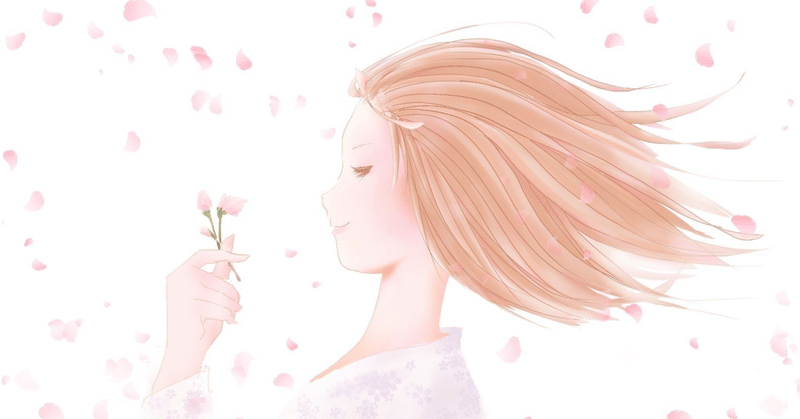
【食育の話】自然農法のプロ、なべちゃん農場に行って食の未来と可能性について気付きました#202
皆様、おはようございます。
佐伯です。
昨日、まちづくりの仲間である「スウプはやし」の店主:林さんと自然農法のプロフェッショナルである渡辺さんが運営されている「なべちゃん農場」に見学とお話をお伺いに行きました。
まずは、下の写真をご覧下さい。

また寒暖差が激しい地域のため靄が立ち上がっており幻想的です。
私はこの風景を見たときに思わず、呼吸を忘れました。
まるで日本画を切り取ったような美しくも力強い景色がそこには広がっています。
自然農法をお伝えするにはこの景色を皆様にお見せしたいと思いました。
惜しむ点は私の写真の表現力です。
実際にはこの写真の何十倍も魅力がここには詰まっています。
是非、皆様には一度この景色をご覧頂きたいです。
そして、ここで生産されている農作物がこちらです。

渡辺さんは引き続き地域農業の活性化と後進の育成に努めておられます。
先に蜂蜜を頂きましたが、甘さと数種類の花の香りが複雑に絡み合い程よく調和しています。
また、後味はすっきりしており、最後にほんのりと苦味が下の奥に残るとても味わい深い蜂蜜です。
玄米はこの後に炊いて頂きたいと思います。
こちらも大変楽しみです。
それではディスカッションした内容と今後の取り組みについてまとめます。
ご一読頂けると嬉しいです。
①自然と調和する農業について
渡辺さんの取り組まれている自然農法の源流は「奇跡のりんご」で有名な木村秋則さんです。
木村さんがお隣、石川県羽咋市で開催されている自然栽培実践塾を受講していることを知った渡辺さんがサラリーマン、兼業農家、そして実習生として3足のわらじを履いて1年間、毎月、自動車で1時間かけて羽咋市まで勉強しに行ったそうです。
熱意がないとできない大変な過密スケジュールだと思います。
そして、卒業後、自然栽培に適した地を探しこの集落を見つけたそうです。
里山の不便な地で、耕作している農業従事者も高齢者ばかりとても明るい未来が見えるようには思えません。
ですが渡辺さんは手付かずの自然と岩から滲み出る美しく美味しい湧水、そして慣行農業(農薬や化学肥料を使用した農法)が行われていなかった綺麗な土に惚れ込みこの地を開拓することを決心したそうです。
「最初はたくさんのご意見を頂いた。」
渡辺さんは笑ってお話しされていましたが、恐らくは大変な苦労があったのだと思います。
自然農法とはJAが推進する慣行農業の常識を打ち破るものです。
いつの時代も挑戦者は批判されます。
渡辺さんも相当の批判を浴びながらも、負けずに続けて結果を出したのです。
そんな渡辺さんからは本当に人を惹きつける雰囲気があります。
渡辺さんとじっくりお話しをさせて頂き、毎年、弟子にして欲しいと若者が集まるのも納得できます。
次に話の途中に出た「慣行農業」とは何かをご説明したいと思います。
②農業の介護化、慣行農業の実態
色々なお話を聞きましたが、1番の問題は「農業の介護化」だと感じたことです。
令和2年の農林水産省の調査によると農業を主な収入としている農業従事者の年齢で最も厚い層が70〜74歳です。
調査から4年が経ちました。
農業従事者のほとんどが後期高齢者であるということは言うまでもありません。
老化は誰にでも起きることなので仕方のないことです。
なので本来やるべきことは次世代につなぐ努力なのです。
若い新規就農者が生活していけるだけの収入を確保するための安定的な販路と流通網、高付加価値の商品作物にチャレンジするための後押しです。
ですが実際には違いました。
年金を貰いながら老いた体に鞭を打って農業をしてもらっているのです。
そのために、JAや農薬メーカーはあの手この手で老いた体でも農業ができるような高齢農業従事者にとって親切な製品を作り続けました。
話を聞いて、あまりの酷さにひっくり返った話があります。
それは化学肥料の話です。
皆さんは水田の中を動力付き噴霧器を背負って霧吹きをしながら歩いている農家さんを見たことがありませんか?
あの噴霧器が重すぎて高齢農業従事者には背負えないと言う話になりました。
すると、肥料メーカーは考えました。
「田植えの時に一緒に撒けばいいんだ!」
しかし問題もあります。
肥料を撒くタイミングがあります。早くに撒いてしまっては効果はありません。
そこで更に考えました。
「徐々に解けるカプセルに詰めればいいんだ!」
そうして出来上がったのが水の中に入れると徐々に溶けるプラスチックに詰められた肥料です。
画期的でした。
田植えと肥料撒きが一度にできて体に負担が掛からず体の弱ったお年寄りの農家さんでも農業が続けられる!
売上も落ちない!(←ここ重要)
あっという間に普及しました。
しかし、今度は溶け切らなかったプラスチックの被膜が水田に滞留したり海に流れ出ることが問題になりました。
そして、さすがに農林水産省も看過できなくなり調査に乗り出しました。
結果は、
① 被覆肥料にプラスチックが含まれていることの周知
② プラスチック被膜殻の農地からの流出抑制対策の実施
③ 新技術の開発と普及によるプラスチック被膜に頼らない農業の実現
「緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の流出防止に向けた対応の強化 について」より抜粋
出ました。先送りです。
ざっくり言うと、
「把握はしているけど、自助努力で対策してね。2030年にはきっと未来の技術が解決してくれているはず。」
とのことでした。
きっと政治が働いたのでしょう。
志を持って農水省に入った役人が真顔でこんな話をしてたら耳を疑います。
さて、食の安全とは何だったでしょうか?
肥料に限らず農薬についても撒く時期、回数まで細かくJAが発行する米作りの教科書に記載されています。

少し前に銀行や証券会社の詐欺紛いの商品販売で心を病む従業員や離職が高まったことは記憶に新しいかと思います。
食の安全と言いながら、農薬と化学肥料をバンバン売るスタイルも現場のJA職員さんにとっては相当の心労だと思います。
③慣行農業と食の安全保障について
次はマクロな話です。
皆様、現在使用されている肥料や農薬の原料などはどのように調達しているかご存知ですか?
実はほぼ100%輸入に頼っています。(尿素のみ4%自給)
それは農林水産省が発表した「食料生産を支える肥料原料の状況」を読むと分かります。
実は、慣行農業とは昨今のグローバル化したサプライチェーンの中でしか成立しない薄氷の農法ことが分かります。
つまり、戦争が起きてこういった肥料や農薬の供給がストップすると自給自足すらできなくなります。
実際、ロシアのウクライナ侵攻で肥料の値段が上がっています。
グローバル化したサプライチェーンに組み込まれた瞬間、世界の出来事は全て自分事になるという事です。
決して他人事と思ってはいけません。
また、食料自給率を上げる事というのは何も食卓に並ぶ食品の輸入率を下げることではありません。
国産の作物においても必要な機器や材料も全て自前で揃えることが肝心なのです。
私は輸入品を否定するつもりはありません。
輸入品のおかげで食卓のバリエーションは豊になりましたし、食べる喜びも格段に増えました。
ただ程度の問題です。
往々にしてある話なのですが「0か1、白か黒」で解決しようとする人がいます。
最低限、絶対に必要な安全に食べれる食料を自分たちで生産し、残りは輸入にして食を楽しめば良いと考えます。
実は農林水産省もこの件については危機感を持っており日本国としてのプランを策定しています。
簡単に説明すると持続可能な食糧生産システムの構築です。
自分たちの食べるも食料をいかに確保するか、生産する食料の安全性を高めるためAIやビッグデータを使用し農薬の使用や化学肥料の使用を減らす取り組み、等の包括的な今後の方針です。
とても大事で重要な取り組みですが、地味なのか殆どマスコミには取り上げられませんし、政治家の関心も薄いです。
④まとめ 〜自然農法から得た知見、農業の可能性〜
自然農法を知ることで自然、環境と調和した持続可能な農業が実現できると知りました。
そして、渡辺さんやそのお弟子さんが作る自然農法の農作物は安全で美味しいという事です。
それは誰がどのように作ったかを知ることができるからです。
私たちは昨晩食べたお米が誰がどのように作ったか分かりません。
例え顔写真が印字してある農作物であってもどのような工程を経て栽培、収穫したのか分かりません。
渡辺さん達は全て開示しています。
実際に「自然栽培の田んぼの教室」という食育や農業啓発の活動も同時に実施されています。

近隣の保育園の子ども達を招き、田んぼの生き物の採取や観察会も実施しています。
保育園の先生達もなべちゃん農場が自然農法に取り組んでいることを知っているので安心して、子ども達に田んぼの水や生き物に触れさせることができます。
情報開示や食育とはこういう事ではないでしょうか?
安心安全な食とはこういう事ではないでしょうか?
渡辺さんの素晴らしい点は先進的な自然農法で持続可能な農業を実現したこともありますが、時間を惜しまず、私たち消費者に対し丁寧に情報を提供し、農法を公開し、啓発活動に取り組んで、安全という無形のサービスを惜しげもなく提供している点も素晴らしいと私は思います。
私は渡辺さんの取り組みを見て一つの解を得た気持ちになりました。
そして、私も食品販売業者として安全で安心な食品を届けるためのこの活動に賛同し取り組みたいと思います。
お忙しい中、貴重なお時間と素晴らしい気付きを頂いた渡辺さんに対し深い感謝を申し上げます。
そして、長文になりましたが最後まで記事をお読み頂きました皆様にも深い感謝を申し上げます。
それでは皆様、ご機嫌よう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
