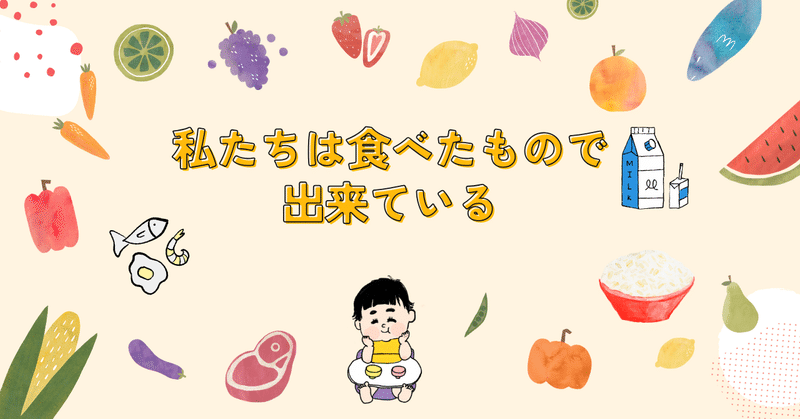
私たちは食べたもので出来ているvol.22#211
皆様、おはようございます。
佐伯です。
毎週土曜日は食について様々な角度から検証していく連載を始めたいと思います。
私は仕事柄、様々な食品に関わることがあります。
一つの製品に生産者様やメーカー様のこだわりや信念など、様々な思いが込められております。
これが製品の美味しさや健康への配慮、地球への配慮など様々な面でも思いが反映されています。
昨日は取引先の方と雑談で味の素の話になりました。
理由は「最近Xや報道で煽られているね。」と話題になったからです。
「佐伯さんは無添加食品などにこだわったお店作りをされているから味の素には反対の立場なんですか?」
と質問を頂きました。
ちなみに私の答えは「No(味の素も素晴らしいと言う立場)」と回答し驚かれました。
今回はその理由についてお答えしたいと思います。
①料理とは生活の一部であることを忘れてはいけない
こう言った議論は往々にして、視点が一方通行なことが多いです。
味の素否定はの方々の意見を見ていると、
「味の素の原料はサトウキビの搾りかす!」
「科学調味料は味覚障害の原因!」
「グルタミン酸ナトリウムは危険!」
と言う内容が散見します。
が、もっと大事なことを忘れてませんか?
料理って誰かが作ってみんなで食べて、片付けて、また作って、食べて・・・と、日常一部であり日々の繰り返しです。
もちろん元気一杯の時は手の凝った料理は楽しいですし、一緒に食べる人たちも喜びます。
ですが、多くの方が仕事を持っており忙しい合間を縫って料理をしていると思います。
残業続きでへとへと、それでも家族や大切な人のために手作りの料理を作りたいと思った時に味の素を使うことは責めらることなんでしょうか?
正直、インスタント食品や外食でも十分だと思います。
それでも、料理を誰かに作りたいと言う思いは本当に素敵な思いだと思いませんか?
私は尊重すべき思いだと思います。
②でも、不満や不安があるのは事実
智に働けば角が立つ情に棹させば流される
これは夏目漱石が39歳の時に発表した「草枕」の冒頭の一節です。
有名な言葉で多くの方が一度は耳にしたことがあるかと思います。
意味は理知的に話しても他人と衝突するだけだし、他人を気遣ってばかりでも自分の足元を掬われる。
兎に角、この世は生き難いと言う内容です。
芯を食った話であり、今も昔も人の心ありようは変わらないと思います。
話を戻しますが味の素論争はもはや情報戦になっています。
色々な方々がポジショントークを行なっており、もはや何が真実で何を信用していいのか分からない状態になっています。
確かに一部の添加物や化学調味料には発がん性や危険性を伴うものがあります。
ですが、科学的には相当な量を摂取しなければ危険性を認められないとも言われます。
仮に味の素が味覚障害を起こす危険性がある、ただし毎日1kg食べると。
となると話は全然変わっています。
仮定の話ですが毎日1kgも食べれます?
無添加醤油だって1日1ℓも飲めば確実に死に至ます。
つまり程度の問題だと言うことです。
そして嗜好の話であると言うことです。
記事にあるように茅乃舎さんや当店とも懇意して頂いている味の和光さんが製造しているだしパックはそう言った味の素に対し不安を感じている方や、もっと深みがあり、美味しいものを求めている方に刺さる商品だと私は思います。
結局のところ、味の素が誕生した昭和と現代の令和時代では趣味嗜好の多様化が進みモザイク的な考えや意見が生まれたことによる軋轢ではないかと思います。
③まとめ
と色々と持論をこねくり回しましたが、要は好きなものを美味しく食べれば万事OKだと言うのが私の意見です。
そして食べた分、運動して、十分な睡眠、ストレスを溜めずに健康的な生活習慣こそ最も大事なことだと言うことです。
何かを一部だけを切り取るのでおかしな話になるのです。
全ては調和の元に成り立ちます。
味の素は食という一部、さらには味付けと言うかなりミクロな話だと思います。
ここだけ抜き取っても健全な議論は成立しませんし、誰も健康にはなりません。
いろんなポジショントークに溢れていますが、疑問に感じたことは自分で調らべ考えを持つことがとても大事です。
それでは皆様、ご機嫌よう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
