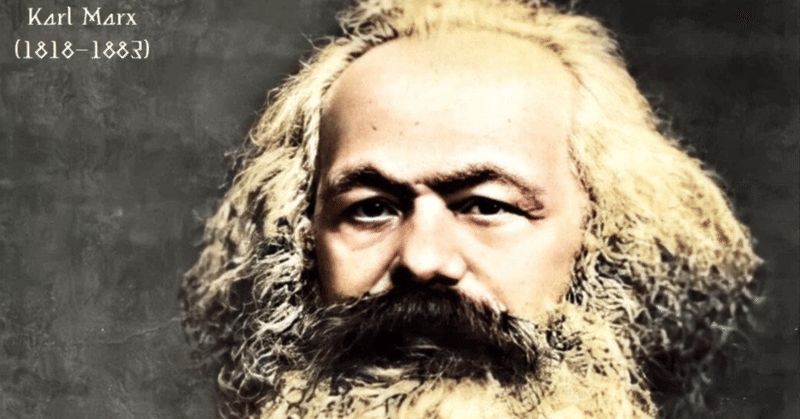
ウタバしかいないのに(第5回):《クルアーン》ファジュル章17-20節をめぐって
そんなことは断じてない!
アッラーからの恩恵に対して、人間は、自分の都合で、厚遇されたと言って喜び、冷遇されたと言って嘆き悲しみ、結局、自分の神への信仰に傾き、アッラーの信仰からは外れてしまう。つまり、アッラーからの試みに失敗しがちなのだが、その失敗とは具体的にどのような形で現れるのであろうか。それが示されているのが、第17節から20節にある4つの事柄である。
كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ (18)
وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلا لَّمّا (19) وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّا جَمّا (20)
⑰断じていけない。いや、あなたがたは孤児をまったく大切にしない。⑱また貧者を養うために、互いを励まさない。⑲しかも遺産を取り上げ、強欲を欲しい侭にする。⑳またあなたがたは、法外な愛で財産を愛する。
それでは、これらの聖句についてのアッラーズィーの注釈を見ておこう。以下、彼の注釈に沿って記述。
まず「カッラー」。これは、厚遇に喜びを、冷遇に落胆を、露骨に表す人間たちへの撃退の一言である。イブン・アッバースは、その意味について、彼は豊かさによって私に対する厚遇を試したのではなかったし、貧困によって私に対する冷遇を試したのでもなかった。厚遇されるか冷遇されるかは、スンニー学派の考えに従えば、純粋にアッラーの決定であり、定めであり、思し召しであり、その判断は、理由による理由付けとはまったく無縁だということになるし、ムアタズィラ学派の考えに従えば、至高なる御方以外は知る由もない隠れた福利がその原因であるとする。したがって、不信心者に対して、厚遇を示すためでなくても、寛大になるかもしれないし、信者に対しては、冷遇のためではなく出費を切り詰めさせるかもしれない。
これを受けて、至高なる御方が彼らの言い草に対して語るとき、こういっているのではないか。『いや、彼らにはその言葉以上に悪い行動がある。それは、至高なる御方が彼らに対して数多くの財によって厚遇しているというのに、孤児を大切にするという彼らがなすべきことがまったく行われていない。
結局カネなのかい
そこで至高なる御方はおっしゃった。《いや、あなたがたは孤児をまったく大切にしていない》(第17節)と。そしてそこにはいくつかの問いがある。
① 2人称への転換はなぜか?アブー・アムルは、この箇所を、「ユクリムーナ」と「ヤー」つまり3人称で読んだ。3人称で表すと、もともと、冠詞付きのインサーンであるゆえ、属と、数の多さを示している。3人称をもちいると、人間のことを大切にして、愛もあるというニュアンスが出せる。しかし、アッラーの御言葉は2人称を用いている。ここで2人称になっているのは、ムハンマドに対して、彼らに言ってやれという命令をうけて、彼らに直接語りかけるという形をとっているためである。
② ムカーティルは言う。「かつて、(初期改宗者の一人)クダーマ・ブン・マズウーンはウマイヤ・ブン・ハラフ(=マッカにイスラームが急速に広がり始め、迫害・拷問がいよいよ激しくなったころ、ウタバらとともにムハンマドとの話し合いに臨んだとされる14名のクライシュ族の長たちの一人)のところで孤児だったのだが、彼は権利を奪われていた」。
孤児を手厚く扱うことの放棄にはいくつかの面があることを知るべき。
その1:その孤児に対する善行の放棄。《彼らは、困窮者の食べ物を互いに制限した》というアッラーの御言葉に示されている。
その2:彼から、彼が確実に持っていた相続権を剥奪し、その財産を自分のものにした。《あなたがたは遺産を食らいに食らう》。
その3:彼の財産を彼から取り上げる。《あなたがたはお金が大大大好きだよね》という至高なる御方のお言葉に示されている。つまり、その孤児の財産を奪って、自分の財産に含ませてしまう。
《その困窮者たちへの食事の施しを勧め合わなかった》という御言葉について、ムカーティルは「あなたがたは困窮者の誰に対しても食事を施さない」としている。その意味は、あなたがたは、困窮者に食事を施せと命じない。それは、至高なる御方の次の御言葉のように《実に彼(=審判の日、その左手に(行状記)記を渡された者)は、偉大なるアッラーを信じなかったし、困窮者たちの食事も促さない》(真実章33-34節)。「タハードゥーナ」を読む者は、これは完了形ではなく、「タタハードゥーナ」(未完了形)の冒頭の「タ」が省略されていて、意味は「互いに勧め合わない」である。イブン・マスウードの読みでは、「トゥハードゥーナ」と「ター」をダンマで読む。
「階級闘争」「信仰闘争」
以上が、アッラーズィーの注釈であった。それによれば、クダーマに対するウマイヤ・ブン・ハラフの扱いが当該4つの聖句の実例の一つであるということなのであろう。イスラームの草創期の記録が物語るように、クライシュ族の各家系による迫害と拷問は、本当に過酷を極めた。当時のアラビア半島には、ギリシャのような哲学も、ローマのような法律もなかった、つまり思索や思想もなければ、ルールもない。しいて言えば、金儲けだけがあった。だからこそ、この宗教、つまり、個と社会のみならず、森羅万象のすべてを覆いつくすような極めて包括的な教えが降ったのである。
そこにいるのは圧倒的に奪う者と圧倒的に奪われる者。圧倒的に踏みつける者と圧倒的に踏みつけられる者。現世とは別次元に来世を設け、天国とは真逆の火獄に彼らを送り込む。それをささえるのが、死ぬということのない世界観であり、最後の審判であり圧倒的に公平な判断者としても機能するアッラーである。そして、それはしんじゃたちがつよい信仰を持てば持つだけ確固たるものになる。他方で、信じれば信じるだけ、いやそれ以上に迫害も拷問が積み重ねられるのだ。しかもそれが、クルアーンとその注釈とともに幾世代にもわたって引き継がれるのだ。
唯物論的な世界であれば、持たざる者が階級闘争を経てやがてみんなが持つ者へ、あるいはみんなで持つ者になるというお話になるのだろうが、イスラームの唯一神教の世界では、「持つ」ではなく「信じる」ことがその中核に据えられている。アッラーに対する絶対的帰依。階級闘争ではなく、信者による不信心者・多神教徒に対する闘争。つまり、信仰闘争。しかもその根っこに、信仰を持ったがゆえに被った筆舌に尽くしがたい、迫害と拷問がある。となると、その怨念がいつ暴力の形になって、その信仰闘争の中に顔を出しても不思議はない。そこでは信仰のために信仰の敵の命を奪うことが正義になってしまう。戦利品にみられるように、敵の財産を奪うこともまたしかりである。信者たちには命と財産の拠出を義務付け、一方で敵から命と財産を奪う。改宗前は、散々に拷問を働いていたウマルが、改宗を経てカリフとなり、善政を行う。これもバランスと言えばバランスだ。
しかし、イスラームのバランスシートは、そこではないはずだ。最後の審判があるのだから。結局、性急に結果を急いでいるのは、信者の方なのではないかという逆説的状況も起こりうるのだ。歴代の諸王朝の君主たちが、クルアーンの楽園の描写を模して、世界遺産に指定されるような名庭園を残しているのがその何よりの証拠だ。楽園を自分の治世の間にこの目で見てみたい。と考えると、仏教徒の仏像を偶像崇拝だと非難することはとてもできないように思う。アッラーフ・アアラム。(次号へ続く)
参考文献
ファフルッディーン・アッラーズィー『大注釈』(第2版)11巻157頁以下
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
