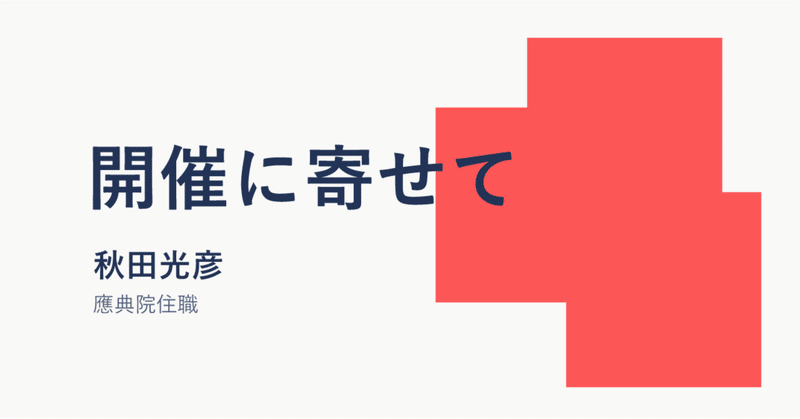
お寺という場所をめぐってー『むぬフェス』開催によせて(秋田光彦|應典院住職)
離れゆく死の光景、そして子どもたち。
わたしたちのいのちの想像力の行方
お寺という場所は、死を身近に感じるところです。
お葬式があればご遺体が搬送されてくるし、余命宣告を受けた人がお墓を探しに来ることもあります。遺族たちは、死者の供養に勤しみ、いのちの行方に想いを馳せたりします。應典院の2階からは広大な墓地が見渡せますが、それは、無数の死者が私たちと共生しているという情景を立ち上がらせます。

日本人の日常から死が遠ざけられて久しいものがあります。
私が子どもだった1960年代、8割の人が自宅で亡くなっていました。高度成長期とともに自宅死が急速に減少していき、その分病院死が増加となって、1976年には自宅死を上回ることになります。病院では家族や生活から分離され、医療のコントロール下にいのちが負託されます。むろん自分の価値観や意思や、わがままは通らない。また、コロナ期がそうであったように、死にゆく人と家族や親しい人が一緒にいられるとも限らない。これは、遺された人のグリーフ(悲嘆)にも大きく影響するのですが、現在もなお7割の方々が病院で最期を迎えています。
お葬式の現場もそうです。
テレビでもC Mが頻繁に流れているように、今の葬儀の主流は家族葬です。私は寺の住職なので、毎月のようにお葬式を執行していますが、家族葬専門の式場もあって、何につけシステム化が進んでいます。喪家はお客様としてもてなされますから、望まない限り、ご遺体にふれることも、直視することもない。完全パッケージ化されたお葬式では、死にまつわる経験が漂白されていきます。
かつて葬儀の場は自宅葬が中心でした。葬儀自体が地域共同体の営みであり、喪家の人々が死者の弔いに専念できるよう、隣近所の人がこぞって協力する相互扶助の仕組みがありました。
自宅死も自宅葬も今ではほとんど見かけることはなくなりました。それは、そのまま生活圏から死や死者の存在が排除されていることを意味します。死が見えない、死にふれない、死を想わない。そういう経験が希薄になるにつれ、いのちについての想像力も枯渇してきているように思えます。

いまは式場が中心に
死ぬと相対しますが、産まれて間もない子どもについても似たような感覚があります。
少子化が加速して、街では子どもの姿を見かけることが少なくなりました。過剰なほど安全対策が徹底しており、学校は監視カメラだらけの要塞になっているし、近くの公園は今や危険な場所のナンバー1です。知らない人がちょっと声をかけると変質者扱いされるので、子どもと接触する機会はどの世代においても消えつつある。
メディアはいじめや虐待しか報道しないから、「子どもは面倒で大変」という負のイメージが増幅されていきます。「子育てに対する不安」とは、つまり、社会全体が子どもを忌避する時代となっていることの写し絵ではないでしょうか。
私はお寺に隣接する幼稚園の園長も長年務めてきましたが、保育の現場では子どもは無心に遊びこみ、今を生きるよろこびを全身で表しています。生きることへの想像力を駆使しているといってもいい。私の幼少期には、親だけでなく、近所のさまざまな大人が関わってくれた幸せな記憶がありますが、それは地域の皆が保育参加していたと同時に、子どものいのちの躍動にふれて、社会の希望や生のよろこびを取り戻すという側面もあったはずです。
しかし、子どもを忌避する時代は、死に対するのと同様、生まれ、生きることへの想像力を削いでいきます。生きることと死ぬことへの考え方を死生観といいますが、それが直接経験のないまま脆く、痩せ衰えたものになっていないか、そういう危うさを感じています。

子どもも他の大人とふれあう機会がない。
死生観をいかに形成するか。
「あなたの死生観は」と尋ねられて、即答できる人は少ないでしょう。死生観に正解はないし、文化や環境に影響を受けやすいものです。ある時代まで、宗教的な物語が死生観の基盤となりましたが、今は医療や福祉の影響が遥かに大きい。QOL、リビングウイル、脳死、A C P、尊厳死等々、死は一貫して医療問題として取り扱われてきました。医療である限り「合理的な解決」が可能なはずと信じられている。つまり現代人の死生観とは、科学技術への信仰が根強く支えています。
應典院という寺の存在理由を、常々「死生観形成の拠点」として語ってきました。
もちろん私自身は仏教者として、特に浄土教の往生観を大切にしていますが、上からの布教や教化をしたいのではありません。應典院が「ひらかれた寺」として取り組んできたものは、アートであり市民活動であり、数々の文化的・社会的プロジェクトとの協働であり、生きること死ぬことを自分ごとして捉える多様な実践でした。
とりわけお寺らしく死生観が滲み出たのは、若い表現者によるアート活動でした。とくにご本尊の安置された本堂空間や、広大な墓地を見渡す2階の広場では、表現が場所と共振しあい、意図したもの以上のエナジーを発揮することがありました。言葉には置き換えられない、アートが内包する聖性といってもいいでしょう。

「私(作家)が主体的に表現しているのではなく、この場所に促されて、表現させてもらっている」
そう言ったアーティストがいました。確たる死生観があったわけではないが、お寺という場所に巡り合い、表現行為のプロセスの中で、それが内発したのではなかったか、あるいは、仏や死者の世界がこの世を相対化し、表現者として異なる価値と出会ったのではないか。そう感じることがありました。アートでしか感じ得ない死生観の兆しでした。
現代は、「死生観は自分で創る時代」(柳田邦夫)と言われています。死期は一度であっても、人生において存在の死に直面するような、危機的な体験は幾度かやってきます。関係の危うさや自己存在の揺らぎ、また生きづらさや不安を感じているのは、いずれの世代を問いません。死生観とは、死を見つめながら、生きるとは何かを考えること。生と死は濃淡のグラデーションのように連鎖している。生きづらさや不安と向き合い、対話と交流を重ね、やがて生き直しへの起点とできるのか。それをともに考えていく場所が、應典院の一つの使命と考えています。
「むぬフェス」の内容については、D C Lの企画と推進力に頼む以外ありません。30代中心の若い世代によるプロジェクトですが、年齢を重ねれば死生観は成熟するという説を私は信じません。世代の違いなどしなやかに超えて、独自の言葉と思索との出会い、あるいはそれを超えるような想像力がここから立ち上がることを密かに期待しています。
むぬフェスについて
むぬフェスは、展示・トークセッション・ワークショップを通じて、「産む」から「死ぬ」まで、生きるをめぐる10日間のイベント。
「産む」にまつわる5組のアーティストの作品や当事者との協働デザインプロセスの展示に加え、葬儀体験、生きづらさ、祖先、生老病死など「死ぬ」ことへの想像力をひろげる対話やトーク、ワークショップをひらきます。
一人ひとりの生き方を問い、仏教者や人類学者に医師にデザイナー…多様な専門家や実践者が集い、これからの社会を想像するきっかけの場を目指します。

「産まみ(む)めも」


■日時:
2024年5月17日(金)〜26日(日)
平日:12:00-20:00
休日:10:00-17:30 (最終日のみ10:00-15:00)
■場所:
應典院 (大阪府大阪市天王寺区下寺町1丁目1−27) google map
■体制:
主催:應典院
共催/企画運営:一般社団法人 Deep Care Lab
展示協力:一般社団法人公共とデザイン
協力:大蓮寺、パドマ幼稚園、創教出版
■料金:
無料 (トークセッション、ワークショップは有料)
■申し込みリンク(トークセッション・ワークショップのみ):
https://munufes.peatix.com/
※『産まみ(む)めも』展示鑑賞のみの場合はチケット不要です。
■ホームページ:
https://munufes.outenin.com/
■SNS:
X :https://twitter.com/asobi_outenin
FB :https://www.facebook.com/asobi.outenin
Instagram :https://www.instagram.com/asobi.outenin/
note :https://note.com/asobi_outenin
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
