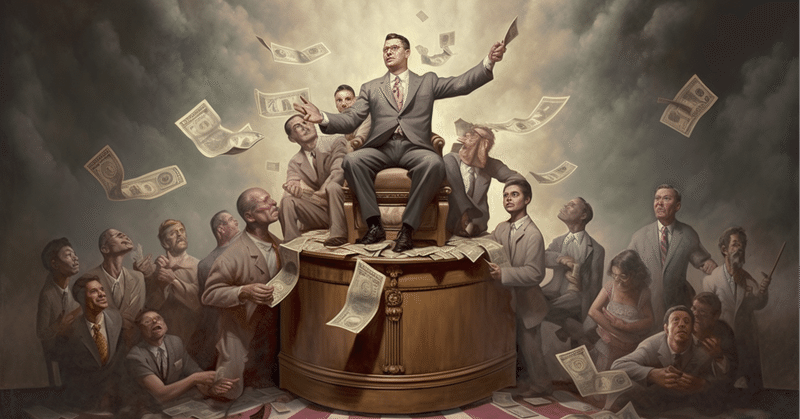
「エイブリズム」:障害者の価値と“能力主義”
最近、SNSを見ていたところ、偶然にも「エイブリズム」という概念を知りました。
今回は、「エイブリズム」について簡単に解説しつつ、ASDである自分の意見も語っていこうと思います。
まずエイブリズム(Ableism)とは、能力のある人が優れているという考えに基づいた、障害者に対する差別と社会的偏見を意味しています。
辞書には「障害(=他の人がすることが難しくなるような病気、怪我、状態)を持っていることを理由に不当な扱いを受けること
(出典元:CambridgeDictionary)」と記載されています。
日本語では「非障害者優先主義」「健常者優先主義」、「能力主義」とも訳されます。
エイブリズムの根底には、障害者は「治す」必要があるという前提があり、障害によって人を定義する考え方が存在します。エイブリズムは、人種差別や性差別と同様に、ある集団全体を「劣ったもの」として分類し、障害を持つ人々に対するステレオタイプや誤解、一般化などを含みます。
具体的なエイブリズムの例として、自分がASD当事者として注目したいくつかの事例を挙げます。
・障害を持つ人は「治す」ことを望んでいると思い込む。
・障害をジョークのオチにしたり、障害を持つ人を馬鹿にする。
・障害を持つ大人と子供を施設に隔離する。
・ニュースや映画などのメディアで、障害を悲劇的あるいは感動的なものとして取り上げる。
・目に見える障害がなければ、実際に障害があることがないと思い込む。
・障害のある人に対して、幸せで友好的で素朴、予測不可能で危険、冷淡で無粋などのステレオタイプに当てはまると思い込む。
・障害がある人に対して、子供に話すように話しかける。
・障害のある人の病歴や個人的な生活について、関係性が構築されていない状態で立ち入った質問をする。
これらの具体例を見ると、自分個人としては場所によっては日常的に目にする光景であり、幸いなことに自分自身は上記のような扱いを受けずに済んでいます。
エイブリズムに関連して、東京大学先端科学技術センターの熊谷晋一郎氏は次のように述べています。
「パラリンピックを見て『頑張っている障害者がいる一方で、私は何て至らないんだろう、無能力なんだろう』と、自分を責めてしまう一般の障害のある人々の存在というものも無視できないわけです。私自身も決して、スポーツは得意ではないどころか、スポーツにコンプレックスを持ってこれまで生きてきた、比較的多数派の障害者です。多くの障害者にとって、スポーツあるいは体育といいますと、のけものにされるとか、うまくなじめない、排除されるイメージというのがあると思うんですね。こうした能力主義の問題とどううまく付き合うのかっていうことが、2020年のパラリンピックを私たちがどう受容するのかという問題と深く関わっているように思います。
さらに、車いすマラソンでパラリンピックに二大会出場した花岡信和氏は、次のように警鐘を鳴らしています。
「目立つ人の姿が世の中の障害者のイメージになりやすいと思うんですよね。パラリンピアンは、そもそも少ない障害者の中のトップアスリートですから、キングオブマイノリティ。そのイメージは、『身体機能を最大限に生かしている人』や『強者』、『清く正しい人』かなと思うんですよね。これが障害者のイメージとして定着すると危険です。選手自身も世の中のレッテルに対して、そうあらねばならないとなったときが一番しんどいんじゃないかと思っています。」
「能力主義」は、「働かざる者食うべからず」といったように、一般社会に深く根付いた考え方です。これは障害者間でも例外ではないと言えます。
例えば発達障害の界隈では、以下のような能力による対立構造が存在しています。
バリ層と呼ばれる「発達障害でもバリバリやれる層。発達障害の特性・才能を生かして社会で活躍できている層」、ギリ層と呼ばれる「頑張れば何とかやれるが周囲のフォローが必要。配慮アリで一般雇用している人など」、ムリ層と呼ばれる「頑張っても学業・就労が難しい層。フォローありでも一般就労や普通学級は難しい層」です。
能力主義に対して、人々が矛盾を抱えている点について、熊谷氏は過去の相模原市の障害者施設殺傷事件に触れ、「能力主義」について問いかけました。
「あの事件の犯人は、『能力のある人には生きる価値があるけれども、能力のない人には生きる価値がない。』こんなことを言ったわけですね。それに対して私たちは、良識を持って、『それは間違いである』と反論をしたわけです。しかし、よく考えてみると、この能力主義というのは、簡単に否定できるものでもない。例えば障害者福祉の現場でよく言われるのが、『今は支援を受けられていないから能力が発揮できないけれども、適切な合理的配慮さえあれば、能力を十分に発揮できるのだ』というようなロジック。これも実は、能力がより発揮できる状態のほうが“よい状態”であるという、ある種の能力主義に基づいた支援の組み立て方なわけです。そして恐らく、そのこと自体、誰も反論できない。」
さらに熊谷氏は、「能力主義に対して一定の距離を保ちつつ、否定し切れない側面をうまく使いこなしていかなければいけない」と述べています。
つまり、能力主義を完全に認めるわけではありませんが、実際の行動には能力主義に基づいた要素が存在していることに向き合う必要があるでしょう。
障害者の強みや可能性を最大限に引き出すためには、社会の認識や意識の変革が不可欠です。
障害者を幅広い視点で捉え、各々が自分らしく生きられる社会の実現に向けて、微力ながら今後も一人のASD当事者として情報発信を続けていきたいです。
【参考HP】
もし、サポートしたいと思っても、そのお金はここではない他の何かに使ってください。僕の方はサポートがなくともそれなりに生活できておりますので。
