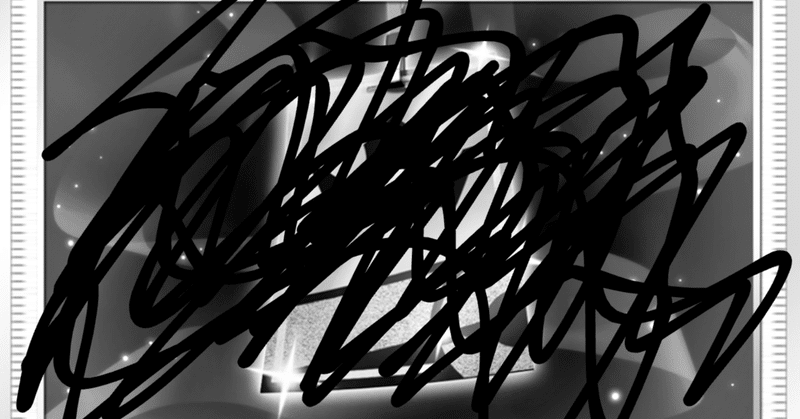
【ポケカアドカレ】デッキ構築の極意~デッキを弱くするというチューニング~【19日目】
本記事はいちょーさん主催によるポケカアドカレ企画の記事になります。
ポケカアドベントカレンダー企画です。みなさんのご参加をお待ちしております。#ポケカAC #拡散希望
— いちょー/アドカレ毎日更新中 (@poke_ichyo) November 1, 2022
ポケカアドベントカレンダー企画募集要項 - いちょーのブログhttps://t.co/2LHBXTRKbf
前日のあむさんの記事はこちらから
今回の記事もいつも通り抽象的な考え方をいかに実践に落とし込むかというお話です。
題材はデッキチューニング。
プレイングの向上と表裏一体であるこのプロセスに対して、どういう視点を持って向き合えば良いのかという考え方の参考の1つになれば良いなという気持ちで書きました。
ちなみに本編は後半から始まります。
デッキのチューニングとは
本記事では、主にデッキ選択が決まった後の細かい採用カードの枚数について調整することを指します。
例えばルギアというデッキタイプは決まっていて強い基盤の構築もわかっている。その上で自由枠にどんなアタッカー採用するのか、サポートの枚数比はどうするのか等を決定することをチューニングと定義します。
自分はチューニングを施す際、そのデッキへの深い理解(環境での立ち位置など)を伴った上で、主に以下の3つを意識して進めます。
特定のデッキのみへの勝率が低い:メタカードの投入
立ち位置は良いが環境のデッキに対してパワー負けする:パワーを底上げするカードの投入
パワーが高く環境のどのデッキにも強く出れる:安定感の向上
本記事で取り上げるのはこのうち3つ目。安定感の向上についてになります。
デッキの安定感
デッキの安定感とは何でしょうか。
一つの答えは同じ動きの再現性が高いということです。
現在流行りのルギアデッキであれば2ターン目にアッセンブルスターでアーケオス2枚を出すというコンボ。この再現性が高ければ高いほど、安定感が高いと言えると思います。
もう一つの回答は、デッキ内に複数の強い動きが詰まっているということです。
例えばメインのコンボAが存在したとして、これと同じくらいにパワーを出せるコンボB, コンボC……が存在したとします。
コンボAの再現性が低くとも、成立しなかった手札でコンボBあるいはCが成立するならば、それは安定感があると言えるでしょう。
いわゆるグッドスタッフ系統のデッキがこれに該当しますが、ポケカはガッチリこれに当てはまるようなデッキは現在は存在しないと思います。強いて言うならば引いたアタッカーやエネルギーによってゲームプランが変わるロストなどのバレット系統が当てはまると思います。
これらを総合して少し抽象的に言い換えると、安定感があるとは一定の出力が担保できるということに他なりません。
もう少しそれっぽい言い方をするのであれば、デッキの出力が正規分布に従うと仮定した際の分散が小さい状態のことを指します。
イメージはこんな感じ
正規分布やら何やらの説明はWikipedia大先生にお任せするとして、分散のイメージは、例えば平均点が60点のテストがあったとしてどれくらいの受験生が60点に近い点数を取ったかの指標だと考えてください。
ポケカに再変換すると、そのデッキが一番取りやすい60点付近の出力で、環境のデッキに勝つのに不十分な回り方であれば平均点を上げる(例えば65点になる)ようにデッキをチューニングする、十分な回り方であれば分散を下げる(より60点が取れる)ようにチューニングをするというのが適切になります。
デッキを弱くするとは?
さてここでようやく本題。
デッキを完璧な状態に仕上げるためにはデッキの出力の平均点を上げ、分散を下げることによって高出力・高安定を叩き出すことが理想と言えます。
しかし、チューニングの段階でこれを両立することはほぼ不可能に近く、平均点を上げるためには分散の上昇を伴い、逆に分散を下げるためには平均点の下降が伴うことがほとんどです。
このうちの後者、分散を下げるために平均点を下げることを筆者やその周辺のShadowverse競技プレイヤーはデッキを弱くすると表現してきました。
デッキを弱くする方法
方法の1つのは特定の状況下でしか使えないカードを排除することです。
Shadowverseではわかりやすくエンハンス・アクセラレートというキーワードが存在しました。
これはマナ・コスト制を採用するShadowverseにおいてそれぞれ本来のxコストで使用する代わりにx+nコストで使用し別の効果を得る、または本来のyコストで使用する代わりにy-mコストで使用し別の効果を得るというものです。
例えばShadowverseの序盤の安定において重要な2コストのカードにエンハンス6という効果がついていれば、6コストのカードの代わりに採用することで、バリューを維持しつつ無理なくデッキの安定感を上げることが出来ます。
当然、6コストでしか使えないカードよりバリューは低くデザインされているので少なからずデッキパワーを落とすことにはなるため、元のデッキパワーが十二分な時にこういったカードを採用するチューニングを施します。


出せば必殺級のフィニッシャーに何故か事故回避のおまけ能力がついている。
しかも終盤でもアクセラレートの効果が強い。バグ。
ポケカではセレナの採用理由はこれにかなり親しいことが多いです。
このカードは0.3博士の研究+0.5ボスの指令のような表現をされますが、まさにボスの指令のn枚目をセレナに変えることによって、デッキを弱くすることが出来ます。
例えば、手札にボスの指令が複数枚とプレイアブルではないカードがかさばったような場面では、その1枚がセレナであっただけでも十分に解決する可能性があります。
一方で、セレナのVポケモンしか呼び出せないというカードパワーの低さが原因で負ける試合も存在するのは間違いありません。
しかし、それが原因で負ける試合よりデッキが回らずに負ける試合の方が圧倒的に多かったり、相手のバトル場のポケモンはこちらのアタッカーの選び方次第でいくらでも誘導できることを考えるとセレナを採用する方が安定に寄っていると考えられます。
したがって、流行りのルギアデッキや以前自分が持ち込んだアルセウスギラティナデッキなど、パワーが高くしっかりテンポを強く取れるようなデッキでは採用を散らすことを強く推奨しています。

デッキを弱くしすぎることはNG
こうしてデッキを弱くすることを覚えると、すぐにデッキのカードすべてをいつでもプレイアブルなカードに置き換えたくなってしまいがちですが、やりすぎはもちろんNGです。
弱くしすぎると今度は安定して何にも勝てないデッキが生まれてしまうためです。
勝てるラインの出力を最大にするというのは非常に難しいです。
カードゲームはルール上相手に圧勝しても意味は無いので、相手の出力を1点でも上回れば良いという目的がこの問題をより難しくします。
そのラインが60点ならば、62点を平均値にして分散を下げる方が良いのか、多少分散が高くとも平均65点を出す方が良いのか。この辺りは厳密に計算できるものでは無いので、感覚と統計に基づいて考えるしか無いので結局数やって確かめましょうと言う他はありません。
また、必要となる出力のラインは基本的に対戦する2デッキによって決定されるものですが、
対戦相手とのプレイスキルの差(例:CL or 四天王決定戦)
デッキ相性(略)
必要とされる勝率と試行回数(例:14勝2敗 or 70勝30敗)
によって、より複雑に変化します。
それぞれの競技シーンに最適なデッキはこれらの要素によって複雑に変化するものであり、デッキの分布による環境だけがすべてを決めるわけではないということを知っておくとより競技シーンへの理解が深まって楽しいかも知れません。
実はここからが本当の本題
今までは強いデッキを弱くすることで、安定感を上げるというチューニングについてお話ししてきました。
しかし、その逆。弱いデッキのパワーを底上げ、つまり平均値を上げて分散も上げるというチューニングも存在します。
このためだけのカードがポケカには存在します。
それがコイツ

ここからは、筆者が世界一嫌いなカードであるバトルVIPパスについてひたすら語ります。
本来パスが入るのはパワーが低いデッキだけ
まずはこれ。
前述の通りこれはデッキを弱くする逆=デッキを強くするカードなので、強いデッキに入れるのはまずチューニングの指針として合致しません。
例えばどうしても構築で使いたいポケモンがあったり(テーマデッキetc.)、環境的な立ち位置は良いがパワーがどうしても劣ってしまうデッキ(現環境で言うとエレキガノンetc.)等に入るのはチューニングとして正しいです。
しかし、デッキ構造上仕方のないミュウデッキを除くとして、Tier1として同列に扱われているロストバレット等に投入されているバトルVIPパスには違和感を覚えますし、それだけならまだしもそれでルギアに有利ですみたいなことを言われると
「安定感を失ってデッキパワーを底上げしなきゃ戦えないのに本当に有利って言えるんですか?」
と、つい口を滑らせてしまいそうになるレベルです。
ロストバレットについて語る
バトルVIPパスが必要ないことについて語るためには、まずロストデッキについて詳細に語る必要があります。
自分の中では現行のロストバレットデッキは大まかに4つに分けられると考えています。
ロストリザードン(ヨネタク or Tord型)
ロストカイオーガ
ロストゲッコウガ(ライコウ等)
ロストギラティナ
このうち、上2つにはパスの採用が必須と考えていますが、その時点でデッキとしての欠陥を抱えていると認識しているので、環境的な立ち位置が良い時以外には肯定されないデッキ選択だと考えています。
なぜパスが必須かそうでないのかが分類できるかについては、ロストの基本的な立ち回りに起因します。
ロストバレットの戦い方
基本的な考え方になりますが、まずロストデッキのゴールはどこでしょうか。
これに自分は瞬時に、強固な盤面を作ることと回答します。
ロストを貯めることは手段でしか無く、その先に行き当たりばったりにボードを作るのではなく、強固に盤面を作り相手の手札干渉を苦にせず相手の勝ち筋を潰して常に高い要求をする。
これがロストバレットの基本的な戦い方になります。
そのためにロストを貯める必要があり、それぞれ枚数ごとに以下の手段で盤面を作ることが出来ます。
ロスト4:ウッウ
ロスト7:ミラージュゲート
ロスト10:ヤミラミ(ギラティナVSTARパワー)
ロストを貯めつつ、これらの中間目標を達成し、その時点で取れる手段を使って盤面を強固にしていくことを細かに繰り返すことでリソースとテンポを維持するのがロストバレットの一番の強みです。
まずリザードン型の欠点はここにあります。
ミラージュゲートという中間目標が無いために、ロスト10まで能動的にボードを作ることができないのです。
したがって、ロストを貯めるためにキュワワーを大量に展開する必要があり、そのためには大量の入れ替え札やバトルVIPパスのような展開カードを過剰に取る必要があります。
ロスト10という中間目標を全力で達成する必要があるのですから、当然不安定なデッキになります。
このデッキを使うには、不安定でも良い(対戦相手のレベルが高い or Bo3環境である)、もしくは対戦相手のロストバレットに対する練度が低い(相手ボードを整えずにサイドを先行して、リザードンでうまくボードを作れる展開になりやすい)などのかなり特殊な状況でなければ推奨されません。
また、盤面を強固にするという目標を達成せずにテンポを失いながら無理やりロストを貯める行為はロストバレットの本筋からかけ離れた行動なので基本的に厳禁ですが、それを肯定するパーツがあります。
カイオーガ型の欠点はここです。
カイオーガでは盤面を作ることの優先順位はあくまで二番であり、安定してデッキを掘り切るという行為が一番上に来ます。
そのため、リザードン型と同様にバトルVIPパスが必須パーツとなります。
またリザードン型と違いミラージュゲートという中間目標がありますが、このうち1枚はコンボのために温存する必要があることや、エネルギーをトラッシュに安定して供給する必要があることからエネルギーを盤面形成に全振り出来ないというのが欠点の1つになります。
さらに、環境に存在するムーランドVに抗うためのザマゼンタやジガルデの採用に伴い、安定に寄与していた入れ替え札の数等が減らされることでリザードンデッキよりもロストの貯まり方が不安定になったことがデッキの不安定さを加速させています。それ以上に現環境ではTier上位のデッキすべてに刺さる雪道+マリィがデッキの掘る速度に如実に影響を与えるため、完全にメタ対象となることが一番の欠点と言えますが。
しかし、カイオーガにはこれらの欠点を補ってなおあり余るほどのパワーを秘めています。
そのためCLのDay1では使わずDay2から使用するなどのピンポイントの採用では非常に良い選択の1つであると筆者は考えています。
これらに対して、通常のゲッコウガ型やギラティナ型はそのリソースをすべてボード形成に注ぐことになります。
したがって、過剰なロストやリソースが必要なく、細かにロストを稼ぎながら盤面を継続的に形成して行く過程にバトルVIPパスのような大量展開カードが不要である、というのがこれら2つの型を使うメリットになります。
というか、どうせパスを採用するなら明確にパワーが高いコンボを持つカイオーガを使った方が良いです。
ただ、自分はロストというデッキのパワーがそもそもとして第一線級であり、パスで底上げせずともルギアと同等に戦える力(≠有利)を持っていると思っています。
そもそもルギアを使わない理由についてほとんどの人が、初動の不安定さを挙げるのにVIPパスで初手に一喜一憂する意味がわからないですし、ましてやパスを理由に後手を選択する人までいるのは理解の範疇を超えます。何ならパスを採用して安定を言うくらいならルギアを使って後手を取った方が多分安定するとまで思ってます。
また、ロストミラーだけ後手を選択する人もいますが、これもカイオーガを使用する以外ではやめましょう。
後手選択の理由に後手1でスピットを打てることを理由に挙げる人もいますが、ロストが4貯まっても少なくない状況でスピットを打たないことが正解になります。脳死でスピットを打つのはロストミラー敗北への一歩です。
盤面を作るという基礎に立ち返ってみて、ゲームプランを考えてみましょう。どうせ半分くらいは途中からサイド取らないゲーム始まります。
ちなみにロストバレットでの再推しカードはキバナです。
いかなる時でも盤面形成に寄与する上に、相手に手札干渉を要求することが出来ます。その上でベンチに2手3手先のアタッカーを用意すれば高確率で詰み盤面へ誘導することが可能になります。
まとめ
デッキチューニングは「メタカードの投入/パワーを底上げするカードの投入/安定感の向上」の3つの指針から適切なものを選びましょう
安定感を向上させるためには多くの場合でデッキパワーを犠牲にする必要があるので、どこまでデッキパワーを犠牲にしても良いかしっかりと見極めましょう。弱くしすぎたデッキは安定して負けるデッキ
バトルVIPパスをデッキから抜きましょう
バトルVIPパスを採用しなくて良いデッキを使いましょう
バトルVIPパスをデッキから抜きまs
以上。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
