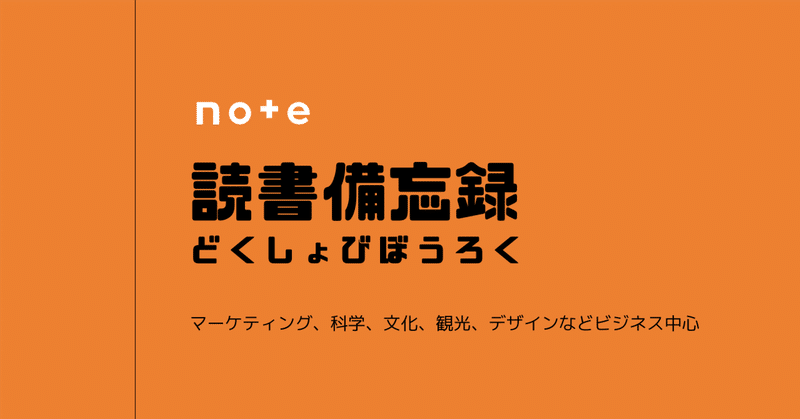
BtoBマーケティングの定石
BtoBマーケティングの定石〜なぜ営業とマーケは衝突するのか?〜(垣内 勇威 著)
はじめに: B2Bマーケティングを機能させるためには
トップ営業の属人性を排除して、マーケティングによる売上の再現を目指す。商品、営業、広報、リサーチ、組織などを含めて戦略・戦術を実行しなければならない。
Chapter1 なぜマーケティングの大半は失敗に終わるのか
売上に繋がらない要因は、営業がマーケティング施策に懐疑的であり連携がスムーズにいかないという組織課題にある。日本では足で売上を稼ぐ営業スタイルで、営業にとってはマーケティングは邪魔になる存在。本来はマーケティングは売上を作るためのサポートとなり顧客価値を提供できる状態でなければならない。
Chapter2 組織の定石:短期売上から顧客視点への革命を起こす
チームの初期メンバーは社内に精通しており根回しが上手い人。マーケティングの専門家この時点では必要ない。この時点で、状況の理解を行うために細かい役割分担しない。また新チームが営業まで行うことも検討する。まずは成果の出やすい案件、部署との事例を作る。メールが最も効果が出やすい手法。
Chapter3 戦略の定石:貴社に本当に必要なマーケティングとは?
B2Bという分類は大雑把すぎる。
・ターゲット企業が100社以下なら接客戦略(顧客を選ばらない広い施策は一切必要ない)。
・既存顧客のリストが多いなら、失敗の少ない既存顧客の発掘を中心に考える。コストをかけずに既存から商談を獲得する。
・既存顧客戦略が使えないなら、新規顧客獲得へ検討を移す。顧客リストを集めることから始める。
・顧客の商品知識が少ないようなら、説得後ろ倒し戦略(商談前の商品説明を避けて営業担当によるクロージングに任せる)
・顧客の商品知識が多いなら、説得前倒し戦略(商品情報を閲覧する顧客の行動から情報を得て、営業担当がクロージングを行う)
Chapter4 先述の定石:トップ営業の生み出す顧客体験を再現する
顕在的なニーズを持ったリードを増やすことはできない。増やせるのは潜在的なニーズのリードだけ。潜在的リードから売上に繋げるソリューション営業は困難。
本当のソリューション営業は、以下の2種類。
1 自分自身が商品となる(コンサルティング)
2 新しい商品を作る
重点顧客に集中できるよう、不要なリードは捨てる。すぐに決まらないリードはマーケチームに戻す。
「戦術を3つのフェーズに分けて組み立てる」
1 日常フェーズ(Chapter5)
2 初回購入フェーズ(Chapter6)
3 継続購入フェーズ(Chapter7)
Chapter5 日常生活フェーズ「信頼」と「純粋想起」を獲得する
50%は営業と会う前に購入を決めている。日常フェーズのゴールは信頼と準想起の獲得。顧客のニーズが潜在化する前から選ばれる状態を目指す。
コンテンツで信頼を獲得するには3つの要素が必要
1 非常識(本音で否定する)
2 網羅性(徹底的に調べて公開)
3 エンタメ性(読んだり見たりして楽しい)
書籍は信頼のコンテンツとなる。ウェビナーは内職を辞めさせる工夫を。広報はターゲット媒体を見つけ、記者との関係性を作る。ホワイトペーパーは信頼を得るに値する内容と量を。展示会は顧客リストを買っていると認識すべき。潜在顧客が大半なので名刺獲得に専念する。メルマガは件名でサービス名を連呼し純粋想起を獲得する(内容はサボり頻度を上げる)。
Chapter6 初回購入フェーズ「商談」と「商品」の障壁を下げる
新規受注は継続受注やアップセルよりも圧倒的に難易度が高い。そのためステップを作ってゴールを目指す。
「4ステップ」
1 商品設計:従量課金、ドアノック商品、代替商品の3つ
2 商談設計:インサイドセールスが潤滑油になる
3 CV設計:WEBサイトでは説得ができない。1stViewからCV直行へ。
フォームはフィードバックが明確、簡単、離脱要因がないように。
4 集客設計:デジタル広告はAIに任せる。SEOは言いたいことではなく検索ニーズを読み取る。メールは送信者名、本文見出し、タイトルを考慮。
Chapter7 継続購入フェーズ LTVトリガーを定性調査で見極める
マーケターは商品そのものを磨きLTVを最大化する。LTVが伸びると集客コストに回せるため施策の幅も広げることができる。定量調査よりも定性調査を優先して行う(ロイヤルカスタマーを募り、商品との時系列を聞いていく。HOWは参考にならないので聞かない)。LTVを高めるために、従量課金などスイッチングコストを上げる仕組みを。
