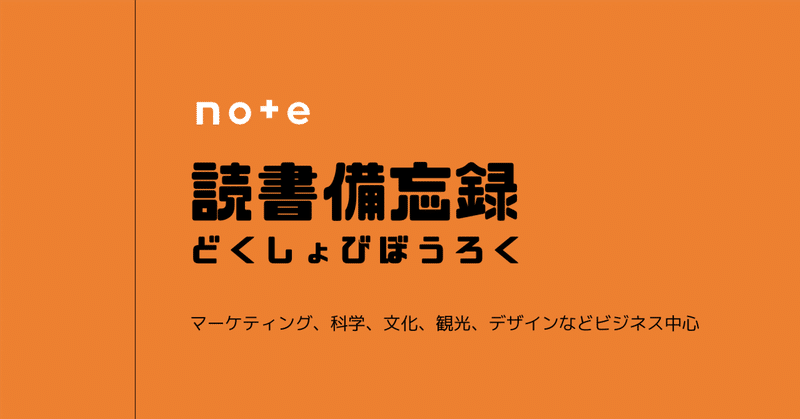
朝日新聞政治部
「朝日新聞政治部」(鮫島 浩 著)
本書は、朝日新聞 鮫島氏の内部告発である。
第一章 新聞記者とは?
(1994-1998年)
・鮫島 浩 1994年 京都大学法学部を卒業し、朝日新聞に入社。
・他新聞社をいかに出し抜いて情報をもらいスクープにするかが昇進への道(特ダネ。逆に自社だけ記事にできなかった場合を特落ちと呼ぶ)
・政治家、警察と仲良くし情報をもらう。都合の悪い情報を掲載するとその後情報をもらえなくなるため、権力に逆らえない構造となる。
第二章 政治部で見た権力の裏側
(1999-2004年)
・大蔵省、外務省からNHK、朝日新聞へ情報が流れる。
・他の政党はNHKや朝日新聞が情報を掲載した後に知ることもある
・総理の番記者は、総理大臣を終日追いかけることと総理秘書官を取材し、総理の本音を探ること。総理秘書官が会食に応じることもある。基本的にオフレコ。番記者は、記事を書くのではなく取材メモで評価される。
・当時は、取材相手との密着取材が評価につながっていた。
・担当する政治派閥が、自身の出世に影響する。
・大物政治家には各メディア15社が番記者を張り付けその中で一番を目指す
(政治記者は1〜2年で配置換えになるため、自分の会社の先輩後輩がライバルにもなる)
・政治家に食い込んだと思っていたら都合の良い情報操作に利用されることもある。だから国会や会見を重要視すべき(オフレコは嘘が発覚しても情報源が不明)しかし、やはりオフレコ取材は政治報道に必要なものでもある
第三章 調査報道への挑戦
(2005-2007年)
・取材をしていないのに虚偽メモが記事として出た事件(朝日新聞)
・デスクやキャップが、記者本人に確認せずに記事にしたことも問題
・デスクは管理職
・当時は政治部が実権を握っていた。そのため社会部との対立があった
・上記の政治部の事件により、社会部からの追及が厳しかった側面も。
調査報道
・調査報道をミッションとした、特別報道部の新設
・社会部にも調査報道担当もあり、疑心暗鬼な目線もあった
調査報道(ちょうさほうどう)とは、新聞社や放送局、出版社などが事件や社会事象について、独自に取材調査して報道するスタイル。取材する側が主体性と継続性を持って様々なソースから情報を積み上げていき、新事実を突き止めていこうとするもの。発表に頼らず自社で調べて、自社の責任で報道する記事やニュースのことを指す
社会部のこれまでの調査報道
1:警察や検察などのテーマを掘り下げる(ネタをもらう以上権力抗争に巻き込まれる)
2:タレコミ(内部告発)により記事化(真偽を確かめると記事にならないネタが多い)
特報チームの調査報道
1自らのテーマに設定によるため他社に抜かれる構造にならない
2枠(社会面、経済面など)紙面を埋める記事にならないようにノルマを持たない
「特報チームの2大原則」
・警察や検察を回らない
・タレコミは受けない
→何を追うのか、テーマ設定を何をするかが重要
・2006年、スケート連盟のスキャンダル(裏金の不正問題)を取材し、特ダネとなった。しかし社会部との確執は一層深まる。
・任期満了後に、鮫島氏は政治部に戻る。
第四章 政権交代と東日本大震災
(2008-2011)
・小泉総理から安倍総理へ、そして菅総理
・官房長官の会見が公式見解となり総理が最も信頼する政治家にあたる
・官房長官番の仕事は、毎日2回の会見と深夜や週末にも情報を追いかける。ありとあらゆる情報が官房長官に集まる。裏付けを取るようにデスクやキャップからプレシャーを受ける。朝と晩に電話をする。嫌われて電話に出てもらえなくなると仕事にならない。
・自民党幹部や各派閥に番記者をつけて、そこからキャップとデスクが分析してまとめて、原稿を築地の本社へ送り、本社の担当デスクが対応する流れ
2011年、東日本大震災(菅総理時代)
・福島県内の原発取材、泊まり込みによる取材
・通常は総理や官房長官と電話の折り返しがある関係だったがこの時は折り返しがなかった
・記者会見の内容を報道するしかなかった(裏付けを取れなかった)
・もし、総理たちは関東が壊滅的になる可能性を報道して世の中に混乱させることをしたかどうか
・記者の安全確保と、正しい情報取得の矛盾
第五章 躍進する特別報道部
(2012-2013)
・鮫島氏、特報チームへデスクとして帰還
・社内は社内の政治力で記事の取り上げられ方が変わる現状だった
・新たな朝日新聞としての売りが必要だった。それが「調査報道」と「オピニオン編集部」だった
プロメテウスの罠とは、福島第一原子力発電所事故および「原発」をテーマとして2011年10月から2016年3月まで掲載された朝日新聞の調査報道による連載記事
特別報道部の強み
1 記者クラブに属さない
2 持ち場がない(他社と競う必要がない)
3 紙面がない(穴埋め原稿を書く必要がない)
4 組織の垣根がない(年功序列もない)
5 ノルマがない(主体的に取材する)
→特報部は、1面トップのスクープだけを追う
→テーマは自分で決める。必要に応じて仲間を呼ぶ
→記者はデスクを自由に選ぶ
・注目された特別報道部。新聞協会の受賞スピーチで、調子に乗ったこと。上司からは快く思われていなかったこと。
第六章「吉田調書」で間違えたこと
(2014)
・政府は原発時の唯一の公式文書である吉田調書を公開していなかった
・朝日新聞が吉田調書を独自入手(A4で400ページを超える)
・記事公開4ヶ月後に政府により公開された
・吉田調書(よしだちょうしょ)
2011年に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故で陣頭指揮を執った吉田昌郎・福島第一原子力発電所所長(当時)が2011年7月22日から11月6日にかけて「内閣官房東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(政府事故調)の聴取に応じた際の記録の通称
・吉田調書の取材源の発覚を恐れ、取材担当2名(木村、宮崎)は慎重だった。加えて堀内、鮫島の4名だけが吉田調書を読んだ
・東電の隠蔽体質を追い続けた記者の結果だった
・メールアドレスを頻繁に変える、撹乱するためのダミーのメールを送る、盗聴を避けるために同じ場所で打ち合わせをしないなど
・吉田調書事件
2011年に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故で、東京電力福島第一原発の吉田昌郎元所長が政府事故調の聴取に答えた記録「吉田調書」をめぐり、朝日新聞が「所長命令に違反、所員の9割が撤退、事故対応が不十分」と大々的に報じた事件。朝日新聞社の木村伊量社長は記者会見で「『命令違反で撤退』との表現」を取り消した。
・朝刊一面の掲載に先駆け、朝日新聞デジタルでスクープの事前告知を行うという実験的試みもインパクトがあった。
・表現自体は行き過ぎたものもあった可能性があるため、続報としての補足対応をすべきであった(撤退という表現など)
・新聞協会賞を意識した上層部が、続報の補足に水をさす事態となった(危機対応が甘かった)
批判
所長が待機命令をしたところ、所長命令が全所員に届いたかは不明、そのため第2原発へ移動・避難したことが待機命令に反したかは不確かというもの
報道の取り消し
結果的に、2014年9月に吉田調書報道は取り消され、鮫島デスクは更迭。個人情報も流出し大炎上。木村、宮崎記者も退社。当時の木村社長も辞任。
慰安婦報道
慰安婦報道の問題が取り上げられ、無関係の吉田調書問題も再度炎上に巻き込まれていった
・慰安婦報道
1990年代、朝日新聞の報道で慰安婦問題が日韓の係争問題になり出した際に、慰安婦と女子挺身隊(第二次世界大戦中、未婚女性が工場などで勤労する団体)の誤解、日本軍の慰安婦強制連行についての証言などの報道がなされた。この誤解が日韓双方に広まっていたため、韓国国内で対日感情が悪化した。その後、2014年に誤報として訂正した。
⚫︎吉田調書問題、慰安婦報道問題、池上彰氏のコラム問題の3点セットにより、朝日新聞へのバッシングは最大の炎上は加熱していった
・池上コラム問題
池上彰氏が朝日新聞のコラムの2014年8月29日掲載予定の原稿で、朝日新聞による従軍慰安婦報道の検証を不充分だと批判的に取り上げたところ、8月28日に朝日新聞から掲載を拒否する連絡があった。これに対して、池上氏は朝日新聞との信頼関係が崩れたとして、連載中止を申し入れた
第七章 終わりのはじまり
(2015-2021)
・鮫島氏は知的財産室への異動。
・ネットでの罵詈雑言に目を背けたことがバッシングの要因と気付いた
・その後、無難な記事を量産しているように感じていた
・鮫島氏はTwitterのアカウントを開設し、発信を始めた
・特別報道部は、管理下の元に変貌し事実上消滅
おわりに
・2021年、鮫島氏(49歳)、早期退職制度により朝日新聞を退職
・フリーとして独立し、SAMEJIMA TIMES公開
