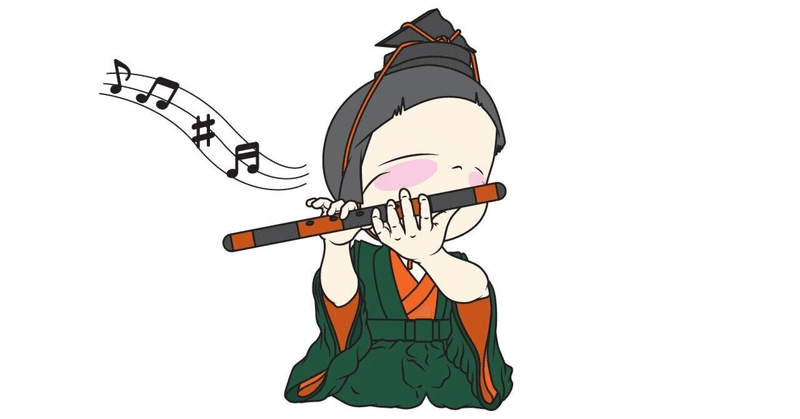
15年ぶりの吹奏楽コンクール
7月の3連休、久しぶりに地元宮崎に帰省した。
コロナがまた流行り始めているのか、唯一会う予定だった友人もコロナに罹ってしまい、2泊3日の中日が丸一日空いてしまった。
鹿児島の友人に声をかけたが、吹奏楽部の顧問をしているため、コンクールシーズンのこの時期に空いてるはずもなく。結局宮崎の吹奏楽コンクールに行ってみることにした。
ー*ー
中学生の頃、吹奏楽部に入っていた。15年くらい前の話だ。
あまり言うと簡単に学校が特定されてしまうので詳しくは言わないが、少なくとも強豪ではなく、かといって小さい部でもなかった。
おそらく当時の他の学校の吹奏楽部と同じように、週7で部活をし、命を賭ける思いでコンクールの練習をし、よくある部内の派閥やごたごたした人間関係や恋愛関係を一通り見てきたとは思う(恋愛に関しては友人のを見守るばかりだったが)。黒歴史ばっかりと言いつつもそれなりに中学生らしい思い出はあるし、青春の1ページになったことは間違いない。
そんな懐かしの当時の自分を重ねに行ってきた。
ー*ー
朝10時、15年前と同じ会場へ。当日券とパンフレットを買ってホールへ。吹奏楽コンクールに観客として来るのは初めて。関係者に優先してチケットを売るため、私のような完全アウェーな観客は基本的に当日券の購入になるらしい。そんなことを知らないくらい、演者と観客では見えてる世界が違う。
プログラムに目を通して驚いたのは、私が訪れた日はほとんどの学校が30人規模だったこと。私たちが学生やってた頃は、3学年出てしまうと規定人数の50人を超えるので、どう絞るかって話をよくしていた覚えがある。私の学校は50人はぎりぎり超えなかったので、基本的には全員舞台に乗っていたが、他校に行っていた友人は1年生が出れなかったり、それぞれ独自のルールで絞っていた。それでも、50人ぎりぎりは攻めていたんじゃなかろうか。
ここ数年強豪と言われる学校でも、なかなか50人に迫る人数を見ることができず、そもそも人数を絞っていないのだろうかとすら感じた。宮崎で教員をしている友人が、少子化の影響でクラス数が減っていると言っていたが、ここにも影響が出ているのかもしれない。
30人に届かないかくらいの人数となると、パート割りも大変。今回、時間の都合で午前中しか聴けなかったが、記憶が合っていれば、オーボエが入った学校は1校、ファゴットはなし、コントラバスもわずか数校。トロンボーンがいない学校もあった。人数が足りなくともなんとか目立つところだけは入れようと、打楽器の人がコントラバスのピチカートのみ持ち替えをしたり、ホルンの人がトランペット三重奏の箇所だけトランペットに持ち替えたり。努力が涙ぐましい。。
ー*ー
それでも、音楽は超越した力を持つもので、人数に関係なく心に響くものである。コンクールの規定に合わせないといけないから大変なだけで、それと音楽という表現活動をすることは別問題。
県内各地から集った学校たちは、多種多様な音楽表現をしてくれた。それは日々の練習の積み重ねの結果というより、この年に一度の晴れ舞台に向けたエネルギーの現れなのかもしれない。そんな演奏を聴いていると、何か宮崎の吹奏楽文化の発展(もっと大きく言うと地方の音楽文化の発展)のために力になれることはないかと考えてしまう。
ー*ー
今、宮崎の吹奏楽界は誰が引っ張っているのだろう。問題提起とかではなく、純粋な疑問。
私の母も学生時代は吹奏楽部だった。当時は宮崎から初めて全国大会に行く学校が出たような時期。全国大会に連れていった学校で指揮をしていた先生の元には、その先生から指導を求める他校の先生が集まっていたという。当時まだ若手だった先生方はその後、私が中学生になった頃に宮崎の吹奏楽界を引っ張っていたように思う。残念ながらその後私が吹奏楽から離れてしまい、それから先が終えていないのだが、あの野球で有名な延岡学園に音楽コースができたり、冬の吹奏楽コンクールをやっていたりと、宮崎の吹奏楽をどんどん活発にしていこうという動きがあるのは聞いている。
少子化や、学校教育の教員の労働環境を改善しようとする動き、さらには学校教育が目指す方向の変化、と、時代と共に学校教育を取り巻く状況が変わっていくことは避けられない。それでも、今日も音を重ね合わせる歓びを感じ、一つの目標に向かって全力を尽くす学生たちがいる。音楽の教員免許を取得したものの今は学校教育には全く関わっていない私だが、いつかどこかで、音楽をする学生たちと交わる機会や、何か音楽文化の発展に寄与できる機会があったら幸せである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
