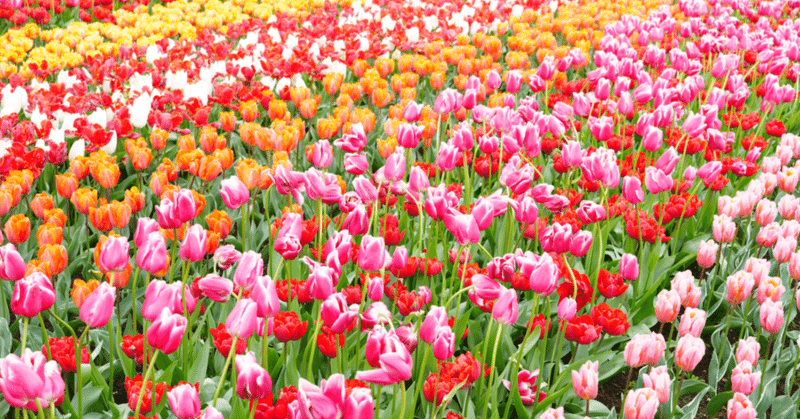
読書記録 論点思考
こんにちは!気持ちの良い気候になりましたね。私の家の近くの公園ではツツジが咲き乱れており、バラももうじき見頃を迎えそうです。
本日は「論点思考」(内田和成 著)を紹介します。
本書は問題解決をする上で正しい論点を見つけるための考え方や手法についてまとめられています。
もう少し簡単な言葉で説明します。例えば、「自分が経営しているレストランにお客様が集まらない」という悩みがあったとします。お客様が集まるようにするには、料理を改善すべきのか、接客スタイルか、広告か。他にも数え切れないほどの要素がある中で、「これを解決したら悩みが解消されるのでは?」という論点を見つけ、策を立てていきます。本書ではその一連のプロセスについて書かれています。
この本を読もうと思った理由は?
「論理的に物事を考える」ということが極端に苦手で、何か克服のきっかけにならないだろうか、と感じたからです。本書は会社の上司から勧めてもらいました。
感情を扱い、「論理」という言葉の対極とも言える音楽に長く親しんできた私からすると、言語を扱うことはもちろん、物事を積み木のように一つ一つ組み立てるという行為は大の苦手です。音楽はあくまで趣味なので、この考え方を仕事の場に持ち込むことはできません。社会人になって7年、論理という言葉から逃げながらここまでやってきましたが、プライベートと仕事で頭の使い方を明確に分ける、そのための第一歩として本書を読みました。
特に印象に残った内容は?
「視野」「視点」「視座」を使い分ける、という点です。論点を洗い出すにあたり、視点を変えて、違う観点から論点を見つけられないだろうか、という手法は頻繁に使われます。会社が新しいPCを導入しようというときに、コスト面だけを見るのではなく、スペックやメーカの信頼性など別の観点も考慮しますよね。
本書では「視点」を変えることだけでなく、「視野」「視座」も扱えるようにすることを勧めています。「視野」は事象をまっすぐ見るのではなく、後ろや横からも見ることで論点が見つからないだろうかと探す手法です。「視座」は自分から離れたポジションから物事を見ることで論点が見つからないかと探す手法です。
私はこの文章を読んで、「視点」を点、「視野」を横方向に広がる帯、「視座」を縦方向に広がる帯のようにとらえました。
論点を探すにあたり、灯台下暗しの状況を避けるために有効な方法だなと感じました。
本を読んで感じたこと
「論点」の話を軸に問題解決のプロセスが丁寧に書かれており、すとんと腑に落ちる感覚がありました。これも、本全体が論理的な構成になっているからなのでしょう。読み終わったあとには、「さぁ、実践してみよう」と前向きな気持ちになることができました。
本を読みきったのは今週の月曜日。今が土曜日なので、4日間実践したのですが、これが難しい。わかるとできるは違う、とはよく言ったものです。
今の業務は論点が無限に上がってきます。論点を挙げきって、絞る作業をしないといけませんが、どれもそれっぽく、どれもそれっぽくないように感じてしまい、なかなか実践しきるところまでできませんでした。わかっているのにできないもどかしさは積もりに積もり、この4日間はこれまでの仕事人生の中でトップクラスにストレスの溜まる時間だったかもしれません。
でも、ここで逃げたくない。本に書いてあることが本当に役に立つかどうかは、自分の身につけてみないとわからないものです。まずは、自分が納得行くまでやりきりたいなと思います。
ー*ー
本日は「論点思考」を紹介しました!
正しい論点を見つけることは、業務を早く行うことや業務の質を高めることにも繋がります。
読んですぐ実践できるほど簡単なものではないですが、スキルアップの一つの観点として読んでみるのはいかがでしょうか?
とても有名な本なので、もし読んだことあるよ!という方がいらっしゃいましたらコメント下さい!意見交換しましょう〜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
