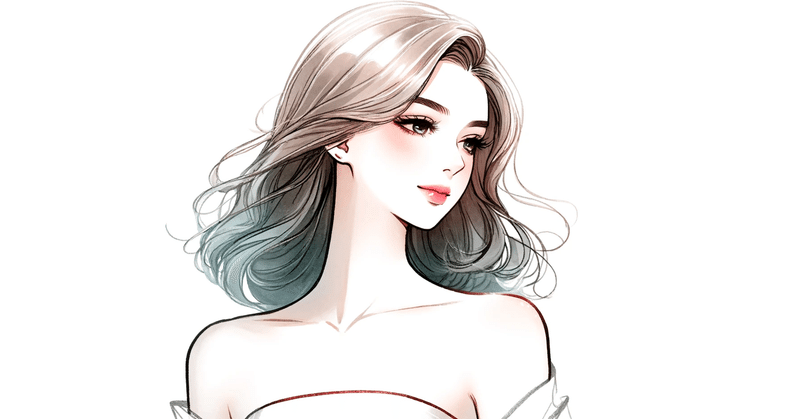
論文まとめ317回目 Nature ミニ結腸システムでex vivoにおける大腸がん発生を時空間的に再現!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなNatureです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
One-dimensional proximity superconductivity in the quantum Hall regime
量子ホール領域における1次元近接超伝導
「微小にねじれた二層グラフェンの中には、ドメイン境界と呼ばれる1次元の線状構造が現れます。今回の研究では、このドメイン境界上に超伝導電極を取り付けることで、量子ホール効果が現れる強磁場下でも超伝導電流を流すことに成功しました。この超伝導状態は磁場に非常に強く、電極自体が超伝導を失う臨界磁場近くまで存在し続けます。これは、ドメイン境界に沿って流れる1次元的な電子のために起こる現象で、将来の量子デバイスへの応用が期待されます。」
Transient loss of Polycomb components induces an epigenetic cancer fate
ポリコーム構成因子の一過的な欠損が、エピジェネティックにがん化運命を誘導する
「がんは通常、遺伝子変異の蓄積によって引き起こされると考えられてきました。しかし今回、ショウジョウバエを用いた実験で、エピジェネティック制御因子であるポリコーム複合体の構成タンパク質を一時的に欠損させるだけで、変異なしにがん化が誘発されることがわかりました。ポリコームを欠損させると、JAK-STATシグナル経路の活性化と転写抑制因子zfh1の発現上昇が起こり、それが自律的に維持されることで、ポリコームタンパク質が回復してもがん状態が継続することが明らかになりました。遺伝子変異を介さない新しいがん化機構の発見です。」
Spatiotemporally resolved colorectal oncogenesis in mini-colons ex vivo
生体外ミニ結腸における時空間的に解析された大腸発がん
「大腸がんの発生メカニズムの解明には、生体内に近い複雑な環境を持つ培養モデルが必要不可欠です。本研究では、工学的手法を駆使して、生体外で大腸がんを再現できる「ミニ結腸」システムを開発しました。光遺伝学を用いて、がん遺伝子の活性化を時空間的に制御し、単一細胞レベルでがん化の過程をリアルタイムに追跡。ミニ結腸内に生じたがんは、生体内のがんと同様の多様性を示しました。さらに、がん化を促進する遺伝子や環境因子を特定するのにも役立ちます。この革新的なシステムにより、生きた動物を使わずに、大腸がんの発生メカニズムを詳細に研究できるようになりました。」
Valleytronics in bulk MoS2 with a topologic optical field
トポロジカルな光場によるバルクMoS2におけるバレートロニクス
「電子のバレー自由度は、省エネルギーな情報処理の実現に向けた有望な手段ですが、これまでは単層構造や特殊な材料設計が必要でした。本研究では、時間反転対称性と空間反転対称性を一時的に破るトポロジカルな「三つ葉」光パルスを用いることで、バルクのMoS2においてバレー分極を誘起し、光学的に高速制御することに成功しました。これは、単層に限らずあらゆる層数の構造や様々な物質で適用可能な汎用的手法であり、量子コヒーレントな時間スケールで動作する効率的なバレートロニクスデバイスの実現に道を拓くものです。」
Regioselective hydroformylation of propene catalysed by rhodium-zeolite
ロジウム-ゼオライト触媒によるプロピレンの位置選択的ヒドロホルミル化
「プロピレンから高付加価値のn-ブタナールを選択的に合成するヒドロホルミル化反応は工業的に重要ですが、これまでの不均一系ロジウム触媒では位置選択性が限られていました。今回、ロジウムをMELゼオライトの細孔内に閉じ込めることで、99%以上の選択性でn-ブタナールを生成できる触媒の開発に成功しました。ゼオライトの骨格が反応中間体を立体的に制限することで、反応経路をn-ブタナール生成に誘導していると考えられます。この触媒は既存の均一系触媒をも上回る性能を示し、工業的に大きなインパクトを持つ成果です。」
要約
量子ホール効果を示すグラフェンにおいて、1次元的な近接超伝導を実現
本研究では、微小にねじれた二層グラフェン中のドメイン境界を利用して、量子ホール効果が現れる強磁場下でも超伝導近接効果を実現しました。ドメイン境界上に形成した超伝導接合は、超伝導電極の臨界磁場近くまで超伝導電流を維持し、その大きさは境界に沿った1次元バリスティック伝導チャネルの量子コンダクタンスで制限されることがわかりました。この系は量子化磁場中でAndreev束縛状態を形成できる特異な能力を持ち、今後のさらなる探求が期待されます。
事前情報
微小にねじれた二層グラフェンには、ドメイン境界と呼ばれる1次元の線状構造が現れる。
量子ホール効果が現れる強磁場下で、エッジ状態を介した超伝導近接効果の実現が期待されている。
これまで量子ホール伝導体中で検出可能な超伝導電流を得ることは難しかった。
行ったこと
微小にねじれた二層グラフェン中のドメイン境界上に超伝導接合を形成した。
量子ホール領域における接合の伝導特性を調べた。
超伝導電流の磁場依存性と電子密度依存性を系統的に測定した。
多数のドメイン境界を含む接合についても測定を行った。
検証方法
微分抵抗の磁場依存性から超伝導電流の臨界磁場を評価した。
磁場中での超伝導電流の大きさをドメイン境界の数で規格化した。
量子ホール領域での抵抗の温度依存性とRFパワー依存性を調べた。
量子ホール領域での超伝導電流の電子密度依存性をファブリ・ペロー干渉で検証した。
分かったこと
ドメイン境界を含む超伝導接合は、量子ホール領域でも超伝導電流を維持できる。
超伝導電流は電極の臨界磁場近くまで非振動的に一定の値を示す。
超伝導電流の大きさは、ドメイン境界に局在する1次元バリスティックチャネルの量子コンダクタンスで制限される。
多数のドメイン境界を含む接合でも同様の振る舞いが見られた。
この研究の面白く独創的なところ
微小ねじれ二層グラフェンのドメイン境界を用いて、強磁場下で1次元超伝導を実現した点が独創的。
量子ホール効果と超伝導の共存という、これまで実現が困難だった状況を生み出した点が画期的。
超伝導電流が電極の臨界磁場近くまで維持されるという驚くべき結果を示した点が興味深い。
1次元チャネルの量子伝導度が超伝導電流を制限するというシンプルな描像を実証した点が美しい。
この研究のアプリケーション
量子ホール効果と超伝導の融合による、新奇量子現象の探索に道を開く。
トポロジカル超伝導や局所的アンドレーフ束縛状態の実現に役立つ可能性がある。
超伝導量子干渉計(SQUID)など、強磁場動作可能な超伝導デバイスへの応用が期待される。
1次元超伝導の物理の理解を深め、ナノワイヤ等の研究にも示唆を与える。
著者と所属
Julien Barrier, Minsoo Kim, Roshan Krishna Kumar, Na Xin, P. Kumaravadivel, Lee Hague, E. Nguyen, A. I. Berdyugin, Christian Moulsdale, V. V. Enaldiev, J. R. Prance, F. H. L. Koppens, R. V. Gorbachev, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. I. Glazman, I. V. Grigorieva, V. I. Fal'ko & A. K. Geim
(Department of Physics and Astronomy, University of Manchester; National Graphene Institute, University of Manchester; Department of Applied Physics, Kyung Hee University; ICFO — Institut de Ciencies Fotoniques, The Barcelona Institute of Science and Technology; Department of Chemistry, Zhejiang University; Department of Physics, Lancaster University; National Institute for Materials Science; Department of Physics, Yale University; Henry Royce Institute for Advanced Materials, University of Manchester)
詳しい解説
本研究は、微小にねじれた二層グラフェン中のドメイン境界を利用して、量子ホール効果が発現する強磁場中でも超伝導近接効果を実現することに成功した、大変興味深い成果です。二層グラフェンを微小な角度でねじれると、モアレパターンと呼ばれる長周期の干渉縞が現れます。このモアレパターンの節に沿って、グラフェン層間の積層構造が入れ替わる線状の境界、いわゆるドメイン境界が形成されます。近年の研究から、このドメイン境界には特異な1次元電子状態が局在していることが分かってきました。
一方、量子ホール効果が起こるような強磁場中では、グラフェンのエッジに沿って流れる1次元のエッジ状態が電子伝導を担います。超伝導体に接したエッジ状態では、クーパー対のトンネリングによって超伝導近接効果が生じると期待されますが、これまで量子ホール伝導体中で有意な超伝導電流を得ることは難しいとされてきました。
本研究では、ドメイン境界上に超伝導電極を形成することで、この難題に挑戦しました。その結果、驚くべきことに、量子ホール領域においても明瞭な超伝導電流が観測されたのです。しかも、その超伝導状態は印加磁場に対して非常に強く、超伝導電極自体が超伝導を失う臨界磁場近くまで維持されることが分かりました。
超伝導電流の大きさを詳しく調べたところ、それがドメイン境界の数に比例し、1本あたりの超伝導電流が量子化コンダクタンスで制限されていることが明らかになりました。これは、ドメイン境界に沿って流れる1次元バリスティック伝導チャネルを介して超伝導近接効果が生じていることを示唆しています。
さらに研究チームは、ファブリ・ペロー干渉と呼ばれる量子干渉効果を用いて、1次元チャネル中の超伝導電流の振る舞いを調べました。その結果、超伝導電流が電子密度の変化に対して周期的に振動することが確かめられ、これが1次元的な起源に由来することが裏付けられました。
本研究の成果は、ドメイン境界という純粋に1次元的な電子系が、量子化磁場中でもアンドレーフ束縛状態を形成する卓越した能力を持っていることを示したものです。この系は、トポロジカル超伝導や局所的マヨラナ状態の実現など、基礎物理学的にも応用的にも非常に興味深い舞台を提供すると期待されます。
超伝導量子デバイスの分野では、強磁場中で動作可能な素子の開発が大きな課題となっています。本研究で示された強靱な1次元超伝導は、この問題を克服する上で重要な糸口になるかもしれません。また、ナノワイヤなどの擬1次元超伝導体の研究にも、新しい知見をもたらすことでしょう。
本研究は、トポロジカル量子伝導と超伝導の融合という新しい地平を切り拓くものであり、今後のさらなる展開が大いに期待されます。二次元物質の豊かな自由度と超伝導の組み合わせは、これからも私たちを驚かせ続けてくれるに違いありません。
ポリコーム複合体の一時的な機能喪失が、がんの表現型を不可逆的に誘発する
本研究は、ショウジョウバエのモデルを用いて、エピジェネティック制御因子であるポリコーム複合体(PRC1)の構成タンパク質PHやPSCを一時的に欠損させるだけで、遺伝子変異なしにがん化表現型が誘発されることを示した。一過的なPRC1の欠損により、JAK-STATシグナル経路の活性化と転写抑制因子zfh1の発現上昇が引き起こされ、それが自律的に維持されることで、PRC1タンパク質が回復してもがん状態が持続することが明らかになった。PRC1の欠損により可逆的に発現変動する遺伝子群と、不可逆的に発現上昇する遺伝子群が同定され、後者のゲノム領域ではクロマチンのオープン状態が維持されていた。この研究は、遺伝子変異を介さない新しいがん化機構を示しており、エピジェネティック異常によるがん促進の可能性を示唆している。
事前情報
がんの発症・進展には、体細胞変異の蓄積が重要と考えられてきた
エピゲノム異常も、がん化に関与することが示唆されている
ポリコーム複合体は、発生関連遺伝子の抑制を介して細胞の運命決定に関わるエピジェネティック制御因子
ポリコーム異常は、がんを含む様々な疾患に関連することが知られている
行ったこと
ショウジョウバエ幼虫の眼原基でポリコーム構成因子PHを一過的にノックダウン
PH一過的ノックダウン後の腫瘍形成の表現型解析と、がんゲノム・トランスクリプトーム解析
PH回復後のクロマチン状態の解析
JAK-STAT経路とzfh1の腫瘍形成への関与の検証
検証方法
条件的RNAiシステムを用いたPHの一過的ノックダウン
腫瘍形成の表現型解析(組織の過形成、極性の喪失、分化マーカーの消失など)
全ゲノムシークエンスによる体細胞変異の検出
RNA-seqによる遺伝子発現変動の網羅的解析
ChIP-seq、CUT&RUN、ATAC-seqによるクロマチン状態の解析
zfh1とStat92Eの二重ノックダウンによる表現型の レスキュー実験
分かったこと
PH一過的ノックダウンにより、変異なしに腫瘍形成が誘発された
腫瘍には、ドライバー変異となりうる体細胞変異は検出されなかった
PH欠損により、一過性と持続的の2種類の遺伝子発現変動が生じた
持続的な発現上昇遺伝子には、JAK-STAT経路の構成因子とzfh1が含まれていた
PHが回復しても、持続的発現上昇遺伝子のクロマチンはオープンな状態が維持された
JAK-STATとzfh1のノックダウンにより、がん化表現型が抑制された
この研究の面白く独創的なところ
エピジェネティック異常だけでがん化が誘発されることを実証した点
ポリコーム複合体の一過的な機能阻害という新しいアプローチを用いた点
可逆的と不可逆的な遺伝子発現変動を区別し、後者の特徴を見出した点
エピジェネティック異常によるシグナル経路活性化とがん化の分子機構を示した点
この研究のアプリケーション
エピゲノム異常に着目した新たながんの早期診断・予防法の開発
ポリコーム複合体を標的とした抗がん剤の開発
遺伝子変異に依存しないがんの新たなモデルとしての応用
エピジェネティクス制御を介した細胞運命決定機構の解明
著者と所属
V. Parreno, V. Loubiere, B. Schuettengruber, L. Fritsch, C. C. Rawal, M. Erokhin, B. Győrffy, D. Normanno, M. Di Stefano, J. Moreaux, N. L. Butova, I. Chiolo, D. Chetverina, A.-M. Martinez & G. Cavalli
(Institute of Human Genetics, CNRS, University of Montpellier, Montpellier, France; Research Institute of Molecular Pathology, Vienna BioCenter, Vienna, Austria; University of Southern California, Los Angeles, CA, USA; Institute of Gene Biology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Semmelweis University Department of Bioinformatics, Budapest, Hungary; Department of Biophysics, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary; Department of Biological Hematology, CHU Montpellier, Montpellier, France; UFR Medicine, University of Montpellier, Montpellier, France)
詳しい解説
本研究は、ショウジョウバエをモデルとして、エピジェネティック制御の異常だけでがん化が誘発されうることを示した画期的な成果です。 がんは、一般に、がん遺伝子の活性化や がん抑制遺伝子の不活性化につながる体細胞変異の蓄積によって引き起こされると考えられてきました。一方で、DNAメチル化やヒストン修飾などのエピゲノム異常も、がんの発症や進展に関与することが示唆されてきました。しかし、遺伝子変異なしにエピジェネティック異常だけでがん化が起こりうるかどうかは不明でした。
研究チームは、ショウジョウバエ幼虫の眼原基をモデル系として用い、エピジェネティック制御因子であるポリコーム複合体の構成タンパク質PHを一時的にノックダウンしました。ポリコーム複合体は、発生関連遺伝子のクロマチン状態を抑制的に制御することで、細胞の運命決定に重要な役割を果たすことが知られています。驚くべきことに、PHを一時的に欠損させるだけで、遺伝子変異なしに組織の過形成や極性の喪失、分化マーカーの消失などの腫瘍形成の表現型が誘発されたのです。
がんゲノム解析の結果、これらの腫瘍からは、ドライバー変異となりうる体細胞変異は検出されませんでした。一方、トランスクリプトーム解析から、PH欠損により2種類の遺伝子発現変動が生じていることが明らかになりました。1つは、PH欠損時に一過性に発現変動し、PH回復後に元のレベルに戻る遺伝子群です。もう1つは、PH欠損により不可逆的に発現が上昇し、PH回復後も高発現が維持される遺伝子群です。後者には、細胞増殖に関わるJAK-STATシグナル経路の構成因子や、分化抑制に関わる転写抑制因子zfh1が含まれていました。
クロマチン解析の結果、可逆的な発現変動を示す遺伝子群では、ポリコームタンパク質の結合や抑制性ヒストンマークの状態がPH回復後に元に戻っていました。一方、不可逆的な発現上昇を示す遺伝子群では、PH回復後もクロマチンのオープン状態が維持されていました。また、これらの領域にはJAK-STATの下流転写因子Stat92Eの結合モチーフが濃縮されていました。実際、zfh1とStat92Eをノックダウンすると、PH欠損による腫瘍形成が抑制されました。
以上の結果から、ポリコーム複合体の一時的な機能喪失により、JAK-STATシグナル経路の活性化とzfh1の発現上昇が引き起こされ、それが自律的に維持されることで、ポリコームタンパク質が回復してもがん状態が持続するというモデルが提唱されました。本研究は、遺伝子変異を介さない新しいがん化機構を実証した点で画期的であり、エピジェネティック異常によるがん促進の可能性を示唆するものです。
ただし、ショウジョウバエのモデルがヒトのがんにどこまで当てはまるかは今後の検討課題です。また、どのようなメカニズムでポリコーム複合体の機能低下が生じうるのか、そしてそれを予防・検出する方法があるのかも興味深い点です。さらに、エピジェネティック制御を標的とした新たな抗がん剤の開発につながる可能性もあるでしょう。
本研究は、従来のがん研究の常識を覆す発見であり、エピジェネティクスの重要性を示す好例と言えます。DNAの配列だけでなく、その発現制御の仕組みに着目することで、がんの本態に迫る新たなアプローチが開けるかもしれません。今後、この知見がヒトのがん研究にどのように活かされていくのか、大いに注目されます。
遺伝子変異という「ハードウェア」の異常だけでなく、エピジェネティクスという「ソフトウェア」の異常もがんを引き起こしうる。そんな新しいがん像を提示した重要な一歩だと感じました。ポリコーム複合体の機能が一時的に失われるだけで取り返しのつかない変化が生じるとは、生命現象の複雑さと脆さを物語っています。がん研究の新たな地平を切り開く成果として、大きなインパクトを与えるに違いありません。
ミニ結腸システムでex vivoにおける大腸がん発生を時空間的に再現
本研究では、マイクロ流体工学、光遺伝学、組織工学を統合することで、生体外で大腸がんの発生過程を再現できる「ミニ結腸」システムを開発しました。このシステムでは、青色光照射によってがん遺伝子の活性化を時空間的に制御し、単一細胞解像度で数週間にわたってがん化の過程をリアルタイムに追跡できます。生じたがんは、生体内の大腸がんと同様の腫瘍内および腫瘍間の多様性を示しました。また、細胞内在性および外在性のパラメーターを調整することで、がん化を促進する因子や治療標的を特定できます。本研究は、生きた動物を使わずに大腸がんの発生メカニズムを研究する道を拓くものです。
事前情報
がんは遺伝子変異の蓄積によって発生するが、その進化的過程は不明な点が多い
現行の培養モデルは単純すぎて、がんの発生過程を再現できない
そのため、がん発生の研究には多大なコストと倫理的問題を伴う動物実験が不可欠
行ったこと
マイクロ流体工学、光遺伝学、組織工学を統合した「ミニ結腸」システムの開発
青色光照射によるがん遺伝子の時空間的な活性化制御
単一細胞解像度でのがん化過程のリアルタイム追跡
細胞内在性・外在性因子の操作によるがん化の促進と抑制
検証方法
光遺伝学的オンコジーンモジュール(OptoCre)の構築と最適化
マイクロ流体デバイスによるミニ結腸の形成と長期培養
ライブイメージング、免疫染色、組織学的解析によるがん形成の評価
シングルセル RNA-seq と系譜追跡によるがんの不均一性の解析
細胞移植によるミニ結腸由来がん細胞の生体内腫瘍形成能の検証
分かったこと
ミニ結腸内で発生したがんは、生体内のがんと同様の組織構造と多様性を示す
がん幹細胞は結腸の下部に位置し、分化度の異なる子孫細胞を生み出す
ミニ結腸内では、多様ながんクローンが共存し、それぞれ特徴的な遺伝子発現を示す
Gpx2はがん幹細胞に高発現し、その抑制はWntシグナルの低下とがん化の阻害をもたらす
腸内細菌代謝物や食事パターンは、管腔側からがん化に影響を及ぼす
この研究の面白く独創的なところ
工学的手法を駆使して、生体外で大腸がんを再現できるシステムを構築した点
光遺伝学により、がん遺伝子の活性化を時空間的に制御できる点
単一細胞解像度で、がん化の過程をリアルタイムに追跡できる点
腫瘍内および腫瘍間の多様性を生体内のがんと同様に再現できる点
がん化の促進因子や治療標的を特定するための実験的な柔軟性を備えている点
この研究のアプリケーション
大腸がんの発生メカニズムの解明
がんの不均一性の理解と標的治療の開発
がんドライバー遺伝子の同定とその機能解析
がんに対する薬剤スクリーニングプラットフォームの構築
動物実験の削減・代替・洗練(3Rs)に向けた培養モデルの高度化
著者
L. Francisco Lorenzo-Martín, Tania Hübscher, Amber D. Bowler, Nicolas Broguiere, Jakob Langer, Lucie Tillard, Mikhail Nikolaev, Freddy Radtke & Matthias P. Lutolf
所属: Laboratory of Stem Cell Bioengineering, Institute of Bioengineering, School of Life Sciences and School of Engineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerlandほか
詳しい解説
本研究は、生体外で大腸がんの発生過程を忠実に再現できる画期的なシステムを開発したものです。従来の培養モデルでは、がん化に伴う組織構造の変化や細胞の多様性を捉えられず、がん発生のメカニズム解明には生体内の動物実験が不可欠でした。しかし、動物実験は時間とコストがかかるだけでなく、細胞動態の時空間的な解像度が低く、倫理的な問題も伴います。
研究チームは、この課題に挑むべく、マイクロ流体工学、光遺伝学、組織工学を巧みに組み合わせた「ミニ結腸」システムを考案しました。まず、ハイドロゲルに埋め込んだ結腸細胞を、レーザーで彫刻したマイクロ流路に播種。これにより、生体内の結腸に似た陰窩構造を持つ単層上皮を形成させます。この上皮は管腔側から灌流でき、数週間にわたって安定的に維持できるのが特長です。
次に、光遺伝学的オンコジーンモジュール(OptoCre)を導入。これにより、特定の遺伝子座にがん遺伝子変異を持つ細胞を、青色光照射によって時空間的に制御できます。変異細胞はGFPで標識されるため、単一細胞レベルでがん化の過程をリアルタイムに追跡可能です。驚くべきことに、ミニ結腸内では、通常の培養では見られない腫瘍形成が観察されました。しかも、生体内のがんと同様の組織構造と細胞多様性を示したのです。
さらに研究チームは、シングルセルRNA-seqと系譜追跡を駆使して、ミニ結腸内のがんの不均一性を精査。CD44陽性のがん幹細胞が結腸下部に局在し、分化度の異なる子孫細胞を生み出すことを突き止めました。また、ミニ結腸内には、遺伝子発現プロファイルの異なる多様ながんクローンが共存していました。この多様性は、ヒト大腸がんの分子サブタイプとも関連づけられました。
そこで、ミニ結腸をがん化の促進因子や治療標的を特定するためのスクリーニング系として応用。解析の結果、グルタチオンペルオキシダーゼGpx2ががん幹細胞に高発現しており、その阻害はWntシグナルの低下とがん化の抑制をもたらすことが判明しました。加えて、腸内細菌の代謝物(デオキシコール酸、酪酸など)や食事パターン(カロリー制限、カロリー過多)が、管腔側からがん化に影響を及ぼすことも実証。こうした知見は、従来の培養モデルでは得られなかったものです。
本研究の意義は、生体外で大腸がんの発生過程を精緻に再現できるシステムを構築した点にあります。分子・細胞レベルのメカニズム解明から、薬剤スクリーニングまで、幅広い応用が期待されます。また、動物実験の代替となる高度な培養モデルとして、がん研究の3Rsにも大きく貢献するでしょう。ミニ結腸は、他のがん種への応用も視野に入れており、今後のがん研究に新たな地平を拓くものと期待されます。生体を再現する力を武器に、がんの謎に迫る日も近いかもしれません。
トポロジカルな光パルスを用いて、バルクMoS2における非共鳴的なバレー制御を実証
本研究では、バルクのMoS2において、トポロジカルな「三つ葉」光パルスを用いて、電子のバレー自由度を全光学的かつ非共鳴的に制御することに成功しました。この手法では、光パルスのスピン角運動量を整形することで、物質の電子的トポロジーを変化させ、時間反転対称性と空間反転対称性を一時的に破ることでバレー分極を誘起します。実験では、非コリニアな光プローブパルスの第二高調波の発生を通じて、三つ葉位相の回転に依存したバレー分極の生成を確認しました。この結果は、単層構造に限らず任意の層数や様々なバルク物質においてバレー自由度の直接的な光制御が可能であることを示しています。本手法は汎用性が高く、光学的な高速動作により、量子コヒーレントな時間スケールで機能する効率的な多元素バレートロニクスデバイスの実現に向けた可能性を開くものです。
事前情報
バレー自由度は省エネルギーな情報処理の実現に有望だが、単層構造や特殊な材料設計が必要
非共鳴的な光制御により、エネルギー散逸を避け、光学的な高速スイッチングが求められる
バルクの半導体におけるバレー制御は対称性の制約から困難とされてきた
行ったこと
スピン角運動量を整形した「三つ葉」光パルスを用いてバルクMoS2を励起
時間反転対称性と空間反転対称性を一時的に破り、バレー分極を誘起
非コリニアな光プローブパルスの第二高調波発生を介してバレー分極を検出
第一原理計算によりバレー分極の生成メカニズムを解明
検証方法
三つ葉光パルスの位相回転に対する第二高調波信号の変調を測定
高調波発生の偏光依存性からバレー分極の誘起を確認
第一原理計算によるバンド構造と光学応答の予測
二色の励起光の組み合わせから三つ葉光パルスの選択則を検証
分かったこと
バルクのMoS2において、三つ葉光パルスによりバレー分極が誘起された
第二高調波信号は三つ葉位相の回転に応じて60度周期で変調を示した
MoS2の6回対称性に由来する選択則と整合するバレー分極応答が得られた
第一原理計算により、トポロジカルな光場によるバレー選択的な励起が裏付けられた
この研究の面白く独創的なところ
バルクの遷移金属ダイカルコゲナイドにおけるバレー分極の直接的な光制御を実証
共鳴励起を必要とせず、エネルギー散逸の少ない非共鳴的手法を採用
トポロジカルな光パルスにより物質の対称性を一時的に操作する新しいアプローチ
単層に限らず様々な層数や物質に適用可能な汎用性の高い手法を提案
この研究のアプリケーション
省エネルギーで高速なバレートロニクスデバイスの実現に向けた基盤技術
量子情報処理におけるバレーコヒーレンスの光学的制御への応用
様々な層状物質や半導体におけるバレー自由度の活用
超高速光エレクトロニクスや量子光学への展開
著者と所属
Igor Tyulnev, Álvaro Jiménez-Galán, Julita Poborska, Lenard Vamos, Philip St. J. Russell, Francesco Tani, Olga Smirnova, Misha Ivanov, Rui E. F. Silva & Jens Biegert
(ICFO - Institut de Ciencies Fotoniques, The Barcelona Institute of Science and Technology, Castelldefels, Spain; Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Spain; Max-Born-Institut, Berlin, Germany; Max-Planck Institute for Science of Light, Erlangen, Germany; Technische Universität Berlin, Berlin, Germany; Technion - Israel Institute of Technology, Haifa, Israel; Institut für Physik, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany; Department of Physics, Imperial College London, London, UK; ICREA, Barcelona, Spain)
詳しい解説
本研究は、バルクのMoS2における電子のバレー自由度を、トポロジカルな光パルスを用いて全光学的かつ非共鳴的に制御することに成功した画期的な成果です。
電子のバレー自由度は、情報キャリアとしての電子のスピンに加えて、バンド構造の極小点(バレー)に由来する自由度を利用するものであり、省エネルギーで高速な情報処理の実現に向けた有望な手段として注目されています。しかし、これまでバレー分極の生成には単層構造や特殊な材料設計が必要とされ、バルク半導体における直接的な光制御は対称性の制約から困難とされてきました。
本研究では、この課題に対し、トポロジカルな「三つ葉」光パルスを用いるという独創的なアプローチを採用しました。この手法の鍵は、光パルスのスピン角運動量を整形することで、物質の電子的トポロジーを変化させ、時間反転対称性と空間反転対称性を一時的に破ることにあります。これにより、本来反転対称性を持つバルクのMoS2においても、バレー分極を誘起することが可能になるのです。
実験では、中赤外の三つ葉光パルスをMoS2に照射し、非コリニアな可視光プローブパルスの第二高調波発生を介してバレー分極の生成を検出しました。その結果、第二高調波信号が三つ葉位相の回転に応じて60度周期で変調を示すことが明らかになりました。これは、MoS2の6回対称性に由来する選択則と整合するバレー分極応答であり、トポロジカルな光場によるバレー選択的な励起が実証されたと言えます。
さらに、第一原理計算によるバンド構造と光学応答の解析から、このバレー分極生成のメカニズムが理論的にも裏付けられました。三つ葉光パルスにより、一方のバレーの電子が選択的に励起され、バレー間の非対称な電子分布が生じることが示されたのです。
本研究の優れた点は、バルクの遷移金属ダイカルコゲナイドにおけるバレー分極の直接的な光制御を実証した点にあります。これまでの手法とは異なり、共鳴励起を必要とせず、エネルギー散逸の少ない非共鳴的なアプローチを採用しています。また、トポロジカルな光パルスにより物質の対称性を一時的に操作するという新しい発想も特筆に値します。
さらに重要なのは、この手法が単層に限らず様々な層数の構造や物質に適用可能な汎用性の高さです。原理的には半導体や層状物質など、幅広い物質系におけるバレー自由度の活用が期待できます。
本成果は、省エネルギーで高速なバレートロニクスデバイスの実現に向けた基盤技術として大きな意義を持ちます。光学的な高速スイッチングにより、量子コヒーレントな時間スケールで動作する効率的な多元素デバイスへの応用が期待されます。また、バレーコヒーレンスの光制御は量子情報処理における新たな自由度としても注目されており、本手法はその実現に向けた重要な一歩と言えるでしょう。
トポロジカルな光パルスによる物質操作は、超高速光エレクトロニクスや量子光学の分野への展開も期待される興味深いアプローチです。今後、様々な物質系への適用と理論的な理解の深化により、バレートロニクスのみならず広範な光・物質相互作用の制御に向けた新たな道筋が拓かれることでしょう。本研究は、トポロジカルフォトニクスと物質科学の融合による革新的な技術の芽吹きを感じさせる優れた成果と言えます。
ロジウムをゼオライト内に封じ込めることで、高い位置選択性を持つプロピレンのヒドロホルミル化触媒を開発
本研究では、ロジウム種をMELゼオライトの骨格内に適切に封じ込めることで、プロピレンのヒドロホルミル化において99%以上の位置選択性でn-ブタナールを生成できる触媒を開発した。最適化した触媒は、6,500 h-1のターンオーバー周波数で99%以上のn-ブタナール選択性と99%以上のアルデヒド選択性を示し、既存の不均一系触媒のみならず、ほとんどの均一系触媒の性能をも上回った。詳細な検討から、ゼオライトの骨格がロジウム中心と反応中間体の間の空間を制限することで、中間体の反応経路をn-ブタナール生成へと導いていることが示された。この触媒は、高付加価値化学品合成プロセスの効率化に大きく貢献すると期待される。
事前情報
ヒドロホルミル化はアルケンからアルデヒドを合成する重要な工業プロセス
プロピレンから高付加価値のn-ブタナールを位置選択的に合成することが望まれる
固定化ロジウム触媒は再利用性や分離性に優れるが、位置選択性は限定的
ゼオライトは分子ふるい効果により特異な反応場を提供することが知られる
行ったこと
ロジウムをMELゼオライトに封じ込めた新規触媒Rh@MELの合成
Rh@MELによるプロピレンのヒドロホルミル化性能評価
XAS, STEM, CO-IR等による触媒構造解析
DFT計算による反応機構の考察
検証方法
高圧固定床流通式反応器を用いたプロピレンのヒドロホルミル化反応テスト
XAFSによるロジウム種の電子状態と配位構造解析
STEM-EDS, CO-IRによるロジウム種の分散状態解析
DFT計算によるゼオライト骨格とロジウム種の相互作用および反応経路の解析
分かったこと
Rh@MELは99%以上のn-ブタナール選択性と6,500 h-1の生成速度を示した
ロジウムはゼオライト骨格のシラノール基と相互作用し、高分散担持されていた
ロジウムはゼオライト細孔内でRh(I)ジカルボニル錯体として安定に存在していた
ゼオライト細孔が反応中間体を立体的に制限し、n-ブタナール生成に有利な配座を誘起した
反応サイクルの律速段階はヒドリド移動を伴うCO挿入過程であることが示唆された
この研究の面白く独創的なところ
従来の常識を覆す、ゼオライト細孔内でのロジウム触媒反応を実現した点
既存の均一系・不均一系触媒を凌駕する高性能なヒドロホルミル化触媒を開発した点
ゼオライト骨格による反応中間体の立体規制という新しい触媒設計指針を示した点
実験と理論計算を融合させて触媒の構造と反応機構を多角的に解明した点
この研究のアプリケーション
n-ブタナールの効率的合成プロセスの開発
ゼオライト触媒を用いた他のヒドロホルミル化反応への応用
ゼオライト細孔内での新しい遷移金属触媒反応の設計指針
理論と実験の協奏的アプローチによる触媒開発の加速
著者と所属
Xiangjie Zhang, Tao Yan, Huaming Hou, Junqing Yin, Hongliu Wan, Xiaodong Sun, Qing Zhang, Fanfei Sun, Yao Wei, Mei Dong, Weibin Fan, Jianguo Wang, Yujie Sun, Xiong Zhou, Kai Wu, Yong Yang, Yongwang Li & Zhi Cao
(State Key Laboratory of Coal Conversion, Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Taiyuan, China; National Energy Center for Coal to Clean Fuels, Synfuels China Technology Co., Ltd., Beijing, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; Institute of Advanced Study, Chengdu University, Chengdu, China; Shanghai Key Laboratory of High-resolution Electron Microscopy, ShanghaiTech University, Shanghai, China; Shanghai Synchrotron Radiation Facility, Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China; Department of Chemistry, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, USA; Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing, China)
詳しい解説
本研究は、ロジウムをゼオライトの細孔内に閉じ込めるという独創的な発想から、プロピレンのヒドロホルミル化における画期的な高性能触媒の開発に成功した注目すべき成果です。 ヒドロホルミル化反応は、アルケンに一酸化炭素と水素を付加してアルデヒドを合成する重要な工業プロセスです。特にプロピレンから直鎖のn-ブタナールを選択的に得ることは、日用品の原料として大きな需要があります。既存の均一系ロジウム触媒は活性と選択性に優れますが、分離・再利用が難しいという課題がありました。一方、不均一系触媒は再利用性に利点がありますが、回転の自由度が高く立体的な制御が難しいため、位置選択性は限られていました。
研究チームは、ロジウムをMELゼオライトの細孔内に閉じ込めることで、この課題を克服する新しい触媒設計を行いました。ゼオライトは規則的な細孔構造を持ち、分子ふるい効果により特異な反応場を提供することが知られています。MELは12員環の中細孔を持つゼオライトで、ロジウム錯体を内包するのに適したサイズです。
XAFS解析から、ロジウムはゼオライトのシラノール基と相互作用しながら、Rh(I)ジカルボニル錯体として安定に存在していることがわかりました。さらにSTEM-EDSやCO-IRの結果は、ロジウムが細孔内に高分散担持されていることを示しています。こうしてロジウムを細孔内に閉じ込めることで、反応中間体の運動を立体的に制限し、n-ブタナール生成に有利な配座を誘起していると考えられます。
実際、最適化したRh@MEL触媒は驚異的な性能を示しました。6,500 h-1というターンオーバー周波数で99%以上のn-ブタナール選択性と99%以上のアルデヒド選択性を達成したのです。これは既存の不均一系触媒のみならず、ほとんどの均一系触媒をも上回る性能です。さらに、100時間の連続反応でも安定した活性を維持しており、工業利用に耐える耐久性も兼ね備えています。
DFT計算による反応機構の解析から、ゼオライト骨格とロジウム種の相互作用および反応経路の詳細が明らかになりました。反応サイクルの律速段階はヒドリド移動を伴うCO挿入過程であり、ゼオライト細孔がこの過程の遷移状態を安定化していることが示唆されました。また、ロジウムとゼオライトの協奏的な触媒作用により、基質の活性化とヒドリドの供給が効率的に進行していると考えられます。
本研究は、ゼオライト触媒の可能性を大きく広げる成果だと言えます。従来、ゼオライトは酸触媒や金属触媒の担体としての利用が主でしたが、本研究は細孔内で金属錯体の反応性を精密に制御できることを実証しました。これは、ゼオライトを用いた新しい遷移金属触媒反応の設計指針を提供するものです。また、ヒドロホルミル化以外にも、ヒドロシアノ化やヒドロアミノメチル化など、類似の反応への応用も期待できるでしょう。
触媒開発において、実験と理論計算を融合させたアプローチは欠かせません。本研究では、XAFS、STEM、IRなどの多角的キャラクタリゼーションとDFT計算を組み合わせることで、触媒の構造と反応機構を原子・分子レベルで解明することに成功しました。このような協奏的アプローチは、複雑な不均一系触媒の理解と設計を加速する上で重要な戦略だと言えます。
n-ブタナールは、可塑剤や界面活性剤、医薬品など幅広い用途を持つ高付加価値化合物です。本研究で開発されたRh@MEL触媒は、その効率的な合成プロセスの実現に大きく貢献すると期待されます。基礎と応用の両面で価値の高い研究であり、ゼオライト化学と触媒科学の新しい地平を切り開く成果だと言えるでしょう。
不均一系触媒における活性点の原子レベル設計。ゼオライト細孔の形状選択性を精密触媒に活かす。実験と理論の協奏で複雑な触媒現象に迫る。そんな触媒化学の真髄を示す研究だと感じました。地道な積み重ねの先に、サイエンスの美しさと技術の力強さが同居する。この成果を起点に、ゼオライト触媒の新しい科学と応用が花開くことを期待したいと思います。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
