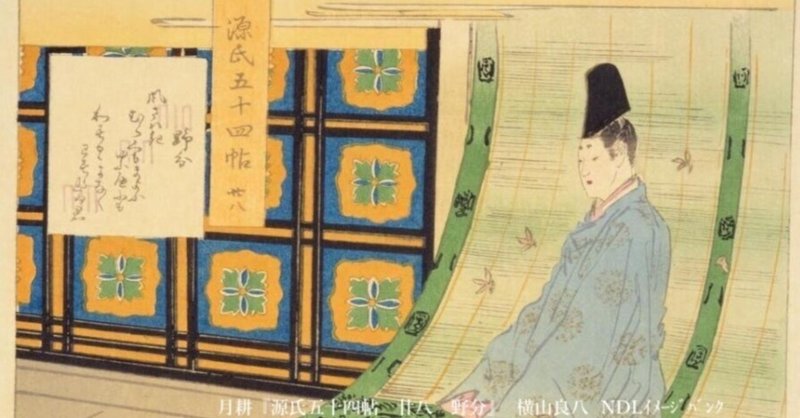
「光る君へ」 第18回 岐路
長徳元年4月。大宰府から宣孝が帰京。内裏では公卿たちが次の関白には道兼が妥当と話す。その様子を一条天皇が壁の窓から聞く(再)。結局、天皇は関白に道兼を指名するが直後に疫病で薨去。伊周を次の関白に決めた帝のもとに詮子が乗りこみ翻意を迫る。帝は母に屈し、道長を内覧・右大臣に。道長とまひろは例の廃屋で再会する。
【今日の行成】
「はい。私は大の道長様びいきにございます」ですか……。
しかし、なんで行成にわざわざこんなこと言わせるんだ?
道長の「まひろのため」に次いで行成の「道長様のため」、来ちゃう!?
どうか行成の脳内に道長の心の声が響くシーンなどありませんように…w
…いや実際、次回のガイド本に嫌な記述を見つけてしまった。。。
死去日が同日だから道長が出る限り行成も出るわけで…もう途中退場してくれた方が気が休まる〜とはならないところがツラいところ。
さて例によって雑な感想を。
帰京した宣孝から宗の科挙制度について食いつくまひろ。
まーた嫌な予感がするんだけど。。まひろって出羽守要素あるよな。陣定は普通「紫宸殿東側渡り廊下=宜陽殿左近衛府陣」(紫宸殿の左近の桜の近く)もしくは「公卿の直盧」で行っていたんだけど、清涼殿の殿上間における殿上定というのもあった。
公式でもコラムになってる。ここには覗き用「櫛形窓」が作られていたとか。そんな天皇用の覗き窓のある場であんな露骨な陰口いう?(聞こえるように言ってる?)
道兼、道隆の死後17日後の4月27日関白となる。
実はこの2日前の25日、検非違使別当が顕光→実資に交替されていた。これが次回の長徳の変で大きな意味を持ってくる(んだけど、たぶんスルー)。
顕光のままだったらあんな大事にならなかったかも?
…いや今回斉信が道長に売り込む発言してたからどっちにしろ斉信→道長ラインで大事にしたか…。道兼、道長を「右大臣にする」。それは“身贔屓“じゃないの?
音声解説「澄んだ瞳で道長を見る道兼」だってー。道兼倒れ、道長を遠ざける。やっぱり疫病=感染るって概念はあるんだ。
思いっきり抱きしめてたけど…。そして道兼薨去。
それにしても関白の身辺に誰もいなさすぎでは。祈祷は?ナレ公卿死。生き残った中納言以上の公卿は伊周、道長、道頼、顕光、公季のみ(道頼も6月には死去)。
詮子、道長・倫子を呼びつける。まぁ同じ土御門殿内なんだけど。
道長に出世欲がない??このドラマでは善人=清貧ってイメージなのかね。
それに「うつけもの!!」??信長!?詮子のキャラ設定もよくわからん。定子様にたしなめられ公卿を懐柔すべく宴会を催す伊周(素直か)。
例によって宴会=悪巧みって描写か。寝所シーン//////
目の保養だけど、道隆の死の直後の内裏還御なので実は内裏触穢中。
最近は全く出てこない穢だけど、さすがに父親の死の服喪は描くべきでは。四条宮で三納言。
いつになったら4人揃うんだ!?意地でも4人の場面作らない気なのかな。まひろ宅を訪ねるききょう。
ききょうの道長評「細かいことにうるさく厳しい」???
このドラマの清少納言の存在意義って何。
定子サロンの様子もないし、公達たちとのやりとりもないし(斉信とだけ)。清涼殿、夜御殿に詮子乱入。無帽の主上が出てきてびっくり。
いや、詮子の物言いの方がびっくりだけども。
自分のことはどうでもいいと言いながら、道長を押すのは自分が伊周、道隆が嫌いだからと言ってるようにしか聞こえなかったんだが。
この場面、大鏡で有名になったけど、実際は一条天皇の方から藤壺にいた詮子の許に渡御している(5/18と6/20の2回)のでたぶん史実ではない。それにしても「中宮に騙されてる」とか「母か妃か」とか下世話すぎない?
大昔の嫁姑ドラマじゃあるまいし次元が低すぎないか。
「主上に寄り添う関白」おっ、こっちは令和の流行り言葉を入れてきたねw
ここ「母の愛」を描いたシーンなんだろうか?(どこが?)
ただの嫉妬&ヒステリーにしか思えなかったんだけど。一夜明け、結局主上は詮子に折れ、道長を内覧とする。一晩で変わってた…。
実際の一条天皇も結構優柔不断というか…krmt先生曰く「先例になるのを避ける」ところがあったようだし(特に後年のあれこれ)。権大納言の道長が一気に関白になるのは身分的に無理だし、伊周の政権担当の可能性も残しておきたかった主上vs道長を関白にしたい詮子のぎりぎりの折衝の結果、内覧宣旨で両者妥協したというところか。
この日、情報が錯綜していたようで、実資が俊賢に問い合わせている。
兼家の長兄伊尹(行成の祖父!)の死後、後を継いだ次兄の兼通(道長と同じく権中納言だった)がまず内覧を務めた先例(972年)に倣ったらしい。
小右記 長徳元年五月十一日条
「大納言(藤原)道長卿が、関白詔を下された」と云うことだ。そこで事情を聞くと、頭弁(源俊賢)が伝え送って云ったことには「関白詔ではない。太政官中の諸事を、堀川大臣(藤原兼通)の例に准じて行なうようにとのことである」ということだ。
キレ伊周、大声で定子様をなじる。
この場面、劇画チックというかアジアドラマの感情爆発シーン並みというか、大袈裟すぎてもう乾いた笑いしか出なかった。。
詮子の女房が円融天皇の中宮だった公任の姉遵子のことを揶揄した「素腹の中宮」を伊周が言わされてたな。
確かにこの頃(これ以降も…)の伊周の行動(随身を賜う件など)はほんとにアホだと思うけど、あの描き方は酷すぎる。
中宮の定子様にあんな暴言吐くわけないじゃん。史実でも十分「ダメ」なことやってるのに、さらに創作でゲスっぷりを割増するのは悪意しか感じない。6月19日、道長が右大臣となる。この時点までは伊周の方が内大臣で上位にいたが、これで権大納言から2階級(大納言、内大臣)飛び越えて一気に伊周を追い越した。
また、道兼薨去と同日に左大臣重信も没し、通常「一上」を務める左大臣が空位となっていたため、道長はこの「一上」も兼ねることに(+氏長者)。言い換えれば、右大臣(のちに左大臣になる)でいれば政務を手放すことなく権力の掌握が出来た(道長はこれにこだわりのちの三条期には関白就任を断っている)。
一上は、太政官の諸公事を執行する職能であり、通例筆頭公卿の左大臣である(欠であれば右大臣以下になる)。(中略)しかし左大臣が関白になると、右大臣が一上となり、関白は一上の職能を行なわないようになる。つまり関白は陣定など公卿議定には加わらないのが慣行となっていき、兼家が大臣を辞して摂関を独立の官としてからは、それが明確になった。また太政大臣も一上の事を行なわない。
このシーンの後、月を見上げてまひろの言葉を思い出してるということは、道長がこの選択をしたのは権力の掌握のためではなく、まひろのためだったってことなんだな。
「まひろの望む世を作る」のに動きやすい身でいるためってか。
道長の行動全てまひろの声に操られてるんだ、こわ…w
いつまでこの「まひろのため」で押し通すつもりなんだろうか。
彰子入内とか定子様の平生昌邸移御を宇治別業遊覧で妨害したこととかも「まひろのため」になるのか!?w倫子と母 穆子の会話、結構しめしめ感あるなw
詮子の里内裏に土御門殿を提供したのも「うまくいったわね」と。
この辺りは実際、道長推しの穆子が言ったかも。
穆子が内覧と関白、右大臣について説明的セリフ言わされてた。
この辺は登場人物に語らせないできちんとナレとか図解した方がよかったんじゃないか。
いくら放映後公式サイトで解説入れたってそこまで見る人がどれだけいるか。
この辺りにも制作側の恋愛ドラマ>歴史ドラマってスタンスを感じるな。
それにしても詮子は道隆が嫌いで東三条殿に寄りつかなかったらしいのに院号が「東三条院」って皮肉だな(実家から採ったとはいえ)。明子と俊賢。「右大臣様一本で行く」ww 行成に足りないのはこの潔さ!
考えたらこのドラマでは明子、倫子の兄弟と道長の絡みが全然ない。俊賢なんて道長と金峯山詣まで一緒に行ってるのに。倫子の異母兄扶義も全くでない。今日の「紀行」は道兼について。これまでの18話であんな創作して紀行でリアル道兼について2分程度やっても焼け石に水、フォローにはならん🙏
【今日のソウルメイト】
夜中、ひとりで廃屋に佇むまひろ。そこにまた!偶然!道長がやってくる。
まひろの言葉を思い出したついでに来てみた?
ここであの一夜過ごしてから7年以上経ってるんだよね?
なぜ浮浪者はこんないい物件に居つかないんだ?
まひろもご近所の道長も歩いて行けるってことは街中なんだよね?…と野暮なツッコミ。
この再会シーン、何か意味があるんだろうか?突拍子なさすぎて…。
そしてただ言葉も交わさず別れる?(さっぱりわからん)
またガイド本から。一番びっくりしたのはこれ。
「道兼が弟思いで、新しい政にも意欲を持っていたことを知る道長は涙を流す」
「弟思い」!?
X見てると同じものを見てるのにほんとにいろんな解釈・感想があるものだなと。
自分には全く理解できない解釈も見かける。そりゃそうだ。
人がどう感じようが自由だし、史実か創作かどちらを重視するかも人それぞれ。
もちろん時に頭に「??」が浮かびまくることもある。
でも自分の解釈も誰かにはそう思われてるかもしれないし…
自分のこのnoteだってテレビの前でぼやくだけにしておけばいいような事をわざわざ毎回4千字以上も書き散らしたシロモノだし…
人のことをどうこう思う前に自分が十分「様子のおかしい人」なんだよな…
…以上、自重の呪文w
今月放送分はハードな場面が多いからここで暴言せぬよう気をつけねばw(手遅れ?)
最近、過去の某大河のwikiを見たんだけど、それが「これ、本当に放送したの!?」というブッ飛び具合だったのだ。ほんとにすごかった。
それと比べたらこの大河はまだ全然マシじゃないかと勇気づけられた。
低いハードルが満足の秘訣とはよく言ったもので…w
自分があの時代クラスタだったら初回下車かもわからん。
次回、まひろが定子様、さらには主上と対面だと!?
科挙のことを進言するらしいけど(何様)そういうことはまひろの望む世を作ることしか考えてない道長に言いなよ。
道長と伊周の殿上の間の口論が7/24で、長徳の変が翌年1/16。
行成の蔵人頭任命がその間の8/29なんだけどちゃんとやるんでしょうね?
ガイド本を見ると今回以上に物議を醸す回となりそう。覚悟しよう…。
ガイド本といえば前編は次回の19話まで。ところが後編の発売が28日。
つまり20(5/19)話、21話(5/26)を全くの未知の状態で見なければならない。
かなりしんどい動きがある2話分なのに!
ガイド本はこういう時の防護壁なのに!
なぜこんな発行日にしたんだろう…。
そういえば後編の書影、そろそろ出るころかな?
第19回予告 またまた出オチタイトル。為光の三の君が登場するみたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
