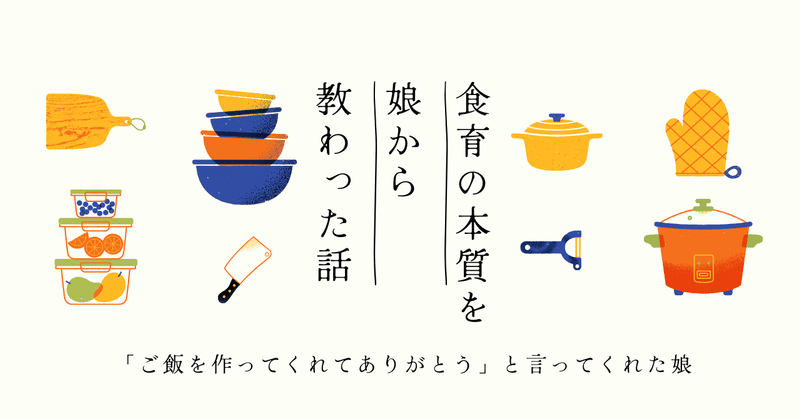
【食育】娘から「ごはんを作ってくれてありがとう」と言ってくれた―食育の本質を娘から教わった体験談
みなさんは「食育」と聞いて、
どのような言葉を思い浮かべるだろうか?
先日投稿した以下の記事に引き続き、
私の食育に対する想いと実際に経験したことをまとめてみたいと思います。
拝啓、食育の本質について理解せずに、食育について勉強していた頃の私へ
食育ってなんだろう?試験勉強のための知識。
「食育」という言葉は大学の授業で出てきた。
その1つが赤黄緑の3色の食品群の表。

エネルギーのもとになるもの、体を作るもとになるもの、体の調子を整えるもとになるもの、といったように分けられていて、各赤黄緑に対して食材が割り当てられている。
専門用語で言うならば、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルの5大栄養素で構成されていて、それの構成要素によって食品が分けられている。
当時の私は、ただ国家試験の勉強のため、試験の勉強のためにやっていた。
それを丸暗記するだけで、食育がなぜ大事なのかは正直わからなかった。
同じ教室で食育について、本当に理解していた人はどれくらいいたんだろうか?
その授業を教えてくれていた先生は、40代の女性の先生で、おそらく子どもも居てらっしゃる。ただ、今思うと授業のカリキュラムという前提での熱量で話を進めていたような気がする。
子どもが生まれて変わり始めた「食育」の考え
そして今、自分に子供が生まれて感じること。
「食育」に対しての考え方が180°といってもいいくらい、捉え方が変わった。
食べ物をありがたくいただくことで、私たちは生かされている
私にとっては、食べる事は生きることであり、食べ物は当たり前にあるものじゃないと感じている。
作り手の思いが込められている。
食材もいるの方や生産の思いが乗っている。
それをありがたくいただくことで、私たちは生かされている。
これが「食育」の1番の本質だと思っている。
拒食症と言われた小学生時代
と言うのも、今だからこそ食に対してとても興味があり、食べることが大好きだけど、
実は小学校5年生までの私は食事に本当に興味がなく、拒食症とさえも言われていた。
習い事でクラシックバレエをやっており、かなりの運動量もあって、本来ならばしっかりとご飯を食べないといけなかった。
でも、疲れきっていたこともあるし、食事が体に及ぼす影響を理解をしていないかった。そして料理が当たり前のように出てくると思っていた。
食べるということが楽しみも持てていなかったから、食に興味がなかった。
更に、すぐに胃もたれする体質だったこともあり、食事があまり好きじゃなかった。
こんな考えだけど、実家は祖父から続く食品商社を営む家系である。
そんな「食」に興味のなかった私が、大学への進学に伴って食物栄養学科に入ることになり、食について勉強することで少しずつ興味を持ち始めた。
「食」に対する興味を持ち始めた大学時代
1番影響があったのは調理実習。
5〜6人の班に分かれてご飯を作った。
食物栄養学科、つまりは食のスペシャリストを目指す学科なので、集まった学生は「食べること」が好きな子が多かった。
けど正直なところ、実家では料理をする機会がほどんどなくて、メニューを言われても何からやり始めたらいいか分からないくらいの調理スキルの人が大半だった。
そんなメンバーで、てんやわんやしながら作った。
当時は今のようにググる、という時代ではない。
なんとかして自分たちが自ら作った料理は、食べてみると美味しかった。
小学校でも調理実習はあったけれど、18・19歳になってから行う調理実習とは捉え方が違ったし、難易度も違った。
家庭料理よりも発展していて、
中華のフルコースを作ったり、
はたまたTHE和食料理(煮物、お吸い物、魚の焼き物など)を作ったり。
おうちでは母が子どもの好みを考えてくれており、
好んで食べるものを作ってくれていて、
THE和食料理のようなメニューはあまり作らないようにしてくれてたんだと思う。
調理実習で、フルコースやひと手間ふた手間もかけて作る和食料理を作ったことで、料理の手間を理解し、さらに美味しく感じた。
ピロリ菌の駆除で長年の胃もたれも改善
この頃、両親が胃のピロリ菌検査を受けて
陽性判定を受けたことをきっかけに、
常時、胃の調子が悪かった私も検査を受けることになった。
結果はバッチリ陽性だったため、ピロリ菌駆除の治療を行った。
これにより胃もたれが改善されて、それまで油物を食べると気持ち悪かったが、お肉を食べても炒め物を食べてもケーキを食べてもしんどくなく、やっとおいしさを感じれるようになったことも「食」に対する興味を持つようになった大きな原因の1つである。
ちなみに、、
ぜひとも、今胃もたれしやすいという方にはピロリ菌検査をオススメしたい。
検査には胃カメラが必須で、胃カメラに対する抵抗感や億劫という方も多いかと思う。私もその一人である。口からカメラを入れるしんどさを想像して、嫌になっていた。
そんな方には、麻酔で眠っている間に検査ができる病院がある。そちらでの検査をオススメしたい。通常より値段はかかるかもしれないが、精神的な苦痛を考えるなら、かなり価値があると思う。検査室で呼気麻酔で眠ることができ、寝て休憩している間に検査が終わっている。私が受けた病院では、検査が終わり次第、個室の休憩スペースに移動してもらっており、目が覚めたら帰宅できた。もちろんピロリ菌がいたとすれば保険適用で受診が可能である。
栄養素に関する知識と身体への影響
調理実習を行ったうえで、栄養素に関する勉強や解剖学の勉強など始まった。
各料理・食事には、さまざまな食材が使われていて、「赤黄緑の3色の食品群」の通り、食品によって、身体そのものになるものや動かすための潤滑油になるものに分類される。このような内容を学び始めた。
好きなものだけ食べていても、体は動かないし、
テレビやネットで流れているような健康食材1つだけを摂ってみても、栄養バランスが崩れるし。そういったことを意識し始めた。
ただ、学校で習うことって、このような効果効能の話がほとんどである。
料理を口にする、その手前の「作り手の想い」は、各家庭で教えるものなのかもしれない。
子どもが生まれて、娘は先日3歳になった。
結婚してから毎日自炊を行ってきて、学生時代のように料理をすることにあたふたすることはなくなった。
そして娘の離乳食が始まってから、1日3回の食事に対していろいろ考えるようになり、私の頭の中はまさに「食」で溢れかえっている状態だ。
0~1歳は出したご飯はゆっくりでも全て食べていた娘も、2歳からイヤイヤ期に入り、自我も生まれてきたことで好き嫌いもするようになった。
小さい頃に食べてきたものが、その後の長い人生においての味覚のベースになる
と思っている。
というのも主人と結婚してから、それをすごく感じている。
具体的には、食事における飲み物。
主人は家でも、特に外食時は必ずドリンクを頼む。
お酒だけでなく、ジュースも頼む。
お茶や水では口が寂しいようだ。
主人は幼少期、大事に愛されて育てられてきており、
ジュースをよく飲ませてもらっていたそうだ。
ちなみに、口の中は虫歯が多い。
私はというと、小さいころジュースを飲ませてもらえなかった家庭で、
食事中はお茶または水で過ごしてきた。
その影響からか、食事中の飲み物はできれば水かお茶がいい。
ジュースが飲みたいときもある。けど料理の味の邪魔をする気がしてしまう。
ちなみに、私は結婚するまで虫歯はなかった。(結婚する直前で、初めて前歯にC0の虫歯ができた。C0なので麻酔なしで虫歯の表面を削る治療で終えた。)
このように、飲み物においても小さいころからの習慣が、大人になってからの好みや味覚にも影響していると思っている。
だから、私には食卓に並べるときにちょっとしたルールを決めている。
食卓における我が家のルール
料理はできるだけ薄味で、素材そのものにしている。
ご飯と一緒に摂る飲み物は、お茶かお水。
和食メインでお野菜多め。
ひじきや高野豆腐を爆食いし、味噌汁を上手に飲み干している。
焼き魚に骨が混ざっていた時、上手に小骨も口から出すことができる。

ごはん、ひじき煮、高野豆腐、蒸しさつまいも、野菜スープでした。
食事の食べる順番も大事だと聞くし(汁物・野菜から食べるというもの)、
一気に出すと好きなものから食べてしまうので、
フルコースのように一品ずつお皿に取り分けて出していく。
(といえば聞こえはいいけど、
実際は食べてもらっている間に次のご飯を作ってる。間に合っていないだけ)
おやつは補食ということを念頭に置いておこうと思い、さつまいもや果物に。食材が切れてたらおむすびとしている。
これらをベースにしているが、もちろんこの限りではない。
お菓子をあげることもあるし、洋食にイタリアンにファストフードを食べることもある。基本があるから、自分たちへのご褒美にジャンキーな食事もすることもある。
ーそれも経験だと思っている。
2歳を越えてから実践できていないが、
それまでは「ごちそうさまでした」のタイミングのときには
その日、食卓に並んでいた食材を一つ一つ言いながらありがとうを伝え、
全ては○○ちゃんの身体の基になりました!と言うようにしていた。
いのちを「いただきます」の意味を伝えたかったのと、
短期記憶の向上に繋がるかな、
そして語彙力の強化に繋がるかな、という想いも込めて実践していた。
我が家の食卓ルールを続けた結果、、
今のところ娘は食べることが大好き。
娘の好きな食べ物は、トマト・なすび・ちくわ・お茶漬け・いちご・バナナ・ヨーグルト。ご飯も大好き。もちろん、パン・うどん・肉・魚も好き。
娘に好きな食べ物は?と質問すると
返ってくるのは「トマトとなすび」という。(大阪弁である)
時々いただいた洋菓子のケーキやマフィンをあげてみると、途中で要らないという。甘すぎるのか、油っぽいからか。
おままごと好きな娘と、遊びの延長線上で一緒にごはん作りを
そして娘は、おままごとが好きになり、よく遊んで~と言われるようになった。
ただ、この繰り返しのおままごと遊びにしんどくなってきた自分がいた。
ほんとは本物のご飯作りたいのに。
そこで、おままごとの代わりに一緒にご飯を作ることにした。
最初は野菜を洗うところから始めてもらい、水遊び感覚で楽しんでもらった。

次に混ぜる工程をお箸を使ってしてもらった。
野菜を切るところも横で見てもらい、切った食材をお鍋に入れたり、ボールに入れる過程を頼んでみた。今ではナイフを使って野菜を切ることにチャレンジすることもある。

本人は「おままごと」のつもりである。
なので、どの工程も一人でご飯を作るよりも1.2~1.5倍の時間は要する。
3歳になる2ヶ月ほど前から、卵を割ることにも挑戦してもらうことにした。黄身は潰れるけど、今では1人で上手に割れるようになった。
卵の殻、割れる感覚、パカーンと黄身と白身が落ちる様子を見てもらえて、楽しんでいるかなーと思う。
何も言わずとも、割れたからの破片をボールから拾うようになった。
一緒にごはんを作り始めて1ヶ月ほど経った娘の変化

そんなこんなで「おままごと」の代わりにご飯作りに携わってもらって1ヵ月ほど経った頃、娘が急に
「ママ、いつもご飯作ってくれてありがとう。
ママ、ご飯おいしいね」
と言ってくれるようになった。
なんてこともない、とある平日の夕方だった。
「ありがとう」と言ってくれてありがとうね、と言いながら娘をギューッとハグした。
この言葉を聞いて、嬉しさと驚きと同時に
「あー食育が成功したんだな」と感じた。
作り手の思い、ご飯ができるまでの過程を分かってくれたんだなと私としては解釈している。
この日以来、
一緒にごはんを作る時、すべての工程が娘にとって学びになるんだと感じ、
「今日は今が旬の春キャベツを使おうね」
と食材の旬情報を伝えたり、
「魚に塩を振って、臭みを取ってから焼くね。その方が美味しくなるからね」
と調理工程と、その過程を踏む理由を伝えたり、
自分にとっては当たり前になっていることや
脳内で処理していることを口に出すようにしている。
こういった考えこそ、食育であり、
作り手である私の気持ちが込められていると思うからである。
最後に・・・
食育の本質を分かっていなかった頃の自分へ
最近、「食育」という言葉が流行っているけれど、
本来の食育とは、知識を暗記するような浅いものではないと私は思う。
栄養素や吸収率、解剖生理学といった専門的な知識は、国家試験対策としては必要だけど、むしろ、本来は無くていい。もっと力を抜いていい。
もっと大事なことは、人の想いだと思う。
生産者の思い。
作り手の思い。
時間のない中で、いかにバランスの良いご飯を食べてもらうかの工夫。
目の前の食事がどのような「過程」を経てあなたの前に出てきているのか。
それを自然と理解できた時、
心から「ありがたい」ときっと感じるはず。
その「食」に対するありがたみを「育」てることこそが、食育の本質だと、娘に教えてもらった。

息子も離乳食後期に突入し、食べられる食材も増えてきた。
形状も少しずつ固形になってきた。
正直、娘のときに比べると離乳食の進め方は強引で、
おかゆや軟飯をぶっ飛ばして普通米になっているけれど、
我が家の食卓におけるルールは継続しながら、
もう少し大きくなったら3人でキッチンに立って
本物のおままごとをしていきたいなと思う。
そして息子にも
一つ一つのご飯・食事に込められた想いが伝わればいいな。
お知らせ①
stand.fm始めましたー!
不定期配信ですが、ちょこちょこっと投稿予定です♪
よろしければお耳にかかれますと幸いです^^
お知らせ②
毎週火曜、10:30頃から
わだきなこちゃんのstand.fmにて
ごきげんラジオライブに参加させてもらってます♪
良かったら覗いてみてください(^^)
※日時は週によって変わることもあります…!
お知らせ③
X(Twitter)を始めました!
日常を切り抜き、日々の出来事や気づいたことを発信しております!
良かったら覗いてみてください(^^)
https://x.com/araiguma_yuchi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
