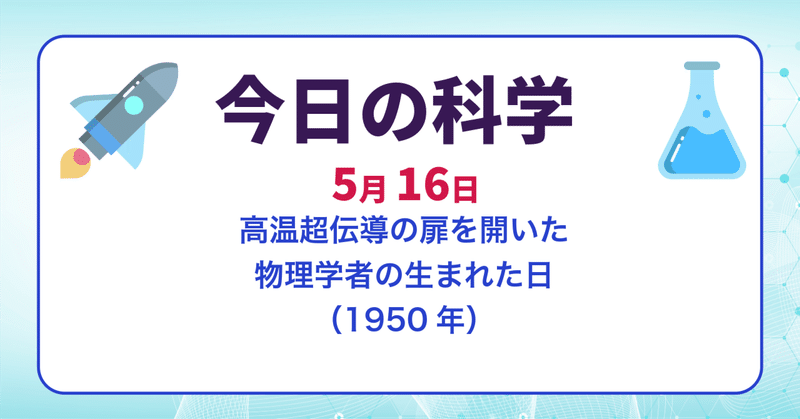
今日の科学 5月16日
1950年5月16日は、高温超伝導体 を発見したドイツの物理学者ヨハネス・ゲオルク・ベドノルツ が生まれた日です。この発見によって、彼は1987年にノーベル物理学賞 を受賞しました。
超伝導とは、物質の電気抵抗が0になる現象のことです。地球上のほとんどの物質は、電気を流したときに熱が生まれ、電気エネルギーの一部が熱エネルギーに変わってしまいます。これが電気抵抗です。電気抵抗があることで、電気エネルギーを使用するときの効率が落ちていました。
そのなかで、電気を流してもエネルギーが熱になって奪われない物質、つまり、電気抵抗が0になる物質が発見されたのです。それが超伝導体です。世界で初めて発見された超伝導体は水銀で、マイナス269℃ほどの極低温にまで冷やすことで超伝導現象が起こりました。
その後、いろいろな金属で超伝導現象が起こることが報告されました。合金や化合物を含めると、超伝導体の数は200種類以上にもなりました。でも、それらはどれもマイナス250℃ほどまで冷やす必要がありました。
この状況を変えたのがベドノルツです。彼はIBMチューリッヒ研究所でカール・ミュラーと研究をし、ランタン、バリウム、銅を混ぜて焼いた酸化物がこれまでよりも高い温度のマイナス243℃で超伝導現象を起こすことを発見し、1986年に発表しました。
専門外の人たちからはマイナス250℃も、マイナス243℃も、同じように思えますが、専門家からすれば大きな違いです。マイナス243℃での超伝導は、当時発見されていたどの超伝導体の温度よりも高く、すぐに世界中の研究者が、酸化物超伝導体の研究を始め、高温超伝導体を探す競争が始まったのです。
ベドノルツたちの発表から1年後の1987年には窒素が液化するマイナス196℃よりも高い温度の超伝導体が発見され、高温超伝導の研究が急速に進みました。ベドノルツたちの研究は高温超伝導の世界の扉を開き、世界中の研究者に衝撃を与えたのです。
その衝撃の大きさは、ベドノルツとミュラーがノーベル物理学賞を贈られた年からもよくわかります。彼らが酸化物超伝導体の発表をしたのは1986年ですが、ノーベル物理学賞が贈られたのはその翌年の1987年なのです。ノーベル賞は、対象となる研究の発表から少なくとも10年以上経ってから贈られることが多いのですが、2人は2人はたった1年後に贈られているのです。それだけ、2人の研究の評価が定まるのが早く、重要なものだったことを物語っています。
サポート頂いたお金は、取材経費(交通費、宿泊費、書籍代など)として使用します。経費が増えれば、独自の取材がしやすくなります。どうぞよろしくお願いいたします。
