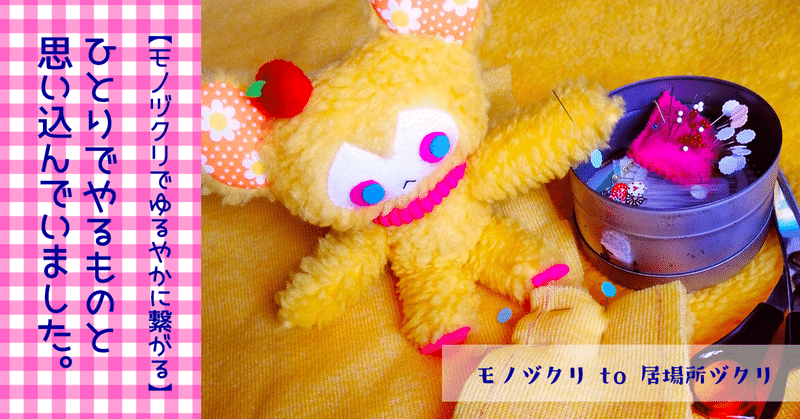
モノヅクリはひとりでやるもの?
ずっとそう思い込んでいました。
父は休みの日にはいつも何かを作っている人でしたし(今もそう)、
1970年代という時代的にも、母も一通りの手芸をやっていたように思います。
ところが私はと言えば、何でも1人でマスターしたいとはりきる子どもでしたので、
傍で端材で遊ぶことはあっても、親から教わったりとか、一緒にやるということはまずありませんでした。
父がやっているのを横目で(でもバッチリ)見ながら、父がいない時に思い出しながらこっそり練習(^▽^;)
友達との遊びも、お家でというよりはお庭や公園で駆けずり回ることがほとんどでしたから、
一緒に作るという環境もなかったように思います。
学校の授業(図工・家庭科)でも、私語は謹んで作業に没頭することを求められましたので、
モノヅクリはひたすら黙々と1人でやるもの…という意識が、どこかにあったのかもしれません。
2年前になりますが、これからの展望として10ヶ年計画の中に「手芸カフェを開きたい」ということを書きました。
この時に、どうして手芸カフェなのかということも、少しだけお話したのですが、
今回は何回かに分けて、もうちょっと詳しく書いていこうと思います。
モノヅクリとコミュニケーション【親子編】
モノヅクリとコミュニケーション【シュタイナー学校編】
モノヅクリとコミュニケーション【子育て支援編】
モノヅクリとコミュニケーション【高齢者自主活動編】
モノヅクリはひとりでやるものと思い込んでいましたし、今もひとりで続けています。
そんな私に新たな発想をもたらしてくれた体験をいくつか書いた後に、
私の考える「コミュニケーションとは何か」や、「どんな手芸カフェにしたいか」など、
【モノヅクリでゆるやかに繋がる】
というシリーズにして続けていきたいと思います。
今回は(その1)ということで…
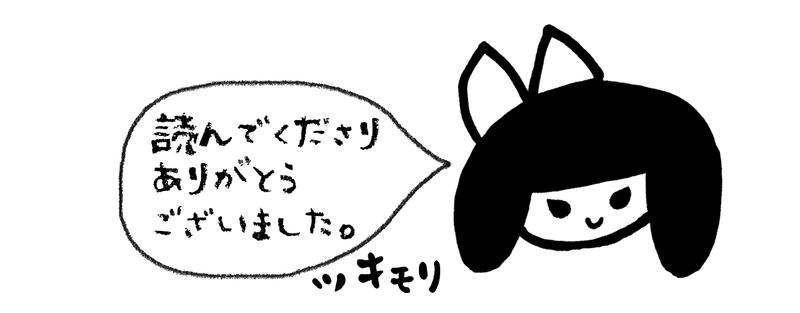
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
