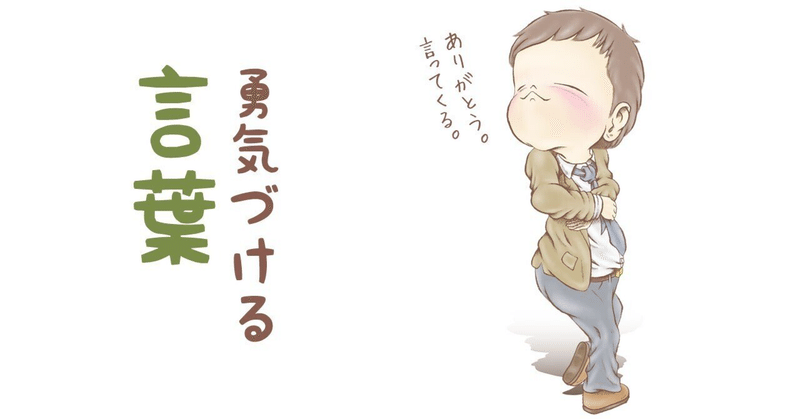
「経営者を育てるアドラーの教え」を読む①
ゴールデンウィーク真っ只中ですね。今年は前半、後半の間に3日ほどウィークデイが挟まっていたので、大型連休にならなかった方も多かったのかな?私は休日はほぼ関係ないので、普通にお仕事していますね^^
それでも一昨日は両親もつれて4人で県内をドライブして出かけてきました。皆さん是非いい休日を過ごして頂きたいと思います!
さてさていつも大体金曜日に更新はしているのですが、ちょっと遅れて今日(日曜日)になってしまいましたが、アドラー心理学と経営のことについて書いてみました。
長く書きすぎないようにしますので笑、最後まで是非お読みください!

私とアドラー心理学
私はアドラーについてはやはり多くの方と同じく、「嫌われる勇気」が出版された時(約10年ほど前ですかね)に読んだことで興味を持った感じですかね。
あとは友人でアドラーが好きな人が何人かいるのでそうした人のおススメで本を読んだり、話を聞いたり、ということをボチボチとしていました。
ところが数年前に職員さんと1on1をしている時に、「嫌われる勇気」を読んでみるけれどもなかなか意味が分からない、という話を聞いたものですから、もう一回読み直したんですよね。

そうすると、なんだか10年前に読んだ時とはくらべものにならないくらい内容がす~~っと入ってきました。
そこで社内職員有志で「嫌われる勇気」の読書会をやったり、あるいはX上で希望者を募って、勉強会を企画したりしていました。
その中で、どうしても分からないことがあったり、あるいはこの内容は自分のこの理解でいいのかな?とか思うことが多くありましたので、以前から事業やお仕事で関係団体としてつながりがあった、岩井俊憲先生の講座を受けることにしたんですよね。
「嫌われる勇気」だけではアドラー心理学の理解が深まらないと思ったのはやはり事実です。
岩井先生は元商社マンであり、中小企業診断士。大学に所属されているので葉はなく在野のアドラー心理学の先生です。
ヒューマンギルドは「嫌われる勇気」がブームになる前からアドラー心理学関連の活動をしてきており、最も長く、広くアドラーの心理学について啓蒙してきた団体なんじゃないかなと思います。
私はこちらでアドラー心理学の講座、そしてそれに関連する講座を昨年受講させて頂きました。とても有意義に学ばせてもらったんですよね。

アドラー心理学と経営
アドラー心理学を学びたいのは私個人が知りたい、というのは勿論ですが、経営者としてどのようにアドラーの教えを活かせるんだろうかということが原点でしたね。
そして講座を受ける前に拝読していたのがこちらの岩井先生のご著書。
なぜアドラー心理学が経営に役立つのか?
岩井先生はこちらの本の冒頭(序章)に次のように書かれています。
大きく3つの理由があると。
まず1つ目。
経営者としての人間観の確立が重要だと。経営者には「人間をどう見るか」という人間観が絶対に欠かせない、とまで書かれています。なるほど。
会社には様々な個性を持つ人間が所属しているわけで、彼ら1人1人の能力を正しく評価して、引き出していくの経営者の仕事ですよね。
アドラー心理学では二元を肯定的に見ることを教えるんだと。。
そしてそういう人間観に基づいてみると、我々には無限の可能性がある。経営者がそのような人間観を持つことが、会社を成長させるもとになる。
ここは綺麗ごと抜きで、私自身も本当にそうだと納得します。
以前は正直に告白すればこれと全く逆な人間観を持って経営していたと言わざるを得ません。もちろん、誰かと接する時にあからさまに不信感を漂わせている、なんて冗談にもならないような振る舞いはしていませんが、腹底に、信用できない、という思いをどこか抱えていたんだろうなと。
これについては後ほど触れます^^
そして2つ目。
未来志向の視点を持つことが重要であると。
過去の失敗を反省することはもちろん大切ですが、原因ばかり追求していても過去にしか目が向いていませんから成長できないです。
人も会社も。
過去の反省を踏まえて未来に向けて何ができるかを考えることで社員のモチベーションを高めて会社の成長力につなげると。未来志向のアドラー心理学は経営に適しています。
3つ目。
アドラー心理学のベースの「勇気づけ」が組織を元気にする。
これは私も意識して実践しているところであります。
先生はアドラー心理学を学んだ経営者が非常に生き生きして元気になる例を沢山見てこられたそうです。
人間の可能性を信じることで「自分だけがひたすら頑張らなくても自分のチームの中に優れた人材がいる」ことに気づけるようになると。
そうすると社内が活気づきます。社員が社長は変わったと思うようになると経営者のビジョンも浸透しやすくなります。
次に、これからの経営者は意識面、行動面で自己変革を通じてでしか自らの会社の組織変革を果たすことはできないと書かれています。
これまでの「恐怖・不信・軽蔑」の支配から、
「尊敬」「信頼」「共感」「協力」の4つの条件を備えた人間関係へと転換させることでそれは実現可能なんですよね。
この4つに関しては次回のnoteで書いていきたいなと思います^^
私自身、この本にも影響受けたのは事実ですし、今自分が組織づくりにおける根本的に大事にしたい思想がやはりアドラー心理学だなと今回改めて感じさせて頂いた次第です。

このご著書の最後に紹介されているアドラーの言葉で今日は〆たいと思います。
「私たちは自分で人生を作っていかなければならない。それは、私たち自身の課題であり、それを行うことができる。私たちは自分自身の行動の主人である。何か新しいことがなされなければならない、あるいは、何か古いことの代わりを見つけなければならないのであれば、私たち自身にしかできない」(人生の意味の心理学)
以上☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
