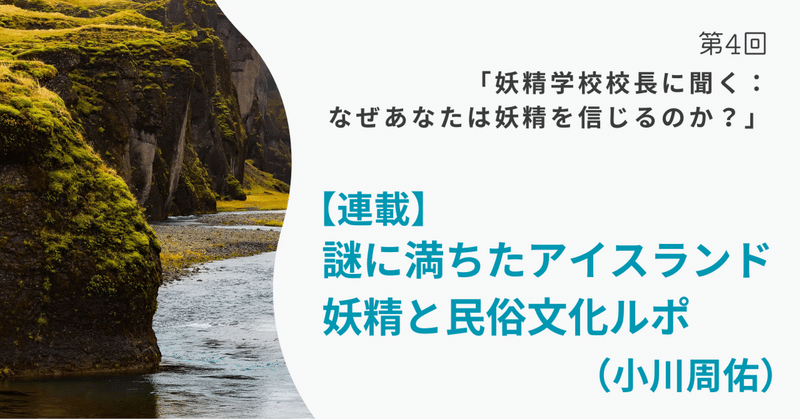
第4回「妖精学校校長に聞く:なぜあなたは妖精を信じるのか?」連載|謎多きアイスランド 妖精と民俗文化ルポ(小川周佑)
■これまでのあらすじ
アイスランドの妖精の謎に魅せられ、現地レイキャビクまでやってきたライター小川周佑。そこではまず「アイスランド妖精学校」という、妖精について教えてくれる学校(おそらく世界でただ一つ)の門を叩いた。校長のマグヌスの口から語られたのは、「フルドゥフォルク」と呼ばれるアイスランド特有の妖精の生態について。その特徴は、いわゆるティンカーベルやドワーフなど日本人がイメージする”妖精”とはかけ離れたものであった。
では、その”人間型妖精”・フルドゥフォルクとはどのようにして誕生したのか?
そしてアイスランド妖精学校校長・マグヌスに、妖精のことや、自身のキャリア、アイスランドの妖精を取り巻く環境などについて直接インタビューを試みた。今回はその2点を主にお届けしたい。
・連載第1回目「日本語文献がほとんどない“アイスランドの妖精”に興味を持った理由」
・連載第2回目「いざレイキャビクへ 妖精学校なるものに入学してみた」
・連載第3回「ティンカーベルには程遠い!?アイスランドの妖精目撃談」
民話「フルドゥフォルクのはじまり」
第3回でもお伝えした通り、アイスランド妖精学校には教科書があり、その中に「フルドゥフォルクのはじまり」という民話がある。アイスランドの民話集を見ても頻出の物語で、微細なストーリーの差はあれ大幅な構成は変わらない。この民話が、アイスランドにおける「フルドゥフォルク」の立ち位置をよく表していると感じるので、今回はまずこれを紹介することから始めたい。
ある日全能の神がアダムとイブに会うために、彼らの家にやってきた。彼らは神を丁重にもてなし、自分たちの家を隅から隅まで案内した。 彼らは自分たちの子供も神に見せた。神はその子供たちを素晴らしいと思った。神はイブに、 「ここに私に見せた以外の子供はまだいるのか?」と尋ねた。 彼女は、「いいえ、いません」と答えた。
実際のところは違った。イブは神が家に来るまでの間に何人かの子供の身体を洗い終えられず、その子供たちを見せるのを恥ずかしいと思ったのだ。なので、彼女はその身体を洗っていない子供を神から隠した。
しかしながら、神にはそんなことはお見通しだった。そして彼はイブに言った。
「私から隠された者たちは、必ず人々からも隠されることになるだろう」

こうして「隠された子供たち」は人間には見えない存在になり、彼らは岩や丘、石や小山に住むようになってしまった。その「隠された子供たち」から子孫としてフルドゥフォルクが生まれた一方で、神に見せられた子供たちの子孫は人間になったのだという。
ふつう人間はフルドゥフォルクを見ることはできない。しかしフルドゥフォルク自身が望めば、その通りではない。なぜなら彼らからは人間を見ることができて、気分次第で人間に姿を見せることもできるからだ。
この物語から読み取れることはいくつもあるが、まず大きなこととしては、「人間とフルドゥフォルクはもともとは兄弟で、それがたまたま別々の道を歩むことになっただけ」ということだ。兄弟であるのだから、その生物的特質は変わらない。「岩に住むこと」「ふつう人間には見えない」ということを除けば、フルドゥフォルクは「人間とまったく同じ生き物」ということになる。
「ふつう人間はフルドゥフォルクを見ることができない」というのも重要なポイントだ。つまり、「ふつう」ではない場合、妖精を見ることができる、とも解釈できる。マグヌスは授業でこんなことも言っていた。
「現代でも、フルドゥフォルクとコミュニケーションをとれる能力を持つ人がいる。その人たちのことを『シャウアンディ』と呼ぶ」と。
つまり、特別な能力を持ち、妖精とコミュニケーションをとれる人間はいるようなのだ。「ロンリープラネット」に記されていた「妖精と交渉するスタッフ」のように。
翌日、マグヌスにあらためてインタビューを申し込んだ。今回のアイスランド妖精取材で、聞きたいことは対象者によってさまざまなのだが、まず聞いておきたいことがあった。それは「妖精を信じているかどうか」だ。そして、逆の立場=妖精を信じていない人についてどう思っているかも、忌憚のない言葉を聞きたかった。
こういった取材をしていると、どうしても「△△は、みんな○○だ!」という安易な結論に飛びつきたくなる誘惑がある。そのほうが派手で、センセーショナルで、わかりやすいからだ。だけれどもそれはほとんどの場合間違った結果を呼び込むことになる。
同じアイスランド人でも、妖精に対する空気感、意見の違いがあるのは当たり前で、それをひとつひとつ丁寧に聞くこと、そしてそれを脚色せずそのまま伝えることを積み重ねることでしか、「全体としての社会像」のようなものにはたどり着けない。
インタビューの内容を以下に記す。マグヌスは「elves(エルヴス)」と「フルドゥフォルク」の両方を単語として使っていたが、フルドゥフォルクも広義の「elves」の中に含有されるため、厳密な区別がつけにくい。ここではelves=妖精、フルドゥフォルク=そのままフルドゥフォルクとして訳している。インタビューを通したイメージとしては、どちらも人間と同じ形・大きさの、「フルドゥフォルク」型のものと捉えて間違いがないかと思われる。
【インタビュー】アイスランド妖精学校校長
―昨日はありがとうございました。まずお聞きしたいのですが、マグヌスさんは妖精を信じていますか?

マグヌス「はい。私は強く信じている」
―アイスランド妖精学校の実際の授業で、あなたからいくつもの妖精の伝承話や目撃談を教えてもらいました。ただ、それは「マグヌスさんご自身の目撃談」ではなかった。マグヌスさんご自身は妖精を見たことがあるのですか?
マグヌス「一度も見たことがない」
―そこが面白いポイントだな、と思いました。一度もご自身で妖精を観たことがないのに、実際に妖精の存在を信じる理由はどのあたりにあるのでしょうか?
マグヌス「数百の目撃談を収集したが、それを伝えてくれた誰しもがその物語の現実性を確信していたし、物語そのものも長編にわたり、また複雑で興味深いものだったからだ」
―いつ頃からこういった妖精の話を収集するようになったのでしょうか?
マグヌス「一番最初にこういった話を聞いたのは私が17歳の頃だ」
―どういった話だったのですか?
マグヌス「その物語は農家をやっていた私の祖母の妹から聞いたもので、彼女は農場を出て下った海岸のほうでフルドゥフォルクを目撃したという。フルドゥフォルクは家族で、その海岸にある崖に住んでいたらしい。彼女は、その崖にドアと窓を見た、との話だ。これは私にとっての大きな謎だった。
―ということは彼女も”シャウアンディ”だったのでしょうか?
マグヌス「はい。私の妹もそうだった」
―「ふつうの人」と「シャウアンディ」の違いとは何なのでしょうか? どこでその違いが生まれるのでしょうか? あなたと妹さんは同じ家庭環境で育ち、同じ両親から生まれながら、別々の能力を持っています。
マグヌス「誰もが超能力的な才能は持っている。そして、ある種の人々は、普通の人よりその能力を持っている、というだけの話だ。彼女はそういった才能に恵まれていて、いつもではないが、時々妖精を見ることができた。さらに、よりそういった超能力的才能をもった人というのもいる。そういった人間は、フルドゥフォルクと死者の違いを見分けられたりする」
―アイスランドには、統計上も妖精の存在をまったく信じない人間がいます。そういった人間はなぜ妖精の存在を信じないのだと思いますか?
マグヌス「彼等自身がまず妖精を目撃していない上に、『近代的教育』『啓蒙』を受け過ぎてしまっているからだと考える」
―そういった近代的な教育システムは、アメリカに影響されているのでしょうか?
マグヌス「いや、典型的なヨーロッパ的、スカンジナビア的教育だ」
―妖精を信じない人に対して、マグヌスさんはどのように考えていますか? 妖精学校の校長として、妖精の実在を彼等に訴えたりはしないのでしょうか?
マグヌス「よくわかんないよ。ただ祈るだけだ」
―教科書にある「フルドゥフォルクのはじまり」ではフルドゥフォルクの起源はイブが神に対して、洗っていない子供を隠したのがきっかけだとに紹介されてますが、そういった観点からも、フルドゥフォルクとキリスト教の関係性は語れないのでしょうか?
マグヌス「私はそれを信じていない。フルドゥフォルクの起源というのは、『よくわかっていない』というのが正直な態度だろう。私見なら誰しも紹介できるが。私は、フルドゥフォルクの起源は、私たちのものと同様と考える」
―妖精の目撃談の収集をはじめるにあたって、誰があなたに一番影響を与えたのでしょうか。
マグヌス「2か月前に89歳で亡くなった女性だ。彼女が1985、6年ぐらいに語った話の数々がとてもとてもとても面白かった。彼女は若い頃から、ひっきりなしにフルドゥフォルクや妖精に会い、フルドゥフォルクの家族や、妖精の少女、妖精の女性と友好関係を結んでいた。そして彼女は本当に、本当に信頼できる人間だったんだ。彼女が、私に他の何よりも、誰よりも影響を与えてくれた」
―人々は、(たとえば、キリスト教の神に対して祈るのと同じようなスタンスで)妖精やフルドゥフォルクのために祈ったりするのでしょうか?
マグヌス「普通はあまりしない。ただ、『友達として』幸運を祈ったりはする」
―若者は妖精について話したりすることはあるのでしょうか?
マグヌス「いや、していない。近代的教育や啓蒙のおかげだ」
―そもそもこの学校で校長として働くようになった経緯は。
マグヌス「金と名声が欲しかったからだ」
―校長になってそれは得られましたか?(笑)
マグヌス「名声は得られたが、金はたいして儲かってない」
―仕事上、大事にしていることは。
マグヌス「私はフルドゥフォルクの目撃談の収集に集中してきた。それが偶然の遭遇であっても、そうでなくても。そして、それが事実に基づいたものであるということを、大事にしてきた。
不幸にも、私がアイスランドで唯一の、目撃談を徹底的に収集している人間だ。そして私には妖精を見る力がない。『私が見たから』『私が見えるから』といった観点から、妖精の存在を立証しようとはまったくしていない。私はとても傲慢な研究者だから、事実に基づかない議論みたいなものを本当に嫌う(机を叩きながら)。

数百のアイスランド人が、『事実としての妖精』と『空想としての妖精』の区別を知っていると思う。そして彼等はその2つを混ぜこぜにしたりはしない。
もちろん、私も妖精関係で商売をしてはいる。だけれども、私は、絶対に事実に基づかない議論というものはしたくない。(机を叩きながら)断固たる事実だけが対象なんだ。(机を叩きながら)しかし、アイスランドを取り巻く観光業は、この妖精への信仰に対して深刻な影響を与えている。事実や客観的証言に基づいた妖精の目撃談の中に、どんどん作り話が入り込んでくるようになってしまった。
アカデミズムの世界の中には、『お前たちは空想と現実の区別がついていない、必要な時にそれだけの話をでっちあげてるだけだ!』と言う人もいる。その意見に私は動じない。私はでっちあげなんてしないし、その必要もないからだ。私は狂気がかっているほど美しい目撃談をいくつも聞いてきた。あなたに授業で伝えたのは、その中のほんの一部に過ぎない。全部伝えようと思ったら、1日ではとても足りない。そして目撃談を私に語ってくれた人々は、泥酔していたわけでもないし、嘘をついているわけでもないし、ドラッグで幻覚が見えていたわけでもない。実際に会ったのだ。そして彼等と10年後に会っても、その話の詳細が寸分違わない。この分野には、学術的な方法論が足りなすぎている。
(机を叩きながら)私は、これから先、アイスランドにいくつか、事実、そう、事実に基づいた妖精についての学校ができてくれるといい、と思っている。私はそれを強く望んでいる」
インタビューは当初の予定時間を大幅に超えたものになった。机を叩きながら、時に声を張り上げてしゃべるマグヌスの姿には迫力があり、その雰囲気はとても「観光客のために、妖精を信じているキャラクターを演じている」ようなものとはとても思えなかった。時折冗談を交えつつ(ここに掲載するのが憚られるぐらいの冗談もあった)、ひとつひとつの質問に対して真摯に回答をしてくれた。
そしてアイスランド取材の舞台は、マグヌスの教室を飛び出し、実際の「妖精事件」の場へと向かっていくことになる―。(第5回「アウルフターネス妖精事件とは何だったのか」へ続く)
文/小川周佑(写真家・ライター)

▼マガジン登録もよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
