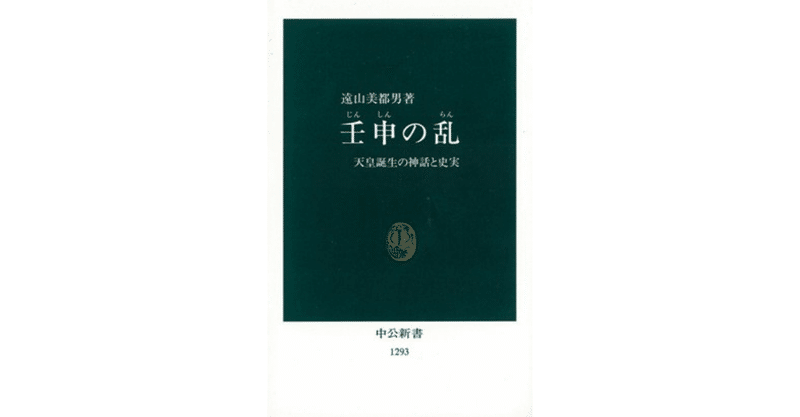
天皇誕生の神話と壬申の乱
『壬申の乱/天皇誕生の神話と史実』遠山美都男(中公新書/1996)
六七一年十月、天智天皇の弟大海人皇子(天武天皇)は王位継承を断わり吉野に隠棲。翌月、天智の子大友皇子は大海人を討つべく五人の重臣と盟約を結んだ。天智後継の座をめぐる壬申の乱の発端である。天智は大友かわいさで大海人を疎外したのか。大友は絶えず後手にまわり敗れ去ったのか。王位継承をめぐる対立はなぜ大規模な戦争に発展したのか。通説を再検討し、古代最大といわれる攻防のドラマを再現、その歴史的意義に迫る。
それまでの壬申の乱は、天智天皇の死後、王位継承を巡って天智天皇の後継者大友皇子を叔父である大海人皇子が追い落としたとされ、大海人皇子悪人説が流布されている。しかし、その時期に天皇だったのは倭姫王の女帝とし天皇についていた。仮の女帝の跡目を巡る大海人皇子率いる豪族と大友皇子率いる豪族間の天下分け目の戦いだったのだ。大海人皇子の逃走(闘争)ルートを徳川家康が巡った関ケ原の戦いになぞらえてみることで見えてくる古代王朝の成り立ち。
第一章は、天智天皇が豪族関係を築きながら子弟が豪族の母方の里で育てられた古代の母権主義的な繋がりを考察する。それは、日本が中央集権的な父権制を築く前は母権社会であって、地方豪族の力はその血縁(妻の出身の里)で持っていた。
第二章は天皇の子弟たちのそれぞれの里(地方豪族)との繋がりを述べたもので、『鎌倉殿の13人』ならぬ『天武(天智)天皇の13人』(数は適当)というような、ただ豪族の名前が古代風なので読みが難しくて覚えられない。土地に詳しい人は面白いかもしれないが、それ以外の人は頭が混線すると思うので飛ばしていいと思う。次章からも関係豪族の繋がりが出てくるのでその時にチェックすれば良い。
第三章から大海人の逃走=闘争線が示されて、それぞれの地方豪族の重要地点が示される。天皇家は近畿地方が支配下であって、尾張から先は未開の地であった。大海人皇子は鈴鹿を抜けて、伊賀へ抜ける。それは未開の地であり、地方豪族との繋がりが必要だった。
一方、大友皇子は天智天皇の葬儀を済ませ大和で万全の体制を整えていた。群臣会議で、吉野から逃亡した大海人を追撃することも出来たがそれをしなかった。中国の故事に倣った「王師の戦い」を望んだのある。その時に、追撃するように進言したのが高市皇子だった。高市は大海人の息子であり、彼も追撃するように見せかけて大海人との合流を目論んでいた。そして、高市も大津を出て、大海人と合流する。高市を護衛したのは、渡来人の豪族であった。
高市は義経という感じだろうか?伊勢で合流する。伊勢で大海人は天照を拝啓する。日本書紀の経路が大海人によって形作られていく。
大津皇子は大海人にすぐに付いていけなかった。それは十歳である大津が幼かったというよりもより重要な地位にいて大和に留まったと考える。鸕野讚良(持統天皇)と共に草壁も出奔していた。大津の母はすでに亡くなっていたので鸕野讚良と一緒に出ていっても良かったのだがそれを大津はしなかった。天智天皇がもっとも期待をかけたのが大津だった。しかし、大津の従者たちは彼を大海人の元へ送り届けた(家臣たちはどっちに付いた方が得策か考えたのだろう)。
鸕野讚良(持統天皇)が桑名で倒れる。後に桑名で鸕野讚良が祀られるほど影響力を残した。大海人は鸕野讚良を残し近江に出兵する。高市がそれに続く。美濃・尾張の2万の豪族はこのとき大友側ではなく、大海人側に付いた。それを読みきれなかった大友の最大の誤算であり、勝敗は決した。
従来の豪族を束ねる大王とい存在から天皇になるのはこの時であった。つまり大海人は直接戦をせずに高市に戦いを任せる。軍事は高市に任せた結果従来の大王の地位を高市に授けて、自身は天皇となった。その転換点として天皇が法体として神になったのだ。
大海人軍は大友軍との違いを際立たせるために赤布を身に着けていた。それは中国の漢王朝の火徳を象徴した。大海人は漢王朝の軍隊編成や戦術を知っていた(渡来人による?)。
壬申の乱は古い体制と新しい体制の総力戦であり、その結果日本に律令体制が整いつつあった。
地方豪族たちは「天皇誕生」に関わったことで神話として祀り上げ、それを日本紀として記憶していく。壬申の乱が回想されるのは、エポックメイキングの転換点、明治維新であり、2.26事件前後の絶対天皇制につながっていく。
関連書籍
『「万葉集」を旅しよう』大庭 みな子 (講談社文庫)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
