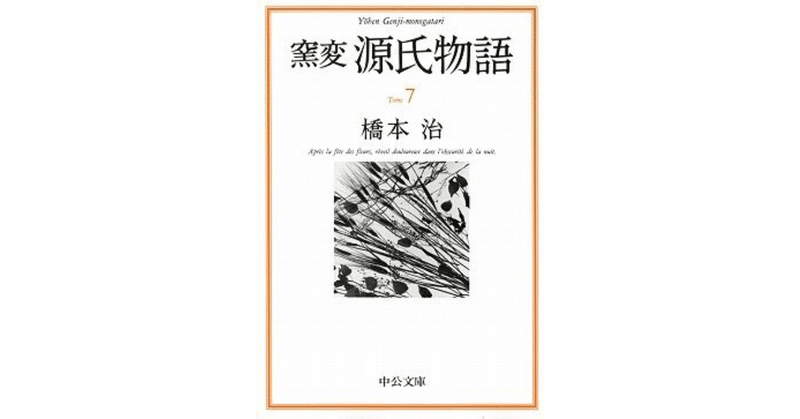
ダース・ベイダーとしての光源氏の老いの世界は喜劇となっていく
『窯変源氏物語〈7〉胡蝶螢常夏篝火野分行幸藤袴 』橋本治(中公文庫)
源氏物語をただの王朝美学の話ではなく、人間の物語にしたかった。『赤と黒』のスタンダールでやろうと思った。(胡蝶/螢/常夏/篝火/野分/行幸/藤袴)
玉鬘十帖のうちの7話。他の『源氏物語』と違うと思ったのは光源氏が「玉鬘」にあしらわれてしまうところが光源氏は六条院という後宮を建てながら老いの中にいてかつての精力はないように思えた。まだまだ玉鬘という娘を得ながら、その娘に手を出してしまうのだが、結局最後まで拒まれてしまったような。そこが喜劇的になっていて、紫の上との会話は漫才のような展開になっていく。それは六条院が女たち中心の世界であって、かつては悲劇として語られる物語であったが次世代の物語は紫式部や光源氏の力が及ばないものがあった。その中心には紫の上がいるということなのだろう。
その対抗馬として玉鬘が現れたがかつての紫の上のように囲うことは出来ない。紫の上と玉鬘の違いは、光源氏と夕霧との違いでもある。
そこに次世代である夕霧との物語も絡ませての喜劇仕立ての男たちの物語のとなっていくのか?その中心に紫の上がいて、そこに明石の君の姫がいる。夕霧は光源氏によって紫の上に出会うことは禁じられているのだが、明石の姫の今後のことを考えると後ろ盾として夕霧の力が必要だと光源氏は考えるのだが、そこの教育方針としての「物語」も紫の上との違いが出てきて面白かった。つまり光源氏は「物語」を教育上よくないものだからあまり見せるなといい、紫の上はそれは女たちのファンタジーなんだからと擁護する。その物語のストーリー以上の体験をするのが玉鬘という姫だった。
つまりかつての悲劇としての女たちの物語は、ここでは自立していく女として展開していくのだ。それは登場人物がすでに紫式部の手に負えない存在になってきた。それは玉鬘が紫式部の中で勝手に物語の方が成長していくような感じだったのかもしれない。次世代の女たちのドラマが玉鬘であり、名バイプレーヤーの一人である近江の君の異彩さなのではないだろうか?それは後宮がすでに作者である紫式部の手に負えない女たちの世界であり、そこが光源氏の思い通りに出来ない喜劇としての物語となっているように思える。
六条院はかつての六条の御息所の住処であった。その闇の力が光源氏の闇をも制御してしまう現れがその娘の秋好中宮なのである。光源氏が苦手とする中宮という存在が面白い。娘なんだけどそこでは役割でしかないのだ。それは六条の御息所の遺言でもある言霊(呪いの言葉)が光源氏に働いて手を出せなかった。『窯変源氏物語』では秋好中宮はすでに顔を拝めない存在となっているのである。手をだすことなんてもっての他になってしまっているのは中宮が天皇の妻であるという存在で事実上は光源氏は家僕なのである。
その家僕であるまめましく働く存在が息子の夕霧であり、光源氏は息子であるが自分たちが生きた時代とは隔世の感なのだ。かつての言葉では新人類と呼ばれたような夕霧の生き方、それは欲望を表出する世代とは違って世界の中で生きなければならない冷静さの現れが家僕としての息子世代の男たちなのかもしれない。そんな夕霧が光源氏に禁じられている紫の上を垣間見てしまうのだが、そこのドラマは欲望の物語としては発展していかないのだ。
そこを光源氏は分析する人となって批評する形が喜劇性として現れているのかもしれない。六条院は後宮であるが、すでに女たちが生きる世界となっている。そこの主人は各部屋の女王たちであって、その中心が春の間(部屋)である紫の上だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
