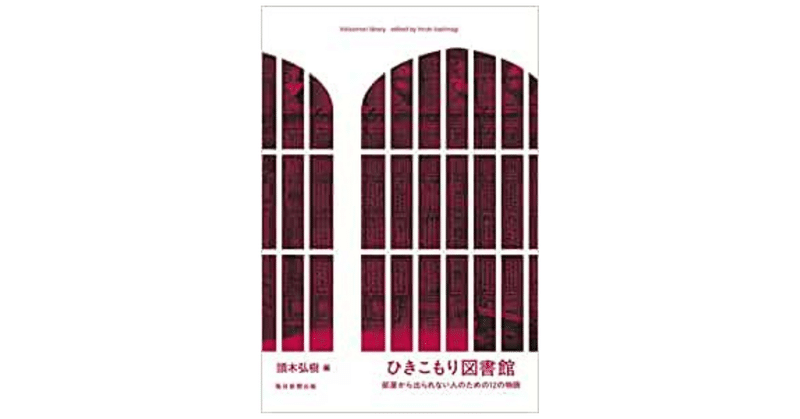
どの世界にひきこもればいいのだろうか?
『ひきこもり図書館 部屋から出られない人のための12の物語』頭木弘樹(編集)
ひきこもるとは、いったいどういうことなのか? 究極のステイホーム・ストーリーズが誕生!
ひきこもるとは、いったいどういうことなのか? 部屋の中で、何が起きるのか? ひきこもっている間に、人はどう変わってしまうのか? 「ひきこもり」をテーマにした斬新なアンソロジーが誕生しました。編者は、『絶望名人カフカの人生論』『絶望名言』『食べることと出すこと』などで知られる頭木弘樹。病のため、十三年間のひきこもり生活を送った編者ならではの視点で選ばれた、必読の名作群。今だからこそ読みたい一冊です!
【目次】
◎萩原朔太郎「死なない蛸」/◎フランツ・カフカ「ひきこもり名言集」/◎立石憲利「桃太郎――岡山県新見市」/◎星新一「凍った時間」/◎エドガー・アラン・ポー「赤い死の仮面」/◎萩原朔太郎「病床生活からの一発見」/◎梶尾真治「フランケンシュタインの方程式」/◎宇野浩二「屋根裏の法学士」/◎ハン・ガン「私の女の実」/◎ロバート・シェクリイ「静かな水のほとりで」/◎萩尾望都「スロー・ダウン」/◎頭木弘樹「ひきこもらなかったせいで、ひどいめにあう話」(上田秋成「吉備津の釜」)/あとがきと作品解説
エドガー・アラン・ポー「赤い死の仮面」
感想を書こうと思っているのだが、いろいろ考えてしまって書けないのであった。それはエドガー・アラン・ポー「赤い死の仮面」を最初に読んだのだが、コロナ感染の最初の頃で、クルーズ船での感染事故がニュースであったりした。その後にカミュ『ペスト』がベストセラーになったりした(「100分de名著」でも取り上げられた)。そうした教訓を得ていたのかもと思ったら未だに感染症は収まらず、ついにマスク外しましょう宣言が出ていた。
その間のことを考えてしまったのだけれども、結局何もしないのが一番良かったのかとさえ思えてくる。確かに私は何もしていない。もう何かをすることもアホらしくなっていたから。そして、再び「赤い死の仮面」を読んだのだ。
文学は禍と共に呼び覚まされて、そういう繰り返しが文学なのかという感想。さらにル・クレジオ『隔離の島』を読もうと思った(積読だった)。最初のプロローグの言葉が痛い。
「ここでは金持ちの楽園は終わり、貧乏人の地獄がはじまる」と言っていたアリス叔母さんの思い出に。
梶尾真治「フランケンシュタインの方程式」
梶尾真治というSF作家は初読みだった。宇宙船内でのスラップスティック・コメディ。気晴らしにはこういう作品もいいもんだ。星新一「凍った時間」もそのような作品。というかそういう「ひきこもり」SFが多いのは考えてもいいテーマかも。
ハン・ガン「私の女の実」
妻が植物になっていく話だが、『菜食主義者』で読んだ話かと思ったらそれ以前に書かれた作品だった。カフカの『変身』の植物版と言ってもいいと思うが、違いはある日突然なるのではなく、徐々に、そして夫の視点から語られているのが面白い。妻を観察する夫は部外者なのか?こういう心的な病の場合は共依存ということも考えて良いのかもしれない。
妻に現れた「痣」の意味するところ。それを夫の暴力ということは言ってないが、そういう症状が妻に出たということだ。そして妻はそうした部屋に置き去りにされている。
妻が母に出す手紙がポイントになっている。妻は母のようにはなりたくなかったのだが、結果として母を求めてしまう。それまで娘は外へ逃げよう逃げようと生きてきたはずだ。母の手から。しかしそれは罠のようにロマンチック・ラブに落ちて結婚すると母のような存在に成ってしまうのだ。それは植物的な生成の物語になっていく。夫が飼い殺しにする構造があると気付かされる。病は妻の症状なのだ。植物化していく病。
その他、ひきこもりの「桃太郎」も面白かった。婆さんに食べられて爺さんのために用意された「桃太郎」だった。ひきこもりたくなる気持ちもわかるよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
