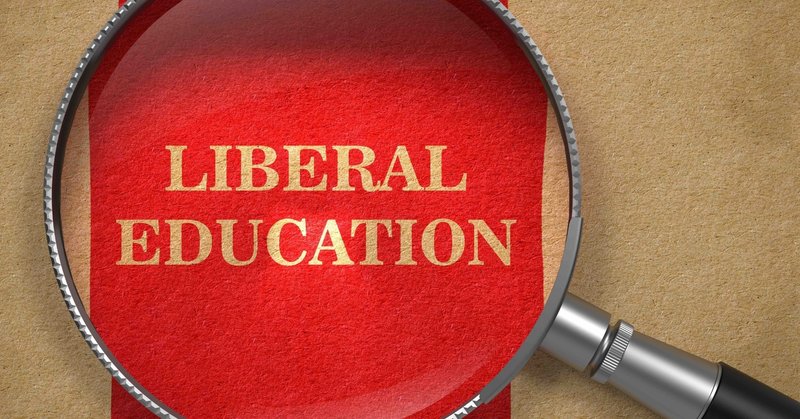
合格したいならアーティストになろう! :後編【リベラルアーツと探究が鍵】
前編【商品ではなく作品を創る】
中編【STEAM教育のAとは?】
前回の記事では、AO・推薦入試で求められる資質も、21世紀型スキルとして世界が国家戦略的として推進しているSTEAM人財も、実は共通して「サイエンスとアートの融合」に鍵があるのではないか?とお伝えしました。
それでは、「論理的な整合と再現性」を主とするサイエンスと、「絶対的な主観と独自性」が主となるアートを融合させるためには、一体どのような考え方が必要になるのでしょうか?
そのためには、私は「リベラルアーツ」が重要な役割を果たすのではないかと思います。
「リベラルアーツ」は日本では教養教育と訳され「幅広く多様な学問領域を学ぶこと」とされ、専門的に一つの学問を極めることの対称にある学びとして認識されているのではないでしょうか?
また大学に入学すると、まずは教養課程で幅広く学んでからその上で専門教育に進むという流れもあり、あたかも専門教育をうける前の準備期間に学ぶ基礎科目いう位置付けとなっているようです。
ですが、リベラルアーツの起源は古代ギリシアまで遡り、もともとは「束縛から解放され人間として自由に生きるための素養」とされています。
専門性を極めることは決して悪いことではありませんが、「それしか知らない」という状態になってしまえば、ある意味においては「不自由」なことなのかもしれません。

つまり、本当の意味でのリベラルアーツとは、専門領域を学ぶ前の準備運動のような学問ではなく「人間らしく生きるために継続して学び続けなければならない姿勢そのもの」なのでしょう。
じつは、一般にはあまり知られていないことかもしれませんが、日本の大学教育の歴史において、かつて、専門教育を推進するがあまりに「教養教育の衰退」を招いたという危機的な状況がありました。
ごく最近まで、多くの大学が「役に立つ人材」を輩出することを重視するがあまり教養教育を削減し、いかに早くスペシャリストを育成できるかに偏ってしまったのです。
こうした大学の傾向は、そのまま受験生にも反映されます。
一般受験において、指定された受験科目しか学ばない高校生がいかに増えたかがその答えです。
大学側も私立文系は英語・国語・地歴、私立理系は英語・数学・理科というように、文系と理系で受験科目を切り分け、科目を絞り込み、受験生の獲得を優先する動きが目立ちました。
しかし、効率よく受験を乗り切るためにいわゆる受験科目だけを限定的に学習しそれで合格したとして、それ以外の知識は全く知らないという人間が、はたして複雑で多様な現代社会を生き抜けるのか、甚だ疑問です。
また、今の社会は一見すると自由に見え物質的にも豊かであるにも関わらず、多くの人が生きづらさを感じているのは、そうした大学教育や受験システムの構造が起因しているのかもしれません。

もともと、人間を解放するために存在した古代ギリシアの「リベラルアーツ」は、まさに「自由七科」と呼ばれ、文法、修辞、弁証、算術、幾何、天文、音楽で構成されていました。
文系も理系も芸術も全てを対等に学び、サイエンスもアートも融合されている世界観です。
つまり、リベラルアーツ的な学びを習得することは、実社会の中で生き抜くために、他者の意見に惑わされることなく、自分の中にある慧眼に目覚め、新しい事象に対する感覚を磨く「アート思考」につながるはずです。
ですが、こうした学びの体得は非常に難しいことのように感じるのではないでしょうか?
私は、自分のやりたいことを「探究」していくことで、誰しもがリベラルアーツ的な学びに没入できるのではないかと考えています。

以前、私がAO・推薦指導を担当したある生徒は、宇宙に強い関心がありいつか宇宙に行きたいと願っていました。理工系の進学を希望していたことから、高校で選択した科目は受験科目の物理と化学でした。
ところが、AO・推薦入試を通して自分の興味を深めていくうちに、宇宙で生活するためにはどうやら食物の栽培が大きな課題になるらしいということに気がつきます。
しかも、宇宙で植物を栽培するためには、重力を感知するある遺伝子が鍵になることがわかってきました。
そこで彼は、ゲノム分野の最新の知見に触れるべく科学専門誌「Nature」の論文を読むようになります。学校では受験科目ではない生物の勉強はほぼしていませんでしたから、かなり大変だったと思います。しかも、原文は英語であったため、結果として英語の勉強も同時に行うことになりました。
このように、自分の興味を「探究」しつづけた結果、学ぶ領域がじわじわと広がって行ったのです。
他にも、経済に興味があったものの、それを自分なりに探究した結果、プログラミングに挑戦するようなった生徒や、医療への関心から絵画や音楽の可能性に目覚めた生徒など、AO・推薦入試をきっかけに、受験科目に縛られない全く異なる分野や領域を自走式で自然と学ぶようになった事例は挙げればきりがありません。
このような受験生たちの変化を見てきた私は、AO・推薦入試を通じて「アーティスト」になるということは、自分の中にある「ささやかな種」を大切に育て上げ、それがいつしか多くの花を咲かせ、実を茂らせる・・・そんなイメージではないかと感じています。
次は「AO・推薦入試に必要な”失敗”とは?」です。
お楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
