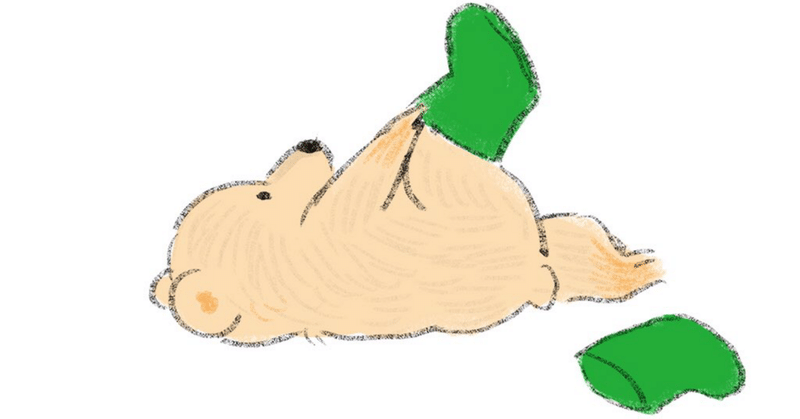
子どもができない時、親が代わりにやってあげていいの?
読書シリーズ、第二弾。
親野智可等著「叱らないしつけ」について書いてみようと思ったけれど、思いの外長くなったので、その前日譚というか、今回はこの本を読もうと思ったきっかけについて主に書いてみる。
ここ最近、感情的に子どもを叱ってしまうことが増えて悩んでいた所、たまたま読んだ雑誌に著者の話が載っていた。
「叱らないこと」、「ほめてあげること」この2つで親子関係は劇的に変わります。
叱りつづけると、子どもはどんどん自信をなくし、「自分はダメなんだ」と思い込みます。
たくさんほめて育てれば、子供は親を信頼し、素直になります。
苦手なことは叱ってまで直さなくてもいい。
できなければ、できるように工夫すればいいし、それでもダメなら、代わりにやってあげればいい。
子育てとは、我が子を良い子にすることではなく、わが子のありのままの姿を愛し、育むことです。
叱らないとか、褒めるというのはよく目にする事だけれど、私が気になったのは、できない時に「代わりにやってあげても良い」という部分だ。最近子どもが帰宅時の荷物の片付けができず、よく叱ってしまっていた。代わりにやってあげた方がお互いに楽だけれど、それだと本人のためにならないかな、、と思い手伝わずにいたけれど、代わりにやってあげてもいいの?と思い、記事を読んだ。
(前略)なるほど、確かにそうですね。ただ、せめて生活の基本的なことはできるように、と願うのが親心。できないと子ども自身も困ると思うのですが。
親野 朝、ちゃんと起きて、ご飯を時間どおりに食べて、支度をし、朗らかに出かける。そんな子は親にとっては便利ですけど、子育ての目標をそこに置くのは危険です。できないから親は子どもを叱っていい、それは大きな間違いです。叱りつづけることの弊害は深刻です。(中略)叱られつづけ、愛情不足を感じた子どもは、親の愛情を確かめようと反抗的な態度をとったり、問題行動を起こすようになります。
叱ることの弊害、怖いですね。でもどうしたら叱らずに、基本的な生活習慣を身につけさせることができますか?
親野 子どもはすべての経験が浅いから、時間の観念も曖昧なら、将来のためにという考えもありません。大人のように頭でスケジュール管理はできません。宿題をやらないのも、ご飯を食べはじめないのも、あとどれくらい時間が残っているかというのがわかっていないからなんです。だから頭ごなしに叱らずに、子どもに残り時間を理解させる工夫をしてみてください。子どもの特性を知り、工夫をすることで子育てはぐんとラクになります。
ということで、叱らないための合理的なシステムの具体例や、褒める時のポイントが説明される。
いろいろ工夫して、叱らずに優しく諭しても、子どもの態度がまったく改善されないと、心が折れそうになります。
親野 もちろんそういう場合もあります。子どもですから。そういうときはあきらめてください。あきらめるというのは見放すということではありません。親がやってあげるということです。着替えが遅かったら着替えさせてあげる。宿題ができないなら手伝ってあげてください。苦手なことは叱ってまで直さなくていい。スローペースな子、片付けが苦手な子、どちらも生まれ持った性質で、短所ではありません。
そもそも子どもというものは自分を変えられない生き物なんです。「鉄は熱いうちに打て」というように、子どものうちに矯正すれば散らかし癖も、頑固な性格も直る、と思いがちですがこれが大きな間違いです。確かに子どもの脳は、乾いたスポンジのように抜群の吸収力があります。でも、将来を見据えて、もっている性質を改善することは大の苦手です。英語を覚える、音楽を覚えるなどの吸収力と、自己改善力はまったく違う脳の働きなんです。
子どもたちを”良い子”に矯正するのが子育てではないし、むしろそれは子どもにとって不幸です。それよりも、ありのままを受け入れて、愛してあげてください。そうすれば自分がやりたいことを見つけたときに、受け入れてもらった、愛されたという自信が、夢に向かって走る力になります。そのときに初めて、あいさつができなきゃ始まらない、片付けができないと支障がある、ぐずぐずしていたら実現できない、と、今までできなかったことにスイッチが入り、改善しようという意志が生まれます。良い子にしなければ、きちんとしつけなければという呪縛を捨てて、子どもとの時間を愛しんで過ごせば、親子関係はきっと、信頼で結ばれた温かいものになっているはずです。
後半の、人は夢を見つけた時に改善しようとするから、それまでに無理に矯正することはないという話は、児童精神科医の本田秀夫先生が発信している事と同じ内容だったので、改めてそうだよなと思いつつ読んだけれど、前半の「そういうときはあきらめてください。あきらめるというのは見放すということではありません。親がやってあげるということです。」というのが、今の自分にとても響いた。
私は基本的には比較的甘いタイプの親だと思うのだけれど、義実家に行くと、お義母さんは優しいけれど、しつけはちゃんとしなきゃというタイプなので、私たち夫婦が優しすぎることを心配していて、子どもに我慢させるのも大事よ、あんまり甘やかしすぎてもね、と結構言われたりする(しかし、そのポイントが私とは結構違い、お義母さんはおやつや洋服やプレゼントを娘にふんだんにくれるけれど、私は質素な家に育ってきたこともあり、そこはそんなに甘やかさないでいいのになと感じたり、一方で、娘が習い事をすぐにやめてしまった時など、私は仕方ないなとそんなに気にしていなけれど、お義母さんは、もう少し我慢も覚えさせないとね、と気にしたりしている)。そんなやり取りにプレッシャーを感じ、自分が甘すぎるのだろうか?と悩んでいたこともあり、やってあげてちゃダメかな、言うべきことはちゃんと言わなきゃ、と必要以上に思ってしまい、最近叱ってしまうことが増えていたなと思った。このあたりの私の悩みに対しては、「叱らないしつけ」の本の以下の箇所にとても励まされた。
子育てでは、目をつぶる勇気が必要になる時が必ずある
では、どうしてもできない子はどうすればいいのでしょうか?
それは、目をつぶればいいのです。
やるべきことはやって、それでもできなければ、目をつぶればいいのです。
どうしても、8時までに提出物を出せなければ目をつぶればいいのです。
どうしても、前の日のうちに次の日の支度ができなければ、目をつぶればいいのです。
どうしても、脱いだ靴の整頓ができなければ目をつぶればいいのです。
別に、それができなくても、どうということはないのです。
一度冷静になって考えてみれば、大人が躍起になって子どもに言っていることのほとんどは、それほど大したことではないと気が付くはずです。
少なくても、子どもの心にトラウマを残してまでもやらなければならないほどのものではないのです。
私は、いつも言っています。
目をつぶる勇気が必要です。
目をつぶる決意をしてください。
大人が子どもに向かう時、この勇気が必要になるときが必ずあります。
でも、ただ目をつぶるのではないのです。
短所に目をつぶる代わりに、長所を伸ばす決意をするのです。
本では、叱ることの弊害について、より詳細に説明されている。著者の長年の小学校教師経験をもとに、具体的なエピソードがたくさん載っているので、とても参考になったし、納得感があった。特に、著者自身も昔は良かれと思ってたくさん叱っていたけれど、それが全く無意味だったと気付かされる苦い経験が綴られているのがとても良いなと思った。
本については、次回続きを書こうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
