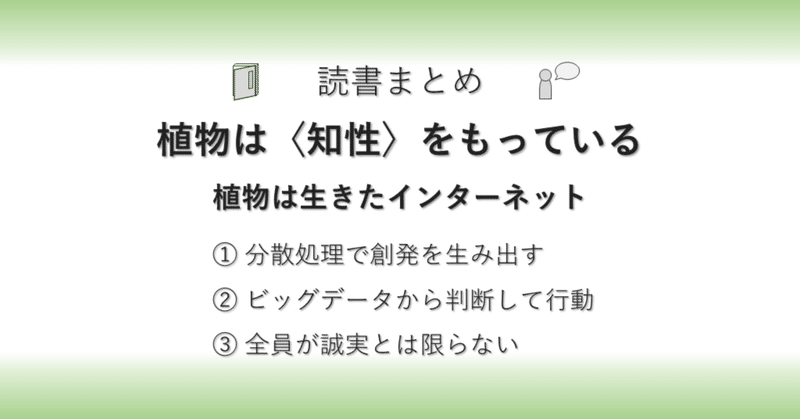
読書まとめ『植物は〈知性〉をもっている』→植物は生きたインターネット
『植物は〈知性〉をもっている』ステファノ・マンクーゾ、アレッサンドラ・ヴィオラ著、久保 耕司 訳
一言で言うと
植物は生きたインターネット
概要
「Web3.0=植物的社会」説の検証のために読んでみました。以前の投稿で「自然界の大先輩である植物に、人類がようやく追いついた」と書いていましたが、追いついたなんて不遜の極みで、先輩の影にやっと手が届きそう、くらいのものですね。まだまだ人類は若輩。
本書は、4月あたりにホモ・ネーモ さんの下記投稿で知った本です。
前作『植物は知性をもっている』は、僕たちとあまりに違いすぎるが故に馬鹿にされがちな植物のスゴさをひたすらにぶちまけるというお祭り騒ぎな本だった。
との言及を見て、読みたい本リストに直行していました。なお、「前作」と書かれているとおり、投稿で紹介されているのは、本書の続編にあたる『植物は〈未来〉を知っている』です。
「植物は生きたインターネット」とは、本書に出てきた表現の引用です。インターネットに関するテクノロジーの発展は、CPUやメモリなどの計算能力を高めることと、高めた計算能力をネットワーク全体で利用することの2つの方向性を持っています。これらの方向性は、前者は脳の発達、後者は知性の分散(社会性動物や植物)として、生物の進化と似ている、と主張されています。
植物の大きな特徴は、一部が破壊されても全体に影響が出ない、モジュール構造である点です。私たち動物の身体は、各器官が固有の役割を持っており、特定の器官を失うと生命を維持できなくなる場合もあります。一方、植物は、器官が各部に無数に存在し、生命維持機能が特定の器官に依存していません。そのため、葉を食べられたり枝が折れたりしても、個体としての生命は維持されます。自然の猛威や草食動物から逃げることができない植物が編み出した、消極的抵抗だと称されています。
この特徴が、Web3.0や暗号資産が植物と似ていると感じた理由です。これらのテクノロジーは、ブロックチェーンをベースにした、分散型で改ざんが困難な仕組みです。メガテックのプラットフォームや中央銀行といった中枢に依存しないところが、今までのWeb2.0・法定通貨と異なる特徴ですね。これは、植物が避けがたい脅威から身を守るために採った、動物とは異なる進化の方法と共通していると感じます。他にも、本書からは植物とIT・ネットワークの共通点を多く見出だすことができました。
本稿では、ネットワークエンジニアの視点から見た、植物とIT・インターネットとで似ていると感じたところを3つ共有します。
① 分散処理で創発を生み出す
植物が持つモジュール構造は、情報の分散処理を可能にしています。動物が持つ脳のような中央情報処理センターがなく、葉から葉へ、根から茎へといった形で情報を送受信していると考えられているそうです。様々な情報を受信した各部位が、個体としての全体最適となる判断を下すことができます。管理職垂涎の、理想の組織ですね。
創発とは、複数の個体が集まって集団になることで、相互作用で強い力を持つこと、といった意味です。動物ではアリやミツバチのコロニー、人間社会ではインターネット・SNSや株式市場などが創発の例として挙げられています。一方、植物は、ひとつの個体がコロニーのような創発を起こしていると言えます。また、ブナ科、マツ科、フトモモ科などには、他の個体(樹木)と葉が重ならないように生育する「シャイな樹冠」と呼ばれる特性もあるそうです。
エッジコンピューティングの考え方も、植物と共通点があると感じます。おなじみのAmazon Web Service(AWS)やMicrosoft Azureなどのクラウドコンピューティングは、クラウドにデータや処理を集約させる方法です。IoTデバイスの急増により、クラウドとつながるネットワークの負荷や処理速度がボトルネックになっていることなどから、近年エッジコンピューティングが注目されています。特定の器官にボトルネックを持たない植物の分散処理的な情報伝達は、エッジコンピューティングを考える上での先行事例になるかもしれません。
② ビッグデータから判断して行動
副題にもあるとおり、植物には20の感覚がある、と主張されています。我々が持つ五感に加えて、温度、湿度、磁場、重力(茎は重力から遠ざかり、根は重力に近づく)、化学物質などを認識しているそうです。動物と比べて動くスピードが極端に遅い植物は、例えば水場を探して歩き回ることはできないので、行動の判断を下すために感覚が進化したと考えられています。
植物は刺激を認識するだけでなく、刺激を区別して学習する、という興味深い実験も紹介されていました。オジギソウは、指で触れると葉を閉じる性質がありますが、風や雨の滴では葉を閉じません。植物学者オーギュスタン・ピラミュ・ドゥ・カンドールの行った実験では、オジギソウを馬車に積んで走ったところ、最初は振動で葉を閉じたものの、しばらくすると馬車の振動に慣れたかのように、葉を閉じなくなりました。データ(振動)を大量に与えることで、どのように行動するべき(葉を閉じる必要はない)かを学習させたとも捉えることができ、この実験からは機械学習・AIの分野を想像せずにはいられません。
動物以上に多彩・繊細な感覚によって情報を得て行動する様子は、ビッグデータの活用だと言えます。20の感覚に留まらず、まだ人間が認識できていないデータを集めている可能性すらあります。また、多量のデータを集められたとして、それらをもとにどのように意思決定するかが難しい問題です。植物の意思決定メカニズムを解明すれば、ビッグデータ活用のモデルに活かすことができるのではと思いました。
③ 全員が誠実とは限らない
本書では、植物と植物の受粉を手伝う動物の関係が、巨大な市場に例えられています。売り手は植物、買い手は昆虫や鳥などの動物、商品は花粉や蜜です。一般的なものだと、植物が動物に蜜を与え、動物は植物の花粉を運んで受粉を媒介する、というWin-Winな共生関係ですね。花の色や蜜の香りは、動物を惹きつけるための広告といったところでしょう。
ところが、売り手である植物は、ちゃんと商品を提供する誠実なものばかりではありません。動物に花粉は運んでもらうけど、植物は対価を支払わない、といった片方だけが利益を得る共生(片利共生)も存在します。オフリス・アピフェラというラン科の植物は、メスのハチに擬態した花を咲かせます。その完成度は高く、見た目だけでなく、硬さや体毛、におい、フェロモンまで模倣しているそうです。オスのハチは、この幻想のメスに夢中になり、交尾を試みている最中に花粉を浴びせられて媒介者にさせられます。
魅力的な広告や無料サービスで引き寄せ、依存させて養分を吸収する… 瞬時に・広範囲に情報が伝達される現代社会において、このようなビジネスモデルも散見されますが、植物はもっと高度にやってのけていたことに驚きを隠せません。Web3.0の土台となるブロックチェーンが保証するのは、データとしての正確性であって、情報の内容の正確性は保証されません。情報を疑う・真偽を見極める姿勢は持ち続けていたいと思いました。
Amazon.co.jpアソシエイトに参加しています。
#推薦図書 #読書 #書評 #最近の学び #植物 #知性 #植物学 #植物生理学 #植物は知性をもっている #知覚 #感覚 #生命 #生物 #インターネット #ネットワーク #ネットワークエンジニア
いつも図書館で本を借りているので、たまには本屋で新刊を買ってインプット・アウトプットします。
