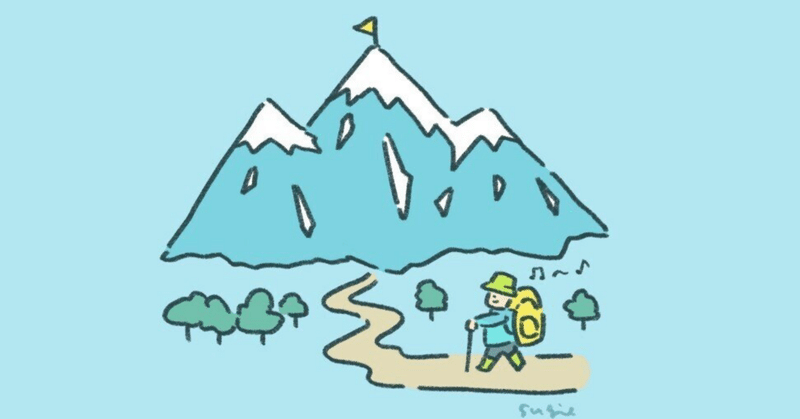
#43 いざ!御朱印
御朱印を集めているタイプです。
御朱印帳は3冊目に突入しました。
“月参り御朱印”を近くの神社がやっており、なかなか評判だと聞いて先月行ってみました。
...正しくは、行ってみる前に、4月はどんな絵柄なのか、インスタやネットで調べてみました。
それほど可愛くなければやめとこうかな、という思いがそこにはあります。。。
調べてもなかなか出てこず、諦めてひとまず行ってみました。
いやはや、神様が知ったらけしからんと言われそうです。
ところで、改めて考えると御朱印とは?
調べてみました。
本来は「御納経御朱印」 などと呼ばれ、経典を写経したものを寺院に納めた代わりに証として受ける領証(証明印)であった。そのため朱印を受けることを「納経」ともいう。現在でも納経(写経の奉納または読経)をしないと朱印がもらえない寺院が存在する。
...!
御朱印の絵柄次第ではやめとこ〜、なんて、御朱印の意義とは外れすぎております。
そんな私に、つい先日、御朱印の意義を感じさせてくれる出来事がありました。(ちょっと大袈裟)
今日は、高尾山と御朱印のお話。
よく晴れて、新緑が気持ち良かったGW前半のある日。
こんな日は高尾山でも登ってみようか!と、私たち家族3人+お義母さんで出掛けました。
もちろん、登山コースを正面から制覇するのではなく、途中までリフトで登り、そこから頂上までを登ります。
新緑の中を進むリフトが気持ちよくて最高!

以前お義母さんから、「昔は仕事終わりに高尾山のビアガーデンによく来てたから、この山はみんなヒールでも登れちゃうのよ〜」なんて聞いていました。
そうかそうか。お手軽なんだな。
リフトで登った先にはちょうど、“スプリングビアガーデン”の文字が。
こんな景色と気持ちいい気候の中で飲めたら最高だなぁ、なんて思いながら、ひとまずお昼ごはん。
みんなでお蕎麦をいただきました。
お蕎麦を食べながら周囲を観察していると、装いは様々ですが、ほとんどがそれなりの登山スタイルです。ステッキや熊除けの鈴を持っている人も多数。
お義母さんの、ヒールでも登れる発言を信じていた私は、身軽な服装にキャップとスニーカー、しかし荷物はトートバッグ。近所のスーパーにでも行くかのようなトートバッグ。
...まぁ、気にせず元気に登り始めました。
気温も高くなってきて、階段も多く、息も切れ切れ進んでいくと、高尾山薬王院の大本堂が見えてきました。
立派な門をくぐり、お参りをして、御朱印の列へ。受け取りは下山の時です。

ここまでで汗はびっしょり、トートバックを掛けている肩も紐が食い込んで痛み始めます。
そして、ここから頂上までの約30分?くらいが本当にキツかった!!!!
何度も現れる階段をゼーゼー言いながら登り、アップダウンが膝に堪え、トートバッグが肩にジワジワと食い込む!(涙)
もう全然ヒールじゃ登れないじゃん!
てか、そもそもそんな山あるわけないか!
なんてツラいんだろうと見回してみると、軽快に階段を登っていく息子、それを走りながら追いかけるパパ、気持ちいいわね〜と言いながらニコニコ歩いているお義母さん...
あれ?私だけ登ってる山違うのか?!(涙)
どうやら、ツラいのは私だけのようで、残りの家族はみんな爽やかに新緑の高尾山を楽しんでいます。
と言うより、私を除く登山者のほとんどが楽しそうに軽快に登っていました。
3歳くらいの女の子に追い抜かれたところで、なんとか頂上に到着。汗だくです。
私1人死んだ顔で記念写真を撮り、少し休憩したら下り道へ。
下り道に大した負担は無いというのに、膝が痛いとか肩が痛いとか文句を言いながらようやく薬王院の大本堂まで戻りました。
そして受け取った御朱印。
なんだか、達成感と重みがありました。
私にとって、何かを買う時や始める時、行ってみる時には当たり前になっている、“ググる”こと。
私だけでなく、現代に生きる人はみんなそうではないでしょうか。
いくらでも情報は出てくるし、レビューや口コミを参考にして、買う前や行く前に最善の判断ができたりもします。
御朱印の絵柄すら、調べてから行くか決めようとしているくらいです。
実際、レビューや口コミ助けられることも多々あるし、情報を得られるって本当に便利なこと。
でも、情報の裏にあるものを自分で確かめてみるって大事なことだなって考えさせられます。
画面の前で悩むより、動き出すことに価値があるかどうか、その見極めを上手になりたいと思いました。
ひとまず、今回の経験を通して言えることは、高尾山はヒールでは決して登ることはできないということです。(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

