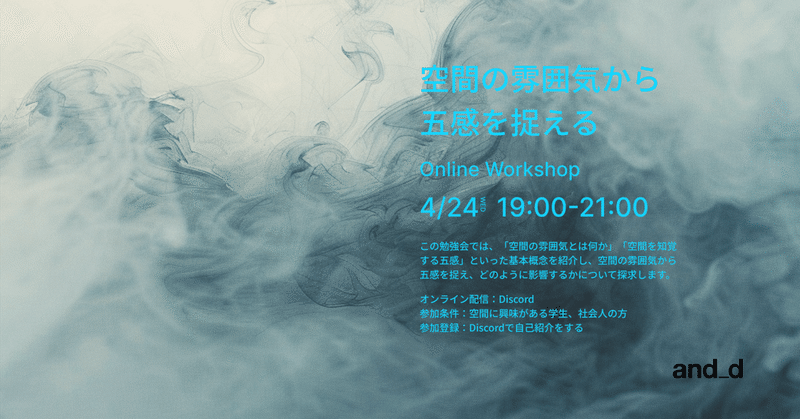
『空間の雰囲気から五感を捉える』オンライン勉強会
and_dの堀涼太です。
2024年4月25日、and_dでオンライン勉強会の第3弾となる『空間の雰囲気から五感を捉える』を開催しました。
概要としては、「空間の雰囲気とは何か」「空間を知覚する五感」といった概念を紹介し、どのように建築や身体に影響するかについて探求しました。
1.「空間の雰囲気から五感を捉える」の発表
発表の主な流れとしては、「身近に感じる言語からの雰囲気」から入り「空間の雰囲気」とは何かについて定義を行い、「身体を媒介とした雰囲気の知覚」について考察し、身体を媒介とした雰囲気の知覚へのアプローチを行っている人物と作品を紹介し、最後に自身の制作のスタディを紹介するという形式で行いました。
・身近に感じる言語からの雰囲気
ここでは身近にある俳句や食リポなどの言語から雰囲気について紹介しました。

俳句では、松尾芭蕉の「古池や 蛙飛び込む 水の音」を例に挙げ、俳句では、言葉の裏にある情景を思い浮かべさせることが重要であり、情景を想像できれば、句からどんな雰囲気が表現されているかを推測できます。
食リポも同様で、アナウンサーは、視覚以外の情報も伝える必要があり、味や触感だけでなく、料理から連想されるイメージを言語化し、視聴者に伝えます。例えば鉄板の音や、新鮮なエビの生命感を伝え、料理の雰囲気を共有しています。
・テーマを選んだきっかけ

建築には様々な理論や文脈が存在していますが、人間は無意識のうちに空間の複雑な雰囲気を感じ取る能力や、細部よりも先に、その場所の特徴的な雰囲気を把握することが出来ます。理論や文脈などの生成論も大事ですが、雰囲気についての今一度考える必要があると考えた為、雰囲気を今回のテーマにしました。
・空間の雰囲気とは

アンドリュー・サンダースは、デジタル方法論やバロック時代の装飾に関する分析を背景に持ち、西洋の雰囲を"stimmung"、"atmosphere"、"mood"の3つに分類しました。特に、"atmosphere"を、個人の感情や心理状態ではなく、物理的な環境や空間の感じ方に焦点を当て、建築における雰囲気とは、『atmosphere』という言葉の一側面に過ぎないということが分かりました。また、マティアス・デル・カンポは、建築における雰囲気とは『色や形、素材といった物理的な特性だけでなくは、作品が醸し出す感情的・存在論的な性質のことである』と定義しています。
つまり、建築の雰囲気を理解し、評価する際には、物理的な特性だけでなく、作品が伝える感情や存在感などの要素も考慮することが重要であると考えられます。
・身体を媒介とした雰囲気の知覚
次に建築やデザインにおける感覚的・情感的な側面を探求しているユハニ・パッラスマーの『建築と触覚』から、身体を媒介とした雰囲気の知覚について紹介しました。

雰囲気の知覚は、空間や食べ物など様々な事象を自身の身体を通して感じ取ることによって行われます。パッラスマーは、雰囲気を単なる感覚的なものではなく、建築が持つ空間的な特性や存在感、その場の独特な質感として捉えており、建築の雰囲気は単なる視覚的な要素だけでなく、触覚や他の感覚との関わりも含めて総合的に捉える必要があると説明されています。空間の形状や素材の触感、空間の温度や湿度、さらには香りや音、人々の動きや声の振動など、さまざまな要因が組み合わさることにより、空間の雰囲気が生み出され、それらを身体を通じて知覚していることが分かりました。

身体を媒介とした雰囲気の知覚の実践として、イザイ・ブロッホ、マイケル・ハンスマイヤー、ヤング&アヤタ、砂山太一・田中義久 等の作品を紹介し、身体を媒介とした雰囲気の知覚へのアプローチを紹介しました。
・実践のスタディ
実践のスタディとして触覚と雰囲気をテーマにスタディを行いそれらの紹介を行いました。

まず、背景としてトーマス・ヘザウィックのTED『「退屈な建築」が台頭するいま、人間性あふれる建築を擁護する』から、現代の空間は細かなディティールや装飾な失われたことで、雰囲気のある建築が減っているのではないかと考えました。そういった原因に挙げられるのは、モダニズム期のアドルフ・ロース「装飾と犯罪」や、産業革命による大量生産などの規格化によってシンプルなデザインが好まれ、装飾は不要なものと捉えられ為、過度な装飾やディテールは失われっていたと思います。

装飾は幅広く、倉方俊輔は『壁面のモザイク、石積の目地、柱頭の彫刻、モールディングすなわち近代以前の建築の細部意匠の大半は装飾で(も)ある。』と述べ、細部意匠である装飾は建築を分類し、価値を判断づける際の重要な要素であると定義しました。
モダニズムを機に装飾が、具象的な彫刻や意匠から、抽象的な形態やデザインにシフトしたのに対し、現代の装飾は表面的な飾りではなく、『物の現われ、様相、いわばテクスチャーと同義に扱われるべきである』と考えられるようになり、現代の建築の装飾は単なる視覚的な魅力だけでなく、触覚的な体験やモノの本質を感じさせる手段として位置づけられると思います。
その為、建築空間における触覚の重要性が高まっていると考えられ、触覚的な要素の持つ新たな装飾の制作を行うことに決めました。

Midjourneyを使用して新たなテクスチャ画像を制作し、その画像が持つ視覚的な雰囲気と触覚的な雰囲気の違いに焦点を当ててスタディを行いました。
ここでは、Y2Kというスタイルと木のテクスチャを掛け合わせることで新たなテクスチャを作りました。

和紙は木を原材料にしているため、その表面には木の繊維や質感が感じられ、視覚的にも触覚的にも自然な雰囲気を持っています。一方、市松模様の印刷紙は、視覚的にはテクスチャが印刷された表面ですが、触覚的にはその表面の質感は、市松模様の質感になり、違和感のある雰囲気を感じました。

次にここでは、CGなどで使われるテクスチャーを生成しました。そのテクスチャーをもとに画像深度から画像に凹凸をつけ3Dプリントしました。ここでは壁紙などの凹凸のないマテリアル表現に凹凸がついた場合どのように感じるかを目的に行いました。その結果、画像という視覚的情報とは違った印象を触覚で受けるのではないかと思います。
2.オンライン議論
オンライン議論では発表を終えての質問をベースに話が展開されました。参加してくださった皆様ありがとうございました。
出てきた質問や議題
・モダニズムにおける空間も一種の雰囲気ではないか?
・stimmung/atmosphere/moodのどの分野に興味があるか?
・規範なき建築とはなにか?
3.まとめ
最後に、今回のオンライン勉強会では身体と雰囲気について考察しましたが、発表者の力不足もあり、議論はたじたじでした。しかし、今後もand_dの勉強会に参加いただければ幸いです。
4.参考
Evoking Through Design: Contemporary Moods in Architecture
建築と触覚
YOUNG & AYATA
Donkeys & Feathers — YOUNG & AYATA (young-ayata.com)
マテリアライジング・デコーディング 情報と物質とそのあいだhttps://www.millegraph.com/books/isbn978-4990543631/
TED:トーマス・ヘザウィック
5.SNS / お問い合わせ
and_dは様々なメディアで情報発信を行なっています。今回のオンライン勉強会でも見られたように実は建築の理論をベースに活動などを行っています。noteではこれから活動録やメンバーの読書録などを不定期に配信していく予定です。よければ、フォローや拡散の程よろしくお願い致します。
【and_dオンライン勉強会開催!】
— and_d (@and_d_official) May 8, 2024
この勉強会では、動的平衡の思想やディスクリートの概念を取り上げつつ、過去から現代におけるメタボリズムの潮流について議論します。
日時:5/8(水) 19:00-21:00
パネリスト:相川隼哉/大本和尚
参加方法:Discord(https://t.co/tIb56bcbxR)で自己紹介をする pic.twitter.com/TfbTBFjVFe
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
