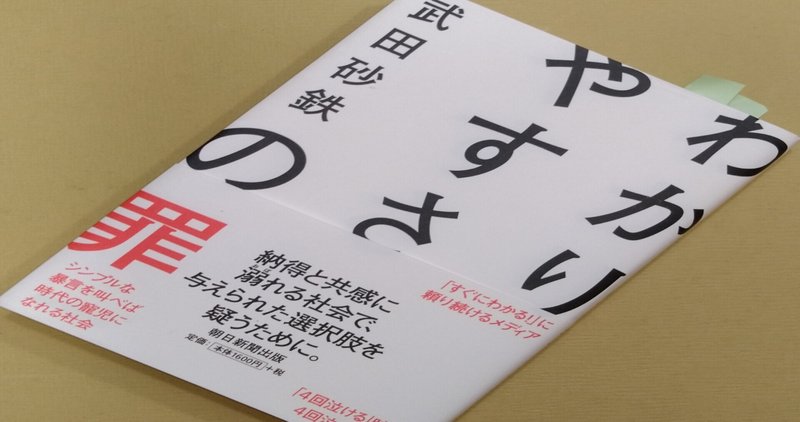
「わかりやすさの罪」武田砂鉄 を読んだ
納得と共感に溺(おぼ)れる社会で、与えられた選択肢を疑うために。
まずはこの本の帯に引き寄せられた。
・シンプルな暴言を叫べば時代の寵児になれる社会
・「すぐにわかる!」に頼り続けるメディア
・「4回泣ける」映画で4回泣く人たち…
裏表紙には
・「どっち?」との問いに「どっちでもねーよ!」と答えたくなる機会があまりにも多い日々。
並んだフレーズがなんとも魅力的。ここのところ、わたしも「わかりやすさ」への偏重を窮屈(きゅうくつ)に感じていた。のどに刺さる魚の小骨のような「なぜそうなってしまうのか?」という疑念の数々。ひょっとして小骨をきれいさっぱり一掃するヒントが書かれているかもしれない。2020年7月30日の初版を買って以来、定期的に読み返している。
「わかりやすく」書くのが当たり前なのが物書きという職業。一般的にわかりにくいことを、わかりやすい表現と正しい言葉で簡潔に説明する技術が必要だ。なのに常に「わかりやすさ」が重宝されるメディアやSNSに対して疑問を感じている。
そもそも音楽などアートに関しては「単純でわかりやすい」より「複雑でわかりにくい」ほうが好みかもしれない。わかりにくいからこそ、わかりたい。少しずつ紐解いていくうちに「わかりはじめる」過程が楽しいのだ。
「万引き家族」で知られる是枝裕和監督は
「僕は意図的に長い文章を書いています。これは冗談で言ってたんだけど、ツイッターを140字以内ではなく、140字以上でないと送信出来なくすればいいんじゃないか(笑)。短い言葉で『クソ』とか発信しても、そこからは何も生まれない。文章を長くすれば、もう少し考えて書くんじゃないか。字数って大事なんですよ」
「だって、世の中って分かりやすくないよね。分かりやすく語ることが重要ではない。むしろ、一見分かりやすいことが実は分かりにくいんだ、ということを伝えていかねばならない。僕はそう思っています」
と語っているという。
音楽ジャーナリストの柴那典(とものり)
『ヒットの法則』(講談社新書)の中で、ロックバンドやアイドルソングの領域で「過圧縮ポップ」が増えてきていると分析している。
要素を全部盛るように短時間の間に圧縮していく。魅力的なフレーズを連鎖させて、短縮、圧縮、密集させることで曲をフル尺で聴かずに次々と飛ばせるようになった環境下では、一気に印象付けるこの過圧縮が求められる。共感してもらうための言葉、そして圧縮される音楽。とにかく結果をすぐに出さなければいけない。
俳優・斎藤工(たくみ)
映画史に寄せた辛辣なコメントも面白かった。2018年のワースト映画を語るくだりで
「去年は下半期に我慢ならない邦画のポスターがあった。作品というよりポスタービジュアルが酷過ぎた。邦画によくある登場人物がブロッコリーみたいに皆載っているデザイン性を無視したモノの下に、キャッチコピーとして”〇回泣けます”と一言。受け取り手の感情を(しかも回数まで)断定するなんて無礼だなと感じたし、事実私はこれで”絶対観るもんか”と決意。この作品のタイトルじゃないけれどコーヒーの前に気持ちが冷めた」
『映画秘宝』2019年3月号
そもそも皆が「泣く」「泣ける」と評判の映画やドラマは苦手だ。そもそも「感動の押し売り」は勘弁してほしいし、流行りものに飛びつくほうではない。なので筆者のように「4回泣けます」には抗いたいと思う。
感情を規定するな。要請するな。こういうものに慣れてはいけない。4回泣けますと言われて、4回泣いているようではいけない。何度だって抗いたい。
置かれた場所で勝っているだけ
昨今、跋扈(ばっこ)している暴力的な断定は、おおよそこの仕組みの中にある。自分の信じていることを、なにがあっても曲げられない人たちが「だって、そう思ったんだもん」と駄々をこね、揺さぶられない確固たるオピニオンであるかのように流してくる。
自分の考えが世の中の考えではないかもしれないことに対して、思い悩む様子が一切ない。これってなかなかすごいこと。「『わからない』ことは人を不安にさせる」もの。
理解できないことに、人は耐えなければいけない。今起きている諸問題を分析すると、その改善策として打ち出したくなるのが「ちゃんと人の意見を聞きましょうよ」とか「自分の中にある迷いを認めませんか」とか「自分にとって快適なことでも誰かにとっては不快なものかもしれないので気を付けましょうよ」
SNSは社会の縮図だ。まさに上記のような状態を目にすることがある。
自分の考えていることとは異なることを考える人がいる。自分の考えていることですら人間は管理することができない。常識やルールをぶっ壊せ!と叫ぶことは、常識やルールをくつがえす特別な自分に酔っており、選択肢を疑わないために、たちまち暴力的になってしまうという筆者の見解にはうなずくばかりだ。
複雑化した社会をシンプルに解決するために、まずは大声を張り上げる。その大声に反応した人々を引っ張り出す。オンラインサロンでは「新宿御苑理論」なるものが提唱されているらしい。オンラインサロンはメンバーを絞り込むことができるクローズドな空間だ。そこでは主たるメンバーへの賛同者だけの空間になり、厄介な議論が生まれなくなるという。
自分のまわりに自分を迷わせる人がいなくなるということは、自分の意見とは違うんで、それは違うと思います、ってなにも言っていないに等しい。
万物は複雑であるのだし、自分の頭の中も複雑なつくりをしているのだから、その複雑な状態を早々に手放すように促し、わかりやすく考えてみようと強制してくる動きに搦(から)め捕(と)られないようにしよう
「わかりやすさ」って?
ニュースリリースのポイントとしてあげられる「簡・豊・短・薄・情」(簡潔、簡明を心がけ(簡)、必要な内容を網羅し(豊)、1文や1行を短くし(短)、全体を1~3枚にまとめ(薄)、あとは情熱をもって書く(情)、メディアはこういうテキストに溢れている。だが、一定期間を経ると、体には何も残らない。
SNSやネット記事をむさぼるように読んでも、残留成分が少ない理由が「わかった」ような気がした。
いま主流となっているネット記事は筆者のいう「モンスターエナジー」的な「誰もがハマる爽快感とパンチのあるテイスト」な文章なのだ。それと同時に「わかりやすさ」が求められるメディアに浸り続けることで、見失いがちなものにも気が付いたように思う。複雑で理解するのに多少、時間や手間がかかろうとも、歯ごたえのある文章に触れていたい。そうすれば安易に「白か黒か」の二元論的な思考停止に陥ることなく、客観的な視点・論点を保っていけそうだと感じている。
#読書の秋 #日記 #読書感想文 #発達障害 #同調圧力 #いじめ #武田砂鉄 #記者 #ライター #読書 #わかりやすさ #社会 #SNS #ネット
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
