
映画「罪の声」を観た
聞くことと、伝えること
日本中を震撼させ、未解決のまま時効となった大事件をモチーフにした小説「罪の声」。犯罪のテープに声を使われた子どもは三者三様の人生を歩む。姉は夢半ばにして命を絶たれ、弟は成人しても保険証さえ持てない絶望の淵に立つ日々。三人のうちの一人、曽根俊也(星野源)は平凡ながらも幸せな家庭を築きテーラーの主(あるじ)として生活を送っている。
「声」とは不思議なものだ。その人の特徴や唯一無二の声、モノマネに至っては目をつむって聞けばまるで本人かと思うほど、そっくりなこともある。それでも声紋鑑定をしてみれば他人が声を偽装したり、意識して声を変えたりしても、簡単に識別出来てしまうという。
相手の顔を見つめ、時にうなずき質問を交えながら、一言も聞きもらすまいとひたすら取材対象の「声」に耳を傾ける。スクリーンの中にいた新聞記者・阿久津英二(小栗旬)は紛れもなく元新聞記者で作家の塩田武士さんだった。
この映画のテーマとしては
・社会の表側に見えにくい弱者と子どもの未来をどう守っていくか
・事実の重み、実在の凄みをどう伝えて考えていくか
があるだろう。
見えない存在に目を向け、届かないような小さな「声」にも耳を傾けること、そしてそれを伝えることの大切さを痛感した。そして代弁していく側であるマスコミのあり方も問われている。元新聞記者の塩田武士さんらしい視点だ。常に「それでいいの?」と社会に問いかける。
その想いとジャーナリズム精神を、登場人物の心情に寄り添って語らせるのが野木亜紀子さんの脚本。正面からぶつけるのではなく、あくまで自然な流れで「問い」を投げかけるセリフの数々。
印象に残っているセリフとシーン
(わたしの記憶なので映画と異なる部分はご了承ください。)
イギリスで曽根達夫が阿久津に語った罪を犯した“理由”
「ふるいたったんやろうね、ずっとくすぶっていた社会に対する怒り」
「社会に見せつけた。警察にこの国がいかに空疎か!」
それに対して阿久津が投げかけた言葉
「自分たちの社会のへの不満を晴らすために子どもの“声”を利用した“彼ら”は子どもたちの運命を変えただけ。子ども達の未来を壊した。そんなものは正義じゃない!」
テーラーを営む曽根俊也からイギリスに住む伯父の達夫へのメッセージ
「社会に不満を抱いてもあなたのようにならない」
声をテープに使われ犯罪に荷担させられた総一朗からの質問。
自分と同じように当時子どもでありながら、罪の意識を背負い社会の裏側で辛酸をなめてきた総一朗。俊也は「平凡だが幸せに暮らしている」とは言えないでいる場面。
「曽根さんはどんな人生やったんですか?」
弁護士事務所で阿久津と曽根が「時効です」と総一朗に伝えたあとのセリフ。
「当たり前にあるものが奪われた。罪の意識をいだくのはあなたじゃ無い。」
声をテープに録音したことを告白した母に対して。
責めるような口調ではなく、あくまで母を諭すように冷静に話す俊也。それに対峙する母は決して「あの時の自分」を否定はしない。間違った正義だったかもと、わかってはいるだろうけれど。
「罪の声を背負っていくことになるんやで。それがお母さんの望みやったん?」
テーラー「曽根」でものすごい剣幕で話す俊也におびえる彼の娘に「驚かせてゴメン」とあやまった阿久津。後の取材に同行するうちに、そのときの阿久津のことを俊也は「ええ人」と言う。
「『驚かせてゴメン』とあやまるええ人。」
総一朗と母の再会シーン。姉の声の入ったテープ音声を聞かせる。犯罪に使われた当時の、まだ幼さの残る少女の声。だが高齢で既に認知症の母は犯罪に使われたテープの声でも娘の声が聴けたことに涙を流して喜ぶ。車いすごと抱き合う二人に、常に冷静な阿久津も涙ぐむ。
「望ちゃんの声や!」
新聞記者としてのジレンマと闘う阿久津英二
阿久津英二が俊也に話す。とても印象的なセリフ。
「演劇や映画を扱う文化部でこんな風に毎日、ぺらぺらの記事を書いてる。以前は社会部にいたが事件記者じゃ無い。」
「毎日、夜討ち朝駆け。小さな子が死んだ親にどんな子でしたか?いい話ですねと相づちを打ちながら、あと一つ話を引き出せれば他の新聞に勝てるのに…と考えている。記者の矜持(きょうじ)も世の中に訴えたいことも何もありません。」
報道記者は精神的にタフでないと務まらない。他紙に抜かれないためには、取材対象から淡々と必要な事実だけを聞き出すことにひたすら注力する。他人の感情を受け取って感情移入してしまうような優しさには、フタをする必要がある。
相手の感情に飲み込まれてしまうような強すぎる感受性は、ある意味危険でもある。取材対象に入れ込みすぎると自分の精神がむしばまれてしまうのだ。
ひたすら感情のスイッチを切って相手に接しなければならない。第一線の現場記者であることに疲れ果てて文化部で「ぺらぺらの記事を書いている」阿久津。“優しすぎる”ゆえに報道現場で踏み込むことができなかったのだろう。
阿久津記者のジレンマは社会への問い
「マスコミは事件をエンタメとして消費してる。」
「『過去を掘り起こして何になるのか?』と曽根さんに聞かれた答えがない…。」
鳥居デスクが阿久津を叱咤激励するセリフも沁みた。
「意義のある記事、書いたれや!」
「俺たちの仕事は素因数分解。素数になるまで割り切って真実を、人の不幸を明らかにせんとアカン。他人の人生に踏み込むことが記者の人生。寄り添っていこう。」
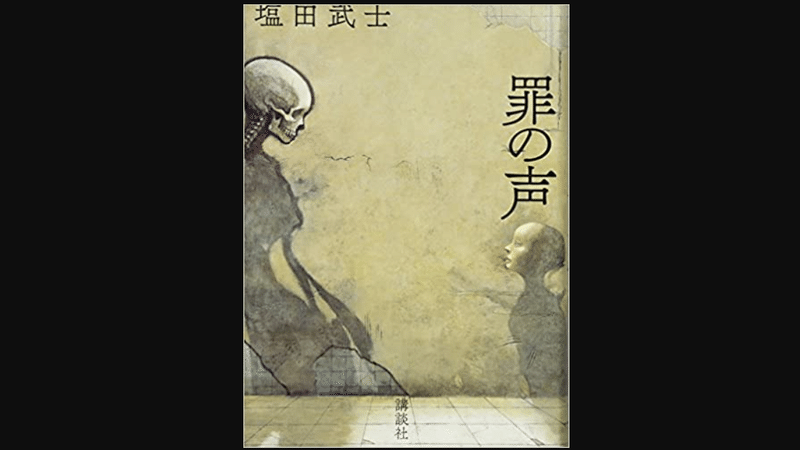
塩田武士さんの原作本も読んでおきたい 単なる謎解きのミステリー小説の域にとどまらない。複雑に絡み合った人間の性(さが)と悲しみ、優しさが伝わってくる。
この映画で一番響いたのはやはり数々のセリフ。脚本家という職業は新聞記者と同じように文章を書く職業だけれども、また、反対の方向も見据えているのだろう。年齢や性別にかかわらず犯罪者から被害者にいたるまで、全ての人生を網羅しなければならない。
登場人物に感情移入しつつ、慎重に言葉を選んで寄り添っていく。塩田武士さんの原作小説に忠実に、しかも確実に深みを添えながら言葉を紡ぐ。野木亜紀子さんの脚本は何度も反芻したいフレーズばかりだった。
阿久津はまた社会部に異動になる。テーラー曽根に社会部らしいスーツを仕立てに現れるが、今着ているのは既製品のスーツで体に合っていない。仕立て上がったスーツは袖のボタンが取れかけてぶら下がったまま、なんてことはないだろう。阿久津がスーツの袖ボタンがほつれて取れかけているのを俊也に指摘され、ボタンを引きちぎってしまうシーンがあった。いかにも報道記者的な雰囲気を演出していたように思う。「ピッタリあうもんは美しい」と俊也が言う。
伝えたかったものとは
「罪の声」映画化のアナウンスを聞いてからしばらくして、日本にも新型コロナの脅威が蔓延し始めた。日常生活でさえも困難を極める中、治療法の確定しないウイルスによって日常が吹き飛んでしまう。病気や事故だけではない。小さなきっかけひとつでほころんでしまう“当たり前“の危うさ。そのきっかけは誰に対しても、すぐそこに転がっている。
情報過多な日常を「本当にそれでいいのだろうか?」自分の頭で考えよう。小さな声にこそ耳を澄まそう。見えないものも見ようと努力しよう。一日、いや一瞬を大切に過ごしたい。そして身近にいる大切な人たちには「好きだ」と伝えよう。当たり前の暮らしこそが”有り難い”ものだから。そんな気持ちになって映画館を後にした。
#罪の声 #映画レビュー #小栗旬 #星野源 #塩田武士 #野木亜紀子
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
