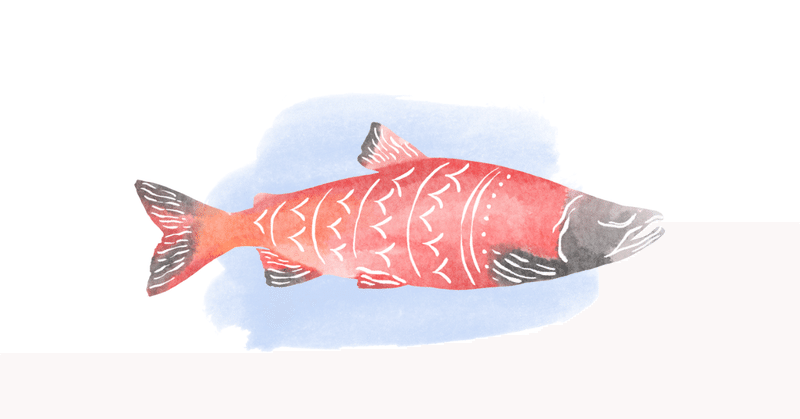
知識はないけど「重要文化財の秘密」を鑑賞してみた
展示されている作品全てが重要文化財という、とにかく豪華な展示「重要文化財の秘密」を見てきました。
実はこれまで、「名画」だの「重要文化財」だのすごそうな名前がついている絵にはあまり興味はありませんでした。
美術史や絵の「見方」を知っていないと楽しめなさそうな、お勉強的な堅苦しい印象を持っていたからです。
堅苦しい知識は抜きにして、主観で自由な解釈ができる現代アートや抽象画の方がとっつきやすくて好きだなと。
しかし、公式サイトの紹介文を見て、この展示に興味が湧いてきたのです。
明治以降の絵画・彫刻・工芸のうち、重要文化財に指定された作品のみによる豪華な展覧会を開催します。とはいえ、ただの名品展ではありません。今でこそ「傑作」の呼び声高い作品も、発表された当初は、それまでにない新しい表現を打ち立てた「問題作」でもありました。そうした作品が、どのような評価の変遷を経て、重要文化財に指定されるに至ったのかという美術史の秘密にも迫ります。
最近読んだ本「13歳からのアート思考」に書かれていた、発表当時は問題作とされた作品が名作と呼ばれるようになった理由が興味深かった。
また、その名作を自分の目線で鑑賞することの面白さも(本の中での疑似体験ですが)味わうことができました。
「13歳からのアート思考」で取り上げられた作品は全て西洋のアートでしたが、今回の展示はいわばその日本版。
今「重要文化財」とされ、高く評価されている作品が、なぜ重要文化財とされるに至ったのかを知りたいと思ったのです。
なぜその作品がすごいとされたのか。
重要文化財の作品はそんなにすごいのか。
美術史や教養を学び、専門家と呼ばれる人たちの視点を学ぶとともに、自分なりに作品を楽しめたらと思い展示を見に行きました。
🌊展示情報🌊
東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密
開催場所:東京国立近代美術館
会期:2023年3月17日(金)- 2023年5月14日(日)
観覧料:一般 1,800円
大学生 1,200円
高校生 700円
公式サイト:https://www.momat.go.jp/am/exhibition/jubun2023/
展示されているのは明治以降に制作され、重要文化財に指定されている作品たち。
上位である「国宝」に明治以降の作品はないそうなので、明治以降の日本の美術作品としては実質トップの評価を受けているということになります。
会場内ではジャンル別・年代別に並んでいるため、作品から日本の近代美術の歴史を辿ることができます。
また、重要文化財に選ばれた時期や経緯が作品横の説明に書かれていたり、年表にもまとまっているので、前提となる知識はある程度展示の中で得られる構成となっています。
印象に残った作品
まずは自分なりの鑑賞記録を。
専門家のお墨付きを受けている作品であっても、やはり自分自身に響くかどうかはグラデーションがあります。
特に印象に残った作品を4点挙げてみました。
横山大観「生々流転」
タイトルを見た第一印象、「鬼滅の刃の技やん」。
水の一生を描いた長さ40mにも渡る水墨画です。
全体を一直線に広げた状態で展示されるのは非常に珍しいのだとか。
「生々流転」本来の意味はこちら。
すべての物は絶えず生まれては変化し、移り変わっていくこと。▽「生生」は物が次々と生まれ育つこと。「流転」は物事が止まることなく移り変わっていく意。
そこから転じて、絶えることなく変化する水の様子からこのタイトルをつけた、ということでしょうか。
描かれた水の一生は穏やかでありながらドラマチック。
まさに鬼滅に登場する「水の呼吸 拾ノ型」の元ネタとなった絵です。
巻物なので、順に見ていくことで時間と空間の流れをリアルに体験でき、壮大な物語を見たような気分になります。
モノクロの水墨画なのに景色が色づいて見えて、本当に上流から水の流れを見ていくかのよう。
川と陸の境目や岩肌に水が跳ねている様子がリアル。
動物や人々の息遣いまでも感じられてきます。
西洋画のような写実性はないのに、没入感がすごい。
そして最後の展開がドラマチックで、起承転結の「転結」のお手本のよう。
水が最後は空に帰っていくなんて、当時の人々は学校で教わっていたんだろうか。
教わっていないのに想像で描いたのだとしたらすごい、でも知識があったら逆にこのラストは描けないかもしれないな、などと考えていました。
川合玉堂「行く春」
桜吹雪舞う川の様子を描いた屏風です。
作品との出会い頭に見えるのは岩肌と川の流れ。
それを見ながら進んでいくと、舟が浮かんでいるのが見えてきます。
つい舟に気を取られてしまい、そういえば全体を見ていないなと思ってふと見上げると、そこには桜の花が。
桜の花と葉っぱはそこだけ油絵の具で描かれているのか、少し盛り上がって立体的に見える。
日本画の平面的な感じに西洋の画材が加わることで生まれる奥行きが、リアリティを感じさせます。
見上げると美しい桜の花が咲いていた。
ちょっと目線を変えると、そこには美しい世界が広がっている。
絵の中だけではなく現実世界にもつながる、心の動く体験でした。
高橋由一「鮭」
キービジュアルやチケットにもなっている、超リアルな鮭。
西洋から新たに学んだ油絵で、従来の日本の技法材料では困難だった本物そっくりの描写が可能になったことへの素直な感動が表されています。由一の興味は、特に質感表現にあったようで、半身が切り取られているのも、ごわごわした皮と脂ののった身との質感の対比を表したかったからに違いありません
https://jubun2023.jp/works
説明文のとおり質感がリアルだなあと思いながら見ていたら、ふと目に入った半身の断面。
鮭の切り身でしかない。
美味しそう。
あまりにシンプルな感想ですがこれに尽きます。
無性に鮭が食べたくなって帰りにスーパーに寄ったら、鮭の切り身が安かったので嬉しくなってしまいました。
生の状態でまじまじと見つめたくなったけど、傷むといけないので我慢。
ホイル焼きにして食べました。すごく美味しかった。
萬鉄五郎「裸体美人」
師の教えに反発し、当時日本に入ってきたばかりのマティスやゴッホの影響を受けて描いたという作品。
作者の反骨心をこれでもかと感じる、かっこいい作品です。
現代的な強い女性を思わせる作品だけど、制作年は1912(明治45)年。
描かれている女性は凛々しい眉の上から目線で、黒々とした鼻の穴が描かれ、わき毛生えっぱなし。
今でさえ「これのどこが美人やねん」と言われそうな作品ではあるけど、当時はどれだけ反発があったんだろうか。
今よりもずっと男尊女卑が当たり前な時代に、上から目線で寝そべるモデルの女性はどんな気持ちでこのポーズをしたんだろうか。
説明文によると作者はかつて優等生だったらしいので、「不良になりやがって・・・」とがっかりされたに違いないだろうなと思います。
けれどその絵がマティスやゴッホの影響を受けた、写実的ではない西洋画表現のはしりとして重要文化財になっていることが面白い。
そして現代にはジェンダー的な切り口も加わってくるのも面白い。
正直、誰が見ても美しいと評価する作品とは思えません。
実際にミュージアムショップでこの作品を使ったグッズを見つけた、私より若そうな女性達が「やだー!」と言っていたくらい。
でも私は好きです。この絵のように強くてかっこいい女性、憧れます。
「重要文化財の秘密」を知ることはできたのか?
展示を総括して、私は重要文化財の秘密を知ることができたのか?
当初の目的を達成することができたのか?
振り返ると、私は今回以下のような目的があって展示を見に行きました。
なぜその作品がすごいとされたのか。
重要文化財の作品はそんなにすごいのか。
美術史や教養を学び、専門家と呼ばれる人たちの視点を学ぶとともに、自分なりに作品を楽しめたら
展示の解説にも書かれていた「評価基準は時代によって変わる」ということ。
確かに、当時は問題作とされた作品も後世になって評価され、今では重要文化財にまでなっている。
とはいえ、大した知識もない素人は、説明文がなければ「それがどう新しいのか、どうして問題作だったのか、どうして後に高く評価されたのか」よく分かりません。
さらに言うと、説明文を読んでも絵のどこが評価されたのかがピンとこなかったりもします。
例えば「西洋画の技法や特徴を取り入れた」ことが評価の理由になっている場合。
江戸時代以前も含めた日本美術史をある程度理解していないと、説明文に書いてある「西洋画の技法や特徴」ってなんなのか、しっかり理解することすら難しいです。
「たぶんここが遠近法なんだよね?」とか「ここが油絵具だよね?」とか微妙な理解で終わってしまうので、音声ガイドがあった方が良かったかもと後から思いました・・・。
重要文化財に選ばれている作品は、日本美術史上重要なポイントである何らかの転換点を象徴する作品が多かったように思います。
作者の考えと時代背景、評価者の考えと時代背景、その両方を知ることでより深く理解できる。
今はまだ専門家の視点は十分に理解できなかったかもしれない。
けど、個人の思いという狭いことから、歴史の流れという広いことまで、もっといろんなことを知りたい!という気持ちになりました。
また、勉強しなければ高尚な美術の世界は楽しめないかというと、決してそんなことはありません。
美術史の知識がなくても純粋に作品を楽しむことはできます。
今の私は知識がない分、誰かがすごいと決めた作品を自分なりに味わうことはできたのではと思います。
「何かよくわからないけどこの作品はすごいんだな」と、専門家が下した評価をそのまま受け入れるだけではもったいない。
ネガティブな評価でもいいから、自分なりの意見を持てると楽しく作品鑑賞ができるのではと思います。
これから美術史について学んでいったとしても、純粋な自分自身の視点で作品を楽しむ心は忘れないようにしたい、などと展示を振り返って思うのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
