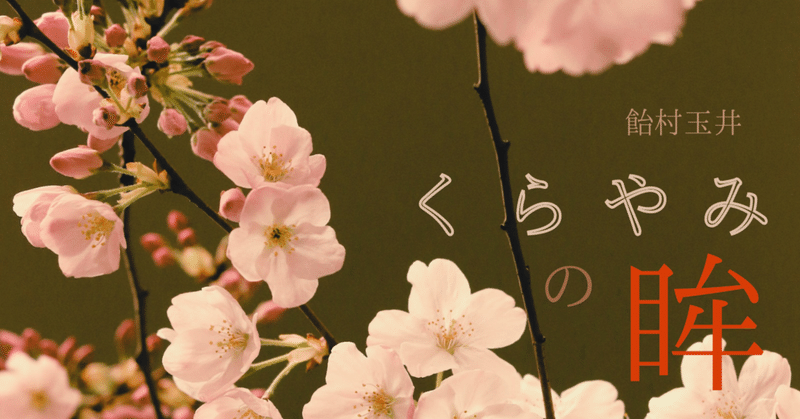
くらやみの眸
あらすじ
古い霊能者の家系である針間一族でも指折りの術師である兄、纏は年の離れた弟・勇次郎が自分と反目した挙句に同じ術師になると言ってきかないことに悩んでいた。そんなある日、彼の元に一通の便りが届く。それは、過疎に悩む集落にて暮らす女性が、職場で起こる怪奇現象について悩んでいるというもので……。
本文
「だから私は嫌いなんだよ、『鰯の頭も信心から』とか、『信じる者は救われる』みたいなおためごかしがさあ。ふざけんなよ、神さん仏さんがガチで救ってくれるっつーなら、私らみたいな稼業のモンなんぞ要らないし、居ないに決まってんだろ。ああ胸糞悪ィ、マスターおかわり頼む。うんと辛いやつ!」
「纏くん、いい加減呑みすぎじゃない? 君、別にそんなに強くないでしょ。そろそろチェイサーに切り替えた方がいいよ、言っとくけど翌朝苦しむのは君だからね」
「うう、マスターまで私をいじめる……この前もたまたま用事があって実家に戻ったら弟も帰ってきててさあ、私を見るなりすげえ顔すんの、もう鬼みてえな顔。そりゃあさ、こんな稼業してんだし他人から憎まれんのも嫌われんのも慣れっこだけどさ、他でもない家族から同じ目に遭うのには一生かかったって慣れねえって! それにしたってあんな蛇蝎の如く嫌がんなくてもいいじゃんねえ」
グイッとグラスの中の溶けかけた氷と混ざってすっかり薄くなったウイスキーを飲み干し、男は塩ゆでした青菜のようにすっかり萎れてしまった。色素が薄く病的に白い肌のせいで、アルコールが回って赤く染まっているのが異様に目立つ。長い銀髪を無造作に括っていて、今日はブカブカの黒いシャツにカーゴパンツというラフな装いだが、仕事の際は喪服のような黒一色のスーツ姿であることは見知っている。小柄でほっそりした体格と少女めいたきれいな顔立ちのせいで見た目の性別は判断しづらいが、一応は男性だ。それも俺と年齢はほぼかわらないときている。学生みたいな容姿に反し、この道二十年近いキャリアの長さを誇る彼は──針間纏。現役最高峰と名高い、歴戦の霊能者である。
俺、三本木高晴がアングラ系の雑誌やゴシップ週刊誌などの低俗読み物をメインの職場とするフリーライターかつホラー小説家という仕事をしていることがきっかけで、彼と細々とした交流を持つようになって何年経つだろうか。オフの日の彼から共に飲みにこうと誘いをかけられるようになったのは割と最近のことで、それまでは俺が商談がてらどこそこの飯屋に連れ出すことの方が多かった。今日は纏がオーナーをしているテナントビルの中にあるパフェバー「pink moon」で夜パフェ会をしようと誘われ、たまたま予定がなかったのもあり応じた次第だ。
この店はまだ俺が売れてない頃に本業の傍ら食い扶持を稼ぐため働いていた元アルバイト先で、その頃から纏は時折フラッと店に立ち寄っていた。当時はまだ俺も駆け出しかつ分野も違っていて針間家の存在など知らなかったし、纏も纏で仕事以外で一般人と関わるのを避けていたから、まだお互いを認知していなかった。たまたま寄稿した実話怪談風ホラー短編がその手の界隈でウケて似たような仕事がちょくちょく舞い込むようになり、ホラーやオカルト専門のライターとなってから纏と知り合ったわけだ。
その纏から時々ネタを提供してもらえるようになり、いくつかの雑誌で連載を持たせてもらえるようになったり、長年の夢だった本を出すことも叶った。まったく纏サマサマである。もっとも本人が俺の書いたものを読んでくれたことは数えるほどだが。今日は特にお互い仕事の話をする予定はなく、まあちょっとした気晴らしのつもりでいた。とはいえ職業柄、会えばなんだかんだと怪談の種になりそうな話題は飛び出てくる。たとえばつい先日、纏が受けた依頼についてとか。
「なんでもさあ、依頼人の母親が熱狂的なカルトの信者で、騙されて変な置物とか経典とか買わされてくるわけよ。まあそれだけなら消費者相談センターか法テラスにでも頼れよって話なんだけど、そのババアがありがたーい教団の教えで猫を飼うようになったそうだ。依頼人は別に猫好きでも猫嫌いでもないが、とはいえ生き物をなんの準備もなく飼育するって大変だろ? 泡食ってとにかく保護してくれそうな施設とか団体に預けようとしたんだけど、まあババアが金切り声上げて反対しやがる。うちで飼うの一点張りでちっとも話を聞かねえ。しかも本人は猫の世話なんか全然しようとしないそうだ。その上ババアときたら、猫が家に来てから原因不明の体調不良が続くんだと。アレルギーを疑って病院で検査しても陰性、しかも家を離れても体調は良くならない。母親は日に日に窶れていって、やっぱり弱ってるように見える。こりゃ猫が原因だ……ってんで、うちへ依頼人、まあそのババアの娘が来たわけ」
そこで最初の盛大な愚痴に繋がるわけだ。どんな依頼も断らない主義の纏は二つ返事でもちろん引き受け、とりあえず様子を見てみたんだろう。結果はクロ、つまり猫そのものではなく、猫にまとわりついていた邪念が依頼人親子を苦しめる要因だった。猫自体は無害でも、大元の教団が動物を介して妙な呪いを振りまき、猫を飼い始めた信者を追い詰めてより依存させようと企んだ──裏事情としてはこんなところか。
問題は、なぜそんな迂遠なやり方を教団は選んだのか、そしてこの手口で教団側の胡散臭さに気づいて正気に返った信者はいなかったのか、という二点の疑問である。纏が言うには、猫がもたらす運気の乱れはより功徳を積む……つまり教団への献金で解決することになっており、逆に猫をいじめるなど危害を加えると更に悪化するんだそうだ。猫には各信者の信心を判断する力があり、もし猫が来てからおかしなことが続くのであれば、猫が教団に対する忠誠を認めてない証なのだという。
むろんこれらは全て教団が更なる献金を得ようと仕掛けたマッチポンプにすぎない。だが、このカラカリに気づかないような馬鹿がそもそも新興宗教に引っかかるわけで、事前に動物虐待を禁じているため表に問題が漏れにくいことから特に世間では思うほど騒がれていないらしい。なかなか巧妙だ。それに生き物を介することで信者をその土地に留めることもできる。猫は家に着くという言葉の通り、引越しなど飼育環境の変化を嫌がるからだ。ストレスで猫が弱れば、どんな報いを受けるか分からない。愛玩動物に対する愛着や罪悪感、元々信者が抱えている恐怖や不安につけ込むのがとことん上手い。
「で、これネタになる? ちなみに依頼は解決したぞ、知人の紹介で特別に保護猫ボランティアしてるやつの家で飼ってもらえることになったのと、依頼人親子の父親の都合で北海道だかの僻地に一家揃って移住することになったから、もうババアは強制的に教団との縁が切れるそうだ。有名どころと違い、土着系のカルトは信者に引越しされるのが一番痛いからな」
「うーん……どうしても特徴でどこのカルトが関わってるか検索されれば一発ですぐ分かっちゃうのと、今回オバケの出てこないヒトコワ系だから手持ちの連載に載せられるかというと微妙かも。すまないな、せっかく提供してくれたのに」
「そっかー、いいネタになるかもと思ったんだけどなあ。まあライターの仕事もそんな甘いもんじゃねえよな。悪いな、力になれなくて。そういえば、あとで調べてみたら猫自体は本物だったぞ。基本は無害だが、招かれた家に不穏があると途端に牙を剥くタイプの式神だ。あくまで飼い主は教団だから、招かれた先である依頼人の家をクロ──襲っていいと判断したらしいな。だから普通の保護猫ボランティアじゃなくて私の名前が通じる相手にお願いして引き取ってもらったんだけど。契約は破棄させたから、もう力を振るうことはないだろう」
「へえ、悪い運気を呼び込む力があったのか。猫は九つの命を持つというし、猫が化けて悪さする怪談には事欠かないからな、なるほど何か特殊な力を備えていてもおかしくないだろう。けど、想像するに依頼人の家庭だけじゃなくて複数、もしかしたらもっとたくさんの信者に猫を預けていそうだが……そんなに都合よく、本物の力を持つ猫とやらが見つかるか?」
「そのカルトとやらの手口は分からんが、作ろうと思えばその手の式神は作れるぞ。色々と仕掛けはいるっていうか、手間もかかるし、おいそれと簡単に試せるもんじゃないが、既にある程度献金を蓄えているなら話は別だ。野良猫を攫って繁殖させたか、もしくはブリーダーを引き込んで大量繁殖させたんだろうな」
「ひでえ、生き物の命をなんだと思ってんだよそいつら。信者共が報復やしっぺ返しを恐れて猫に何かすることはないだろうからまだいいけど。依頼人親子がせめて今は穏やかに暮らせてるといいな」
「この前仕事用の携帯にメールは来てたぞ。ようやく母親も落ち着いてきて、前までの生活に戻りつつあるそうだ。それにしてもあの子、歳の割にずいぶんしっかりしてたな、まだ小学生くらいなのに。まったく今どきのガキってのは侮れねえよな」
「うわ、小学生の女の子が……トラウマにならないといいな。その歳で母親がおかしくなるなんて、そうそう経験したくないだろうに」
年端もいかぬ小学生の娘がよくもまあ纏を見つけて依頼に漕ぎつけられたものだ。それだけ必死だったのだろう、大好きなお母さんを変えてしまった宗教と同じくらい胡散臭い、霊能者なんて存在に頼るほどに。きっと怖かったはずだ、追い詰められていたはずだ。もし自分の選んだ行いが更に事態を悪化させるようなものだったら、と不安や心配に押し潰されそうになったことだってあるだろう。しかし子供はインチキではない、本物をきちんと探り当てた。そして纏は誠実に仕事をした。
どうか今は、心穏やかに日々を過ごせていることを願うばかりだ。
「しかし、そんな後味悪い仕事をこなしてきたんじゃ愚痴りたくもなるよ。聞いてるだけの俺でさえ胸糞悪いと思うもん。別に何を信じようが本人の勝手っちゃそれまでだけどさ、せめてガキを巻き込むなよと言いたいよな」
「めんどくせえのは、そのカルトとやらが悩める母親──家庭を狙い撃ちしてるってことなんだよな。その家も、娘が学校でうまくやっていけてるかとか、教育に関して母親が悩んでたところに近所のお節介ババアがつけ込んで教団に引き入れたのが全てのきっかけだし。依頼人の子供も、自分が親を安心させられなかったのが悪いんじゃないかってすっかり落ち込んでてさ、いやー正味依頼そのものよりフォローに時間食ったわ」
「うわしんどそう……こういう依頼、なんかこれから増えそうだよなあ。SNSなんか見てると育児アカやママアカの愚痴だの悪口だのしょっちゅうバズったり炎上してるし。なるほどそういう団体も出てくるわけだ」
纏がいつになくしょげる理由にも頷ける。おそらく年の離れた弟を無意識に重ねてしまったのだろう。基本的に依頼人に対して素っ気なく、愛想も良くないやつだが、ガキにはなんだかんだ甘いところがある。わざわざアフターフォローまでしてやったあたり、依頼してきた子供のことがよほど気がかりだったのだろう。なおこれがいい年の大人であれば、そこまで首を突っ込んだりはしない。それくらいは自力でどうにかしろと突き放すタイプだ。
それにしても話を聞くだに怪しいというか、いかにも悪徳カルト団体であるようにしか思えないが、警察は動いているのだろうか。普通なら依頼人もまず先に警察を頼ったはずだろう。しかし相手にされず、他に誰に相談すればいいか分からなくなり、困ってついに纏にまで行き着いた。メディアに顔出ししていない、ネットの有名人でもない、大規模に宣伝しているわけでもない、そんな纏をどうやってその子供は知ったのか。話の中にほとんど父親が出てこないのも気になる。
「……やっぱりこの件、ちょっと詳しく調べてみようと思う。記事にできるかは分からないけど」
「やめておいた方がいいんじゃないか? 案件自体は解決してるし、ああいう団体は関わるとろくなことがない。お前の職業がどういうもんなのかは分かっちゃいるが、その上で忠告しとく。一般人がおいそれと首を突っ込んでいいモンじゃねえぞ、こいつは」
「そうか。お前にそこまで言われるんじゃ、やっぱダメか。色々と疑問点もあるし、放置するのもなあ、と思ったんだけど……友達の忠告を無碍にして危険に巻き込まれて迷惑かけんのも心苦しいし」
「ああ。この件は深追いはすんな。私もこれ以上は関わる気はない。それより最近は呪詛関連の依頼が増えてきてよお、まったく冗談じゃねえよ。誰だよ徒人にも使用可能な呪いなんか撒いてるやつ、そのせいでひっきりなしに事務所に予約の電話かかってきてめんどくせえわ」
丑の刻参りなどが有名だが、実際に呪いを実行しようとすると一定以上の素養を要求されるものが多い。本人に霊的なものとの親和性がある──霊力がある場合において、呪詛なり儀式なりは成立する。どんなに体裁を取り繕ったところで、実行者に何も力がなければ、それはただ上っ面を真似ただけにすぎない。だが、素人でも簡単にできる呪いってやつが昨今のホラーブームやオカルト人気に推されて流行りつつある。
種類は様々。嫌いな人間の本名を特定の掲示板スレッドに具体的な呪いの内容を添えて書き込むとか、数日かけて消しゴムに呪いたい相手の名前を彫って完成したら火をつけて燃やすとか。大概元ネタや源流はあり、元を辿れば名作ホラーに出てきたおまじないのアレンジだったり、現実にある儀式を簡略化させたものだったりする。その手の胡散臭い儀式もどきは昭和の時代にもあったが、近頃広まっているのはお遊びではない「本物」である。被害報告も既にいくつも上がっていた。
纏はそうした流れを一種の宣伝とみている。どこぞの呪詛専門の術師が、あくまで「試供品」として比較的手軽で効果も酷くなりにくい本物の呪いをばらまいているのだ。迂闊に試して実際に効けば、もちろん本命を狙うだろう。無論、靴紐が勝手に解けるとかタンスの角に小指をぶつけるレベルでは済まない。本気の死を願うに決まっている。呪いを商う者というのは、人間が持つ情念や仄暗い欲望を見抜いて近寄ってくる。サンプルとして配った呪いをわざわざ試すような輩は、彼ら悪しき術師にとっては葱を背負った鴨に他ならない。
纏の元にかかってくる予約の電話は、そうした呪い被害者からの霊障相談だけではない。サンプルをうっかり実行してしまった人間も含まれる。元恋人、嫌いな上司、ムカつく客や取引先、気に食わない同僚や部下、いけすかない友達……そんな人間関係のトラブルを抱えた、あるいは現在進行形で抱えている相手に、出来心で些細な悪意をぶつけようと企む者はいる。愚かで悪質だが、人間というのは大概そんなものだ。そして実行した本人は「ほんのちょっとだけ苦しめたい」だけなのだ。
結果としてより巨大で邪悪な悪意につけ込まれ、破滅する。「ひとを呪わば穴ふたつ」というように、生半可な気持ちで呪いなどに手を出した人間が無傷で済むわけがない。必ずしっぺ返しをくらう。そして困って行き着く先が纏のような存在なのだ。前述のような、愛する母を助けたい一心で連絡してくる者もいる。一方で何も考えず無知なまま火遊びした代償に苦しめられて助けを求める人間も。どちらも纏にとっては等しく救済対象であり、見捨てるという選択肢はない。
「呪い被害の方は啓蒙にもなるし、新しい連載としてスタートしてもよさそうだ。とりあえず持ち帰って編集長と相談してみようと思うんだけど、具体的に話を聞けそうな人に思い当たりってあるか?」
「あー、その呪い代行業者から仕事をいくつか受けてた人間がいるな。本人曰く足を洗って闇バイトで生計立ててるっていうから、まあ針間纏の仲介って言っときゃ簡単に取材させてくれるだろ。ホイこれ連絡先」
「さてはお前、初めからやり返すつもりで連絡先控えてたな。名前とか住所買い替えてたりしないといいけど」
「ふふん、なんのことだか。足を洗った先が闇バイトな時点で性根の汚さは変わんねえよ。この先きっちり反省して法の報いを受けるってんなら話は別だが」
言いつつパフェグラスにロングスプーンをつっこみ、クリームと苺を掬って口に運ぶ纏。彼は特別に甘党ではないらしいが、酒に弱く味の濃い食べ物も比較的苦手にしていて、好んで食べられるものが限られている。要するに偏食だ。幼少期、好き嫌いが激しかった纏が抵抗なく食べられた数少ないメニューがパフェで、その名残で今も好物なのだという。お気に入りは季節限定メロンパフェだが、今日は品切れということで仕方なく選んだのは新作の塩キャラメルバニラいちごパフェという名前からして死ぬほど甘ったるそうな逸品である。
店主の内海さんが今回の新作どうだった、とわくわくした顔で味の感想を訊ね、纏はいつになく満面の笑みでクリームのもったり感が良かったとかバニラの風味がたまらんだとか細々と述べている。あいつは術師なんぞやるよりグルメ系インフルエンサーとかブログでもやったらいいんじゃないかと思わなくもない。このビルには他にもキャバクラやらホストクラブやら色んなテナントが入っているが、足繁く通っているのはこの店くらいなので、よっぽど気に入ってはいるのだろう。
パフェの最後のひと口をじっくり味わってからようやく食べ終え、名残惜しそうにごちそうさまを言ってから残りの酒も飲み終えた纏は席を立った。そろそろお開きにしないと明日の仕事に差し支えてしまう。お互いなかなか休みの取れない身だ、あまり羽目を外すわけにはいかない。今日のようなささやかな催しも彼なりの、休暇の代わりの息抜きである。まったく、依頼を吟味すれば少しは余裕のある生活も送れるだろうに。
会計をそれぞれ済ませ(割り勘にすると頼んだ酒の量的に纏が損をしてしまう)、地下階の事務所兼自宅へ戻っていく彼とは店先で別れ、俺は帰路に着いた。似たような作りのテナントビルがひしめき、ネオンサインの洪水に溢れる繁華街は深夜を過ぎてもまだ賑わしい。映画館横の公園では若者が乱癡気騒ぎを起こし、警官がわざわざ駆けつける事態になっている。通りは若い男女がそれぞれ腕を組んで歩いていたり、風俗店のチラシが入ったポケットティッシュを配っているバイトくんが突っ立っていたり。俺が若い頃とはまた種類の違う治安の悪さに、この街も変わってないようで変わりつつあるんだなと思う。
自宅までは距離があるのでタクシーを捕まえ、マンションに着いた時にはもう深夜というより未明に近かった。この時間ではシャワーを浴びるのさえ躊躇われ、疲労と酔いによる眠気もピークに差し掛かっているのもあり、ネクタイとスラックスだけどうにか脱いでベッドに潜り込む。しこたま酒を飲んできてよかった、と心底思った。眠れない夜は厭な夢を見る。だから。酒でも飲んで、全て忘れて寝入ってしまえ。何も見ないように。
それでもいつか眠りは覚める。目覚めると七時半で、帰宅してからまだ二、三時間しか経過していなかった。
◆◆◆
懇意にしている編集長から「気になるファンレターを見つけたので、うちに確認しに来てほしい」というメッセージをもらったのは、纏と会ってから数日後のことだった。俺は複数の雑誌でそれぞれシリーズ連載を持たせてもらっており、実話怪談を紹介する系のものから都市伝説や地方の怪異譚について深堀りした記事など、雑誌ごとにまるで違う内容の連載を担当している。
今回連絡をくれたのは、そのうちの一つで「忌・怖」というホラー専門の季刊誌の編集長だった。四半期に一回、有名どころのホラー作家による書き下ろしで短編小説や読み切り漫画、ちょっとしたコラムやエッセイ等を掲載しており、中身の充実さと雑誌本体の鈍器のごとき分厚さから界隈でもそれなりの人気がある。何年か前までは月刊だったが部数低下により季刊に移行したとはいえ、中身の充実っぷりは以前変わらないままだ。
俺が本を出せるくらいの人気を獲得するきっかけになつたのもこの雑誌で、季刊誌とはいえ本が売れないこの時代に部数を減らしつつも長く発行し続けているのだから、さすがは業界の雄というところだろう。編集長はホラー雑誌を担当しているとは思えないほど温厚で優しい人物で、人当たりも良く朗らかなおじさんである。とはいえ手腕は確かなもので、売上が低迷していた「忌・怖」を復活させたのもこの人だ。最初に出した本も担当編集を買って出てくれた恩もあり、何かと彼には頭が上がらない。
呼び出しを受け、古ぼけた雑居ビルの二階にある小さな編集部を訪ねると、校了日を過ぎているからか割と空気は穏やかだった。人もまばらで、いつもは雑然としている室内も多少は片付いている。とはいえ各デスクを見やれば書類が積み重なっているのだから、万年人手不足がいかに現場に負担がかかっているかをうかがわせる。彼はオフィスの窓辺にあるデスクでお気に入りの漫画本を顔面に乗っけたまま、うたた寝しているようだった。
「沢渡さん。俺です、三本木です。あのう、大丈夫ですか、起きてますか」
「んえぇ……三本木くん? うわごめん、もうアポの時間になってんじゃん、昼寝してて気づかなかった、ごめんよ。お詫びにお昼でも奢ろうか」
「すみません、もう済ませてきてしまいまして」
「じゃあお茶でも。近くに新しいカフェができてね、事務の子が言うにはティラミスがおいしいんだって」
「そういえば、来るときに見慣れない店があるなあとは思いましたが、あれですか。そろそろ小腹の空く時間帯ですもんね」
「うんうん。君も疲れてるでしょ? 疲れたときには甘いものがいいって聞くし、一緒にどう? 奥さんからは少しは節制しなさいって怒られるんだけど、好物ってそんな簡単にやめられるものでもないもんねえ」
ニコニコと丸っこい輪郭の顔に笑みを浮かべ、白髪混じりの髪を撫でつけてポロシャツにチノパン姿の小太りな男は仕事用らしい大きなショルダーバッグを肩にかけて席を立つ。俺達の会話を盗み聞きしていた社員が、お戻りは何時頃になりますかと尋ね、沢渡さんは夕方には帰社するからと答えて俺を先導した。
向かった先は社屋があるビルのお向かいにある小さな喫茶店だ。今どきのオシャレカフェというより、昔ながらの純喫茶をイメージした店構えは、昨今のレトロ喫茶ブームを受けてのことらしい。落ち着いた雰囲気の店内にはたくさんの古本もディスプレイされ、あえて窓を小さく作って陽射しを遮る代わりに、個性的なデザインのランプを各テーブルに飾って光量を確保している。
ガラガラではないが、かといい満席でもなく、程よく賑わう店の奥にある二人掛けのソファ席へ通され、とりあえずアイスコーヒーを二つ注文する。沢渡さんがいうにはティラミスがおいしいらしいが、おすすめメニューには昔ながらの固めプリンなるものがあったので、飲み物が運ばれてきたついでに追加でそれを頼むことにした。沢渡さんの方はメニューと睨めっこしてあれこれ悩んだ挙句、結局ティラミスに決めていた。
「あえて外に連れ出したってことは、他の編集部員に聞かれたくない内容だったってことですよね。一体何が問題だったんですか?」
「いや、特に何かトラブルが発生したなんてことはないよ。三本木くんが寄稿してくれた記事はとても評判が良くってね、ほとんどの読者さんには喜んでもらえたんだ。また読みたい、続きが気になるって好意的なコメントやファンレターが大半だったよ。あとでまとめて送るね」
「ありがとうございます。まあ祓い屋シリーズは比較的好評のようですし、いずれ書き下ろしも加えて一冊にまとめられたらなあとは思いますよ」
「いいね! 今度みんなにも意見を募ってみるよ。うちで出せるといいんだけどなあ、もしうちがダメでもどこかの出版社さんで声がかかったら遠慮なんてしなくていいんだからね」
「いやいやそんな。俺も沢渡さんには長いことお世話になってるし、恩を仇で返す真似なんて! それより、記事の内容が物議を醸したとかではないなら、一体なぜ今日呼び出したんですか?」
「……ええっと、これ他言無用でお願いね。詳しくは君の目で確認してくれるかな」
座席の横に置いていたカバンをガサゴソ漁り、ややあって薄っぺらいクリアファイルを彼は差し出した。両面にアニメキャラのイラストが全面にプリントされているが、これは別に当該アニメが好きで使っているのではなく、中に挟めているものを覗き見されにくくするためのようだ。よほど周りの目が気になるのだろう。ファイルを開くと、開封済みの封筒がひとつ収まっている。
封筒の表面にはなめらかな筆致で宛名と住所、郵便番号が書かれ、裏返すと送り主の氏名と住所がやはり添えられている。おそるおそる中身を出すと、それは手書きの文字が端から端までびっしり刻まれた数枚の便箋だった。パッと見た感じ、ずいぶんな長文であるということ以外は今のところ、さほど不気味だとか奇妙だとは思えない。本文も時候の挨拶から始まり、冒頭はつらつらと記事への感想が書かれている。しかし読み進めると次第に様子がおかしくなり始めた。
以下は問題の文章を一部抜粋したもの(原文ママ)である。
(前略)
──半年ほど前から、わたしは職場の人間関係に悩んでおりました。うちは零細ですので従業員もわたし含めて数えるほどしかいません。その中でも何十年と長く勤めている、いわゆる「御局様」というのに嫌われてしまいますと、ろくに業務が立ち行かなくなるわけです。わたし自身は御局様に睨まれているわけではありませんが、若い新人さんが「なぜ、このご時世にもなって女性社員がお茶くみやオフィスの清掃など雑用を押しつけられているのか」と不満を漏らしてしまいました。御局様は大変怒り狂い、任された仕事に文句を言うような使えない人間に重要な仕事は与えられないと言い、実際に新人さんはほどなくして辞めさせられてしまいました。
事件が起きたのは、このすぐあとです。毎日、一番遅くまで残った社員が全室の戸締りと機械警備をかけることになっているのですが、翌朝出社してみると全て外れているのです。機械警備がアンロックされたら必ず警備会社に通報がいくはずなのにそれもない。他にも細々とした異変は起こりました。お客様用の玉露の茶葉が全て湿気ってだめになっていたり、大事な書類がファイルから抜き取られてシュレッダーにかけられていたり、設定したはずのパスワードが書き換えられてパソコンが開けなくなったり。このままでは業務が滞るばかりだと、誰が嫌がらせをしているのか社内で会議が開かれました。お察しのことと思いますが、つまり吊し上げでした。
誓って申し上げますが、わたしは何もしておりません。動機がないからです。誰が日々働く職場で子供じみたイタズラなどしましょうか。しかし御局様は、わたしを疑いました。理由は明白でした。辞めていった新人さんの次に若い従業員が、他ならぬわたしだったからです。ただそれだけのことで、嫌がらせの犯人に仕立てられたわけです。狂っている、と思われるのも致し方ありません。わたしとて外野の人間なら同じ感想を抱くでしょう。しかし田舎の家族経営の小さな会社なんてものでは、そのような因習さえまかり通るのです。たまたまわたしが「よそさん」……昭和の頃に移住してきた家の人間であったことも、御局様の疑念に拍車をかけたのだと思います。
そうそう、会社構成について触れていませんでしたね。うちは八十すぎのおじいちゃんが会長(創業者)で、その息子が社長として跡を継いでいます。事務を一手に引き受けるのが社長の妻である御局様です。他数名は社長と会長が個人的に仲良くしている友人で、俗に言うコネ採用です。基本は現場作業なので社内にほとんどいません。わたしは社長の息子、会長の孫に当たる人物の「嫁候補」として雇われました。たまたま彼と学生時代同じクラスで親交があり、気に入られて他の社員と同じくコネ採用された形です。
だから、きっと元々心証は良くなかったかもしれません。御局様からしたら、かわいい息子を知らない女に盗られるようで面白くなかったのでしょう。わたし自身は給料さえもらえればなんでもよかったので、彼と真剣に交際する気はなかったのですが。ちなみに新人さんは普通に彼の遊び相手になる予定だったのだと思います。仮にわたしが彼らの目論見通りに妊娠にまでいきつけば、性欲を発散する相手がいなくなりますから。
こんな職場でも辞めてしまっては路頭に迷ってしまいます。地方で仕事はなかなか見つかりませんし、わたしの「悪評」は地元に知れ渡ってしまっていますから、辞めたところで雇ってくれる会社なんかありません。窮屈な地元を出て都会に出るのはおそろしい。地縁も何も頼れない世界など想像したことさえないのに、どうしてやっていけるでしょうか。それに年老いた両親を田舎に置き去りにして自分だけ逃げるだなんて、あまりにも親不孝者です。ここで生きていくしかないのです。御局様からどんな嫌味を飛ばされ、嫌がらせをされたとしても。
ですが、このまま黙ってやられ続けるなんて性にあわない。せめて少しくらいは仕返しがしたく思います。もっといえば、わたしはわたしの潔白を証明してやりたいのです。誓って嫌がらせなんかしていないと。真犯人は他にいるはずだと。何より真実が明らかにならなければ、心を病んで自殺してしまった新人さんがあまりにも浮かばれないではありませんか。
新人さんは、御局様のパワハラを理由にその後重い心の病にかかり、間もなくして自ら命を絶ってしまったと聞きます。後から両親を経由して知ったことです。我々は当然ですが葬儀に列席させてもらえず、亡くなったことも教えられていませんでした。ご遺族が娘を死に追いやったも同然のわたしたちを許さないのも当たり前です。ですから、彼女が何も悪くなかったことを証明するためにも、わたしは「彼ら」の罪を暴かなければなりません……。
(中略)
──この手紙を読んだ方へ。お願いします、どうかわたしと彼女を助けてください。このまま全てをなかったことにはしたくありません。これは弔い合戦なのです。だからどうかあの人に取り次いでください。わたしは知っています。わたしは気づいています。「祓い屋A」は実在する人間であることを。
「……なるほど。確かに異様ですね、これ」
「そうでしょ? もう困っちゃってさ。単なる怪文書にしては送り主の個人情報を開示しすぎてるし、悪いかなあとは思ったんだけど一応、送り主の名前で検索したら出てきちゃったんだよねえ、これ」
流麗だった筆跡はだんだん荒れていき、うまく筆圧がコントロールできないのか震えが目立ち、ところどころインクも滲んだり掠れたりしている。狂気じみていく文面に慄きつつどうにかコメントを絞り出すと、沢渡さんは再びカバンの中をゴソゴソし始め、クリップで留めたコピー用紙の束を差し出した。パソコン画面のスクリーンショットをそのまま印刷したものと思しきそれは、送り主の名前で検索した結果とそのリンク先をまとめたものだ。
本人名義のSNSアカウント──主にプロフィールや直近の投稿内容、母校のホームページに記載されている過去の受賞記録、本人住所の航空写真及び地名の検索結果、そしてSNSのつぶやきを元に特定された勤め先、つまりは例の御局様がいる会社について。これだけのデータが一気に出てくることに、つくづく情報化社会の恐ろしさとやらを実感せざるを得ない。調査資料に目を通せば、手紙に書かれていることは概ね事実だとわかる。語られていた会社の内情についても、ある程度はフェイクも混ぜられているにせよ、おそらく本当なのだろう。
さすがにこれだけの長い文章をわざわざ手書きで綴り、編集部まで送りつけるなんて手の込んだイタズラを大の大人がするとは想像しづらい。つまり送った相手は本気で助けを求めている。文面にある祓い屋Aというのは俺が連載するシリーズに登場するメインキャラクターのことで、モデルになったのはもちろん纏だ。口調外見性格などは全てオリジナルで本人とは似ても似つかないものに設定してあるため、おそらく記事だけ読んでいても──彼の存在が世間にほとんど知られていない以上、表面的に調べただけでは針間纏という人間には辿り着かないだろう。
だから送り主は俺宛に手紙を書いた。祓い屋シリーズの主人公にモデルがいることはわかっても、そこから直接纏へ依頼を出すことは難しかったからだ。彼は信条として依頼を決して断らないが、そもそもの話、針間纏に直接仕事を頼める人間というのはそんなに多くないのである。上記の通り、こちらの世界に詳しくない一般人が簡単にアクセスできるところに纏や針間一族の情報はないからだ。もちろんこの仕事を通じて、俺のようなオカルト専門のライター連中は纏と繋がりを有していたりはするが。
「弱ったなあ。こういうケースって何気に初めてで……どうしましょう。一応、繋いでやった方がいいんですかね。でも仮に送り主さんがこの件を吹聴して『忌・怖』経由で纏に依頼できると噂が広まったりしたらあいつの迷惑になるし、断った方が無難かなあ」
「そうした方がいいと僕も思うんだけど、文面を見てると切迫性があるような気がして、放置していいものやら悩んじゃって。これ、全てコピーは取ってあるから、良かったら三本木君にあげるよ」
「いいんですか? すみません、ではお預かりします。念のためあいつに見せて判断を仰いでみますね」
「ありがとう〜! 本当に助かるよ。僕自身は取材で何度か電話越しにお話させてもらったことがある程度で、気軽に会いに行けるほどの関係じゃないから、君が引き受けてくれて本当に助かったよ。祓い屋シリーズ、単行本化に向けて色々と企画してみるね!」
「いやあ、こちらこそ助かります。なんだか俺の方こそお世話になりっぱなしで……そろそろお暇しますね。沢渡さんもくれぐれも体調には気をつけてください。甘いものの摂りすぎは禁物ですよ」
「もう、奥さんとおんなじことを言うなあ君は。じゃあね、帰り気をつけて」
奢るというのでここは遠慮なく甘え、退店してすぐ纏宛にメッセージを送る。電話連絡の方が手っ取り早いとはいえ夕刻に差しかかりつつある今は、なるべく電話はかけたくない。俗に逢魔が時と呼ばれるこの時間帯、通話という「点と点を線で繋ぐ」行為は、良くない何かを呼び寄せてしまう。別にメッセージならその危険性がゼロになるというわけではないが、電話よりはマシだ。
すぐに既読がつき、仕事が終わり次第すぐに戻るとの返信が届いた。夕飯時には間に合うとのことだったので、適当にフードデリバリーの予約を入れ、事務所で纏の帰宅を待つことにした。距離的には徒歩移動してもいいが、できればあまり外を長時間うろつきたくない。ほぼワンメーターなのを謝りつつタクシーに乗り込み、いつものビルに到着する。繁華街のど真ん中にあるため、建物に面した通りはこれからが賑わいだす時間だ。
ビルの一階部分はエントランスと管理人室、二階から上は雑多に個人経営のクリニックやバー、キャバクラ、ホストクラブ、居酒屋などが入っている。最上階のみ空き室になっていて、オーナー曰くテナントを新規に募集する予定はないそうだ。周囲に高い建物が密集するせいで最上階でも大して見晴らしは良くないし日当たりも微妙と、単に条件が悪いのもあるが、大掛かりな儀式をするのに広々としたワンフロアがあると何かと都合がいいらしい。
元々はテナント向けの駐輪場だった地下を改築して事務所兼自宅に作り替えたのが纏の住まいである。湿気が酷く空調を常にかけっぱなしにしないと部屋中が黴だらけになるほどで、特に梅雨時のじめっとした空気はいただけない。その代わり年中室温が一定で陽の光が一切入ってこないのが住人的には「最高」なんだとか。吸血鬼か何かかよと思わなくもない。
室内はやはり荒れていた。デスクに大量の書類や本が積み上がり、革張りの高そうなソファにはボロっちい毛布が畳まれもせず放置され、テーブルの上も中身が入ったままのマグカップや吸殻が山になった灰皿が置きっぱなしという有様だ。生ゴミは一応袋詰めされており、衣類が脱ぎ散らかされてないだけマシかもしれない。ここは名目上「事務所兼自宅」なのだが、実際に事務所として使用されていないことは明白だった。当たり前だ、こんな汚い部屋に客を通せるわけがない。
家主が帰ってくる前に片付けくらいはしておくか、と掃除用ロッカーから勝手に道具を拝借して埃の溜まった床を掃き清め、灰皿とコップも中身を処分して水洗いする。食器用洗剤とスポンジなんて気の利いたものはこの家にはない。掃除用ロッカーと清掃用具に関してはビルの備品で纏が買ってきたものでもない。もちろんマグカップ以外の食器やコンロやレンジや調理道具もなく、かろうじてあるのは冷蔵庫くらいだが、なんと酒と水しか入っていない。なんなら流し台さえ使われた形跡がないときている。
そうこうするうち、ようやくこの惨状を作った本人が戻ってきた。この前顔を合わせた時は私服だったが、今日はいつもの黒スーツである。ネクタイまで黒なのは、しょっちゅう急に弔問の予定が入るせいでいちいち着替えるのが面倒になったかららしい。そういう理由で彼は黒以外のスーツを一着も持っていない。おそらくだが弟に嫌われるのもこういうだらしない性格が原因だと思っている。
「おかえり。お前なあ、少しは部屋どうにかしろよ。ていうか生活感無さすぎなんだけど。毎日どうやって生きてんの? メシは?」
「来るなり説教かよ。別に業者に頼んで届けてもらえばいいし、普段は外で食ってくるし、どうせ寝に帰るだけの家だし……で、何か用があったんじゃないのか」
「やべ、忘れるとこだった。そうそう、その件で連絡したんだよ。説明する前に持ってきた資料があるから、先にそれ読んで」
「おー。わかった。……なにこれ? 手紙の写しか?」
渡した書類一式にさらっと目を通した纏は形のいい眉をピクリと跳ね上げた。やはり何か引っかかる点があったのだろうか。
「……祓い屋Aって私のことだろ。なんでこいつは直接こちらへ連絡してこない? 祓い屋Aが実在の人物をモデルにしたことが理解できるなら、モデルとなった人間を探すはずだ。そしたらいずれは私に行き着くだろ、なのにこいつはなぜ他でもない三本木宛てに手紙を書いたんだ? 狙いは本当に私か?」
「盲点だった。針間纏の情報は確かに少し調べた程度では分からないが、同業者が全員『そう』であるわけじゃない。術師が構築する人脈や横の繋がりを辿ればどこかで『針間纏』に行き当たる。わざわざ俺に対して手紙を宛てる必要はない……」
「つまりこいつは私ではなく三本木に用がある可能性が出てきたな。というか、どちらもか。心霊オカルト関係ない現実的な視点から三本木の意見が聞きたいのと、もし本当にこいつが想像する通りの事象が発生しているならその道のプロに対処してほしい……ってところか? 悪意はあんまり感じないんだよな、切羽詰まった様子なのは伝わってくるけど」
会話がひと段落したあたりで、予約していたフードデリバリーの配達員が商品を届けにきたので受け取る。頼んだのはそれぞれ月見うどん(大盛り)と、たぬきそばセット(お新香つき)である。蕎麦派が俺で纏はうどん派だ。メシはあったかいうちに食おうぜということになり、議論は一時中断して先に食事を済ませる。味は悪くないがリピートするには微妙だなとか思っていると、先に食べ終えた纏は再び資料とにらめっこしていた。慌てて平らげ、ゴミをまとめてから話を再開する。
「他にも気になることがあるのか?」
「……受けようか迷うラインだなあ、と思ってさ」
「珍しいな。依頼は必ず引き受けるのがモットーなんじゃなかったのか?」
「それはそうだけど、依頼じゃねえじゃん。まだこの段階じゃ。正直、依頼の予約が結構先まで埋まってて余裕がないってのもあるんだけどさ、弟が……」
「あー……勇次郎くん? 彼、確か今年高校一年生なんだっけ? 俺まだ顔合わせたことないんだよな、勇次郎くんてこっちの事情とかなんも知らないんだろ? さすがに会いに行きにくいよなあ」
「その件なんだけど、バレた。全部。針間の家業とか色々諸々。まああいつが悪いんだけど」
「は? どういうこと? 確かご両親にお願いして死ぬまで隠し通すつもりじゃなかったのかよ」
「あー……その件はあとで話す。そんで勇次郎のやつ、何をトチ狂ったのか、この仕事始めるつもりでいるんだと。結からの又聞きだけど」
実家を離れてからだいぶ経つ纏には、年の離れた弟がいる。名前は針間勇次郎、現在高校生だ。あんまり現代の子供っぽくない厳つい字面の名前は纏と、母親である結さんが話し合って付けたものだとか。針間は血族の人間に共通の部首を持つ漢字を名前に入れるので、勇次郎くんは最初から術師のルートから外すつもりで名付けたことになる。そして実際に彼は普通の人間として育てられた。針間家の人間や纏のように訓練や修行を積むことはなく、他の子供と同じようにして。
つまり彼は生まれてからずっと実家の稼業が何かも知らずに生きていたことになる。もちろん理由はある。他ならぬ纏が、跡継ぎではない次男に術師の仕事をさせる必要はないから修練させなくてもいい、と当代当主である父親とその妻である母親に申し立てたからだ。実際、勇次郎くんは人外じみた強さを持つ結・纏親子と比較すると、素養という意味ではやや劣る。視る力はともかく祓いにかけてはパワー不足、というのが纏の評価だ。
どんなに努力を重ねたところで人並みか人並みよりやや強い程度なのであれば、何かと危険も多く、加えて履歴書に書けない仕事である祓い屋などにならなくてもいい──という跡継ぎである長男の意向に添う形で針間夫妻は遅くに授かったもう一人の息子を一般人として養育することにした。彼ら両親も思うところはあったのだろう、特に父親である紬さんは勇次郎くんと同様に術師の素養に恵まれず、結さんという伴侶を得るまで何かと気苦労が多かった立場だ。
しかし家族ぐるみで隠してきた秘密は、とうとう本人にバレた。纏が言わないからどんな経緯があって明らかになったかは俺の知るところではない。だが勇次郎くんは纏と同じ術師になるつもりだという。なんとなく彼がそう決意するに至った原因は察せられるが、纏本人はおそらく気づかないだろう。そういう悪い意味での鈍感さもこの男が弟に嫌われている理由の一つではあるのだが。
「始めるつもりってことは、まだ開業はしてないんだな。そりゃそうか、依頼受けられるようになるまで何年もかかるのが普通だし。纏も確かデビューは高校出てからだったろ?」
「正式にはな。親に黙って小遣い稼ぎに軽いやつなら受けてたから、それを含めると……中学生くらい?」
「義務教育期間中に何やってんだお前は。まあ纏だから火遊びが火遊びで済んだだけだろうな……それより今は修行中の身の上なんだろ? 纏じゃあるまいし、その年で依頼任せるのはどうなんだ」
「えー、だってちょっとくらい死にかけた方が向いてないって諦めもつくだろ。人間、痛い目見なきゃ学ばないからな。そしたら勇次郎だって自分がどんだけ甘ったれてるかわかるだろ、さすがに」
「そいつぁどうかなあ……俺は無駄な足掻きだと思うなあ」
勇次郎くんがまだ小学生の時分に、纏は早々に独立しているため、実はこの兄弟が一緒に暮らしていた時期は意外なほど短い。しかも纏は物心ついた頃からずっと修練に明け暮れていたため、同居していても顔を合わせる時間は更に少なかっただろう。当然だが相互理解など無理である。結果として針間兄弟の仲は壮絶に悪い。
纏自身はさほど嫌ってなくても、このように弟のことを全然わかっていないのでは和解など不可能に近い。なお勇次郎くんは前述の通り死ぬほど纏を嫌っている。でなければ同じ道へ進むなど言い出さないだろう。「それを纏が嫌がるから」彼は術師になると決めたのだ。
……というのを他ならぬ纏本人は全然ちっとも全くこれっぽっちもわかっていない。外野の俺でさえ簡単に想像できることなのに、同じ血を分けた家族である兄は弟の心などまるで知らないのだ。これだから嫌われるのだろう。今も、どうしたら弟を挫折させられるかについて真剣に方法を検討している最中である。応援してやろうとか先達としてサポートしようという気概は一切見られない。
「……一応確認するんだけどさ、お前が傍について面倒を見てやる、という選択肢はないのか? 現役最強術師のお前が師匠として鍛えるなら、勇次郎くんだって心強いしお前も安心するだろう。何も無理して諦めさせようとしなくてもいいんじゃないか?」
「えー、やだよ。向いてないもん、人に教えるとかそういうの。だいたいあいつも私なんかに教わりたかないだろ、そもそも術師なんかになろうとしなきゃ何もかも丸く収まるっつうのに」
「そんなだから勇次郎くんも意固地になるんだろうなあ。たまには会ってちゃんと話してやれば? お前ら会話が足らなすぎだよ、だから拗れるんだよ」
「私はともかく勇次郎に話すことなんかないだろ。会って何を話すんだよ。最後に顔を合わせたの、私が去年の盆に仕事先から立ち寄った時だぞ。それもたまたま行先が実家に近かったからだし」
「ええ、せめて盆だけじゃなくて正月も帰省してやれよ。ご両親も寂しがってるんじゃないか?」
「正月は正月で針間一門総出で祓除の儀式やるから何かと忙しいんだよ。あいつ構ってやる暇ないし余裕もないし」
さすがに勇次郎くんが可哀想になってきた。思った以上の針間家の惨状に、そりゃ両方とも拗らせるに決まっているだろうなと内心で嘆息する。兄だけじゃなく親類一同もダメダメときては、やはり勇次郎くんは針間を捨てて完全な一般人として生きる方がなんぼか幸せだろう。皮肉にも纏の「術師にならなきゃ丸く収まる」という言葉が的を射ていることがよくわかる。
「まあ勇次郎くんの進路についてはさておき、結局どうすんだ? この件は」
「うーん……一旦はあのバカに預けるつもりでいるかな。まあ最初の一回くらいは付き添ってやってもいいだろ、死ななきゃそれでいいんだし」
「そ、そうか……まあお前が決めたことなら俺が口を挟む余地はないな。じゃあ遠慮なく取材させてもらうが、それで構わないだろ?」
「ええ、私にあいつの他にもお前のお守りまでさせる気かよ! まったくしょうがないな……」
「ははは、なんだかんだ言って勇次郎くんのことはほっとけないんじゃないか。素直じゃないんだから。それじゃ具体的な打ち合わせはまた後日」
「おー。気ィつけて帰れよ。じゃーな」
気づかぬうちにずいぶん話し込んでいたようで、お開きになる頃にはもう夜もだいぶ更けていた。終電に間に合ってよかったと連日のタクシー利用に思いを馳せつつホームへ滑り込んできた列車に乗り込み、遅い便にも関わらず満員に近い車内にげんなりする。明日が休みでつくづく良かった。まあフリーランサーなんか毎日が仕事で毎日が休みのようなものなのだけど。
家賃の安さだけが取り柄の自宅アパートへ着いた頃には既に、日付は変わっていた。急いで風呂を沸かしつつ、その間に家を出るときそのままにしてしまった朝食の残りや何やらを片付ける。まったくこれでは纏のことをどうこう言えないではないか。深夜でも掃除機を使おうが洗濯しようが何も言われないのが一人暮らしのいいところだ。なぜかこのアパートは俺以外の住人が転居してしまい、ほぼ空っぽだからできることだが。
なんにせよ明日は終日オフにすると決めている。行くべきところがあるからだ。もしも俺が誰に会おうとしているかを知ったら纏は怒るかもしれない、けれど。今回、本人の口から聞いて改めて顔合わせしなければならないと決意した。このままにはしておけない。放置も看過もするつもりはない。なぜなら俺にとって針間纏というひとは、ただ取材対象であるということ以外に──どうか幸福であってほしいと願う、ひとりの友人でもあるからだ。
◆◆◆
今どきはどこの子供も中学受験を経て偏差値の高い進学校へ通い有名大学までストレートで進学するというルートが一般的だそうだが(俺自身は地方出身だし大学も大したことない私立文系なのでよく知らん)、彼は首都圏でも大して頭の良くない……もっというと名前さえ書ければ誰でも受かるような高校をわざわざ選んだという。
実際、学校付近の様子を眺めてみれば、なんとなくこの地区が抱える事情もわかってくる。前衛的なラクガキだらけのシャッターに外壁、酒の空き缶やタバコの吸殻がその辺に放置され、立ち並ぶ団地や家屋も古さが目立つ。その中にある校舎も何年改修してないんだと言いたくなるくらいボロっちい。
兄が中高大学と金持ち向けの全国的に有名進学校へ通っていたから、逆張りで底辺校を選んだであろうことは想像に難くない。一応、学校関係者に来訪することは伝えたが果たして本人にちゃんと連絡がいってるかは疑わしい。とりあえず校内へ入り、来客用の玄関でスリッパを借りて職員室まで挨拶しにいく。生徒とは親戚とだけ教えていたから特に教員も疑うこともなく、本人のクラスまで案内してくれた。
夏休みを間近に控えた一年生の教室はやはり浮かれたような空気が漂っていて、授業中にも関わらず歓声が廊下を歩いていてもあちこちから飛び交っている。生徒に清掃させているのだろうが校内も外装同様に薄汚い。割れ窓理論なる言葉がなんとなく脳内に浮かぶ。
彼の所属するクラスは廊下の突き当たりにあって、ここは周りの部屋に比べるとまだ静かな方だった。それもそのはず、教師はダルそうに教科書を読み上げていてるがそれを聞いている生徒はほぼおらず、大抵寝ているか内職しているかスマホをいじっているかという惨状だったからだ。まあ俺が現役高校生だった頃も似たような感じだったが、さすがにここまで酷い割合ではなかった。まさか誰も板書するフリすらしないとは。
「ええっと……すみませんがここで待たせてもらえますか。授業中のようですし、他のみなさんの邪魔になっても良くないですから」
「いえ、どうせ聞いてないんですから別に呼び出して構いませんよ。ちょっと八雲先生に聞いてきます」
「申し訳ない。どうもすみませんね」
案内してくれた教師がわざわざ教室に割って入り、八雲という名前らしいおばちゃん先生に何事か話しかける。すると彼女は部屋の後方で机に突っ伏して寝ていた彼に呼びかけ、廊下で突っ立っている俺を指さした。人を指さしちゃいけませんという最低限の礼儀もここの教員連中は知らないらしい。かったるそうに立ち上がった少年は、引き戸の窓から俺を見つけるなり、あからさまにギョッとした顔をした。
「やあ、勇次郎くん。お久しぶり」
「お……お久しぶりッス、三本木……サン」
「おお、敬語使えるようになったじゃないか。だいぶ雑だけど。どうせこの後ヒマだろ? 昼飯奢るからちょっと付き合ってくれないか」
「エッでも俺まだ授業が」
「受けてなかっただろ。まともに。寝てたじゃないか」
「ヴッ」
「さ、立ち話もなんだし行こうか。すみません、こいつお借りしますね。放課後までには返しますので」
教師連中が無関心な態度なのは気にかかるが、とはいえ急を要するこの時に変に抵抗されても面倒なので、ほっと安堵しつつ元来た道を引き返して学校を出る。三歩後ろで不審そうにしながらもついてくる少年は、まだサボタージュを経験したことがないのだろう、そわそわと挙動不審に辺りを見回している。
「キョロキョロするな。職質されるだろう。ただでさえ成人男性と制服姿の学生の組み合わせなんか目立つし怪しまれるんだから」
「ンなこと言って連れ出したの三本木サンじゃん……つーかオレに今更なんの用?」
「お前、術師見習いになるんだろう。纏から聞いた。最近ちょっと厄介そうな案件がウチに来てな、あいつと話し合った結果、今回はお前に任せてみようってことになった。その件で今日は打ち合わせに来たってわけだ」
「……オレはアイツの代打ってことかよ。胸糞悪ィ、アンタもどうせスペアって思ってんだろ、クソが」
「ハア、短気で喧嘩っ早いところは昔から変わらんな。代打だろうがなんだろうが、名を売る絶好の機会には違いないだろう。『あの』針間纏の弟ってことで注目されている今しかチャンスはないぞ、あいつの名声を利用しないでどうやって売れる気でいるんだ?」
つまらなそうに口を尖らせている勇次郎は昔と比べ、すっかり様相も変わっていた。脱色しパサついた髪にピアスだらけの耳、学ランから夏服に切り替わっているためか柄シャツを羽織っている。あんまり今っぽくない、ちょっと昔のヤンキーみたいな格好なので、一体何をファッションの参考にしたのだか。以前は黒髪を短く刈り上げた、濃い眉ににきび痕の目立つ真面目そうな子供だった。
小柄な兄と違い、未成年のガキにしては上背はかなり高く、目線は俺とほぼ同じくらいだ。身長に対し筋肉がつききってないのか、線は細いが非力そうには感じない。美形一族の生まれなので顔も悪くはないはずなのだが、眉根に皺を寄せた不機嫌そうな表情が全てを台無しにしている。よくいう黙っていればイケメンの類だ。
「オレは別に……売れたいとか、そういうの思ってないし。纏みたいな金の亡者になんか」
「あいつの逆張りして術師を目指してるくせによく言う。まあいい、何食いたい?」
「……コーヒーでいい」
「あ、そ。変なとこ遠慮しいだよなお前」
というのでファーストフードのチェーン店へ入り、アイスコーヒーを二つ買って適当な席につく。オフィスカジュアルの成人男性とチャラそうな高校生の組み合わせが午前中からハンバーガー屋にいる構図に、歓談中のご婦人方から訝しむ視線が飛んでくる。よく冷えた、大してうまくもないコーヒーをひとくち啜って本題に入る。纏に渡したのと全く同じ資料のコピーを彼に見せると、目の色を変えて熟読し始めた。
「……どう思う?」
「どうもこうも、起きてんじゃん。霊障。手紙越しでも厭な気配が伝わってくんぜ。あの野郎はなんでこれで放置する気でいるんだ?」
「そりゃ正式に依頼が来ているわけではないからな。あくまで手紙の宛先はウチの編集部だ。これはただの怪しいファンレターどまりにすぎない。本来、針間に仕事を依頼するなら正式な手順に則る必要がある。これは違う。だから纏は引き受けられない」
「けっ、掟だルールだとめんどくせえ。結局は多忙を理由に逃げてるだけだろ」
「そう思うなら受けるか? お前が。そうなるとデビュー戦ってことになるな」
「ったりめーだ! アイツにできないってんなら、オレがやってやるよ。アンタもそれで文句ないだろう」
「もちろん。じゃあ送り主……依頼主というべきか、彼女にはこちらからコンタクトを取ってみるから、当日はよろしく。くれぐれもそんなチャラついた格好じゃなくて、それなりの服装で来てくれよ。髪も染め直すこと」
「生活指導のオッサンみたいなこと言いやがる……分かったよ、仕事なら仕方ねえ。連絡先、あんときから変えてねえから。なんかあったら連絡よこせ。じゃーな」
せっかく奢ってやったコーヒーをいくらも飲まないうちに席を立つと、彼は先に店を出ていってしまった。やれやれ思春期の子供は扱いにくいなあ、とため息をつきつつ、飲みかけの紙コップをゴミ箱に捨てて俺もひとまず退店することにした。
予定の上では一応休みということになっているけども、今日も午後から仕事が詰まっているし、この件ばかりにかまけているわけにもいかないのである。これから二日かけて信州の山奥まで取材に行かなくてはならない。フリーライター稼業も楽ではないのだ。
──針間勇次郎と知り合ったのは、彼がまだ小学生の頃、当時駆け出しのライターだった俺へ「面白い子供がいる」と同じ作家仲間が紹介してくれたことがきっかけだ。つまり兄である纏とはなんら関係がない。オカルト専門の雑誌記者やライター連中の間で、針間一族の名は知られていて、特に気鋭の天才術師という触れ込みで纏は既にかなり有名だった。何かと詐欺師やインチキ霊媒師の多いこの業界において、纏を含む針間の人間は数少ない本物だったからである。
その中でもメディアに一切露出がない次男坊の存在はミステリアスさや神秘性を帯びており、躍起になって正体を突き止めたがる者も多かった。俺に話を持ってきたやつもその一人。新人時代の俺はまだこの業界に来て日が浅く、加えてオカルト専門でもなかったため、相手に警戒心を抱かせないと思われたのだろう。だから代わりに取材してくれと頼まれた。たかがガキ一人にスクープ性があるとは微塵も感じなかったが、先輩に恩を売るのも悪くない、と二つ返事で引き受けた記憶がある。
勇次郎は、そのとき小学校に通っているような年齢の幼い子供だった。やんちゃでわんぱくな、という表現がぴったり合うまさに絵に描いたようなクソガキであり、いたずらっ子だったことを覚えている。クラスのリーダー格というかガキ大将というか、妙に求心力があっていつも他の子に囲まれているような子供で、特に同じ男子には慕われていたようだ。代わりに女子からは「ちょっと男子〜!」されていたようだったが。
針間の人間はあまり一般人と関わらず、術師の家系の子供が多く通う学校や私立の一貫校を選ぶ傾向にあるので、公立の「フツーの」小学校で他の子供と同じように学んでいる様子というのは珍しい。それもそのはず、家系の人間の大半が術師である針間の子にしては珍しい、素養を持たない人間だと(まだこの時は)思われていたからだ。一番は次期当主である纏の意向が強く反映されている。年の離れた可愛い弟には、普通の人と同じ暮らしや人生を送ってほしい、という。
そういうわけで当時も勇次郎は自分の家系のことなど何一つ知らず、日々を「普通に」過ごしているようだった。ところが問題が起きる。針間と敵対する他の家系の術師が勇次郎に目をつけ、呪詛を仕掛けたのだ。実力が足りず纏本人は害せなくても徒人同然であるその弟ならば手出しが可能と踏み、実行に移してしまったのだろう。勇次郎はそれこそ死ぬような苦しみを味わい、なんなら二、三度命を落としかけたこともあるという。
もちろん身内に手を出されて黙っている纏ではなく、相手術師は家系ごと全て壊滅させた。呪詛返しを行ったことで本人だけでなく血筋に連なる者も全て死に絶えた。文字通り末代まで呪ったというわけだ。勇次郎は自身に起きたことを覚えておらず、今でも当時については重い病に罹って長らく伏せっていただけと思っている。兄はこの件で二度と愛する家族を危険に巻き込まないよう勇次郎と絶縁することに決め、間もなく独立した。
そのせいで彼は、未だに兄に対して「己が一番辛かった時に傍にいてくれもせず、あまつさえ一方的に縁を切った冷酷な人間」と思い込んでいる。纏へ強烈な敵愾心と嫌悪を向けるのはそのせいだ。憎まれている方が都合がいいとして積極的に誤解を解こうとせず、むしろ会う度に憎悪を煽る纏サイドにも問題はあるのだが。こうして元は悪くなかった兄弟仲は現在、徹底的に断絶してしまい今のところ修復される様子は見受けられない。
俺は取材を通して一連の流れをつぶさに観察していたので本来ならば纏の代わりに真実を説明する義務がある。しかし勇次郎に関する事件は業務命令でお蔵入りになり記事にできなくなったのと、他ならぬ纏がこのことについて口止めしているため、外野の俺が勝手にペラペラ喋ることはできないのだ。
実際、勇次郎が纏を嫌っている間はこちらの世界に関わってこないだろう、という目論見もあって誤解を解かないことがある種の防衛策になるものと思われていた。嫌いな相手について知ろうとしなければ針間の稼業に興味を示すこともないだろう、という予想をしていたからだ。ところが勇次郎は何をトチ狂ったのか、いきなり方向転換し術師見習いになると言い出した。他の針間に比べて、実力も才能も欠けた状態のくせに。
おそらく「何か」はあった。何も知らない次男が長男と家族の秘密を知るような、彼ら兄弟の関係を大きく揺るがすイベントが。これについては纏本人に問いただしてみても決して口を割らない以上、もう一人の当事者である弟に聞くしかない。手紙の主には悪いが、この件を利用して長らく交流を控えていた勇次郎に再び近づいたのは、過去に二人に何があったか明らかにするためだった。
◆◆◆
別件での取材を終え、東京に戻ってきてから正式に勇次郎へ協力を要請すると二つ返事で了承の旨が返ってきた。当然だがこれはボランティアではなく、れっきとした依頼料が発生するからだろう。針間の人間はそれぞれ独自の計算方式で料金表を設定しており、最も高額なプランだと一回につき数百万もの額を支払う必要がある。手間賃、かかった時間、使った機材等によって細かく変動するが、基本料金だけでも結構高額だ。
纏の場合は依頼主の懐事情に応じて料金を決めており、大企業の役員や政治家資産家などには高額の依頼料を請求する一方、学生や主婦など所得が低い者にはパート代やアルバイト代を何ヶ月か貯めれば払える額しか要求しない。一見すると良心的だが、後者に関しても親や夫が金持ちならもちろんそれなりの金額を支払わせているし、踏み倒すようなら式神をけしかけて延々と追い込みをかけるので別に優しくはない。
しかし針間のルールにおいて見習い身分はプロフェッショナルではないとされており、原則的には依頼料を受け取ってはいけない(それも修行のうちに入るから)と決められている。このため何か依頼が来ても基本的に無給で引き受けなくてはならないのだが、今回は俺がしばらく取材のアシスタントとして同行してもらうという名目でアルバイト代としていくらか支払うことになった。針間における原理原則に反するとはいえ、さすがに子供に無賃で働かせるのは社会人としてありえない話だ。
修行中はお小遣い制でアルバイト禁止なため、彼は初めて自分の働きによって得られる対価に純粋に喜んでいるようだ。というのも拘束時間がどの程度か読めないので、ひとまず三日間程度を想定し、最低賃金に少し色をつける形で算出した額を手付金として前払いしている。大人しても割と大きな持ち出しなので、就労経験のない子供にしてみればかなりの大金に感じるだろう。最新型のゲーム機を購入してもお釣りがくる。
行先が遠方なので普段なら費用を編集部持ちでレンタカーを借りられるのだが、今回は勇次郎というオマケがくっついているため新幹線での移動となる。この場合の交通費も経費として編集部に請求できるが、勇次郎に関しては俺が個人的に雇っている形なので、もちろん宿泊費や食費も諸々全て俺持ちだ。少々痛い出費だが仕方ない。
取材当日が土曜なので、できれば明日の夕方までには解決したいところだ。まさか学生に授業をサボらせるわけにもいかない。本人は学校休めてラッキーくらいにしか思ってなさそうだが。並行して手紙を送ってきた相手とも連絡を取り、こちらの事情もある程度説明しつつ具体的な打ち合わせの日取りを決め、そして当日。
新幹線で約一時間、そこから路線バスに乗り換え、待つこと更に一時間。なおバスの間隔は数時間おきに一便という交通の便の悪さに泣けてくるほどだ。たとえ自費になろうがやはりレンタカーを使えばよかったかもしれない、と軽く後悔する。目的地まで向かうバスに乗り込むが、乗客は俺たちだけである。数十分ほど揺られ、いくつもの停留所を通り過ぎ、ようやく着いた頃にはもう夕刻に差し掛かりつつあった。
言いつけ通りに髪を黒く染め直し、あんまり威圧的でないカジュアルな私服姿の勇次郎と俺は、依頼主の暮らす北関東のとある田舎町へと訪れていた。待ち合わせ場所であるチェーンのファミリーレストランで遅い昼食(もう夕食に近いが)を済ませ、依頼主が来るのを待っていると、予定の時間より少し早めに依頼主は姿を現した。
手紙を送ってきた彼女──広岡さんは、軽い自己紹介をしたあと、このあたりの特産だという手土産を俺に渡し、ぺこりと頭を下げた。白髪まじりの髪をひっつめにしており、あまり化粧っ気のない素朴な顔立ちで、地味目のワンピースの上にカーディガンを羽織っている。社内で自分が二番目に若いという文面から受け取る印象とは違う。なんとなく職場の平均年齢も予想がついてしまった。
「今日はすみません、わざわざこんな席を設けていただいて……あの、そちらのお若い方は?」
「先に連絡を差し上げた通り、本件に携わる術師の方です。まだ見習い身分ですが実力は確かですよ、あの祓い屋のお墨付きですからね」
「まあ……! それを聞いて安心しました。それにしても本当に、ずいぶんお若いんですねえ」
「拝み屋さんなんかだと長くやってらっしゃる方もいますからね。祓いに関しては若い人もかなりいますよ、危険な仕事だから長生きするのが難しいという事情もあるんでしょうが。それで今回はどうしたいですか? 手紙だけですと不明瞭というか……広岡さんがどういう解決を望んでいるのか、ちょっと分かりにくくてですね」
「すみません、気持ちが昂ってちゃんと推敲もせず送ってしまって……実のところ、わたし自身も判断しかねているのです。御局様、お名前は安田さんというのですが、彼女に身の潔白を証明したいというのもありますし……そもそもの霊障とかいうのをどうにかすれば、それで丸く収まるならそうしたいです」
「えーと、あのさ、手紙、読んだけど……広岡サン、だっけ。アンタさ、本当に嫌がらせとかしてないんだな?」
「しておりません! 失礼な! 長年勤めた職場にそんな子供じみた真似などしますか、だから他に犯人がいるはずなのです。亡くなった新人さんの霊が無念のあまりに霊障を引き起こしているのか、それとも考えたくないですけど他の社員が何か良からぬことを企んでいるのか……それを明らかにしてほしいのです」
「なるほど。わかりました。ではその方向で話を進めていきましょう。やはり現場を実際に視てみないことには手がかりは掴めなさそうだ」
「……えっ? 今からですか?」
「今回同行してくれた彼が一応学生なもので、なるべく早くカタをつけたいんですよ。うっかり授業をサボらせようものなら俺がこいつの保護者から叱られてしまうもので。すみませんが協力お願いします」
「はぁ……そういうことなら分かりました。あの、車を家に置いてきてしまったので、取りに戻る必要があって……申し訳ないですが、自宅まで歩きでも大丈夫ですか」
「構いませんよ。急がないと日が暮れてしまいますし、そろそろ行きましょう」
今回、取材にやってきた広岡さんの故郷は山奥にある小さな農村で、人口のほとんどが後期高齢者という現代日本にありがちな、限界集落一歩手前の地方である。一家に一台ではなく一人につき一台車が必要で、コンビニへ行くにも車を出さなきゃならないような、辺鄙な村で彼女は生まれ育った。店も遊ぶところもない、閉鎖的な田舎の娯楽といえば噂話くらいしかない。
広岡さんの会社はそこで農機具などを取り扱う卸売業者で、事務要員である女性社員二名(御局様と広岡さんだ)以外は基本、お手伝いのために農家さんのところに出払っている。まあ営業とか宣伝も兼ねているのだろう。だから社内には彼女たち二人しかいない。会長の息子である社長や創業者である会長も日頃はどこかに出かけているそうだ。想像するとなんとも寂しい光景である。
ファミレスを出たあと、自宅までの道のりを歩きながら彼女はポツポツと身の上話をしてくれた。家族構成は彼女の他に年老いた両親と弟妹がそれぞれ一人。年子の妹は学生結婚で家を早々に出ており、歳の近い弟もやはり高校卒業後に地元を離れ県外就職している。長女として親の介護をしなければならない彼女は、そうした道を選ばず、たった一人で故郷に残ると決めた。
大学を卒業し、縁故採用されたのは社員のほとんどが元からの知り合いという小さな会社。それも社長の嫁候補としての、本人の実力など期待されてのことではない採用理由。腰掛けとして働く日々の中、数少ない友人も結婚や進学就職等で疎遠になっていき、一人地元に取り残されたその寂しさは一体どれほどだっただろう。そんなさなかに起きた新入社員が自殺し、時同じくして発生した怪奇現象。そりゃあ情緒不安定になるのも頷ける。
つい同情的になってしまうのは、彼女と似たような境遇だったからだろうか。
「本当にうちに泊まるんですか? 確かに地元には旅館とか泊まれるところはないですが……」
「いやあ申し訳ない。最寄り駅にビジネスホテルがあると伺ったのでそちらを予約しようとしたのですが、まさか満室とは思わず……」
「いえ、きっと両親も喜ぶと思います。兄さんが帰ってきたみたいで」
「……お兄さん? アンタ兄貴がいるのか。さっきはそんな話、全然してなかったよな」
「ええ、まあ……その、兄はずいぶん前に死んでいるものですから。ちょうど祓い屋さんと同じくらいの年の頃に。生きていれば、そろそろ還暦でしょうか」
「……そうだったのですか。差し出がましいことを聞いてしまいました」
「いえ、気にしないでください。わたしも兄の顔は写真でしか知らないんです。ちょうどわたしと入れ違いになるみたいに死んでしまったので」
暮色に染まる空の下には青々と茂る見事な田圃が整然と続き、ビニールハウスや露地植えの野菜畑があちこちに点在している。広大な田園地帯にポツポツと民家が佇んでいるが、この時間に出歩いている住人の姿はやはりなく、車すら一台も通らないので本当にここに人が住んでいるのかも疑わしい。聞けば住民は減る一方で、それも転居ではなく高齢の住人が老衰や病気などで亡くなることが主な理由だそうだ。
過疎化に苦しむ小さな集落。日本各地どこにでもありそうな村だ。ここだけが特別なのでもないし、閉鎖的で排他的な性質というのは過疎が進み人がいなくなれば余計に強くなる。それは住民同士の結束の強さの表れでもあるから一概には批難や否定はできないし、日頃からお互い密に関わることで住民の孤立や村を狙う悪人による犯罪を予防するという効果もある。
ただし、そうした恩恵に与れる者ばかりではない。具体的にいえば「よそさん」である。いつから村にその家が住んでいるかが村内ヒエラルキーにおける指標であり、家が若ければ若いほど階級は下になる。のんびり田舎暮らしやスローライフに憧れて都会から移住してきた若者なんて特に立場がない。村のルールや掟とかいうバカバカしい因習に従えなければ即座に排斥される。
広岡さんの先祖は昭和の初めにこの村へ来たという。それでも扱いは「よそさん」のままだ。たかが百年程度では受け入れるに値しないということだ。村自体の歴史が古ければ古いほど、古参の影響は強くなる。会社の御局様が強権を振るえるのも、おそらくこの村の古参だからだ。単に社長の妻だからではない。
彼女はそれを意図的か無意識にかは分からないが手紙に書かなかった。書く必要がないと思ったのか、注釈がいることだと認識していなかったのか。おそらくは後者だろうが、それだけ広岡さん本人にも村でのヒエラルキーや暗黙のルールが身に染みついているのだろう。他人にとっては異質なことだと気づかなかった。よくあることだ。俺だって上京しなければ村の常識は世間の非常識であることに無自覚なままだっただろう。
あぜ道をしばらく歩いていると、周囲を防風林に囲まれた大きな日本家屋が見えてきた。木造二階建て、瓦葺の屋根はなかなか立派で、枯山水風の日本庭園なんかも設えられている。同じ家を東京で建てようと思ったら地代だけで億単位の金がかかるだろう、地べたが有り余っている田舎だからできることだ。広岡さんが玄関の引き戸を開け、俺達に入ってくるよう手招きする。
「お、おじゃましまーっす……なんかやけに暗いな。広岡サンの親ってのはいねえのか?」
「両親は自分の部屋でもう休んでいる頃合です。入浴と食事は介助してもらわないといけないのでヘルパーさんに来てもらっていますが、夕方にはヘルパーさんも帰っちゃうので、今からが就寝なんですよ」
「なるほど。だから家の中も暗くしてるんですね。ひとまず荷物置かせてもらってもいいですか。それからお仏壇に挨拶させてください」
「ええ、どうぞ。兄も……皆さんを歓迎してくださると思います」
ベッドが二組置かれた、この家唯一の洋室である客間に手荷物を運び終え、居間へと案内してもらう。縁側に面した広々とした室内には作り付けの大きなテーブルとソファが並べられ、あちこちに日用品や書類などが置きっぱなしになっていて雑然とした印象を受ける。賑やかしにつけたままになっていた、これまた巨大なテレビには地方局のよく知らないローカル番組が映し出されている。
仏壇は居間にあった。これだけ大きな家だから仏間くらい余裕で作れただろうに、わざわざ居間の中に、それも今は障子の閉められている両開きの窓から見える位置という外から目立つ場所に安置されていた。今は、というか常に障子は閉まったままなのだろう。本来は明かり取りを兼ねつつ庭へ出るための窓だが、仏壇が日光で傷まないために閉めきらざるを得ない。仏壇そのものより内側に飾ってある遺影が青く日焼けしてしまうからだ。
もちろん普通に仏間を作るときも日当たりの良さは重要だろう。でも仏壇自体を窓際に配置することはないし、ましてや直接日差しが当たるような位置に据えるのも滅多に見ない。しかもこの仏壇、扉が閉じたままになっている。開放できない何らかの理由でもない限り、仏壇の扉は基本的に開けっぱなしにされているものだ。つまり「中身を見られたくないから」閉めているということになる。そこに疚しさを感じずにはいられない。
一見するとごく普通の家だ。でも、この家はやはり何か、おかしい。
「……あの、兄に挨拶、されますか」
「ええ。故人に来訪を報告した方がよいかと思いまして。ご迷惑でなかったらの話ですが」
「わかりました。……実は、わたしも『これ』を開けるのはずいぶんと久しぶりのことなんですよ」
どこか緊張した様子で彼女は微かに震える指先を扉の取っ手にかけた──緊張? なぜ仏壇の扉を開くだけのことが、そこまでの緊張を強いる? らしくもなく俺の方まで背筋がひやっと寒くなった。それまで黙ってやり取りを見ていた勇次郎が、完全に開ききる前にそっと広岡さんの手を押さえた。
「……よくわかんねえ、けど、やめた方がいいと思う、たぶん。ごめん、なんでかはオレにもわかんねえ。勘っつーのかな、それが開けんなって言ってる……くそ、兄貴ならもっと上手くやれるんだろうけどよ」
「俺には霊感とかそういうのはないからな。ここは現場の人間の判断に従っておくとしよう。広岡さん、とりあえず今のところ開放するのはやめておきましょう、別にお線香はこのままでもあげられますから」
「わかりました。すみません、正直ほっとしてるんです。遺影とはいえ兄の顔を見るのがなんだか怖くて。……わたしにとって血縁上では兄ではありますが、本音を言うと彼を自分の兄であるとはどうしても思えないんです。よく似た他人であるようにしか」
長女である広岡さんと、亡くなった広岡さんの兄は二十以上歳が離れている。一人息子が若くして命を落としたことがショックだったのか、その後しばらく彼女の両親は子供を作らなかった。一転して一男二女もの子供をもうけたのは、それから何年も経っていよいよ母親の年齢が適齢期を過ぎてからになる。現代でもそうだが、高齢出産は何かとリスクが高い。しかし彼らはそれに踏み切り、結果として大過なく三人の子宝に恵まれた。
広岡さん自身、自分達に兄がいたことを知ったのは成人してからだという。それまでは親戚の誰かだと無意識に思い込んでおり、別段両親に遺影の人間が何者なのか尋ねることもなかったようだ。これはまあ想像しやすい。子供というのは親の情緒に敏感だから、自覚しないところで兄の件については触れてはいけないタブーだと気づいて言及を避けてきたのだろう。
彼女によれば「昔は別に仏壇の扉は閉まってなかった」そうだ。だから遺影の男は毎日のように目にする存在だった。タブーとなったのは、両親が兄について子供達に話をしてからのことだという。つまり「兄の存在を明かした」ために禁忌とせざるを得なくなった、と考えられる。勇次郎が仏壇から何かを感じ取り、開けるのをやめさせたのもそこに何か理由が隠れているはずだ。
三人でそれぞれ順番に線香をあげたあと、広岡さんは自身のスマートフォンに保存してある、とある一枚の写真を見せてくれた。たまたま一枚だけ持っていたという生前の兄を写したショットだった。男にしては長い髪を肩口で切り揃え、タレ目がちの柔和な顔立ちをした、学生服姿の少年である。高校の入学式に撮ったもので、このあと一年もしないうちに亡くなった。
なぜ広岡さんがその写真を所有していたかというと、例の会社の社長が亡兄と同級生だった繋がりで、当時の写真が残っていたら見せてほしいと頼まれたためだとか。断りきれず仕方なく入学式の写真をスキャンし、メッセージアプリを経由して送ったという。その後も消すに消せず、携帯に残したままにしているそうだ。アルバムには幼少期の写真もあるそうだが、全て両親の寝室にある鍵付きの戸棚にしまわれていて、勝手に持ち出せないという。
成人し、名実共に娘が大人になるまで「成人する前に死んだ」兄の存在は伏せていた。アルバムを簡単に持ち出せないところへ隠すまでして、徹底的に。家族以外の人間から兄について仄めかされることもなかったのだろう、でなければもっと前に彼の存在は明らかになっているはずだ。他の親類縁者や近所の人間にも固く口止めしていたことは想像に難くない。
解せないのは両親がそうするに至った理由だ。社内で度々発生する怪奇現象よりもこの兄にまつわる謎の方が明らかに異常性を帯びている。なぜなら身内である広岡さん本人さえ、家族構成について話すときに「うっかり」兄の情報を欠落させてしまうほど彼の存在は希薄なのだ。死者というのは時間が経てば過去のものになっていくもので、それ自体はなんら悪いことではない。だが、あえて過去の存在へと無理やり忘却させようと、風化させ埋没させようとするその扱いには疑問が残る。
──もしも、全然関係ないように見える二つの事象に繋がりがあったら。いや繋がりは既にあると言えるかもしれない。どちらも広岡さんを基準に起きている、あるいは広岡さんが原因で起きているのだとしたら。
「広岡さん、もう少しお兄さんのことについて詳しく教えてもらえませんか。ご両親は彼に関して他に何を言ってましたか?」
「え、他にですか……すみません、わたし自身はあんまり知らなくて。両親なら兄のことはよく知っていると思うのですが、さすがに無理やり起こすわけにもいかないですし」
「……いや。すみませんこちらこそ。無理なことをお願いしてしまって。俺とこいつでひとまず社屋を確認してくるので、案内だけ頼めますか」
「ああそれなら……でももう遅いですよ?」
「さっきも言いましたが、明日の昼にはここを発たなきゃならないんで。なるべく早く解決したいんですよ」
「わかりました。ちょっと待っててください、車出してきますから」
普段通勤に使っているという軽自動車に乗せてもらい、五分ほど走ると古びたコンクリート造りの二階建ての社屋が見えてきた。一体どのくらい昔からここにあるのか、外壁は元の色がなんだったか分からないくらい黒ずみ、手入れが行き届いていないのか窓ガラスも曇ってみえる。だだっ広い駐車場には社名のロゴが入ったバンが数台停められていて、その近くに広岡さんは駐車すると職員玄関用の鍵を預けた。彼女には車内で待機してもらい、内部には俺と勇次郎の二人だけで潜入する。
ボロっちい外装の割に、内部はまあ普通のオフィスといってよかった。やたら大量の観葉植物を飾った応接室は立派な革張りのソファとテーブルがあって、事務員が普段使う仕事部屋は人数分のデスクがあるものの、使われている様子があるのは二つだけだ。これは御局様と広岡さんの机だろう。男性社員は基本的に出払っていて現場作業ばかりというのは本当のようだ。二階の会議室も一応用意したとはいえ使ってないのが丸わかりで、オフィス用の椅子も円卓もうっすら埃を被っている。
会社規模の割に自社ビルを所有しているのは単に地べたが有り余っている田舎ゆえに地代も建築費もかなり安く抑えられるからだろうか。一通り見て回ったので帰ろうとリノリウムの床を歩きつつ、隣の勇次郎を見やると不思議そうに辺りを見回していた。何か気にかかることがあるのかと尋ねてみるも、首を傾げて眉間に皺を寄せるばかりだ。
「……普通なんだよな。いや、本当に普通なんだよ。怪奇現象だっけ? 起きてるならもっとイヤ〜な感じがすると思うんだけどさ、別にそんなん無いんだよな。マジで普通。霊的な気配とか全然ないの。あの家は居るだけでめちゃめちゃヤバかったのに」
勇次郎の特異性はその高い感知能力だ。針間の人間はごく僅かな例外を除き、ほぼ全員が大なり小なりある程度の霊力を持つが、何を得意とするかはそれぞれ違う。結・纏親子は祓いに特化した力を備えているが、次男の彼はむしろ視ることに長けている。単なる霊視能力だけなら一級品というのが纏の評価だ。
だが、術師というのは視るだけではなく祓えなければ意味がない。悪しきものを退ける力があってこそ術師は術師足り得るのであり、その技術も実力もない勇次郎では依頼者の役には立てない。ゆえに兄は弟の素質を見抜きながらもこちらの世界に関わらせず、一般人として生きていけるよう手を打った。実際、過去に勇次郎を狙った輩も幼い彼の優れた霊的感受性を恐れて排除しようと呪詛を行ったと自白している。
それほど見鬼として高い能力を持つ勇次郎が「あの家はヤバい」と感じ取った以上、広岡家に何か問題があるのは確定とみていい。視るも祓うもできない徒人である俺でさえ、ただ本人から話を伺うだけで違和感を覚えざるを得なかった。あの家で何十年も暮らしてきた彼女は慣れてしまって今更奇妙さを感じないのだろう。
二階には会議室の隣に社長室もあり、念のためこちらも見ておくことにする。重役が使う部屋だというのに鍵はかかっておらず、簡単に入ることができた。手前に二人がけのソファとテーブルのセット、奥に大きめのデスクと高そうな椅子がある以外に調度らしい調度もなく、清掃が行き届いているのか綺麗なものだ。一階のオフィスに比べればまだ使用感がある。ご丁寧にも机の上にはネームプレートがあり、書かれている名前に勇次郎が目敏く気づく。
「……あれ、社長の名前、広岡ってなってる」
「ほんとだ。でも広岡さん、社長が身内とか特に言ってなかったよな」
「手紙によると社長の息子……まあ跡取りだろうな、そいつと結婚させられそうになったとか書いてあった気がするんだけど。元から親戚かなんかだったってこと?」
「広岡さん本人が既に息子とやらと籍を入れていて苗字が変わっているとか? でも彼女は結婚を受け入れなかったというし、あの家の表札は『広岡』だった……田舎だから同じ広岡って苗字の家がたくさんあるのかも」
「なんにせよ、本人から直接聞くしかなさそうだよな。そろそろ帰ろうぜ」
他に探索したいところもないのでさっさと退散し広岡さんが待つ車に戻ると、彼女は視てみてどうだったかとこわごわ訊ねてきた。特に何も問題はなさそうだと伝えると落胆した様子でそうですか、と力なく応えた。無理もない。本人にしてみれば、霊能者にお祓いしてもらって終わりのつもりでいたのだろう。むろんこういう案件で本当にお祓いで済むケースは俺が知る限り、ほぼゼロなのだが。
元きた道を引き返し、広岡家へ戻る頃にはもう辺りもだいぶ暗くなっていた。街灯もほぼなく、家々や店の明かりもない田畑が広がる中にぽつんと建つ、日本家屋の黒々としたシルエットはなんだか不気味にみえた。
「あの……夕食、どうされます?」
「済ませてきたのでご心配なく。シャワーだけ使わせてもらってもいいですか?」
「それはもちろんどうぞ。台所の横、廊下の突き当たりにありますから。今、タオルとか持ってきます」
「助かります。すみませんね、何から何まで」
「こちらこそ何もお構いできなくて申し訳ないです。うちにお客様が泊まりにくるのなんて、両親がああなってからは一度もありませんでしたから」
彼女が成人した時には既にもう古希を過ぎていた広岡夫妻は、現在はもう介護を必要とするようになってしまったそうだ。日中もほぼ寝ているような状況で、まともに会話することも覚束ない。両方とも重度の認知症かつ、寝たきり状態というのは、娘である広岡さんへの負担があまりに大きすぎるのではないだろうか。遠方にいるという弟妹からいくらかの金銭的援助はあるというが、だとしても実際に面倒を見なければならない彼女とは物理的・心理的負荷がまるで違う。しかも広岡さんはそんな過酷な日々を自ら望んで選んだというから、全く頭が下がる。
仮に俺が故郷にいる家族の世話をしろと言われても絶対に無視するだろう。そもそも絶縁したも同然で上京してからは一度も連絡を取ってないので、いい加減向こうも俺の存在はないものとして扱っているかもしれないが。とはいえ広岡さんの両親は、我が子が進んで自分達の介護をやると決めたことに何を思ったのだろう。もし自分が親の立場なら、子供にそこまでの迷惑をかけられないと固辞するだろう。少なくとも手放しに喜べる気はしない。
だが。高齢出産のリスクを承知で、母体が耐えられるギリギリの年齢を計算して三人もの子供を作ったとしたら、ちょっと話は変わってくる。というのも死んだ第一子から次の第二子までがあまりに離れすぎているのだ。それだけ心の整理がつくまで時間がかかったと好意的に捉えてもいいが、おそらく真意はそんなものではない。何か目的はあったはずだ。でなければ、それまで頑なに子供を作らなかったのに立て続けに三人もの子供をもうけたことへの説明がつかない。
それぞれ手早くシャワーを済ませ、使わせてもらっている客間へ引き上げ、今日のところは解散する。明日の昼にはここを発たないと東京へ帰れないので、動くとしたらヘルパーさんがやってくる時間よりも前──早朝だ。それまでに祓いの支度を終わらせなければならない。本当にお祓いが必要であればの話だが。
「で、どう思う。お前の観点から話してみろ」
「どうって言われても……オレ頭良くねえし、アンタみたいに口も回んねえから上手く説明できる気がしねえんだけど。ただ、」
「──ただ?」
「……あの仏壇は、たぶん何かある、気がする。勘だけど。なんか変なんだよ、フツー仏壇って開けっぱだろ? 閉めてるなんておかしい。きっと開けたらダメなんだ。開けると良くないんだ。中にいるものが出てきちゃうから。出たら、どうにもなんなくなるから」
「中にいるものってのは、広岡さんのお兄さんか?」
「違うかもしれねえ……って、思う。断言できねえけど。広岡サンの兄貴ってやつの気配は確かにあるっちゃあるんだけど、すっげえ薄いんだよな」
シャワーを浴びたあとの濡れ髪をわしゃわしゃとタオルドライしながら、勇次郎はうまいこと言おうとして結局諦めたように口を閉ざした。慣れないこと続きで疲れているだろうに、疲労をおくびにも顔に出さないのは、なかなかできることじゃない。これは纏に報告してやらなくっちゃなと脳内でメモしておく。しかし感知に優れる勇次郎でさえハッキリと感じ取れないとは。
「人間だったものって言ったらいいのかな。オバケとも違う、ユーレイでもない、どっちでもあってどっちでもないもの……それが、あの中に『ある』」
「……今も?」
「今も。でも『それ』は別に、どっかに行きたいとか、あそこを出たいとは思ってない……自由は求めてないみたいだ。でも完全に無害ってわけでもない。怪奇現象ってのが実際に起きてるわけだろ」
「仏壇の中のそいつが原因なのか、やっぱり。でも、そしたらそいつ動機はなんだ? 大体、封じられてんのか閉じこもってんのかは分からんが、あそこにいたんじゃ外の様子なんか分からないはずだろ?」
「ドローンみたいなもんなんだろ。広岡サンが。憑依とかじゃなくてさ、眼を借りてるんだろうな。きっと。そんで広岡サンを通して『あいつ』は世界を見てる。なんでかって言ったら……守りたいからなんだと思う」
「守りたい? 彼女を? ……何から?」
「わかんねえ……広岡サンに何か危険があるとも感じられねえんだよ。フツーなんだあの人。会社も。おかしいのはこの家だ。仏壇を基点として……あ、だからか」
ペンと紙をくれと言うのでスケジュール手帳のフリーページを一枚破り、愛用のペンと一緒に渡してやると、勇次郎はへたくそな三角屋根の家らしきものを描き始めた。絵心はないらしい。この家は現在俺達が逗留している広岡邸で間違いないだろう。彼は、その周りにデフォルメされたオバケのイラストをいくつか描き足した。微妙なかわいさのせいであんまり怖くは感じない。
「元々、この辺は変なのが寄りつきやすいんだよ。ほら鬼門とか忌み地とかいうのあるだろ。でもそれって特定の方角や場所がそうってことじゃなくて、やっぱ土地ごとに違うわけ。なんつうの、空気より重い毒ガスって窪地にたまるじゃん。それと同じで悪いものが集まりやすいスポットってのが色んなトコにできちゃうんだよな。自然と。んで『ここ』もそういうスポットなんだよ」
言いつつ勇次郎は仏壇のある居間の方向を睨む。彼の口にする「ここ」の中心がおそらく家の真ん中なのだ。この家は居間が家の中央にくるよう設計されており、かつ外へ直接繋がる縁側に面しているため居間が最も日当たりがいい。それはどこの家でも同じだが、少なくとも悪いものの溜まり場と化しているらしいこの家に関しては、何か意図があってのこととみていい。
おそらくこの村の人間は、広岡家がある土地が良くないものの寄りつきやすい一帯であると知っていたのではないだろうか。広岡一家は昭和の始め頃にここへ越してきた「よそさん」だ。長いこと共同体の一員だったわけではない新参だ。もしも村の人間が何も告げず教えず、家を建てるのにここを提供したのだとしたら。もっというなら押しつけたのかもしれない、ある種の生贄として。
だが忌み地の中心部を囲うように居間を設計し、光と風の通り道を作って吹き溜まったものを散らすことで、厄を溜め込まないように工夫した。つまり建築に携わった人間は土地の異常性に気づいて手を打ったことになる。施主である一家がそれを存じていたのかは不明だが。けれども、いくら対策を講じても土地自体が汚染されたまま浄化されないのでは、いずれ限界が出てくる。
であるならば、広岡さんのお兄さんがその犠牲となった可能性は否定できない。散らしきれなかった厄が家で最も弱い存在である子供へと牙を剥いた。本当に幼いうちではなく、ある程度大きくなってからなのは、事前の対策が効いてそれだけ時間が稼げたからだろう。その後、長いこと子供を作ることを避けていたのに、再び三人もの子を産み育てたのは──子供が厄を引き受けられることを察知してしまったからかもしれない。
厄はその場で一番弱いものに向かう。子供、女、老人、あるいは何かしらの障害を持つ人間。息子という身代わりを失った以上、次に被害を受けるのは妻だ。もし長いこと子供を「作らなかった」のではなく「作れなかった」のだとしたら、少し話が変わってくる。それだけ散らせなかった厄が強く、母体へのダメージが深かったとしたら。広岡さんの母は、広岡さんを産んだことでようやく厄を逃れた。それから立て続けに二人の子供を授かれたのも、その間は広岡さんが厄を引き受け続けていたから。
一人の子供では受け止めきれない厄も、三人で分け合って一人一人の受ける量を調節すれば耐えられるかもしれない。そうして長らく平穏を保ってきた。だが、弟妹はどちらも(事情を承知しているかは不明だが)この家を出た。残されたのは広岡さんたった一人。その間は彼女だけが厄の防波堤となって両親を守ってきたのかもしれない。だがいずれ人は老いるものだ、そして厄は最も弱いものへと牙を剥く。結果として、彼女は厄から解放された。本人の預り知らぬところで親を身代わりにする形で。
全ては状況から邪推したただの憶測、ただの想像でしかない。ただ、この家が良くないものの寄りつきやすい場所であることは確かだ。忌み地、鬼門、呼び方はなんでもいい、どちらにせよ人が住める土地ではない。とはいえ引越しというのも現実的ではない。日常生活を自由に送ることもままならない年寄り二人を抱えた独身女性に、この家を出てよそで暮らせというのはあまりに酷だ。現実的なことを抜きにしても故郷への愛着だってあるだろう。つまりは根本的な解決が望ましい。
「……なあ、疑問なんだけどさ、広岡サンのお兄さんってなんで死んじゃったんだ?」
「あー……そういや聞いてないな。それがどうかしたのか?」
「仏壇の中にさ、いるんだよね。まだ。その人が。だから力を借りられないかなって思って」
「……待て、それはどういうことだ?」
「あの中にいんのは、長年この土地に巣食ってきたやつらと、それから本来の仏壇の主だ。ふたつは混じったり溶けたりしてなくて、それぞれ別なところにいる。んー、なんて言えばいいんだろ。同じトコだけど、ちょっと違う……そう、層が違うんだ。低いとこにいるのが悪いもので、その上にいるのがお兄さん。で、お兄さんが蓋をして押さえつけてる。でも全部は押さえておけなくて、漏れ出たやつが広岡サンの近くとか、両親の傍にいる」
「怪奇現象の発生は、その『あまり』が原因ってことか」
「まあ、平たく言えば。お兄さんはなんとかして妹を守ろうとしてるっぽいんだけど、ちょっと力が足りてないみたいだな。オレに警告してきたのも、仏壇の扉を物理的に開けちまうと押さえつけてたものが全部出てきちゃうからだと思う」
「……なるほど。見えてきたな」
「どういうことだ? なんかいいアイデアでも思いついたのか?」
「まあ聞け。お前、名付けの儀式はできるか?」
「えっ。いや、うーん……ごめん。無理かも。今まで霊力ゴリ押しで無理くりどうにかしてたから、儀式とか細けえ手順がいる祓いってしたことない」
ここでようやく勇次郎にできることとできないことがハッキリしてきた。見習いとして活動し始めてまだ日の浅い彼がどうやって祓いを行っているか疑問だったが、馬力不足の勇次郎がどんな手を使って霊力をブーストしているかは未だ不明ながらも、どうやら対象を直接的に修祓しているようだ。つまり霊力を単にエネルギーとして用いて強引に立ち退かせているということだ。
元がヒトではない百パーセント純粋な怪異、つまり本物の化け物は意思の疎通が不可能なので、場合によっては力ずくで対処しなければならないが、それはあくまで正攻法ではどうにもならない時の最終手段だ。基本的には交渉こそ祓いの基礎基本であり、相手に条件や利害を提示して穏便にお引き取りいただくのが「お祓い」である。真言や祝詞に代表する言霊はそのための補助であり、儀式は相手から譲歩を引き出すためのおもてなしだ。
針間一族が特殊なのは、前述のようなこの界隈における一般的な祓いをあまり用いないことである。要するに正攻法では解決できなさそうな案件を請け負い、言葉が通じない化け物を相手にするのが彼らの役目だ。他の霊能者が仲介やネゴシエーションを仕事とするなら、さしずめ針間は強行突破を担当する特殊部隊というところか。勇次郎にそれは荷が重いからこそ纏は術師の道を諦めさせようとしているわけだが。
できれば今回ばかりは針間式の祓いは避けておきたい。ほんの僅かであっても力加減を間違えた瞬間、確実に広岡さんのお兄さんにも影響が及ぶからだ。おそらく勇次郎はそうした細やかな力の使い方に習熟していないだろう。となると対策方法も色々と限られてくる。
「……なあオレちょっと思ったことあるんだけどさ、広岡サンの勤め先で起きている怪奇現象って、なんか変じゃないか? うまく言えないけどベタすぎるというか、いかにもって感じっていうか」
「ああ、言われてみれば確かに……演出がチープすぎるというか、どっかで見たようなって印象ではあるな。ホラー映画のよくあるシーンをそのまま模倣したような。何か学習元があるとか? よくあることと思って気にしてなかったけど、今回の一件における原因は土地の持つ性質に起因する厄だ。具体的でわかりやすい、目に見える霊障となることの方が稀だし、実際にお兄さんは怪死している」
「ユーレイや元人間のオバケがなんか悪さしてるって時は人が理解できる『こわい』出来事を引き起こしがちだからな。本物はそういう条理の通ったことはしねえ。今回は『犯人』と『犯罪』の性質がおかしい、食い違ってる。バケモンが人間の知るホラー映画とか小説だのを参考にするわけがねえんだ、だから変なんだよ」
「つまりミステリ風に喩えるなら、真犯人は別にいる……ってことか? 思いつくのは例の自殺した新入社員くらいだが」
「うーん……わかんねえ! ここまで色々推理してみたけど情報がなさすぎる。とりあえず今やれることをやってみるしかないだろ。他にどうしようもないし」
「それもそうだな。そろそろ夜も遅いし寝るか」
念のため、俺達が滞在する客間に雑霊や仏壇の中の何かが来れないよう勇次郎に軽い浄めの術を執り行ってもらったあと、四隅に盛り塩をしておく。結界というよりは現場に知らない誰かが勝手に侵入してこないよう、関係者以外立入禁止の看板を立てかけておくイメージだ。
オバケが必ずしも人間の理屈や常識を理解できるとは限らないため、こちらの意図が相手に伝わりやすいよう工夫する必要がある。こういうのは日本語の分からない人に日本語で話しかけても意味がないのと同じで、翻訳やジェスチャーを駆使するしかないのである。
目覚ましを日の出の時刻に合わせてセットし、ふとんに潜り込むとさっそく睡魔がやってきた。自覚していたよりもかなり疲労がたまっていたようで、特に夢も見ずぐっすり眠れた。
◆◆◆
──翌朝。いよいよ今日が本番だ。結局、正攻法でどうにかするのは難しそうだという結論になり、加えて大掛かりな儀式を今から準備して本日中に完了させるのも厳しいということで、いっそ「仏壇を開けてみる」という強硬策に打って出ることにした。内部にいる「なにか」を引きずり出し、無力化して散らす。それしか現状で実行可能な対策はない。
勇次郎曰く仏壇内には広岡さんの兄、有象無象の雑霊、元からこの地に溜まった邪気としかいいようのないものが、それぞれ混ざり合うことなく共存している状態なのだという。雑霊は滞留する邪気により呼び寄せられて集まってきたものなので、積極的に家人やその周囲にいる者達を害する意思はないようだった。ほとんどはお兄さんが重石となって抑え込んでいるが、漏れ出た一部が広岡さんに取り憑く形で悪さしていた、というのが今のところ考えられる怪奇現象の要因だ。
問題は、土地自体に長らく巣食うモノ……邪気そのものだという。全国各地に良くないものが溜まりやすい場所、俗にいう忌み地は点在しており、ここもそのうちの一つにすぎない。忌み地自体をどうにかするのは困難で、仮に土地の浄化を執り行ったとしても、また別な場所が何らかの理由で忌み地化してしまうだけだ。それそのものを失くすのは無理といっていい。
ではどうするか。理想的な手段としては、今ある仕組みをうまく利用するという方法だ。具体的には広岡さんの兄をこの家の守り神にしてしまうことである。彼は現時点で長い間家族を厄から守ろうとしてきた実績があるが、力量不足でどうしても取りこぼしが出てしまっていた。そこで神に祀りあげて位階を上げてしまえば、より強固な守りを確立できるはずだ。
だが、ここで一つ課題があった。儀式を執り行う本人である勇次郎に肝心の知識がないことである。更にもう一つ難点があった。彼女の兄を神として祀るということは、二度と人としてこの世に生を受けることはできなくなる、という意味を持つ。たとえ守護すべきものが残らず消えても役目からは逃げられず、永久に全うし続けなければならない。人としての記憶がすり減ってしまったとしても。果たしてそんな非道を元はただの人間だった存在に強いていいかといえば嘘だ。
そこで上記に戻ってくる。まず邪気とそれに集っている雑霊を追い出して散らし、一時的にこの家へ近づけないように結界を敷く。結界自体の強度を段階的に上げていき、忌み地と化している状態を改善する。仏壇という狭く限られた空間に閉じ込めるより全体的に邪気を広めることで濃度を下げ、雑霊や悪いものが集まりすぎないようにしつつ何十年、何百年単位で時間をかけ、徐々に浄化していくという試みだ。
日曜はいつもデイサービスを利用しており、寝たきりの両親は終日自宅にいない。朝食も施設で取るというので、迎えにきた職員に車で運ばれていくのを見届けつつ、揃って準備にかかる。といってもやることは居間の掃除と家財道具の片付けくらいなものだ。三人がかりなのであっという間に終わってしまい、お次は買い物である。
広岡さんの運転で近所のスーパーまで向かい、店内併設の花屋で仏花を購入し、このあたりの銘品らしい地酒と季節の果物もいくつか見繕う。帰宅後、炊きたての白米を茶碗に盛りつけ、カットしたフルーツと杯に注いだ地酒を御神酒代わりに供える。これで下ごしらえは完了だ。広岡さん本人には居間から退室してもらい、いよいよ仏壇を開ける時がきた。
「……準備はいいか」
「ああ。覚悟はできてる。よし、開けんぞ」
事前に持参してくるよう言いつけていた白一色の狩衣に袖を通し、黒染めした髪を括った勇次郎は、何度か深呼吸したのち仏壇の扉に手をかける。瞬間、目に飛び込んできたのはずいぶんと立派な遺影だった。彼女に見せてもらった入学式時の写真よりもいくぶんか成長した、目元の笑い皺が特徴的な優しげな顔立ち。少年と青年の境目にある、幼さがまだ少し抜けきらない輪郭。
彼こそが、死してからもずっと家族を守ろうとしてきたのだ。そして今も自分の死後に生まれた妹を気にかけ続けている。きっと彼はそこに「いる」のだろう、視える眼を持たない俺には決して見ることは叶わないけれど。勇次郎はある一点の方向を見つめ、問うた。
「ひとつ、アンタに確認したいことがある。アンタ神様になる気はねえか? この家の守り神だ。アンタの妹や、その更に弟と妹をこれからも守っていくためには、アンタ自身に力がなくちゃいけねえ。ただし神に祀り上げられたものは二度と輪廻に戻れない。そのまま消える運命にある。それに、アンタのことを知らねえ遠い子孫のことも、たとえアンタが気に入るようなヤツじゃなくても守らなくちゃいけない。それが役目だからだ。それでもいいなら、アンタを神様にしてやるよ」
もちろん勇次郎に今すぐそんな高難度の儀式が可能かというと無理なのだが、纏に頼めば話は別だ。彼は暴力的な最終手段を好むが、もちろん正攻法についても明るい。なんだかんだで弟に甘いところのある纏のことだ、頼られれば二つ返事で引き受けるに決まっている。あいつはそういう人間だ。しかし彼は、人の道を外れることを拒んだようだった。無理もない。俺が逆の立場だったとしても守り神なんて面倒なポジションは選ばないだろう。
「……そうか。人としてまた生まれ変わって、今度は一緒に家族として生きていきたいんだな。わかった。ごめん、無理なこと言って。え? いいよ、別に。オレも本当は、アンタにもちゃんとまた人間として生まれ直す権利があると思うから──始めるぞ」
ざわり、と周囲の気配が変わった。朝日の差し込む爽やかな空気に満ちていた室内が、妙に薄暗く感じる。大気に重力があるとしたらきっとこうだろう、というような目に見えない重みが両肩にのしかかり、まともに立っていられない。夏場なのに半袖から覗く肌は冷えきって、鳥肌まで立っている始末。突如襲いかかる悪寒と吐き気に、その場へ倒れ込みそうになるのを堪えるので精一杯だ。
これほどのプレッシャーを与えてくるものとは一体なんだ。古戦場跡のような霊場へ行ったとしてもここまで酷い霊障にかち合うことはない。長い時間をかけて仏壇に蓄積されていった邪気がいきなり解放されたことで、ここまで急激に状態が悪化したということか。胃の中身を吐き戻さないよう口元を押さえながら視線を向けると、きつく眉根を寄せ、顔を紙のように白くした勇次郎が視界に飛び込んできた。
「……ッ、勇次郎!? オイどうした!?」
「おかしい……いない! なんでだ、絶対にいたはずだ、ここに、『あれ』が!」
「ハア!? 『あれ』ってなんのことだよ、まだなんかあんのか、何も聞いてねえぞ!」
「あ……そっか、アンタ視えてねえのか、ちくしょう、ここに確かにいたはずだ、広岡さんが!」
「……は? お前さっきから何言ってる、広岡さんならとっくに別室に」
「ちげえ、それは生きてる方のだ。死んでんのがもう一人いただろ、自殺したっていう社員が! そいつが、さっきまでずっとここに」
「話が読めない……お前、一体何が視えてたんだ?」
「説明してる暇がねえ、あとで全部話す! 一旦これをなんとかしなきゃなんねえ、悪いがちょっと『借りる』ぞ」
何をだ、と訊き返す間もなかった。前触れもなく突然勇次郎は俺の胸ぐらを掴むやいなや、唇を合わせたかと思えば舌を噛みちぎりやがったからだ。だらりとこぼれた血を舐め取り、挙句の果てに不味そうに顔を歪める少年のなんと失礼なことか。せめてもう少し味わえよ。
狩衣の袂から取り出した呪符を手に、勇次郎はまだ流暢とは言いがたく覚束ない口ぶりで、なんとかギリギリつっかからずに「大祓詞」を唱える。迷ったらとりあえずコレという感覚で何かと使い倒されることの多い祝詞だが、実際効果は抜群だ。間欠泉のごとく湧き出ていた邪気の湧出がだんだんと勢いをなくし、全身にまといつく怖気や威圧感が少しずつ失せていく。
杯の中の御神酒を少量だけ室内にぶちまけ、ついでに粗塩を少々ふりかければ簡易的な浄めは終わりだ。全く祓いに必要な霊力がちょっと足りないからって急に奪ってこないでほしい。俺自身はただの徒人なので、差し出せる霊力だってほんの僅かだ。邪気による吐き気や悪寒はとっくに治まっていたが、心臓破りの坂を激走したときのような疲労のせいでもう一歩も動ける気がしない。
「はぁ、はあっ、ハア……クソ、おい今度こそ説明してくれるんだろうな!」
「う。……はい。まずもう一人の広岡さんについてだ。例の自殺したってやつだな。こいつはここの広岡家の人間じゃない、別な広岡さんだ。この辺一帯は、みんな同じ『広岡』なんだと思う、たぶん」
「……あー、なんとなく話が読めてきた。つまり「昭和の始め頃に越してきた」ではなく、広岡一族が別な土地からこの地に移り、村を作ったということか。彼らは『よそさん』じゃなかった。社長室のネームプレート、それに死んだ新入社員が彼女と同じ苗字なのも当然だ」
「本当のよそ者は、会社を牛耳っていたようにみえた御局様ってことだな。あの人は確か名前が違ったよな、安田っていったっけ」
「ああ。けど新入社員は自分が『広岡』であることは内緒にしてたんだろう。だから相手が手を出してはいけない人間だと御局様は気づかなかった。パワハラに耐えかねた彼女は自死を図り、死後に御局様への復讐を始めた。それが社内の怪奇現象だ」
「……同じ苗字を持つということはある意味、運命を共にするにも等しい。一つの広岡に不穏が起これば、他の広岡一族にも連鎖し波及する。ただでさえこの家は忌み地にあるんだ、及ぶ影響は尚更デカいだろうな」
「同じ広岡なのに扱いに差がある理由は分からんが、家の造りをみるに担当者が決まってるんだろう、どの家がここを抑えておくか。この一家がなぜその役目を引き継いだかまでは分からんが、とにかくしばらくは上手くいってた。でもいつまでも続けられることじゃない。忌み地の管理はオレらのような人間と協力して行うものだ。徒人が独学でどうにかできることじゃない」
「……話を戻すぞ。新入社員は自分を自殺に追いやった御局様を恨んでるだろうし、まだ復讐の途中だろ。完遂させたらまずい、地獄に堕ちてしまう。その前になんとかしないと」
「まだ気になることが一つある。広岡サンは同族婚をさせられそうになってた。社長の息子とかいうやつと。そして新入社員はお妾さん候補としてコネ入社してきた。実際にはどっちも成功してないけど、なんで社長一家は広岡サンと広岡さんに目をつけた?」
「三つの広岡には繋がりがある……? それに、なぜ死者の広岡さんが仏壇に?」
「それはたぶん、ここに呼び寄せられたんだと思う。忌み地って霊的なものに対する引力が桁違いに大きいだろ? 日頃はここにいて、もう一人の広岡サンを使って会社に移動してたわけ。だから社内に本霊の気配はなかった。根城はあくまでここだからだ。寄り集まった霊は忌み地に留まり続けるけど、御局様への嫌がらせって目的があったから、自分と同じ苗字の生者に惹かれて一時的に離脱できたんだな、きっと」
「……でも、強制的に吹き溜まった邪気ごと全て散らした以上、そいつはここじゃないどこかへ向かっている。なんとかしないと御局様まで死ぬぞ」
まだそんなに遠くへ行ってはいないはずだ。死者となり時間や空間の軛から外れたとはいえ、霊の意識が人から完全に離れきっていないうちは瞬間移動や壁抜けのような真似はできない。元々の常識や知識がストッパーとして働くからだ。フラフラになりながらもどうにか立ち上がり、さっさと狩衣を脱いで私服に着替えた勇次郎と共に玄関を出ようとしたそのとき、広岡さん──生きている方が別室からこちらへ出てきた。
「……あのっ、お二人とも! わたしが送ります。ここまでずっとお世話になっているのですから、見送るだけなんてとてもできません」
「えっ、ああ……助かります。でも、危ないかもしれないですよ」
「さっきの方がよっぽど怖かったですよ。見えないし、聞こえないけど、すごく嫌な感じが続いていて……でも今はなんだか少し、家が明るくみえます」
まだ事態は何も解決していない。土地の浄化が終わらない限り、広岡家の敷地が忌み地として災いを招き続けることには変わりないし、強引に散らした邪気や雑霊だって時間が経てばまたここに集まってくるだろう。でも今は確かに彼女の言う通り、ほんのちょっとだけ一帯が、雨上がりの空のように眩しく映った。水気を含んだ風がそよぎ、僅かな邪気の残滓をも吹き飛ばしたように感じられ、改めてこのままでは終われないと思い直す。
勇次郎の誘導と彼女の運転する車で向かった先は、昨日も訪れた広岡さんの勤め先だった。前回来訪時と違い、社屋はどこか禍々しい気配に満ちている。霊感があってもなくても肌感覚でなんとなく察せられてしまうほど、今のこの場所は危険だ。全員で入るか入らないかの問答の末、結局彼女には送迎のために車内で待機していてもらい、俺達二人だけで踏み込むことになった。
「それにしても、なんであの霊はここに向かったんだろうな。狙いは御局様なんだろ、ならそいつの居る場所へ行きゃあいいのに」
「霊ってのは人間ほど自由に動けないんだよ、会いたい人のところに行くためには、何か別なものを経由しなきゃならない。だが縁を持たない御局様のところに行きたくても足がないんじゃ無理だ」
幽霊は足がない姿で描かれることが多いという。しかしそれは物理的な足の有無を意味しているのではない。彼ら彼女らは自分と深い繋がりを持つ物、場所、人間の元へしか行けないようになっている。己と縁のある人や場所といったものに執着するのもそのせいだ。他に行くところがないから留ならざるを得なくなっている。
祓いとは、そうした行き場を失くした霊に本来行くべき場所まで導くことを言う。ひとが最後に向かうところまで案内し、道を指し示し、見送ることが仕事だ。だからこそ祓いにおいてコミュニケーションこそが最も肝要であり、無理やり立ち退きを迫ればいいというものではない。そんなのはただの地上げ屋である。
本来の目的とは違う、慣れ親しんだ職場へと彼女が向かったのも、ここが最も強い縁を持つ場所だからだ。実家あるいは自宅も同じくらい縁があるとはいえ、今回は関係ないから行先に選ばないだろう。となると消去法でここが彼女の目的地ということになる。実際、先ほど弾き飛ばした邪気ごとここへ来ているせいで、昨日とは大違いの酷い瘴気が渦巻いているようだった。
エントランス、一階のオフィス、応接室、給湯室、物置にはいない。やはり二階の社長室だろうか。階段を駆け上がり、ドアが開けっぱなしになっていた部屋へと飛び込むと、半透明に透ける人影が突っ立っていた。腰まで届きそうな長い髪に、ほっそりしたシルエット。くるりとこちらへ振り向いた、温度のない表情は、どこかもう一人の広岡さんの面影を微かに残していた。
「別に怒ってないんです。あのおばさんに大しては。だって安田さんって元々はこの村の人じゃないもの。あの人、社長の妻だからって大きな顔ができてるだけで、一歩会社を出たら誰にも何も言えなくなるんだから。あんな人に今更どうこうしようなんて気はありません」
勤務時の衣服か、彼女はシャツにベストとタイトスカート姿だった。おそらくこの会社の制服だろう、ベストにはネームプレートが取り付けられていて、やはり「広岡」という苗字だった。未確認だが、一階のデスクにもそれぞれ同じ名前のプレートがあるはずだ。ここでは御局様一人だけが「よそもの」なのだろう。
まだ若く、新入社員である彼女の方が、ある意味では立場が強いのかもしれない。広岡一族が作った村の一員である以上は。では御局様と周囲に呼ばれるほどの権勢が安田なる人物にあったかというと微妙なところではないだろうか。社長の妻だからといって偉そうな態度が許されるかというと、ちょっと疑問である。
「では、なぜあんなことを。それに自死だなんて」
「だって生きていたら呪いなんてかけられないじゃないですか。あの家、見たでしょ? あれほどの淀みをモノにするには、人のままでは無理……なのにあの男、いつもいつも邪魔ばっかりしやがって! だから今回助かりました、あいつを追い出してくれて。これで全てあたしの思うがままにできる!」
「……あんたの狙いは社長とその息子か! どうりで夫婦関係にあるのに苗字が違うと思った、御局様はいわゆる内縁の妻なんだろう、そして社長の息子の『正妻』が広岡さん……あんたは社長の息子と結婚する手筈になっていた。だが、何らかの理由でできなくなった。それは」
「あたしが一番って言ったくせに! 他にも女がいるなんて聞いてない! 何が『夫婦関係は冷めきってる』だよ、ふざけんな! ナメるのも大概にしろ! あいつも、このクソオヤジも、どっちも許さない……殺してやる……みんなみんな、ぶっ殺してやる!」
最も嫌なパターンを引いてしまった。痴情のもつれが原因だとすると厄介だ。恋愛関係を起因とする嫉妬、憎悪、怨恨、殺意といった負の感情からくる霊障は長引く上にタチが悪い。同じ苗字でも既に血筋がそれぞれ分かれているがゆえに起きた出来事が、事態を更に複雑なものにしている。広岡さん自身はあくまで書類上の妻というだけで、夫婦としての実態がないだけに余計に。
だが彼女は紙の上の結婚すらも許せなかった。法律上の妻が自分より年上の女性であることも、社長の息子が彼女から怒りを買った理由の一つだろう。性欲発散目的の遊び相手にされたと本人から思われても仕方ない。仮に本気なら広岡さんとの婚姻関係は解消しているはずだ。そしたらこんな面倒くさい状況になっていない。この場にいない両名に対しムカムカしてくるが、とはいえ彼女の殺意を完遂させるわけにもいかない。
今更だが、彼女が社長一家の元へ行けず、会社まで乗り込むしかなかったのも、彼女がどれほど軽んじられてきたかを物語っている。そこに縁がない、だから行けない。縁がないのは、生前彼らが決して寄せつけないようにしていたからだ。関係は全てこの会社の中で完結していた。二人でどこかへ出かけることもなく、恋人らしい時間などもろくに与えられてこなかったのだろう。
男はどちらの女もどうでもよかった。だから平等に酷い扱いをしてきた。それはおそらく、父もまた内縁の妻を軽んじていたのを見て育ってきたから。他人に対するそういう振る舞いがきっと許されてしまう家に生まれ、特に疑念を抱くこともなく鵜呑みにし、何も考えず実行に移した。現実はどうだか分からない。実際に二人をこの目で見たわけではない。全て想像で、いわば邪推でしかない。でも。
「……アンタの言い分は分かった。その恨みつらみも理解できる、とまでは言えねえけど、分かってやりたいって思ってる。けど、オレはその上でアンタに言いたい。道を示すから、向こうに行こう、って」
「ハア? このまま何もせずに死ねって言うの、もう死んでるのに、また死ねって、あなたはそう言うの! 酷い人ね、あたしは絶対許さない、絶対殺してやる……そのために命を懸けたんだから!」
「ダメだ! それだけは絶対ダメだ、それをやったら逝けなくなる、行かなきゃいけないところに辿り着けなくなる! その先は、地獄だ。アンタはどこかへ行きたくてもどこへも行けずに、この世を彷徨い続けることになるんだ、還る場所もなくなっちまうんだぞ! そんなの嫌だ、アンタが良くたって、オレはいやだ。だから頼むよ、お願いだ、向こうに行こう。案内するから」
「やだ……やだっ、その手には乗らない、乗らないんだから! うるさい、もううるさい、所詮あんたらは外野でしょ、あっち行ってよ、邪魔しないでよ!」
長い髪を振り乱し、イヤイヤとむずがるように頭を激しく揺さぶりながら叫ぶ彼女は、ずいぶん混乱しているようだった。心なしか辺りに満ちる禍々しい瘴気が薄れ始めているように感じられるが、これはもしかしたら彼女の迷いが反映されているのかもしれない。
目の際から伝い落ちる涙は、けれど床にこぼれることなく空気に溶けて消えてゆく。死者となった瞬間から、ひとはこの世にどんな足跡も残すことはできなくなる。たとえ霊障や怪奇現象を引き起こしたとしても、それで気づいてもらえるケースは非常に稀で、見鬼を持たない徒人では決して彼ら彼女らを見つけてやることはできない。そうしていつか死者の記憶すら、大いなる時間の流れによって風化し忘れ去られてゆく。
だから。だから、彼らがいる。そして俺がいる。そこで確かに生きていた「誰か」のことを書き残し、忘れられたとしてもまたいつか思い出せるように。
「ちゃんと伝えます。みんなが忘れないように。忘れたとしても思い出せるように。あなたがここに居たことを、あなたが生きていたことを。だから行きましょう、彼が行くべきところまで送ってくれますから」
「……ほんとに?」
「ええ。本当です。そのために俺はここへ来た。ここで起きたこと、ここで体験したこと、ここで生きていた人のこと、その全てを書き残すために。これからも、色んな人、色んな場所、次に体験するであろう出来事、その全ても。だから行きましょう」
「……なら、いっか。もう、べつに」
微かに笑ったその顔は、生きているもう一人の広岡さんとよく似ていて、彼女は本当はこんなに穏やかに笑える人間だったのだということを教えてくれる。勇次郎が片手を差し伸べ、もう片方を天上へ向けて指し示す。目の前の手のひらを取った彼女の姿が、だんだんと空気に溶けていくように透けていき、やがてささやかな光の粒と化して消えていった。ようやく終わったのだ。
「……帰ろっか」
「ああ。もうここでやるべきことはなくなった。東京に帰らないとな」
社屋を出ると、もう一人の広岡さんがわざわざ車から出て待っていた。よほど心配していたのか、初めて会った時と比べると十歳くらい老け込んでいるようにみえる。終わりましたよ、と報告すると、彼女はその場に膝から崩れ落ち、両手で自身の顔を覆った。時折漏れ出る嗚咽は、風にさらわれていく。
「……そうですか、やっと」
「ええ。彼女はちゃんと行くべきところへ行かれました。正直、正面からのぶつかり合いになったらこちらは打つ手がないので……素直に応じてもらえて僥倖でした」
「とっくに、もう全て知っているんですよね。黙っていてごめんなさい、どうしても、言えなくて……誰にも知られたくなかったんです、疚しいことだと分かっていたから」
「あなたは手紙で意図的に伏せていたんですね。あなたともう一人の彼女が、それぞれ同じ男性と関係していることを。『自分のせい』とは思いたくなかった、あるいは分かっていたけど認めたくなかったのか、そのどちらなのかは分かりませんが」
「仕方がなかったんです。あの土地の管理を言い渡された時点で、わたしは外へ出て働くことなんかできません。でも、ここにはろくな仕事なんてありません。年老いた両親のためにも働かなくちゃいけない。コネだろうがなんだろうが、仕事が見つかるならそれでよかった。だから実際ちは関係を持たないという契約で、わたしは婚姻届にサインしました。なのにあの人は、それを伏せて彼女と関係を持つようになって……」
「……あなたが謝る必要はない。もう全て終わりました。全て済んだことです。それでも心残りがあるなら、どうかお兄さんにその気持ちをあげてください。彼は、ずっとあなたを案じていた。あなたを守っていた。今も、あなたの笑顔を待っている」
「兄が……わたしは、兄の顔もろくに覚えてない、妹だった記憶もないのに。なのに、それでも」
「……お兄さん、アンタとまた家族になりたいんだって。だから待ってるって言ってた。次こそ、また同じ家族として生まれて、一緒に生きたいって。守り神として家を守っていくこともできるよって勧めたけど断られちまったよ、一人だけ先に行って、置いてくのも、置いてかれるのも、もう嫌なんだってさ」
「兄がそんなことを……わたしなんかのために。わたしは今まで、兄になんにもしてあげられなかったのに……お二人とも、ありがとうございます」
「いや、オレらは別になんもしてねえよ。丸く収まったとしたら、それはあのお兄さんがめちゃくちゃ頑張ってたからじゃん? ってことでそろそろ帰るわ」
「そうだな。ここに残ってももうやることはないし。すみません、慌ただしいお別れになってしまって」
ゆっくりと立ち上がった彼女は、目尻に溜まった涙を拭い、穏やかに微笑んでいる。
これからやってくる夏を思わせる、熱気を孕んだ風が吹き渡り、周囲に広がる田圃の稲を揺らす。嘘みたいに綺麗な快晴の空から、眩い日差しが差し込んで、目も眩んでしまいそうだった。
◆◆◆
今回の顛末を(個人を特定できる情報などを伏せた上で)連載中の祓い屋シリーズ番外として記事にまとめ、編集部に送る。「忌・怖」は季刊誌なので次に発刊されるのは来月のことになるが、果たして読んでもらえるだろうか。他にも書きかけの記事や依頼原稿があるので、自宅にこもって仕事していると、慣れ親しんだ番号から着信がかかってくる。
そういえば纏にこの件について何も報告してなかったことを思い出す。どうせ勇次郎のやつは兄に連絡なんかしないだろうし、きっと首を長くして俺からのメッセージを待っていただろう。内心冷や汗を掻きつつ電話に出ると、案の定声色だけで人を呪い殺せそうなひっくい重低音が電話口から聞こえてきた。
「……聞いてないぞ。あんな危険な目に遭ってるなんて」
「え? 発行はまだ先なのに読んだのか? もしかして沢渡さんがお前に入校前のデータを送ったりしたのか?」
「私が! 直接! 編集部に行って読ませてもらったんだ、お前が何も言ってこないから!」
「うわ、マジか。あとで菓子折持って編集部に謝りに行かねえと」
「その前に私に謝罪すんのが筋だろーが! おい、お前という人間がありながらウチの末っ子を危ないことに巻き込んでんじゃない!」
「行く前は痛い目見てほしそうな口ぶりだったくせに……」
「それはそれ! これはこれ! ったく次はないからな、次は……やっぱりあいつに術師は向いてない、なんだあの荒っぽい雑な仕事は。アレで祓いのつもりか、片腹痛いわ。あれに針間の名前は継がせられん」
「素直じゃねえなあ、もう。初心者にその物言いってことはそれだけ期待してたんだろ、内心でよくやったくらいに思ってるくせに。……ところで一つ聞きたいんだが」
「ああ? なんだよ」
──十秒後。俺から「あること」を聞かされた纏は、鼓膜が破れるんじゃないかという大音声を張り上げた。
「な、な、な……なんだと、うちの子に男ォ!? ハア!? 聞いてない、聞いてないぞ! 誰だその馬の骨はァ!! 許さん、絶対にッ、許さんからな! 認めねえからな!! あいつに彼氏なんか百年はやーい!!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

