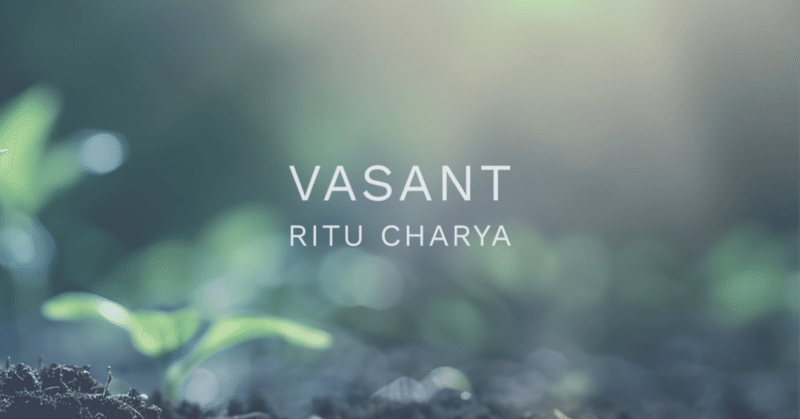
【 アーユルヴェーダ的季節ごとの養生法 - Vasant 】
「リトゥチャリヤ」という言葉を聞いたことはありますか?
アーユルヴェーダでは、季節を意味する「リトゥ(Ritu)」と規律を意味する「チャリヤ(Charya)」という 2 つの言葉から成り立つ、古代から実践されてきた季節ごとの養生法のことを意味します。
リトゥチャリヤでは季節を約2ヶ月ごとに6つに分けて考えます。
・Shishir(シシーラ)1月中旬〜3月中旬
・Vasant(ヴァサンタ)3月下旬〜5月中旬
・Grishma(グリシュマ)5月下旬〜7月中旬
・Varsha(ヴァーシャ)7月下旬〜9月中旬
・Sharad(シャラト)9月下旬〜11月上旬
・Hemant(ヘマンタ)11月中旬〜1月上旬
今回は、上記の中から今の時期にぴったりな「Vasant(ヴァサンタ)」の過ごし方 について書いてみようと思います。
日本では、3月下旬から5月半ばくらいにあたる「 Vasant (ヴァサンタ)」と呼ばれる時期。凍れる冬がゆるみ、雪が溶け、陽の光も眩くなり、あちらこちらで花が咲き始め、植物が芽吹く季節です。
「Shishir(シシーラ)」の時期に増加したセマ(インドのアーユルヴェーダではカパ)のエネルギーは、春の太陽の熱によって液化します。 それは消化の火(アグニ)を弱め、セマ関連の多くの不調を引き起こす要因となります。
セマは、「水」と「地」のエネルギーで体の保水や構成を担っています。春を迎える前に冷たいものや消化しにくいものを多く食べたり、眠りすぎたり、運動不足になっていたりすると、セマの蓄積により体の重だるさやむくみ、鼻炎などの過剰な粘液の分泌といったセマ関連の不調が出てきやすくなります。また、寒くて乾燥した冬の天候から暖かく湿気の多い春の天候への移行により、元々セマが強い体質の方は、油分の増加やニキビや炎症などの肌荒れの症状が増えてくる方も少なくありません。精神面では、眠気が強かったり、ぼんやりしたり、やる気が出なかったり、不活発な症状が表に出てきます。
したがって、この時期にはセマのエネルギーを出来るだけ鎮静させる必要があります。
ちなみにアーユルヴェーダ発祥の地・インドでは、ちょうどこの時期に「 Vasanta Navratri (ヴァサンタ・ナヴァラトリ)」※ というヒンドゥー教のお祭りがあります。毎年春の初めと秋の初めに開催される、ドゥルガー女神の9人の化身を祀る9日間のお祭りで、その期間に断食をする習慣があります。断食といっても、水も飲めない断食ではなく、決まったものしか食べないという方が多いとか。でも断食をすると断食前にあった体の重だるさやむくみがスッキリし、また食べるものも消化の早い食べ物ばかりなので胃腸が軽くなり、水分が抜けて体の調子がとても良くなるそうです。暑い季節になる前に冬の間に蓄積したセマのエネルギーを排出してバランスを整えるという理に適った習慣なのですね。
※ Chaitra Navaratri(チャイトラ・ナヴァラトリ)とも呼ばれています。

Vasant の季節にこのナヴァラトリが開催される。
この話を聞いて、インドの風習にはアーユルヴェーダの理論が深く根付いているんだなぁとあらためて思いました。ますますアーユルヴェーダやインド・スリランカ文化への探究心が止まらなくなりそうです。前世はきっとインドかスリランカで生きていたのかな?と最近よく思います。笑
少し話が逸れましたが、セマのバランスを整えるには、消化しにくいもの、冷たいもの、脂っこいもの、塩分の強いもの、酸っぱいもの、甘いものを控え、苦味・渋味・辛味を積極的に摂取しましょう。日本の春野菜はまさにセマの鎮静に良いものばかりです。菜の花や春菊、山菜類(たらの芽やふきのとう)、小松菜、かぶなど、春が旬の野菜は自ずと苦味や渋味が多いもの。きっとこれも自然の摂理なんですね。また、消化に時間のかかる乳製品や小麦製品も控えることをお勧めします。日中の睡眠も避け、 早寝早起き、体操、ドライマッサージ、適度な運動なども意識して過ごしましょう。

季節や自然の流れに体をひたすことこそが宇宙の一部である人間が心身共に健やかに生きることなのではないか・・とアーユルヴェーダを学んでいると結局いつもそこに行き着くのでした 🌱🌱
この記事が、読んでくれた方の健やかな日々へ
少しでもお役に立てたら幸いです。
ambara Director
Miu
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
