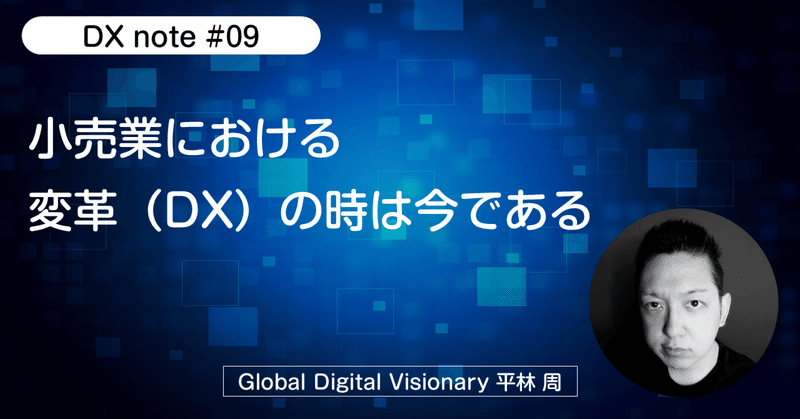
小売業における変革(DX)の時は今である
小売業におけるデジタルトランスフォーメーションの必要性
小売業界は、アマゾンのようなeコマース大手の台頭と、デジタル体験に対する消費者の期待の変化により、かつてない混乱に直面している。伝統的な実店舗型小売企業にとって、包括的なデジタルトランスフォーメーションに取り組むか、あるいは時代遅れになるリスクを負うか、という命題は明確である。
本章では、デジタルトランスフォーメーションとその構成要素を定義し、その緊急性を高める市場トレンドについて説明し、小売企業が達成できる主なメリットを概説し、十分なスピードで変革しない場合の多大なコスト(代償)について警告をしていく。
デジタルトランスフォーメーションの定義
「デジタルトランスフォーメーション」とは、具体的にどのような意味を持つのか?基本的なレベルでは、スマートフォン、ウェブサイト、ECプラットフォーム、クラウド・コンピューティング、データ分析、人工知能などの新しいテクノロジーを採用することである。
しかし、単にバラバラのテクノロジーを導入するだけでは不十分だ。真のデジタルトランスフォーメーションには、進化する消費者のニーズを中心に、ビジネスモデル、戦略、プロセス、オペレーション、文化を根本から見直し、デジタルファーストで再構築することが必要である。
小売業のデジタルトランスフォーメーションの主要な構成要素には、以下のようなものがある。
①デジタルチャネルとリアルチャネルを統合し、シームレスなオムニチャネル体験を提供する。
②データとインサイトを活用して顧客を深く理解し、エンゲージメントをパーソナライズする。
③フルフィルメントとロジスティクスを確立し、柔軟な配送を可能にする。
④製品だけに頼らず、デジタル・コンテンツ、サービス、エンゲージメント・ツールを創造する。
⑤実験とリスクを厭わない、機敏で革新的な企業文化の育成。
変革にはさらに、アナログ時代に構築された硬直した組織構造やサイロ化したシステムを解体する必要がある。マーケティング、eコマース、テクノロジー、アナリティクス、サプライチェーン、店舗運営などの機能は、より緊密に統合されなければならない。目標は、絶え間ない変化と実験を受け入れるのに十分な俊敏性を備えた、柔軟で協力的な環境を作り出すことだ。
Amazonに見る先進的な事例
アマゾンのような先進的な事例は、デジタルトランスフォーメーションが、明確な終着点を持つ1回限りの取り組みではないことを示している。絶え間なく高まる消費者の期待を先取りするためには、継続的にビジネスを改革していく必要がある。立ち止まることは、遅れをとることに等しい。
このような全体的な変革は、アマゾンのようなプレーヤーによって激変した環境において、小売企業が競争に打ち勝つための力となる。アマゾンの台頭は、デジタルトランスフォーメーションに十分に取り組まなかった場合に何が起こるかという教訓を与えてくれる。ブロックバスターは、ネットフリックスがビデオレンタルを変革したときに倒産した。シアーズとトイザラスは、アマゾンが小売を再定義した後、店舗を閉鎖した。
今日、アマゾンは米国のeコマースの40%近くを占め、食料品やヘルスケアといった新しいカテゴリーを破壊し続けている。一方、ShopifyやInstacartのようなイノベーターは、新たなデジタルの脅威を可能にしている。消費者の期待は一変し、迅速、無料、便利なショッピング体験を求めるようになった。従来の小売企業が生き残るためには、大規模なデジタルトランスフォーメーションが必要だ。
小売業のデジタルトランスフォーメーションを成功させるメリット
①売上の向上
デジタルトランスフォーメーションを成功することで、莫大な利益がもたらされる。
②顧客体験の向上
パーソナライズされたエンゲージメント、モバイルの利便性、インタラクティブなデジタル環境。
③オペレーショナル・エクセレンス
プロセスの合理化、サプライチェーンの可視化、ワークフローの自動化(業務効率を向上させることで競争優位性を獲得する)
④データ主導の意思決定(データドリブン)
アナリティクスと実験によるリアルタイムの洞察。
⑤オムニチャネル体験
物理的およびデジタルなタッチポイントを通じた一貫したカスタマージャーニー。
⑥新たな収益の流れ
デジタル製品/サービス、サブスクリプション、ダイナミックな広告ターゲティング。
⑦組織の敏捷性
迅速なイノベーション、市場投入の迅速化、フェイルファスト文化。
⑧将来の回復力
テクノロジーと消費者行動の進化に継続的に適応する基盤。
つまり、デジタルトランスフォーメーションを適切に行うことで、小売企業はデジタル機能と人間的なつながりをシームレスに融合させ、比類のない顧客体験を提供できるようになる。
逆に、トランスフォーメーションが遅れている企業は、デジタルの破壊者によって形成された消費者の期待に応えるのに苦労するだろう。オムニチャネルのフルフィルメントを実現するサプライチェーンインフラ、パーソナライゼーションのための強固なデータ、継続的に反復するアジャイルな企業文化が欠如している。こうした欠点は競争力を著しく低下させる。
無策がもたらす脅威
デジタルトランスフォーメーションの失敗がもたらす脅威には、次のようなものがある。
①関連性の低下
消費者がより便利な代替品に移行するにつれ、ブランド価値とロイヤルティが低下する。
②市場シェアの喪失
電子機器、衣料品、食料品などの主要セグメントを、オンライン の敏捷な競合他社が切り崩す。
③売上の減少
デジタル化の進展に伴い、実店舗の売上が停滞または減少。
④利益率の圧迫
肥大化した諸経費、高い在庫、非効率なオペレーションに関連するコスト増。
⑤体験価値の低下
タッチポイント間の一貫性がなく、バラバラなカスタマージャーニーがフラストレーションにつながる。
⑥データの欠点
統一された顧客データと取引データの欠如がパーソナライゼーションを妨げる。
⑦人材の流出
デジタルに精通した人材が集まらない。
⑧存続リスク
消費者がオンラインに移行するにつれ、徐々に関連性が薄れ、戻ることのできない地点に到達する。
ブロックバスター、シアーズ、トイザらスは、市場の変化に対応するのを長く待ちすぎた。レガシー・プロセスが破綻し、業績が急降下したため、破綻は避けられなくなった。硬直化したビジネスモデルが壊れる前に適応することが重要だ。
変革を必要とする市場トレンド
小売業とテクノロジーのいくつかのマクロトレンドは、積極的なデジタルトランスフォーメーションを必要不可欠なものにしている。
・アマゾン効果
アマゾンの利便性、品揃え、低価格への執拗なこだわりは、あらゆる小売カテゴリーにおいて、消費者のEコマースへの期待を高め続けている。
・モバイルコマース
消費者は現在、デジタル利用時間の大半をスマートフォンで過ごしている。小売企業は、これらのデバイス向けに体験を最適化する必要がある。
・パーソナライゼーション
強力なデータ分析と人工知能により、高度にパーソナライズされたマーケティングと体験が可能に。一般的なマス・マーケティングはもはや通用しない。
・オンデマンド・エコノミー
Uber、Amazonプライム、フードデリバリー・サービスによって、消費者は即座に満足することを期待するようになった。小売企業は、配送スピードと柔軟性を実現しなければならない。
・実店舗の縮小
Eコマースのシフトは、特に大型小売店において、実店舗の閉鎖を促進し続けている。残された店舗は、デジタル機能を融合させる必要がある。
・体験型小売
オンラインショップが商品をコモディティ化する中、消費者はますます体験を重視するようになっている。小売企業は、店舗内で魅力的なデジタル拡張機能を提供する必要がある。
・コグニファイド・コマース
会話型アシスタントのようなAIを搭載したインターフェースが、より没入的で文脈に即したコマース体験を可能にする。
これらのトレンドが示すように、消費者の期待は常に変化している。デジタルを活用した自己改革に失敗した小売企業は、その変遷に直面することになる。真の変革には、派手なテクノロジーを導入するだけでなく、根本的なビジネスモデルの再構築が必要なのだ。
デジタルトランスフォーメーションの成功要因
小売業のデジタルトランスフォーメーションを成功に導く具体的なステップとはなにか?各組織の変革の道のりはそれぞれ異なるが、共通の戦略的柱は存在している。
・オムニチャネル体験
実店舗とデジタルのタッチポイントで一貫したブランド体験を提供する。オンライン購入や店舗での受け取りなど、柔軟なフルフィルメント・オプションを提供する。モバイルアプリ、ウェブサイト、ロイヤリティ・プログラムを一貫したエコシステムに接続する。チャネル間の境界線を曖昧にし、デジタルとフィジカルのハイブリッド・ジャーニーを実現する。
・デジタル化された店舗
体験型ショールームおよびフルフィルメント・ハブとしての店舗の活用。AR/VR、スマートミラー、ビーコンなどの店内デジタル技術の導入。店舗スタッフにデータインサイトとデジタル販売ツールを装備。ハイパーローカル・データに基づく商品選定の実現。
・統合データ
チャネル横断的なデータを集約し、顧客と業務に関する単一の統合ビューを実現する。クラウドプラットフォーム上に一元化されたデータインフラを構築。アナリティクス、機械学習、AIを適用してインサイトを導き出す。価格設定、在庫、マーケティング、サプライチェーンにわたるデータ主導の意思決定を可能にする。 (データドリブンの実現)
・テクノロジーの近代化
レガシーシステムからクラウドネイティブなコマースプラットフォームへの移行。読み込み速度の速いモバイルアプリとプログレッシブWebアプリを優先。ヘッドレスアーキテクチャの採用による柔軟性の向上。エコシステムへのシームレスな統合のための全システムのAPI化。サプライチェーン全体でIoTセンサーなどを活用し、可視化を実現。
・オペレーションの刷新
予測データを活用して在庫とサプライチェーンの俊敏性を最適化。調達、物流、フルフィルメントのワークフローのデジタル化。店舗、ダークストア、サードパーティを活用した分散型フルフィルメント・ネットワークの導入。サプライチェーンの各段階における完全な可視化と追跡を実現。
・敏捷性の文化
データのサイロ化を解消し、製品チーム体制に移行する。迅速なプロトタイピングから継続的なデプロイメントまで、テストと反復のアプローチを促進する。イノベーションの前提条件として失敗を受け入れる。ビジネスとテクノロジーのハイブリッドスキルを持つ人材を優先する。インパクトのあるプロジェクトを特定し、実行する権限を社員に与える。
デジタル変革の成功例
ここからはこれらの柱を実行して成功した小売企業の事例と、失敗の教訓を探ってみる。
①ウォルマート(~2021年までの情報)
ウォルマートは、その巨大な物理的フットプリントを、負債ではなくデジタルのアドバンテージに変えた点で傑出している。取り組み内容は下記の通り。
・オンラインでの品揃えを積極的に拡大し、7,500 万 SKU を超える。
・フルフィルメント・ハブとして店舗を活用するため、オンライン注文の店舗受け取りを対応している。
・ボノボス(Bonobos)、モドクロス(Modcloth)、ムースジョー(Moosejaw)といったデジタルネイティブ・ブランドの買収。
・サードパーティーセラーのためのオンラインマーケットプレイスの構築。
・Eコマースに特化した大規模な自動フルフィルメントセンターの構築。
・AIを活用したレジなし店舗の試験運用。
ウォルマートはまた、デジタル・イニシアチブを実現するために、テクノロジー・スタックとオペレーションを全面的に見直した。これには、スケーラビリティのために基幹システムを社内のクラウドプラットフォームに移行し、アジャイルソフトウェア開発にシフトし、外部のAIスタートアップを買収し、2017年に破壊的技術を試験的に導入するStore No 8インキュベーターを立ち上げた。物理的なインフラを活用しながら、テクノロジーと企業文化を積極的に改革することで、ウォルマートは、レガシーな小売企業がデジタル時代にいかに競争力を維持できるかを示している。
②ターゲット(~2021年までの情報)
ターゲットは、実店舗を基盤に、強固なオムニチャネル体験を構築した。
・オンライン注文の80%以上を店舗で対応。
・オンラインで購入した商品の店舗受け取りは通常 1 時間以内に提供。
・ShiptとInstacartの提携による即日配達の提供。
・総合的なモバイルアプリを立ち上げ、利便性を高める。
・Google ExpressやPinterestと提携し、ビジュアル検索を統合。
ターゲットはまた、店舗を体験型ショールームとして再構築した。店舗では、没入感のあるデジタルディスプレイや、商品と触れ合う機会を提供している。ターゲットでは、洗練された在庫最適化アルゴリズムを導入し、地域市場向けの品揃えと在庫を管理している。
③イケア
家具の大手イケアは、デジタルと物理的な体験を融合させている。
・ARモバイルアプリを開発し、顧客が自宅の家具をデジタルでイメージできるようにした。
・商品よりもカウンセリングに重点を置いた小型店舗をオープン。
・店舗をeコマースのフルフィルメント・ハブとして活用。
・家具の組み立てを支援するTaskRabbitを買収した。
イケアは、単なる販売取引にとどまらず、より深い顧客エンゲージメントを可能にするデジタルイニシアチブを示している。
④ノードストローム
アパレル高級小売店であるノードストロームは、チャネル統合のために多額の投資を行っている。
・店舗とeコマースの在庫を統合し、シームレスなフルフィルメントを実現。
・オンライン注文を店舗またはカーブサイドで受け取れるようにする。
・店舗を配送ハブとして活用し、オンライン注文を発送。
・モバイルPOSで販売員を強化し、どこでもチェックアウトできるようにする。
・BevyUpやMessageYesのようなデジタル新興企業を買収し、機能を拡大。
ノードストロームは、デジタルトランスフォーメーションが、量販店だけでなく、小売セグメント全体で不可欠であることを示している。
これらの事例では、デジタル時代に適応するために、テクノロジーとプロセスに多大な投資を行った小売企業を紹介した。彼らは、最先端のデジタル体験を提供しながら、健全な店舗を維持している。重要なのは、勝利を宣言するのではなく、反復的に能力を拡大し続けていることだ。次に、これらの成功事例と、変革の失敗や行き詰まりを示す注意すべき事例を対比してみよう。
失敗または停滞した変革
①バーンズ&ノーブル
1997年にオンライン販売を開始し、早くからeコマースに取り組んできた書店だが、新たなデジタルの脅威に対して失敗している。
・ウェブサイトを独立させ、不採算のBarnes & Noble.comを設立。
・オンラインと小売の在庫とシステムを完全に統合しなかった。
・急成長する電子書籍市場をアマゾンに独占させた。
・オンライン売上が利益を相殺することなくカニバリゼーションしたため、60%以上の店舗を閉鎖。
バーンズ&ノーブルはデジタルでは先行していたが、
一貫した戦略の欠如により、競合他社にその能力を抜かされてしまった。
②トイザらス
トイザらスはいくつかの失策を犯している。
・ウォルマートやターゲットのようなライバルの積極的な 玩具品揃えの拡大を許した。
・メインストリートの店舗に匹敵する魅力的なデジタル体験の創造に失敗した。
・Eコマースと実店舗の完全な統合を実現しなかった。
・店舗の売上減少をオンラインの成長で補えなかった。
2017年にトイザらスが最終的に破産を申請したとき、デジタル変革への努力はあまりにも小さく、遅すぎた。
③Kマート
ディスカウントチェーンのKマートでは、変革にあまりにも長い時間がかかっていた。
・初期のインターネットを無視し、2006年までオンライン販売がなかった。
・フルフィルメント・オートメーションへの投資でウォルマートに及ばなかった。
・閉店した店舗に依存する時代遅れのサプライチェーンを見直さなかった。
・貧弱なデザインのウェブサイトとアプリでモバイル消費者を遠ざけた。
Kマートがシアーズと合併する頃には、そのブランド価値は著しく低下していた。デジタルで遅れを取り戻そうとしても、その下降スパイラルに歯止めをかけることはできなかった。
このような事例は、変革には文化、戦略、テクノロジーを同時に刷新することが必要であり、単にイニシアチブを追加するだけでは不十分であることを強調している。次に、変革を成功させるための前提条件をいくつか見てみよう。
必要な文化的転換
デジタル技術は重要な手段ではあるが、ツールだけで変革を推進することはできない。変革には、いくつかの側面にわたる文化的進化が必要なのだ。
顧客重視の文化
・新たな顧客ニーズを満たすことに絶え間なく注力する。
・強固なフィードバック・ループと満足度測定基準の導入。
・データ主導の顧客洞察に基づくエクスペリエンスの設計
テストと学習のマインドセット
・リスクを取り、迅速な実験を通じて検証する。
・失敗を災害ではなく学習の機会と捉える。
・継続的に新しいコンセプトを試し、データに基づいて改良していく。
コラボレーション構造
・イノベーションを妨げる硬直したサイロを取り払う。
・アジャイルで機能横断的なチームモデルへの移行。
・オープンなコミュニケーションと透明性の確保。
変革へのコミットメント
・デジタルトランスフォーメーションには長期的な投資が必要であることを受け入れる。
・短期的なコストよりも長期的な利益を優先する。
・目先の取引ではなく、生涯顧客価値を重視する。
デジタルファーストの視点
・顧客体験を創造する際に、オンライン・ファーストの考え方を採用する。
・すべてのプロセスとタッチポイントがデジタルにどのように変換されるかを想定する。
・統合された洞察のためにチャネルを横断してデータを集約する。
このような文化的特性は、現場レベルでの変革イニシアチブの実行を可能にする。リーダーシップのメッセージは、一貫してデジタルの優先順位を繰り返し、変革を推進するためのインセンティブを再調整する必要がある。更にデジタル志向の人材を社外から採用することで、進化を加速させることができる。
文化的な変革には時間がかかるが、次のセクションでは、小売企業が具体的な変革を加速させるために並行して導入できる主なテクノロジーについて詳しく説明する。
変革を加速されるテクノロジー
デジタルトランスフォーメーションは、組織のテクノロジースタックの近代化に依存している。必要な技術は以下のとおり。
・クラウド・インフラストラクチャ
レガシーなオンプレミスデータセンターからクラウドプラットフォームへの移行。無制限のストレージ、コンピューティング・パワー、より高速なソフトウェア展開の活用。機械学習やAIなどの高度なサービスの実現。
・統合コマース・プラットフォーム
単一のクラウド・コマース・プラットフォームにビジネス・システムを統合。オンライン・ストアフロント、POS、注文管理、在庫管理、フルフィルメントを接続。チャネル間で一貫した顧客体験を提供。(OMO)
・ヘッドレスアーキテクチャ
フロントエンドのインターフェースをバックエンドのシステムから切り離す。顧客向けアプリ、ウェブサイト、デバイスの迅速な構築と反復処理。フロントエンドがバックエンドのイノベーションを制限することを防ぎ、将来性を確保。
・IoTとサプライチェーンの可視化
店舗、倉庫、出荷、設備にセンサーを導入。在庫とフルフィルメントをリアルタイムで透明化。消費シグナルに基づく在庫の自動補充。
・モバイルコマース
摩擦のないモバイル・コマースのためのプログレッシブ・ウェブ・アプリケーションの構築。モバイルアプリによる便利なチェックアウトと支払い手法の導入。位置情報、通知、拡張現実をサポート。
・顧客データプラットフォーム
すべてのチャネルとシステムから顧客データを集約。購買履歴、エンゲージメント、デモグラフィックなどを統合した顧客プロファイルを作成。小売業者が顧客をよりよく理解し、パーソナライズされたエンゲージメントを実現する。
・予測分析
取引、在庫、その他の履歴データを分析し、パターンを見つけ出す。機械学習を活用して予測インテリジェンスを継続的に改善。在庫レベル、マーケティング費用、価格設定、プロモーションの意思決定に活用。
・会話型インターフェイス
チャットボット、音声アシスタント、AIを採用し、没入型ショッピングを可能にする。パーソナライズされたレコメンデーションと文脈に沿った商品回答を提供。
・位置情報テクノロジー
モバイルの位置情報を活用し、顧客の購買行動を把握する。
店舗のトラフィックパターンに基づいて、人員配置と在庫を最適化する。顧客が近くにいるときに、ロケーションベースのプロモーションを送信。
これらのテクノロジーは、文化的・組織的な準備と組み合わせることで、デジタルトランスフォーメーション・イニシアチブを実行するためのビルディングブロックを提供する。しかし、変革の旅を導くロードマップやフレームワークのサンプルを詳しく説明する前に、懐疑論者が抱いているいくつかの重要な神話を払拭することが重要である。
デジタルトランスフォーメーション神話の払拭
急を要する市場トレンドにもかかわらず、一部の小売企業幹部はトランスフォーメーションの推進に懐疑的であり、多くの場合、次のような神話を引き合いに出してくる。
●神話:顧客は依然として、デジタルよりも実店舗や人との対話を好む。
↓
●現実:顧客は、実店舗とデジタルをシームレスに行き来できる柔軟性を求めている。
調査によると、買い物客の60%以上が統合されたコマース機能を期待している。小売企業は、消費者が狭いステレオタイプに当てはまると考えるのではなく、多様な消費者の嗜好に対応しなければならない。
●神話:基本的な消費財よりもテクノロジーを販売する小売企業にとって、デジタルはより重要である。
↓
●現実:デジタルの破壊は、家庭用品から食料品に至るまで、あらゆる小売カテゴリーに影響を与えている。ウォルマートやターゲットのように、オムニチャネル・コマースを実現するために変革したリーダーは、その青写真を示している。どのカテゴリーにおいても、後発企業は確実に取り残されている。
●神話:デジタル化しすぎると、店舗でのコア・コンピタンスが失われる。
↓
●現実:体感型ショールームやフルフィルメント・ハブとして実店舗を活用することで、競争力を高めることができる。アマゾンがオフラインを拡大する中、伝統的な小売企業はオンラインを拡大しなければならない。
●神話:デジタルトランスフォーメーションはリスクが高すぎる。
↓
●現実:時代遅れのビジネスモデルを優先することは、デジタルを取り入れるよりもはるかにリスクが高い。Eコマースの台頭とオンライン消費へのシフトは、紛れもない世俗的トレンドである。小売業が取引以外の目的を提供しない限り、店舗の閉鎖は続くだろう。
●神話:デジタルを活用した変革には、多額の先行投資が必要だ。
↓
●現実:適切なペースであれば、小売企業は生涯顧客価値の向上を通じて、デジタルイニシアティブからROIを得ることができる。デジタルトランスフォーメーションを行わないことの代償は、関連性の喪失である。持続可能な成長のためには、大胆な投資が必要。
●神話:過去にデジタルイニシアティブを試したが失敗した。
↓
●現実:過去の失敗は、アイデアそのものよりも、サイロ化した施策や戦略的コミットメントの欠如に起因することが多い。小売企業は失敗から学び、教訓を織り込んで再挑戦しなければならない。変化は継続的な旅なのだ。
●神話:デジタルは誇大広告に過ぎない。
↓
●現実:パンデミックは、間違いなくオンラインショッピングの採用を加速させた。パンデミック後に消費者が突然、便利なデジタル体験を放棄することはないだろう。小売企業は新たな常識に適応しなければならない。
まとめると、これらの神話は時代遅れの思い込みや言い訳である。ビジョンとコミットメントがあれば、規模の大小を問わず、小売企業はデジタル時代に成功するビジネスモデルを再構築することができる。
デジタルトランスフォーメーション戦略の策定
誤解を解くことは重要な第一歩。疑念を払拭した上で、小売企業は包括的な変革戦略を策定する必要がある。現実的な戦略の要素には、以下のようなものがある。
①現在の能力の監査
・組織の準備、文化、スキルを評価し、ギャップを特定。
・技術スタックの老朽化、限界、統合ニーズの分析。
・カスタマージャーニー、オペレーション、アナリティクスにおける現在のペインポイントの把握。
②戦略的ビジョンの設定
・将来のデジタルビジネスのあるべき姿について、3~5年後のビジョンを定める。
・必要な主要機能とビジネスへの影響を概説する。
・リソースを提供し、緊急性を維持するための経営幹部のコミットメントの確保。
③競合および顧客分析の実施
・競合他社が導入しているデジタルサービスを調査し、期待を高める。
・アンケート調査やフォーカス・グループを通じて、必要とされる機能やペインポイントに関する顧客からのフィードバックを直接収集する。
・この市場インサイトに基づいて満たされていないニーズを特定し、差別化プランを策定する。
④データ戦略の詳細
・現在のデータソース、フロー、ガバナンスポリシーのカタログ化。
・パーソナライズされ、最適化された顧客体験を可能にする統合データ基盤のビジョンを定義する。
⑤実行ロードマップの策定
・テクノロジーとプロセスのイニシアチブの優先順位を決定し、迅速な勝利と長期的な機能のバランスをとる。
・依存関係のニーズと組織の準備状況に基づいて、タイミングを順序付ける。
・責任を共有するために、部門横断的なオーナーを任命する。
⑥KPIをビジョンに合わせる
・デジタル・チャネルの売上、モバイル・コマースのシェア、フルフィルメント・コスト、コンバージョン率など、中核となる指標を定義する。
・KPIを追跡して進捗をベンチマークし、イニシアチブを目標通りに維持する。
⑦変化を管理する
・デジタルトランスフォーメーションの緊急性を全社的に伝える。
・新しいプロセスやテクノロジーについて従業員を教育し、能力を高める。
・望ましい行動を奨励し、デジタル文化を推進する。
この構造化されたアプローチにより、トランスフォーメーション・イニシアチブは、漫然と前進するのではなく、強力な戦略的根拠とガバナンスを持つようになる。完璧な計画よりも、継続的なフィードバックと学習に基づいた調整が重要である。
世界の小売業の動向
デジタルトランスフォーメーションは、小売業にとって世界的な急務である。しかし、導入の成熟度や戦略は地域によって大きく異なる。地域ごとの差異を検証することで、小売企業は自社の変革への取り組みが同業他社と比較してどの程度のレベルにあるのかを理解することができる。
・北米
競争が激化する中、米国の小売企業はデジタルトランスフォーメーションへの取り組みで世界の支出をリードしている。注力分野は、統合コマース・プラットフォーム、AIベースのパーソナライゼーション、クリック&コレクトなど。小売企業は、社内の能力を補完するため、技術革新企業とのパートナーシップを活用している。主な課題は、レガシーシステム、店舗の統合、データの分析。
・欧州
英国および北欧の小売企業は、高いEコマース導入率に牽引され、デジタル・リーダーとなっている。(南欧は遅れている。)投資はオムニチャネルとモバイルエンゲージメントに集中。厳格な個人情報保護法が、パーソナライゼーションのための顧客データ活用を阻害している。北米に比べ、チャネルを超えた顧客サービスの強化が優先されている。
・アジア太平洋地域
アジア太平洋地域は、小売業のデジタル変革にかける1社あたりの投資額が北米の35%にとどまる。導入にはばらつきがあり、オーストラリアは欧州並みだが、東南アジアの一部はオンラインインフラが脆弱という問題を抱えている。投資は、高度な機能の前に、基本的なコマース・プラットフォームの構築に重点を置いている。モバイル・ペイメントと会話型コマースは、人気のイノベーションである。
・中国
スマートフォンの普及により、消費者のデジタル・エンゲージメントにおいて中国は他の市場を大きく上回る。 WeChatやライブストリーミングを通じたソーシャルコマースが浸透している。デジタルの普及にもかかわらず、オムニチャネルの統合は依然として課題となっており、在庫とフルフィルメントの最適化は、投資の重点分野である。
これらの地域別スナップショットは、変革はテクノロジー、インフラ、規制における地域市場のニュアンスに沿ったものでなければならないことを強調していると言える。
小売業のデジタル変革の実行
戦略的ロードマップを策定した小売企業は、その実行を運用化する必要がある。そのためには、俊敏性を養う仕組みとプロセスが必要である。ここでは、実行のための10のベストプラクティスを紹介する。
1. 定期的なレビューによるリーダーシップのコミットメントの確保。
2. 複数年の変革予算を確保する。
3. デジタルの専門家とビジネスリーダーを融合した部門横断チームを結成する。
4. ラボを設立し、試験的な規模拡大の前にコンセプトをプロトタイプ化する。
5. メトリクスとKPIダッシュボードを導入し、進捗を追跡する。
6. イノベーションを加速するために新興企業や技術パートナーを獲得する。
7. デジタル能力に関する従業員研修プログラムを開始する。
8. 組織の合理化のための組織変更を計画する。
9. テクノロジーではなく顧客重視を維持する。
10. 文化の醸成に失敗した実験については、原因を理解する。
イニシアチブの範囲に圧倒されるかもしれない。小売企業は、複雑なプロジェクトを推進する前に、明らかに迅速な勝利から始めるべきである。
モメンタムと緊急性を維持することが重要である。最後に、小売企業は、継続的な進捗を促進するために、シニアリーダーの「デジタル・チャンピオン」を特定し、育成する必要があります。変革は下層のチームだけに任せることはできない。
まとめると、小売業のデジタルトランスフォーメーションの実行には、
戦略的ビジョン、技術的能力の構築、文化的変革のバランスが必要である。
各組織は、将来のビジョンに向かいながら、その成熟度と強みに基づいてナビゲートしなければならない。しかし、この章では、どこから着手し、目標とすべき主要なマイルストーンを示す青写真を提供できたと思う。
・不作為のコスト
最後に、本章では、小売企業が、緊急かつ果断なデジタルへの変革なくして
直面する存亡の危機について、改めて 強調する。
- eコマースのピュアプレイ(純粋な小売企業)やデジタル対応小売企業への市場シェアの漸減。
- オムニチャネル機能の欠如による来店者数の減少。
- 顧客から「行きつけの店」と見なされなくなり、関連性が低下。
- 売上、利益率、キャッシュフローなどの財務指標の悪化。
- 事業の衰退に伴う、設備投資、従業員数、イノベーションの削減。
これらの結果を総合すると、無関連性や倒産への道筋が見えてくる。ひとたび組織がデジタル化に大きく遅れをとると、その文化は石灰化し、変革はさらに困難になる。否定と無策は有害であり、小売企業はデジタルの自己評価において残酷なまでに正直でなければならない。経営幹部にとって問われているのは、未来を切り開く業界のリーダーになるのか、それとも時間を借りて遅れをとるのか、ということだ。
ウォルマートやターゲットなどは、前者の道を選んだ。集中力とコミットメントがあれば、他の小売企業も業界の混乱の中で成功を収めるために追随することができる。しかし、優柔不断で中途半端な実行は、失敗のレシピだ。今こそ行動すべき時なのだ。
おわりに
本章では、小売業界におけるデジタルトランスフォーメーションをめぐる大きな緊急性をお伝えした。消費者の行動と期待は永久に変化している。消費者は、バラバラなジャーニーを許容するのではなく、デジタルとリアルが統合された体験を要求している。
Eコマースのピュアプレーやデジタル変革を遂げた既存企業は、現代的な小売体験がどのようなものを包含し得るかを顧客に垣間見せてきた。彼らの高い基準を満たすには、ビジネスモデ ル、組織構造、テクノロジー、アナリティクス、企業文化にまたがる全体的な変革に着手する必要がある。
変革は、チャンスであると同時に、存続の必須条件であることを認識しなければならない。カスタマー・エクスペリエンスを積極的に再構築する小売企業は、強靭な競争優位性を築くことができる。遅れをとったり、レガシーモデルにしがみついたりする企業は、急速に衰退するリスクがある。
この章が、トランスフォーメーションは大げさだとか、特定の小売企業には関係ないといった誤った考えを払拭してくれることを願っている。商品がファッションであれ、食品であれ、家庭用品であれ、消費者はデジタルを活用した体験を期待している。現実的な戦略を立て、新たなテクノロジーを受け入れることで、既存企業はその能力を飛躍させることができる。
前途は容易ではない。しかし、困難である必要はない。これまで述べてきたように、小売企業には、この道を歩んできた企業の明確な手本がある。
パートナーシップを構築し、計算されたリスクを取ることは、恐れを抱くよりも良い選択肢である。
本章では、なぜ変革が不可欠なのか、変革には何が必要なのか、誰が成功したのか、小売企業はどのように進めるべきかを概説することを目的とした。今後数年間で、リーダーとフォロワーが分かれるだろう。小売企業は、目指すべき軌道を選択しなければならない。それは、過去に取って代わられるか、未来に向けて再発明されるかである。集中力と勇気があれば、後者の道も実現可能だ。変革の時は今である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
