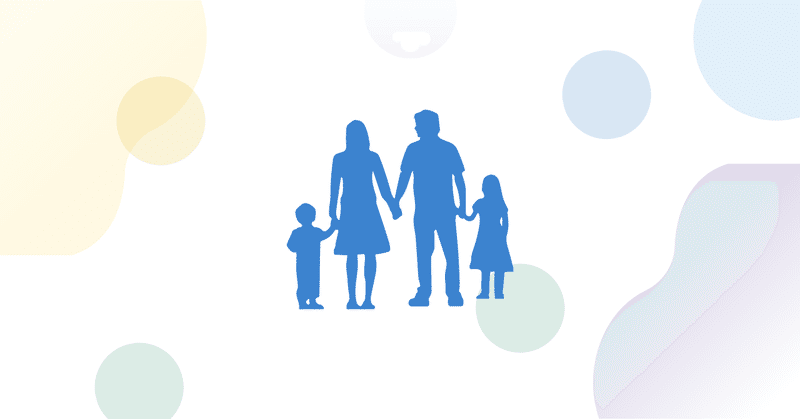
『「ヤングケアラー」とは誰か』を読んだ2つの感想
久しぶりのnoteになりました。
年明け以降、仕事がだいぶ忙しくなり、noteを書くだけの気持ちの余裕がなくなっていたのですが、やっと少し余裕を取り戻したところです。
たまには読書のことを書いてみます。
村上靖彦さんの『「ヤングケアラー」とは誰か』を最近読み始めました。
仕事柄、関心のあるテーマだったので買ってみました。
まだ序章と第一章を読んだばかりですが、すでにインパクトが強かったので、メモがてら感想を書きます。
あらすじ。
第一章は、長期脳死の兄を持っていた麻衣さんの体験談。
両親は「兄がまだ生きている、生きようとしている」という幻想を抱きながら兄を見舞う。
その一方、彼女は独りその状況を覚めた目でとらえているものの、兄を中心としてまわる家族のストーリーのなかで、彼女が日々抱く考えや感情を露わにする相手はどこにもおらず、孤立していく。
そんな当時の状況や感じていたことを彼女が振り返りながら語る。
読んで感じたことを2つ書きます。
1つ目は、「ケア」と一口に言ってもなかみは様々であるということ。
序章で「ヤングケアラー」の一般的な定義が紹介されていますが、それはあくまで一般論。本の帯にもある通り、介護や家事労働だけがケアでありません。
個別具体のケースを見ていくと、ケアラーが<誰の・何を・どのように>ケアしているかは本当に多岐にわたるのだろうと、第一章にしてすでに思います。
また、「そのケアを通じてケアラーがどんなことに苦悩や困難を感じ行動しているのか」という個人の主観的な体験も、ヤングケアラー問題を考えるうえで捨象できない要素なのだと思いました。
この章でいえば、麻衣さんは、まず長期脳死状態の兄に生を見出すことができず恐怖していました。しかし両親や周りの大人は「兄は生きようとしている」と疑わず、麻衣さんはその空気に強い違和感や不安を抱いていました。
彼女は恐怖や孤独を両親に打ち明けることができないどころか、両親が望む世界に合わせて演じることで親をケアしようとし、「兄の分までがんばる」と、兄が元気だったらしていただろう行動を取るようになります。
そうした生活のなかで彼女は徐々に自己を喪失していきます。
こうした個人の内面的な姿は、「社会問題」というマクロなフォーカスの当て方だけでは見えてこないものだと思います。
感想の2つ目は、1つ目の内容と関連しますが、「ヤングケアラー」という問題・事象は、社会福祉のフィールドだけで語られるものではないのだと改めて考えました。
職業柄、「ヤングケアラー」という言葉は、社会福祉・心理の分野におけるタームあるいは問題として捉えていましたが、それは捉え方のひとつにすぎません。
とりわけケアの当事者たち(ケアする人・される人・その周りの人)の視点からすれば、「家族のつながり」「理屈では語れない人と人との関わり」という、ごく個人的でドメスティックな話題なのだろうと思います。
この「社会的-個人的」という視点のギャップが存在することを、福祉に携わる者としてはよく理解しないといけないと感じました。
支援者は当事者の話に傾聴・共感しつつも、自分の軸は常に保っておくことが求められます。冷静かつ理性的でないといけません。相手の苦しい境遇や述懐に引き込まれることなく、必要な支援を提供したり制度に接続することができるようにするためです。
一方、ケアの当事者たちは、そもそも社会的なサポートが必要な事態だと自覚していない可能性が大いにあります。なぜなら「個人的でドメスティックな問題」であり、その解決の責任は自らにあると考えているからです。ゆえに社会的な支援の手につながること自体が難しい。
そういったことを理解しておくことが大事なのだと、改めて気づかされました。
第一章だけでも相当にハイカロリーな読み応えでした。そして深く考えさせられました。
ヤングケアラーはきっと身近にもたくさん存在するのでしょうけど、上述のような理由から認識されにくい存在でもあります(家族の世話をしている中学生の割合は17人に1人。学校や大人にしてほしい支援は「特にない」が約4割だそう)。
なのでこの本を通じてヤングケアラーの実態を深くうかがい知れることは貴重だなと思います。本書で語られる体験談の濃さに私自身があっぷあっぷしないよう、少しずつ読み進めていこうと思います。
お読みいただきありがとうございます。 私の記事であなたの気持ちが動いてくれたのなら、スキでもコメントでもサポートでも構いません。リアクションいただけると励みになります!
