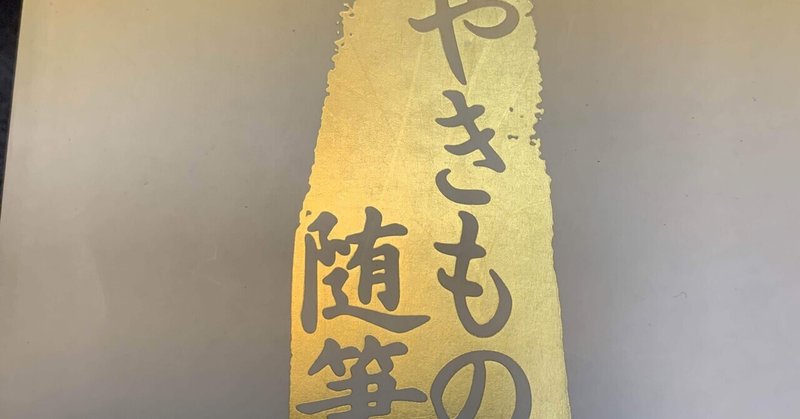
加藤さんと柳さん
前々回、器との出会いはそれを作った人との出会いでもあることを書きました。
さてそれから2冊の本を読みました。
加藤唐九郎「やきもの随筆」
柳宗悦「柳宗悦随筆集」
どちらも随筆、エッセイなので読みやすかったです。柳宗悦氏には前から興味があったのですが、先に読んだ加藤氏の随筆の中では結構辛辣にこき下ろされていました。
「柳さんの民芸運動は、たとえていうと新興宗教と似たような」
「次第に色あせた観念的なものに」
「人が聞きあきてからもなお同じ歌を歌い続けたので『もうけっこう』という感」
などなど。
ただ柳氏の民芸運動の前は「やきもの」というものは大変高価な茶器などで鑑賞できる人も限られていました。それを「昔の普通の人たちが使っていた器にも美しいものがある」「高価なものの中にだけ美があるのではない」ということを主張したのが柳氏で、この考えは発表当時は衝撃だったようです。この運動があって器に対しての一般人の見る目が開かれたものになった。それは加藤氏も認めています。
では何が気に入らないのか。加藤氏はそれを柳氏の「貴族性」にあると考えていて、例えば貧しい農民が作った器にも美しいものがある、というのをわざわざ「無学の」と付け加えたりして、要するに上から目線なのが加藤氏は嫌だったようです。
さてこれを読んでから柳氏の随筆を読むと「確かに」と思えるところもあります。例えば嫁入り道具の器には真に美しいものを選びなさい、と説いているものがあるのですが、これもそんなものを選べるようなお金や時間に余裕のある女性限定なんじゃないかな、と感じました。他にも自分がいた学習院は言葉が綺麗な人が多かった。途中で転学してくる人はどうも言葉が汚かった、なんていうちょっと差別的なものもありました。
なので加藤氏の主張も全くの的外れではないかもしれません。ただ柳氏の中には明らかに禅の精神があって、「祈り」について論じた中にはハッとするものがありました。
菅原道真の
「心だに誠の道にかなひなば祈らずとても神は守らん」
という言葉に猛反発していて、この言葉は「まじめに生きていればたとえ祈りを捧げなくても神様が守ってくださるでしょう」という意味なのですが、そもそも祈りとは自分の利益のためにあるものではなく、「自分が」祈る、というその時点でもう不純である。真の祈りとは自分を消すことである、というこれまた中世の修道僧エックハルトと同じことを書いています。これは禅にもつながる考えだと思います。
つながると言えばなんとオッペンハイマーについて書いている箇所もあって、まさに映画を見た直後に読んだので「ここもつながっている!」と少し興奮しました。
「この世から東西の陣、南北の朝などという考えが消えた時、初めて平和が来るのではないか」
という柳氏のこの言葉には全面的に同意しました。どちらが東か西か、というのは一体どこが基準なのか。本来は真っ平であるはずの世界を分断するから争いが起きるのではないでしょうか。
なので加藤氏の主張もわからなくはないけれど柳氏の思想には非常に深いものがあると感じました。
ちなみに加藤氏は志野焼の高名な陶芸家で、日本の陶芸の歴史についてはとても詳しく解説していてとても勉強になりました。日本陶芸の源流が織部焼、志野焼、黄瀬戸であると知り、先日やきもの展に行って現物を見ました。



どれもとても美しいと感じました。志野焼の作家さんは縄文土器も作陶されていて、それは売り物ではなかったのですが息を呑むほど素晴らしい作品でした。
陶芸の世界は知れば知るほど深いですね。そして知れば知るほどもっと知りたくなります。
加藤さんも柳さんも器に対して(柳さんは織物などにも)深い愛情があることは読んでいて伝わってきました。柳さんの本はもう少し他のものも読んでみたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
