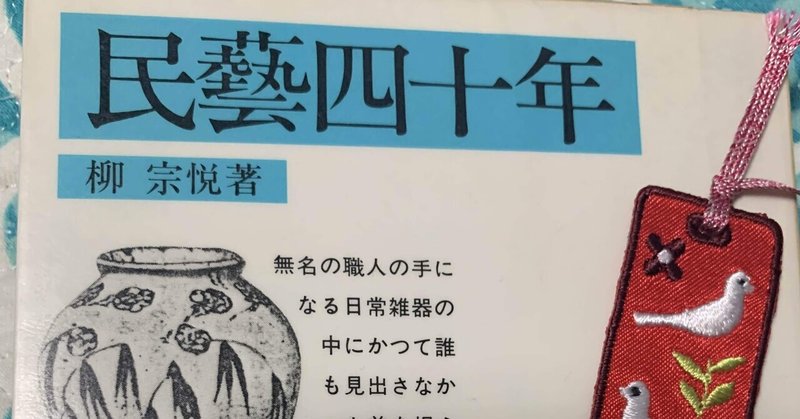
言葉の意味について
柳宗悦氏の「民藝四十年」を読んだ。
読みやすい、というのは前も書いたけれど、それでも時々あれ?と思う表現もある。
たとえば「変態」
これって今では痴漢とか性に関して悪い意味で使う言葉だけれど本の中では
「さもないと文化は変態的なものに陥ってしまう」
という感じで、だいぶ今とは違う感じである。
わたし的に衝撃というか「そうだったのか」と思ったのは「瀬戸もの」。小さい頃、お茶碗などを多分親が「瀬戸もの」と言っていたので、その時わたしはそういう陶磁器全般を「セトモノ」と呼ぶんだと思い込んでいた。
「瀬戸ものは割れやすいから気をつけなさい」
とか言われていたのを覚えている。けれど「瀬戸もの」は瀬戸で焼いたもの、という意味で、恐らくその頃は全国的に広く流通していたのだろう。でもわたしの脳内ではカタカナのイメージだった。
それから「民芸」も。旅行に行ってお土産屋さんにいくと「民芸品」という札とか看板が出ていて、ご当地の名産のこけしだとかそういうものを売っていた。なのでわたしの脳内では「民芸品」=お土産だった。
でもこの言葉も柳氏が産んだ言葉で、この言葉を使う前は「下手物」と呼ばれていたそうだ。
で、またその「げてもの」も今とはだいぶ意味が違う。今は何か気持ち悪いものとか、嫌悪感をもよおすようなものとして使うけれど、その頃は「上手物」といういわゆる高級品の対義語としての「下手物」だった。つまり下手物=雑器だったのである。
一般に出回っていたもの。誰も見向きもしなかったものの中に芸術品がある、という主張なので、もっと良い呼び名はないめのかと色々考えた末に生まれたのが「民藝」という言葉だったわけで。なんでそれが「お土産品」みたいに使われるようになってしまったんだろうか。
言葉というのは生き物なので時代によって変化していく、というのは知っているけれど、ずいぶん最初と違ったイメージがついたものもあるんだなあと思った。「瀬戸もの」については完全にわたしの無知からくる誤解だったけれど「民芸」に関しては柳氏の熱い思いのこもった言葉だったのに、ただのお土産みたいなイメージに変わってしまったのは残念すぎる。
ただ最近も大阪で「民藝」という展覧会が開かれていたし(わたしは行けなかったけど)無印良品のセレクト本になったり、柳宗悦氏の思想は今また静かなブームになっていると感じる。
わたし的に柳氏のいいな、と思うところは朝鮮もの、それから琉球ものについてその美しさ、圧倒的な個性を認め愛でているところだ。現代なら別に普通だろうが、柳氏が誉めた時代、朝鮮は日本の属国として蔑まれていた。沖縄も日本とはいえ、その独自の文化は全く評価をされていなかった。そういう時代にもかかわらず「美しいものは美しいのだ」ときっぱりと断言したその潔さが、わたしはいいなと思った。けれどあとがきを読むと、そのような柳氏の美意識は世間では高評価だったけれど、当時の政府にとっては都合が悪いものだったらしく、たびたび刑事が家に来たり、見張られていた、とも書いてあった。それを読んでわたしは暗い気持ちになった。
ロシアとウクライナの戦争、そして今イスラエルによるガザへのジェノサイドが行われていて誰も止めようとしない。特に後者はこの現代においてなぜこれほどまでにむごい殺戮が堂々と行われているのか。なんの罪もない小さな子どもがたくさん犠牲となっていて本当に悲しみと怒りで胸がいっぱいだ。
なぜ同じ人間なのにこんなにひどいことができるのか。みんなで美しいものを生み出せるはずなのに。なぜ自ら壊してしまうのか。そしてなぜ同じあやまちを繰り返してしまうのか。
言葉の話から少し離れてしまったけれど、わたしは今、この悲劇が1日も早く終わってほしいと心から願っている。そしてこの日本という国が再び過ちを犯すことがないようこれからも政府を監視し声を上げていこうと思う。弾圧に屈しずに自らの主張を堂々とつき通した柳氏の姿勢にならいたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
