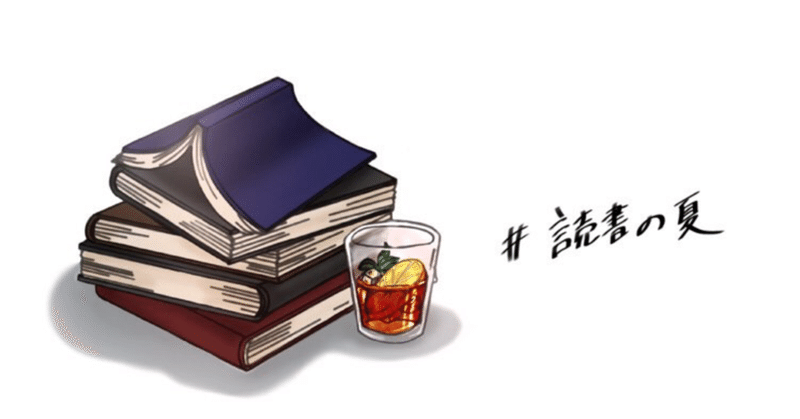
【夏休みの読書感想文に!】おすすめの本30選〜中学生・高校生向け
1、「教育」に関心がある人へ…………西岡常一ほか「木のいのち木のこころ〈天・地・人〉」
法隆寺を守りつづける宮大工が代々継承してきた技術と精神。その伝統を“伝説の宮大工”西岡常一が語る。「教育」に関心がある人にはもちろんのこと、学校が好きな人にも、嫌いな人にも、ぜひ読んでほしい本。人を「伸ばす」ことと木を「育てる」ことの共通点とは。
2、「プロ野球」が好きな人へ…………佐々木健一「神は背番号に宿る」
野球選手の背番号には「物語」がある。その数字は単なる数字以上の不思議な魔力をもつ。たとえば「完全数」28番を背負った「完全なる投手」江夏豊の、ドラマに満ちた野球人生。背番号に導かれ、数奇な運命を辿り、プライドをかけて野球に打ち込んだ名選手たちの記録。
3、「数学」が好きな人へ…………M・デュ・ソートイ「素数の音楽」
素数に関する重要な仮説、「リーマン予想」の証明にいどんだ天才数学者たちの物語。“数学界のワーグナー”リーマンは、それまでのあらわれ方に規則性の見られなかった素数の順列に、一つの規則性、一つの「音色」を聴き取った!数学愛に満ちた、情熱とロマンの書。
4、たくさん「食べる」人へ…………辺見庸「もの食う人びと」
生きることは食べることだ。人は世界中で働き、食べる。箸で、フォークで、ときには素手で。筆者が見たのは、文化の数だけ異なる食事の風景だった。読んでいると、ドキッとする言葉に出会う。「あなたの家の猫の缶詰が、どうやってできたものか、想像したことはありますか?」
5、毎日が「退屈」な人へ…………國分功一郎「暇と退屈の倫理学」
私たちの「退屈」はいつ始まったのだろう?人類はいつから「暇」を持て余し始めたのだろう。本書は「暇」と「退屈」の起源にせまり、現代社会の問題点を鋭く指摘する。「暇人」は尊敬されていた?
6、「アメリカ文学」に興味がある人へ…………E・ヘミングウェイ「老人と海」
海に生きる孤独なおじいさんのモノローグ。読みおえて、退屈な話だったとがっかりする人もいるかもしれないし、臨場感あふれる漁の描写に心を奪われる人もいるかもしれない。いずれにせよ、20世紀アメリカ文学の金字塔オブ金字塔。短いし、読んでおいて損はなし。
7、「フランス文学」に興味がある人へ…………F・サガン「悲しみよ こんにちは」
「あの夏、わたしは十七歳で、文句なく幸せだった。」――古今東西、誰もが恋に落ち、悲しみを知り、大人になる。だからきっと誰もが共感できる、一人の少女の夏の物語。行間から、そこはかとない哀愁と、潮の香りが漂ってくるような、情味豊かな文章です。
8、「イギリス文学」に興味がある人へ…………カズオ・イシグロ「わたしを離さないで」
ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロの傑作。世界の「謎」が徐々に明らかにされてゆくストーリーは最後まで引き込まれるが、そこには「ドキドキハラハラ」というより、胸が締め付けられるような切なさがある。設定はSFなのに、物語の手触りはリアル。他に類をみない小説です。
9、「見えないもの」が見える人へ…………川端康成「白い満月」
川端康成の小説は「死」の予感に満ちている。そして詩的に、官能的に描かれる、人の「孤独」やさまざまな「愛」のかたち……それらは別々の角度から見た、一つの事象なのかもしれません。不思議な力をもつ少女と肺に病をかかえる男の、神秘的な運命のみちびき。
10、「故郷」を見つめ直したい人へ…………柳美里「JR上野駅公園口」
どんな人にも「居場所」はあるのか?誰にも帰るべき「故郷」があるのか?いま、生きているこの場所は、自分にとって「最良の場所」といえるだろうか?誰もがぶつかる問いに、少数者の視点から向き合った小説。生者も死者も、光も影も、この国の「いま」をつくっている。
11、あの「文豪」が気になる人へ…………夏目漱石「硝子戸の中」
日本人に限らず「文豪」とよばれる人たちのイメージは、気難しかったり、ちょっと近寄りがたかったりと、好意的でない場合も少なくない。けれど夏目漱石にはそれはまったく当てはまらない。晩年の漱石はその実績のみならず、その人間性で、後輩にも、女性ファンにも、猫にも慕われていた。
12、「建築」に興味がある人へ…………B・タウト「忘れられた日本」
ドイツの大物建築家が、日本の歴史的建造物を褒めちぎる。読んでいて、日本人の歴史に誇りが持てるし、同時にそれを継承してゆくことの責任の重さも感じる。では私たちが受け継ぐべき日本人の「精神」とは?それはこの本を読み終えればわかるだろう。
13、「翻訳」に興味がある人へ…………鴻巣友季子「翻訳教室」
いま、世界中で出版された本の多くを、日本人は日本語で読むことができる。反対に、日本人が日本語で書いた本が海外の人に読まれることも、珍しいことではない。私たちにあまりにも身近になった、「翻訳」という貴重な文化について、第一線で活躍する翻訳家が易しく語る。
14、「日本語の未来」について考えてみたい人へ…………水村美苗「日本語が亡びるとき」
日本語が亡びる?そんな馬鹿な……と思う人にこそ読んでほしい本。副題は「英語の世紀の中で」。ほとんどの受験生が「現代文」より「英語」の勉強に時間と力を割く現状を、日本語教育の立場からどう捉えるべきか。言語の垣根を超えて、言葉の力を見つめ直す。
15、「宇宙」に興味がある人へ…………S・ホーキング「ビッグ・クエスチョン」
ホーキング博士の宇宙に関する本はたくさん出ている。宇宙に興味がある人ならどの本から手に取ってみてもいいと思う。あえてこの本を推薦したのは、第一章のタイトルがずばり「神は存在するのか?」だから。コレ、宇宙の本ですよね、博士?ホーキング氏こそ宇宙研究の「神」なのだ。
16、「変身」にあこがれる人へ…………F・カフカ「変身」
言葉も失うほどの不条理を前に、人間に何ができるのか?ある朝、グレゴール・ザムザが目覚めると、彼は巨大な「毒虫」に変身していた!現代人には単なる「おとぎ話」ですまされない、「他者の視線」や「疎外」の恐怖。カフカがこの話で表現しようとしたことは何だろう。
17、「自分って、変わってるかも?」と思う人へ…………村田紗耶香「コンビニ人間」
「普通」って何?「ヘン」ってどういうこと?「普通」であることは、現代社会を生きる条件なのか。コンビニという身近な風物の中にも人間の奇態さやおもしろさが垣間見える。社会に溶け込んだ現代人の「無個性」性に文学は鋭く切り込み、人間の多様さや滑稽さをあぶりだす。
18、「コツコツ続けたい」人へ…………菊池寛「恩讐の彼方に」
罪をおかした市九郎は、出家し、世のため人のために働く覚悟を決めた。それは事故の多い岩場に人の通る道をつくるという、大事業へのたった一人の挑戦だった。嗤われ、けなされ、無視されても、穴を掘りつづける男のもとに、彼への復讐を誓う侍がやってくる。
19、すべての「先生」へ…………壷井栄「二十四の瞳」
作者は香川県小豆島出身の壺井栄。自転車で颯爽と現れる新米教師の「大石先生」と、島の子供たちとの心のふれあいを描く。やがて日本は戦争の時代に突入し、子供たちはそれぞれの道を歩みはじめる。どんなときにも優しさと強さを失わない、「まなざし」の物語。
20、「大学生活」を夢想する人へ…………森見登美彦「夜は短し歩けよ乙女」
京都が舞台の青春エンターテイメント。はじめてこの本を読んだとき、「この本の作者、すげぇ」と思った。なぜなら、どちらかというと硬い文体で、難しい言葉も多いのに、すらすら読めちゃうから。そしてめちゃめちゃ面白い。これから大学生になる人には、とくにおすすめします。
21、「人生」について考えたい人へ…………五木寛之「大河の一滴」
人生とは悲しみと絶望の連続だ。――そう信じることは、「人生をあきらめる」ことではない。むしろ、小さな出来事にも喜びを見出し、自他の生を前向きに見つめ直すことである。私は中学の頃、サザンの歌でこの本を知った。ガキのくせにヘンな「悟り」を開いてしまいました。
22、「マイノリティ」を学びたい人へ…………上間陽子「海をあげる」
「泣ける」と紹介される本は山ほどある。でもそんな本で泣けることなんてほとんどない。この本を読めば、泣くことよりも、「耳を澄ます」ことが、読書の姿勢として大事なのだと痛感する。筆者の声に。本書で紹介される、弱者の声に。沖縄に生まれ、沖縄に住む、教育学者さんの本。
23、「戦争のリアル」を学びたい人へ…………アレクシエーヴィチ「戦争は女の顔をしていない」
女性にとっての戦争を、その証言を、聞き書きの方式で詳細につづった本。この本にかけた筆者の大変な労力とその思いの強さに感服する。戦争の痛ましい記憶は、男たちだけのものではない。「なかったこと」にしてはならない、「本物の声」が、この本には詰まっています。
24、「海外の学校」に興味がある人へ…………鈴木賢志「スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む」
日本の「社会科」とスウェーデンの「社会科」は、こんなにも違う!その相違の根底には、市民や社会という言葉への、両国民の捉え方の違いがあるようだ。たとえばスウェーデンの教科書には、「SNSの正しい使い方」が載っている。日本の教育の「常識」が揺さぶられます。
25、「生き物」に関心がある人へ…………福岡伸一「動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか」
「動的平衡」。あまり聞きなれない言葉だが、生命という現象について核心をとらえた表現だ。生命は「流れ」のなかにある。命とは「よどみに浮かぶうたかた」なのだ。では、記憶とは何か。エントロピーとは。日々生まれ変わる、自分自身の生の神秘を見つめ直すための本。
26、「こども心」を忘れない人へ…………宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」
宮沢賢治の童話はピュアだ。だから、この本の印象を「自己犠牲は素晴らしい」というような単純な言葉にはしたくない。賢治はこの物語にどんな願いを込めたのか。子供のようにピュアな作家の、想像力の豊かさと、世界の深さを、ぞんぶんに味わってほしい。
27、この夏、「冒険」したい人へ…………三島由紀夫「夏子の冒険」
別の夢を追いかけて都会を飛び出した夏子と青年が、北海道で出会い、恋に落ちる。ぶっとんだストーリーだし、夏子はさらにぶっとんでいるが、作者の鋭い批判精神が根底にはある。いわく、「青春のはけ口を託するに足る夢を、今の時代が与へてくれない」ことへの、反乱と冒険。
28、「SF」が好きな人へ…………アーサー・C・クラーク「幼年期の終わり」
ある日突然、人類の前に現れた謎の存在「オーバーロード」。彼らは何者で、いったい何を企んでいるのか?超越的な存在を前に、人類の未来に希望はあるのか?創造性豊かなこの作品が1950年代に書かれたことに驚く。巨匠クラークが打ち立てたSF界のマイルストーン。
29、「青春」を見つめ直したい人へ…………夏目漱石「三四郎」
熊本から東京の大学へ入学した、純朴な青年・三四郎を翻弄する、天真爛漫な女性・美禰子。未知の世界で空回りする三四郎がかわいらしくて面白くて、ときどき共感もできる。「東京より、日本より、頭の中のほうが広いでしょう」とのたまう、広田先生のモデルは漱石自身か。
30、「1945年8月15日」を学びたい人へ…………半藤一利「日本のいちばん長い日」
多くの日本人が戦場に向かう時代があった。その悲惨な時代の終わりに、祖国の未来のため、決断をせまられた者たちの記録。歴史を学ぶことにどんな意味があるか?悲惨な過去を振り返ることが必要か?そんな疑問も吹っ飛ぶほどの、圧倒的熱量のノンフィクション。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
