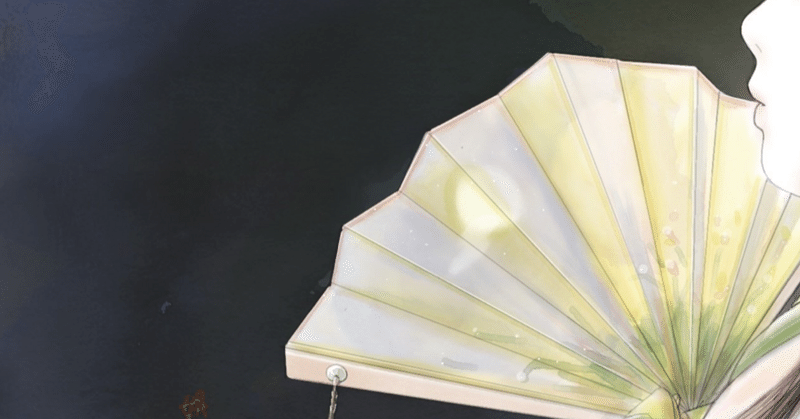
【小説】「静鼓伝」(二)
【あらすじ】
静御前は母・磯禅師とともに讃岐の地を訪れ、剃髪し僧侶になった。静は源義経との別れの際、彼の形見として授かった小鼓「初音」を大切に持ち歩いていたが、かつての侍女・琴路が彼女のもとを訪れたときには、その鼓はなくなっていた。静が「初音」を手放した背景には、亡き母の深い愛と教えがあった。香川県東部地域に実際に伝わる静御前伝承がもとになった作品。
*
――悲しみは突然、やってきた。
その日、長尾寺と静たちの庵とを結ぶおよそ一里の道のりには、昼過ぎから粉雪がちらついていた。
磯禅師はいつものように長尾寺へ参詣するため支度をととのえていた。磯は出家以来、得度を得たその寺への参詣を一日たりとも欠かしたことがなかった。寒さの厳しい戸外へ出て行こうとする高齢の母を静は引きとめようと説得したが、反対にたしなめられてしまった。病気がちのあなたのぶんまで、と信仰心の篤い磯は体の弱い娘の回復を祈願するためと、いっそう意気込んで出掛けていった。
磯は日が傾きかけても帰って来なかった。たまらなくなって庵を飛びだした静につづいて、琴路も一心不乱に磯を探した。その夜更け、冷たくなった彼女の体が庵の近くを流れる川のほとりで見つかった。足を滑らせ落ちたらしい深い草の茂みで事切れた老女の小さな背中に、粉雪が舞い降りたまま溶けずにいた。二人は声にならない声をあげ、一晩中泣き明かした。
その日から、琴路と五つしか歳の違わない静の衰弱ぶりは、琴路の目に見えてはっきりと深まっていった。……
琴路は潤んだ目で、たった今寝床から体を起こしたばかりの静を見つめた。この小さな体は、いったいどれほどの過酷な時間を乗り越え、きょうまで生きてきたのだろう。琴路はそれを思うたびに、胸が張り裂けそうになった。
せめてあの鼓があれば、と琴路は一度ならず考えた。あの鼓の音色さえ、この暮らしのなかに生きていれば。主人の孤独はわずかなりとも癒されたであろう。「初音」を、あれほど大切にしていた宝物をなくしてしまったことが、彼女にとってどれほど辛いことであっただろうか。恋人と別れ、鎌倉ではその人との間に授かった子を理不尽にも奪われ、母親を亡くし、そのあげく、たった一つの宝物をもうしなった彼女の心に、現世への救いを求める気持ちがはたしてどれほど残っているだろうか。それを思うと琴路はたまらなくなる。少しでも長く、主人のそばにいてさしあげることを、琴路は自らの使命のように感じていた。
「かわいらしい、小鳥たちの夢を見ておりました……」
静は消え入りそうな声で繰り返した。
剃髪し、僧侶となった静たち母娘は、長尾寺で、弘法大師の「いろは歌」に接した。色は匂えど散りぬるを、と歌われる「いろは歌」は当時、「今様」としてよく知られた歌ではあったが、静の傷ついた心には、その諸行無常の教えがいっそう真に迫るものとして響いた。
静の気がかりは、母とともに讃岐の地へやってきた直後から、鼓の奏でる音色が変わってしまったことだった。母から教えられたとおり、手のひらに力をあつめて注意ぶかく打ち鳴らしてみても、「初音」は本来の高く澄みわたる音を鳴らさなくなった。
初音は、静にとって命よりも大切な鼓だった。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
